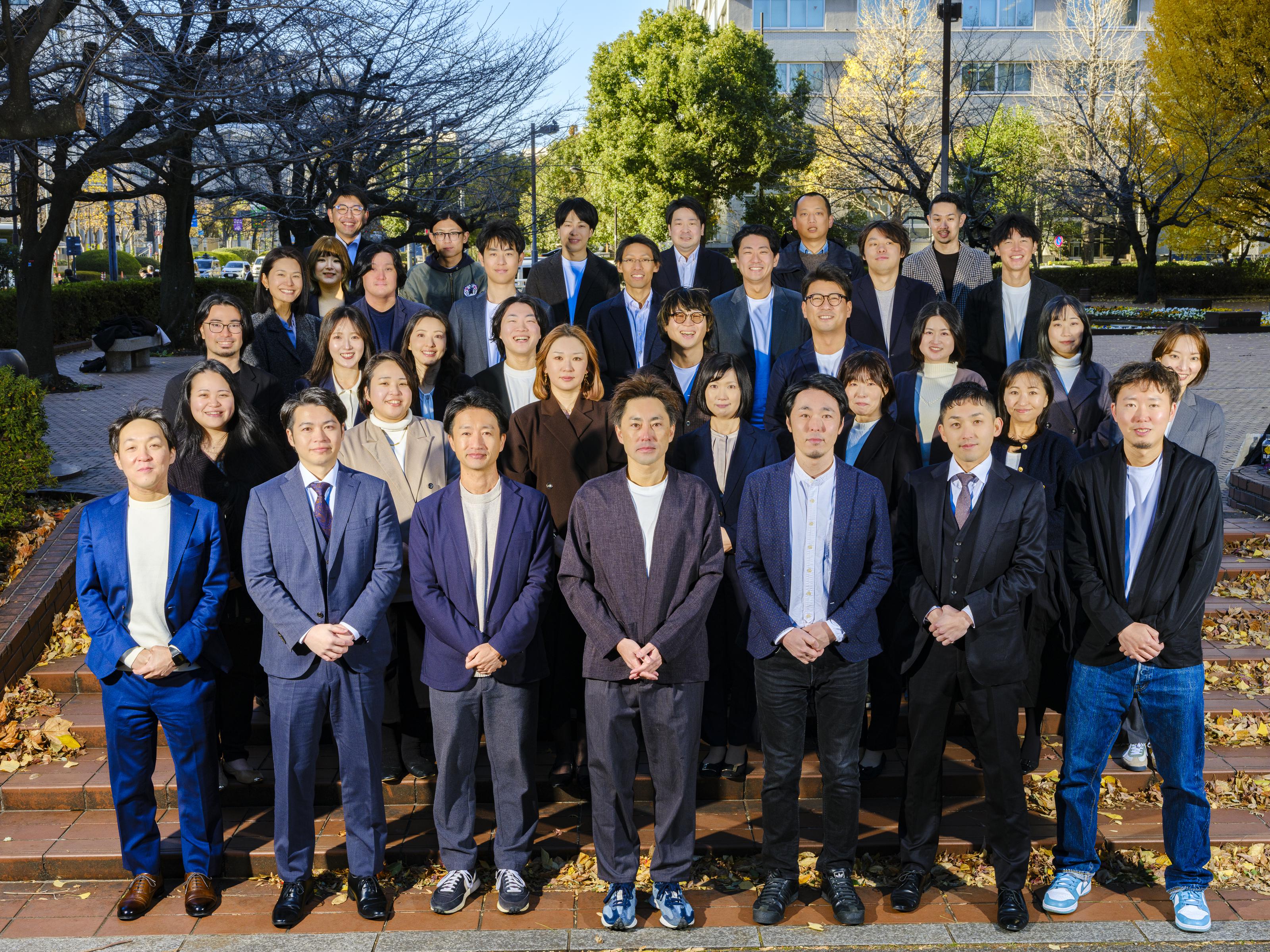株式会社ネオキャリア
- サービス系
- IT/Web・通信・インターネット系
人の力をテクノロジーで加速させ、 より良い社会の創造のために挑戦し続けます。
企業について
2000年の創業時から一貫して人材総合サービス事業を運営し、
"社会になくてはならない会社"となるべく、歩みを進めています。
求人広告事業と中途採用支援事業から開始した当グループですが
社会のニーズやお客様の課題解決に向き合い続けた結果、ヘルスケア領域、HR Tech領域、アウトソーシング領域など
幅広く事業を展開し、現在では約60部門を擁する規模となりました。
今後も日本が抱える人口問題やライフステージで訪れる課題の解決に向けて事業を展開して参ります。
社会に必要とされる会社へと成長し続けるために
「人の力をテクノロジーで加速させる」べく、2022年にDX推進部を新設。
複数にまたがる事業を安定稼働させる情報システム部門とともに
全社戦略に基づいたデジタル化をスピーディかつ、本格的に取り組んでいます。
今後グループの更なる成長には
先端技術を積極的に活用した業務効率化や新規事業開発にチャレンジしていく必要があります。
グループ全体のデータ活用とデータリテラシーの向上に努め、
新しい価値の提供と社会貢献を目的に全社のデジタル化を推進していきます。
全社員が参加でき、IT/DXを活用した課題解決コンテストが「BLUE CARPET」です。
デジタルを活⽤した課題解決策を⽴案できる⼈材の育成を目的とし、
「新規事業」と「業務改⾰」の2つのカテゴリで、社内外問わず課題解決に向き合うテーマを募集します。
最優秀プランには予算が付与され、企画実⾏にむけて動き出します。
募集している求人
営業職の求人(2件)
サービス職(人材/店舗/医療)の求人(2件)
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)
専門職(金融/不動産/コンサルタント/士業)の求人(2件)
クリエイティブ職(ゲーム/マルチメディア)の求人(1件)
経理・管理・バックオフィス職の求人(1件)
社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
株式会社ネオキャリア
サービス系 > 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > Webマーケティング・ネット広告
100,000,000円
2025年 2月 524億円
2024年 2月 508億
2023年 2月 496億
2000年11月
代表取締役 西澤 亮一
■採用支援
・新卒、中途、アルバイト、派遣の採用支援
・専門職の採用支援(介護、エンジニア等)
■就労支援
・就職活動支援
・転職活動支援
・各種専門職への就労支援
■業務支援
・営業代行、コールセンター代行、集客支援
・システム受託開発
・保育所、学童保育室 など
非上場
東証一部上場企業、ベンチャー企業、外資系企業など幅広く取引をしております。(敬称略) (株)NTTドコモ /(株)ディー・エヌ・エー/グリー(株)/クルーズ(株)/(株)ポッカコーポレーション/(株)AOKI/味の素(株)/丸善(株)/日本電気(株)/麒麟麦酒(株)/楽天(株)/(株)サイバーエージェント/(株)ベネッセコーポレーション/(株)ドワンゴ/(株)ネクスト/中央三井信託銀行(株)/(株)テイクアンドギヴ・ニーズ/(株)ニトリ/(株)ドン・キホーテ/エイベックス・グループ・ホールディングス(株)/(株)ぐるなび/GMOインターネット(株)/ユナイテッド(株) /SBIホールディングス(株)/アルプス電気(株)/スターティア(株)/エムスリー(株)/デジタルアーツ(株)/トレンドマイクロ(株)/ネクステック(株)/ネットワンシステムズ(株)/フィンテックグローバル(株)/パーク24(株)/フリービット(株)/(株)TYO/(株)オウケイウェイヴ/(株)キャリアデザインセンター/(株)ゲームオン/(株)サミーネットワークス/(株)ネットプライス/(株)マクロミル/(株)リンクアンドモチベーション等
3486人
30歳
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル 2F
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- サービス系
- 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
- 株式会社ネオキャリアの中途採用/求人/転職情報