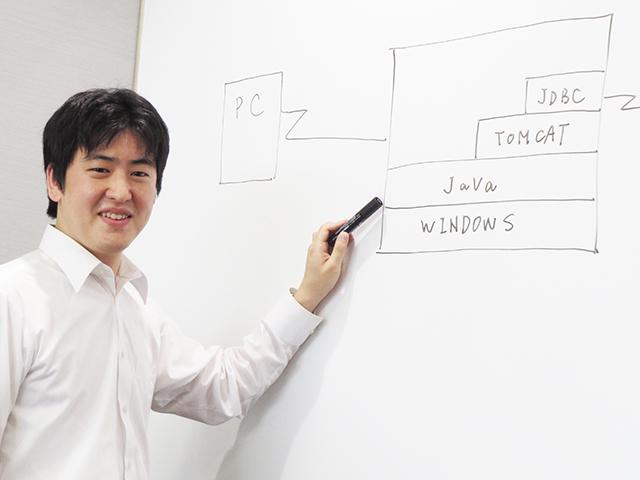株式会社アイピーエス
- IT/Web・通信・インターネット系
東京ガスのコアパートナーとして、システム維持・管理で無類の強みを発揮。
残業少なめ
カジュアル面談歓迎
企業について
顧客業務の深い理解を土台に、ITソリューションをワンストップで展開。
株式会社アイピーエスは、1985年に設立以来、企業の情報化戦略を形にするITソリューションを展開している。現在の代表取締役である原田幹雄氏と仕事を通じた仲間5~6名でスタートし、顧客ネットワークの拡大および実績を積み重ねながら事業規模を少しずつ拡大し、今の姿に至る。
売上構成は、大手企業(2社)が約7割を占め、その他、SIer系・エンドユーザー系が約3割を占めている。いわば、2大柱となる取引先との関係性により、同社の業績の大部分が支えられている。1社は東京ガスグループで、取引実績は23年近くになる。もう1社はエーザイグループであり、取引実績は実に33年を超える。
同社のITソリューションは、上流から下流まで一貫して手がけるワンストップサービスが特徴だ。特に先にふれた2社については、グループ会社のIT相談窓口として機能しており、BPO支援・システム分析・システム計画といった最上流から、その後の開発・導入・運用保守まで行っている。領域もWebオープン系からメインフレーム系まで幅広い。
自社の強みは「維持管理のノウハウ」であり、同社はこれまで、お客様のシステムの依頼に対して、"どこよりも早く"、"丁寧に"応えることをモットーとしてきた。「要望を正しくキャッチし、要望を具現化する」 「決められたルーティンワークを正確に継続する」など、派手なことをやらずとも、当たり前のことを当たり前のように継続し、大手企業グループのITインフラを着実に支えてきたのである。維持管理のノウハウは、継続してきたからこそ蓄積された武器なのだ。
同社に対する信頼の深さは、東京ガスのコアパートナー(8社)に選ばれている事実が物語っている。8社のうち、未上場企業は同社のみであることも特筆すべきポイントだ。エーザイグループについては、システム部門の一員として、ユーザーと開発ベンダーとの橋渡しの役割を担っているとのこと。
東京ガスグループ、エーザイグループ共に、現場の知識教育には力を入れており、今までの積み重ねのおかげで、業務に対する理解度の深さは自慢できるポイントです。自社ならではの強みを付け加え、さらなるパートナーシップを深めていく。
売上構成は、大手企業(2社)が約7割を占め、その他、SIer系・エンドユーザー系が約3割を占めている。いわば、2大柱となる取引先との関係性により、同社の業績の大部分が支えられている。1社は東京ガスグループで、取引実績は23年近くになる。もう1社はエーザイグループであり、取引実績は実に33年を超える。
同社のITソリューションは、上流から下流まで一貫して手がけるワンストップサービスが特徴だ。特に先にふれた2社については、グループ会社のIT相談窓口として機能しており、BPO支援・システム分析・システム計画といった最上流から、その後の開発・導入・運用保守まで行っている。領域もWebオープン系からメインフレーム系まで幅広い。
自社の強みは「維持管理のノウハウ」であり、同社はこれまで、お客様のシステムの依頼に対して、"どこよりも早く"、"丁寧に"応えることをモットーとしてきた。「要望を正しくキャッチし、要望を具現化する」 「決められたルーティンワークを正確に継続する」など、派手なことをやらずとも、当たり前のことを当たり前のように継続し、大手企業グループのITインフラを着実に支えてきたのである。維持管理のノウハウは、継続してきたからこそ蓄積された武器なのだ。
同社に対する信頼の深さは、東京ガスのコアパートナー(8社)に選ばれている事実が物語っている。8社のうち、未上場企業は同社のみであることも特筆すべきポイントだ。エーザイグループについては、システム部門の一員として、ユーザーと開発ベンダーとの橋渡しの役割を担っているとのこと。
東京ガスグループ、エーザイグループ共に、現場の知識教育には力を入れており、今までの積み重ねのおかげで、業務に対する理解度の深さは自慢できるポイントです。自社ならではの強みを付け加え、さらなるパートナーシップを深めていく。
“第3の顧客”の確立を目指し、積極的に組織・業務の仕組み構築に着手する。
今後のさらなる成長に向けて同社が掲げているテーマは、新しい分野の開拓による売上拡大だ。それを実現するためには、大手企業グループ2社に続く“第3の顧客”の確立が早急のミッション。
同社が抱えている課題の一つとして、スキルの偏りを挙げている。仮に、大手企業のシステム運用・保守プロジェクトへの配属では、長期スパンの業務となる。担当する現場の知識はどんどん深まっていくが、逆に新しい領域の技術・知識にふれる機会が減るのだ。こうなると一つの現場にエンジニアが張り付き、業務や知識が徐々に属人化する。つまりローテーションが難しくなってくるのである。
新しい顧客の柱を開拓するプロセスでは、当然のことながら新規案件の企画・提案が必要になってくる。同社では、豊富なキャリアを持ち、営業力に長けたタイプのエンジニアに新規プロジェクトを任せるため、今後エンジニアがローテーションしやすくする仕組みづくりに積極的に取り組む構想だ。具体的に着手する施策として、以下の3つが挙げられている。
1つ目は、ローテーションに対するお客様の協力姿勢だ。大事なITインフラを長期安定して運用・保守するため、"個々の業務"ではなく"チームの業務"として取り組んでいくことの重要性をお客様に説明し、すでに理解をいただいているとのこと。
2つ目は、担当プロジェクトの業務プロセスおよびシステムの可視化だ。一例を挙げると、東京ガスのメンテナンスフローの理解度を数値化し、知識のボトムアップを図る勉強会もスタートさせている。
3つ目は、プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャーを担える人材の育成および採用だ。現在現場で活躍しているエンジニアに対する教育をさらに充実させ、スキルのボトムアップを図る。それと並行し、さまざまな強み・個性をもったエンジニアの中途採用を強化し、柔軟に体制を組める組織の確立を目指すという。
「新しい分野の開拓は同社のテーマであるが、“お客様を大事にする”という姿勢は今後も継続していくべきである」と、付け加えている。なぜなら、この姿勢があってこそ成長してきたわけで、同社の強みと密接にリンクしている姿勢だからだ。
これまでに培ってきた財産を土台に、さらなる飛躍を目指して業務改革を推進する同社。これから入社する人材も、経験・能力を十分に加味され、最も力を発揮できるプロジェクト・ミッションが与えられるだろう。
同社が抱えている課題の一つとして、スキルの偏りを挙げている。仮に、大手企業のシステム運用・保守プロジェクトへの配属では、長期スパンの業務となる。担当する現場の知識はどんどん深まっていくが、逆に新しい領域の技術・知識にふれる機会が減るのだ。こうなると一つの現場にエンジニアが張り付き、業務や知識が徐々に属人化する。つまりローテーションが難しくなってくるのである。
新しい顧客の柱を開拓するプロセスでは、当然のことながら新規案件の企画・提案が必要になってくる。同社では、豊富なキャリアを持ち、営業力に長けたタイプのエンジニアに新規プロジェクトを任せるため、今後エンジニアがローテーションしやすくする仕組みづくりに積極的に取り組む構想だ。具体的に着手する施策として、以下の3つが挙げられている。
1つ目は、ローテーションに対するお客様の協力姿勢だ。大事なITインフラを長期安定して運用・保守するため、"個々の業務"ではなく"チームの業務"として取り組んでいくことの重要性をお客様に説明し、すでに理解をいただいているとのこと。
2つ目は、担当プロジェクトの業務プロセスおよびシステムの可視化だ。一例を挙げると、東京ガスのメンテナンスフローの理解度を数値化し、知識のボトムアップを図る勉強会もスタートさせている。
3つ目は、プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャーを担える人材の育成および採用だ。現在現場で活躍しているエンジニアに対する教育をさらに充実させ、スキルのボトムアップを図る。それと並行し、さまざまな強み・個性をもったエンジニアの中途採用を強化し、柔軟に体制を組める組織の確立を目指すという。
「新しい分野の開拓は同社のテーマであるが、“お客様を大事にする”という姿勢は今後も継続していくべきである」と、付け加えている。なぜなら、この姿勢があってこそ成長してきたわけで、同社の強みと密接にリンクしている姿勢だからだ。
これまでに培ってきた財産を土台に、さらなる飛躍を目指して業務改革を推進する同社。これから入社する人材も、経験・能力を十分に加味され、最も力を発揮できるプロジェクト・ミッションが与えられるだろう。
“人と人のつながり”を大切にすることで、エンジニアの高い定着率を実現。
社風は一言で表現するならば"アットホーム"である。先輩と後輩、部署間、経営と現場など、全てにおいて人と人の距離が近いのだ。同社はエンジニアを一人でプロジェクトにアサインすることは、余程のケースでない限りは避けているという。プロジェクトでは、複数人のチームをつくり、業務に詳しい先輩が知識を一つひとつ後輩に教えている。
社員同士の交流を目的とした社内イベントも活発である。毎月1回・夕方に開催される定例ミーティングの後には、みんなで飲み会を開くのが恒例パターン。飲み会には社長をはじめ経営陣も参加している。役職や部門の垣根を超えてコミュニケーションを図ることで、社員同士の絆を深める場になっているそうだ。この他、賞与時の懇親会や、創立記念日パーティー、社員旅行、年末の納会など、節目ごとにイベントを開催している。
現場で活躍するエンジニアに話を聞くところ、こうしたイベントの存在は大きく、前向きに参加しているという。普段、別々のプロジェクトで勤務していると、なかなか外部の情報を得る機会は得られないもの。お酒を飲みながらお互いの仕事を語り合うことも、確実に刺激の一つになっている。
このように、職場で肩身の狭い思いをせず、気心が知れた自社の仲間と一緒に働けることも影響しているかもしれないが、同社はエンジニアの定着率が非常に高い。新卒で入社した人間も脱落することなく、5年選手・10年選手に育っているそうだ。
最後に、同社が描いている人物像について聞いた。能力面に関しては、コミュニケーション能力を発揮し、顧客折衝で強みを発揮するタイプの人材に期待しているとのこと。実は技術力に関しては、そこまで重要視していないと言う。技術は自ら覚える気があればいくらでもカバーできると考えているからだ。そういった意味で、人間性や適性、向上意欲などが重要視されているため、あらゆる技術分野の人材にチャンスがあると言えるだろう。
プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャーに成長してもらい、将来的には会社の中核社員として次世代のアイピーエスを切りひらいてほしい―。これは同社が理想とするキャリアの道筋である。「マネジメント力を磨きたい」「いずれは経営に近いポジションで会社づくりをしてみたい」など、現状よりさらにステップアップしたいと考える人であれば、きっと高いモチベーションを維持しながら働けるはずだ。
社員同士の交流を目的とした社内イベントも活発である。毎月1回・夕方に開催される定例ミーティングの後には、みんなで飲み会を開くのが恒例パターン。飲み会には社長をはじめ経営陣も参加している。役職や部門の垣根を超えてコミュニケーションを図ることで、社員同士の絆を深める場になっているそうだ。この他、賞与時の懇親会や、創立記念日パーティー、社員旅行、年末の納会など、節目ごとにイベントを開催している。
現場で活躍するエンジニアに話を聞くところ、こうしたイベントの存在は大きく、前向きに参加しているという。普段、別々のプロジェクトで勤務していると、なかなか外部の情報を得る機会は得られないもの。お酒を飲みながらお互いの仕事を語り合うことも、確実に刺激の一つになっている。
このように、職場で肩身の狭い思いをせず、気心が知れた自社の仲間と一緒に働けることも影響しているかもしれないが、同社はエンジニアの定着率が非常に高い。新卒で入社した人間も脱落することなく、5年選手・10年選手に育っているそうだ。
最後に、同社が描いている人物像について聞いた。能力面に関しては、コミュニケーション能力を発揮し、顧客折衝で強みを発揮するタイプの人材に期待しているとのこと。実は技術力に関しては、そこまで重要視していないと言う。技術は自ら覚える気があればいくらでもカバーできると考えているからだ。そういった意味で、人間性や適性、向上意欲などが重要視されているため、あらゆる技術分野の人材にチャンスがあると言えるだろう。
プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャーに成長してもらい、将来的には会社の中核社員として次世代のアイピーエスを切りひらいてほしい―。これは同社が理想とするキャリアの道筋である。「マネジメント力を磨きたい」「いずれは経営に近いポジションで会社づくりをしてみたい」など、現状よりさらにステップアップしたいと考える人であれば、きっと高いモチベーションを維持しながら働けるはずだ。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)
PR
すべて見る企業情報
会社名
株式会社アイピーエス
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
IT/Web・通信・インターネット系 > その他IT/Web・通信・インターネット系
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、残業少なめ資本金
1500万円
設立年月
1985年03月
代表者氏名
代表取締役 原田 幹雄
事業内容
■システム受託開発
■システムコンサルティング
■システム構築
■運用支援・維持管理
■リプレース提案 ほか
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
株主総会交換できるくん(東証グロース市場上場)
主要取引先
エーザイ株式会社 東京ガス株式会社 東京ガスiネット株式会社(旧 株式会社ティージー情報ネットワーク) 東京ガスコミュニケーションズ株式会社 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 東洋熱工業株式会社 森ビル株式会社 山伸マテリアル株式会社 他(順不同)
従業員数
68人
本社住所
〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー12F
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社アイピーエスに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社アイピーエスの中途採用/求人/転職情報