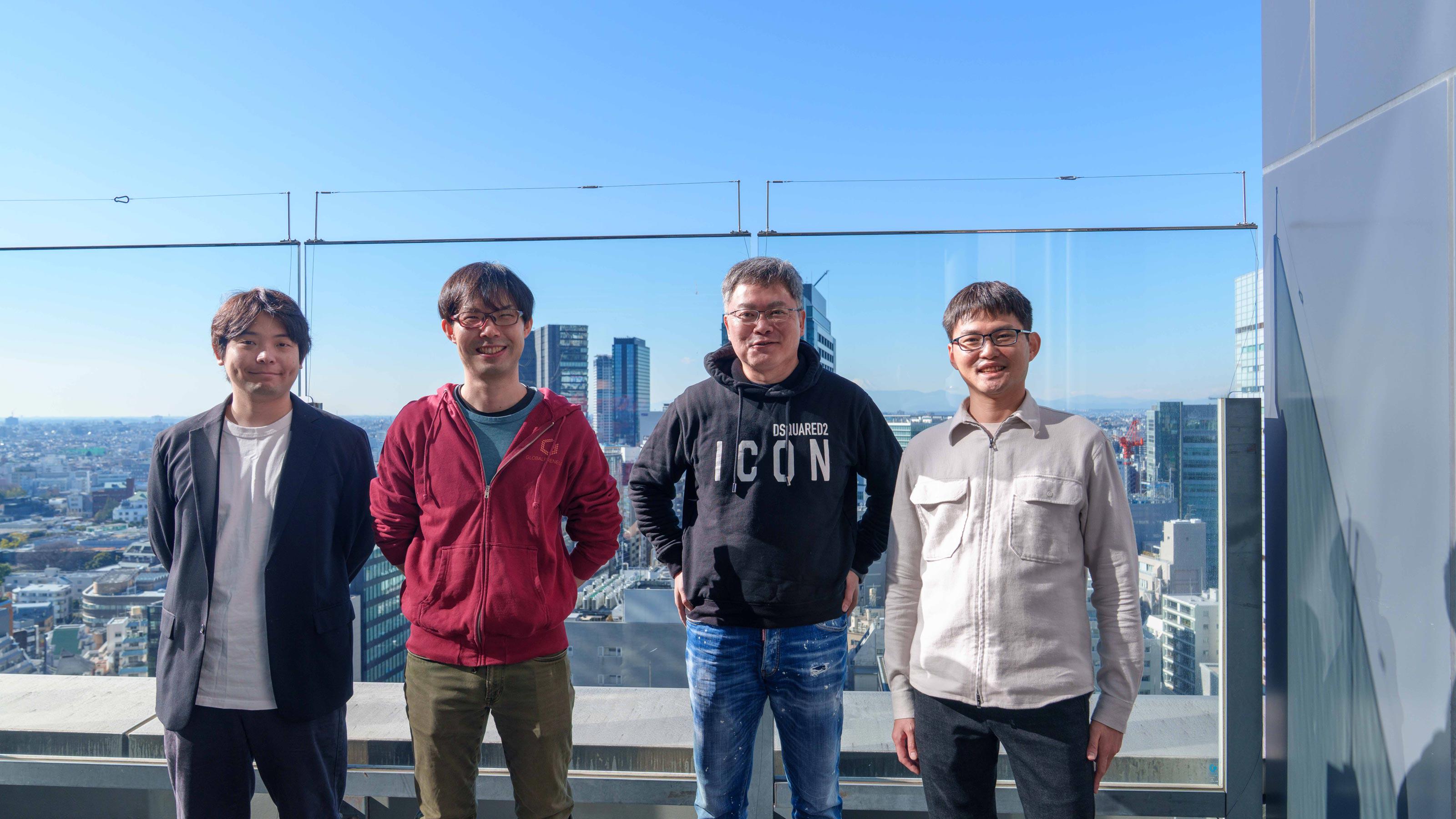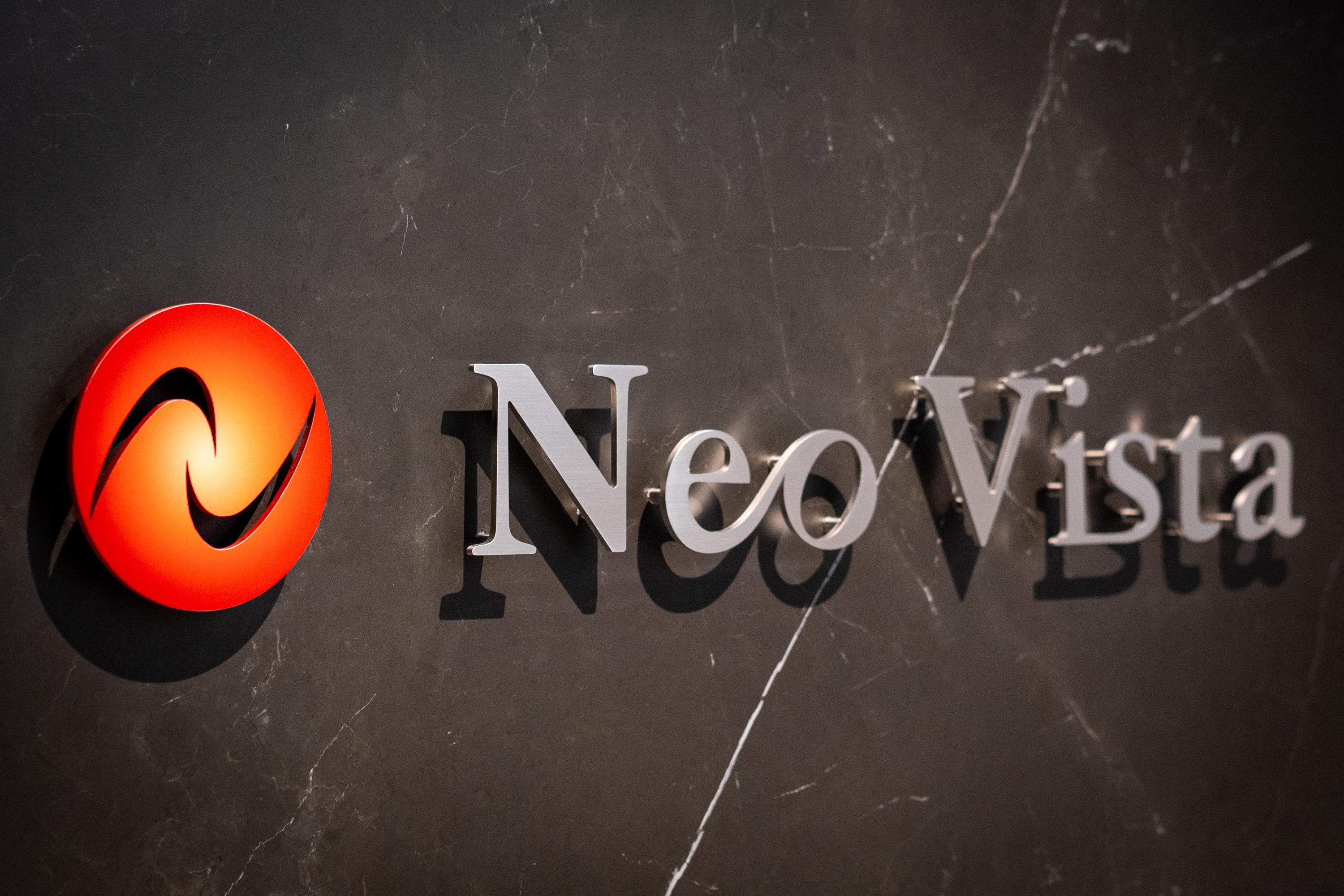ハイブリィド株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
企業のIT部門の成長を最上流から一貫して支援します
上場を目指す
企業について
“ITコーチ”という独自ポジションとベンダーフリーの中立性、グループ会社の強み
【社名の由来】
当社は中堅・中小企業の情報システム(IS)部門に対する組織機能強化を支援しており、“HiBlead”という社名の由来はIT人材(Human)の育成に貢献し情報システム(IT)× 事業・経営(Business)が融合された状態へと導く(Lead)、というコンセプトで2015年3月に設立されました。
【事業内容】
現場密着型でITコンサルティングサービス・エンジニアリングサービス・IT運用サービスを提供しています。
クライアントのIS部門に常駐し、IT戦略の立案からシステム構築の要件定義・開発・運用・保守をはじめとする、ITライフサイクルの一連のプロセスにおいて、日々発生する諸業務の実行支援やマネジメントの支援を手がけています。
【代表取締役より】
ITの利活用に対する複雑性多様性が増加し、企業のIT部門が担うべき役割は広がり、業務の難易度が高くなる中自社だけで対応することは多くの企業にとっては容易ではありません。私たちは知識や経験、何よりお客様のそばに立ち一緒に歩んでいく現場重視の志向をもってIT部門の強化に貢献していきたいと考えております。
当社は中堅・中小企業の情報システム(IS)部門に対する組織機能強化を支援しており、“HiBlead”という社名の由来はIT人材(Human)の育成に貢献し情報システム(IT)× 事業・経営(Business)が融合された状態へと導く(Lead)、というコンセプトで2015年3月に設立されました。
【事業内容】
現場密着型でITコンサルティングサービス・エンジニアリングサービス・IT運用サービスを提供しています。
クライアントのIS部門に常駐し、IT戦略の立案からシステム構築の要件定義・開発・運用・保守をはじめとする、ITライフサイクルの一連のプロセスにおいて、日々発生する諸業務の実行支援やマネジメントの支援を手がけています。
【代表取締役より】
ITの利活用に対する複雑性多様性が増加し、企業のIT部門が担うべき役割は広がり、業務の難易度が高くなる中自社だけで対応することは多くの企業にとっては容易ではありません。私たちは知識や経験、何よりお客様のそばに立ち一緒に歩んでいく現場重視の志向をもってIT部門の強化に貢献していきたいと考えております。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(6件)
PR
すべて見るインタビュー

── よくあるITコンサルティングと、ハイブリィドが提唱する「ITコーチ」の違いはどのような点にあるのでしょうか?
ITコンサルティング企業の多くは、「コンサルタントが抜けた後、支援先の企業にノウハウが残らない」という問題を抱えています。
これはなぜかというと、コンサルタントが支援先の企業に参画した後、本来ならばその企業の社員がやるべき業務を巻き取ったり、自分の持っているノウハウを教えずに独り占めにしたりするケースがよくあるからです。
これでは、情報システム部門はいつまで経っても強くなりません。ノウハウがコンサルタントにしか蓄積されていないため、コンサルタントが抜ければすぐに業務が回らなくなってしまうからです。中には、契約を継続し続けるために意図的にそう... 続きを読む
求職者の声
企業情報
会社名
ハイブリィド株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
企業の特徴
上場を目指す資本金
3億3100万円
設立年月
2015年03月
代表者氏名
代表取締役 中山 大輔
事業内容
・ITコンサルティング事業
・ITエンジニアリング事業
・ITサービスマネジメント事業
・IT人材紹介事業
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
スカイライト コンサルティング株式会社
主要取引先
・
従業員数
91人
平均年齢
42.4歳
本社住所
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町二丁目19番地23 Daiwa秋葉原ビル7階
この企業と同じ業界の企業
👋
ハイブリィド株式会社に興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- ITコンサルティング
- ハイブリィド株式会社の中途採用/求人/転職情報