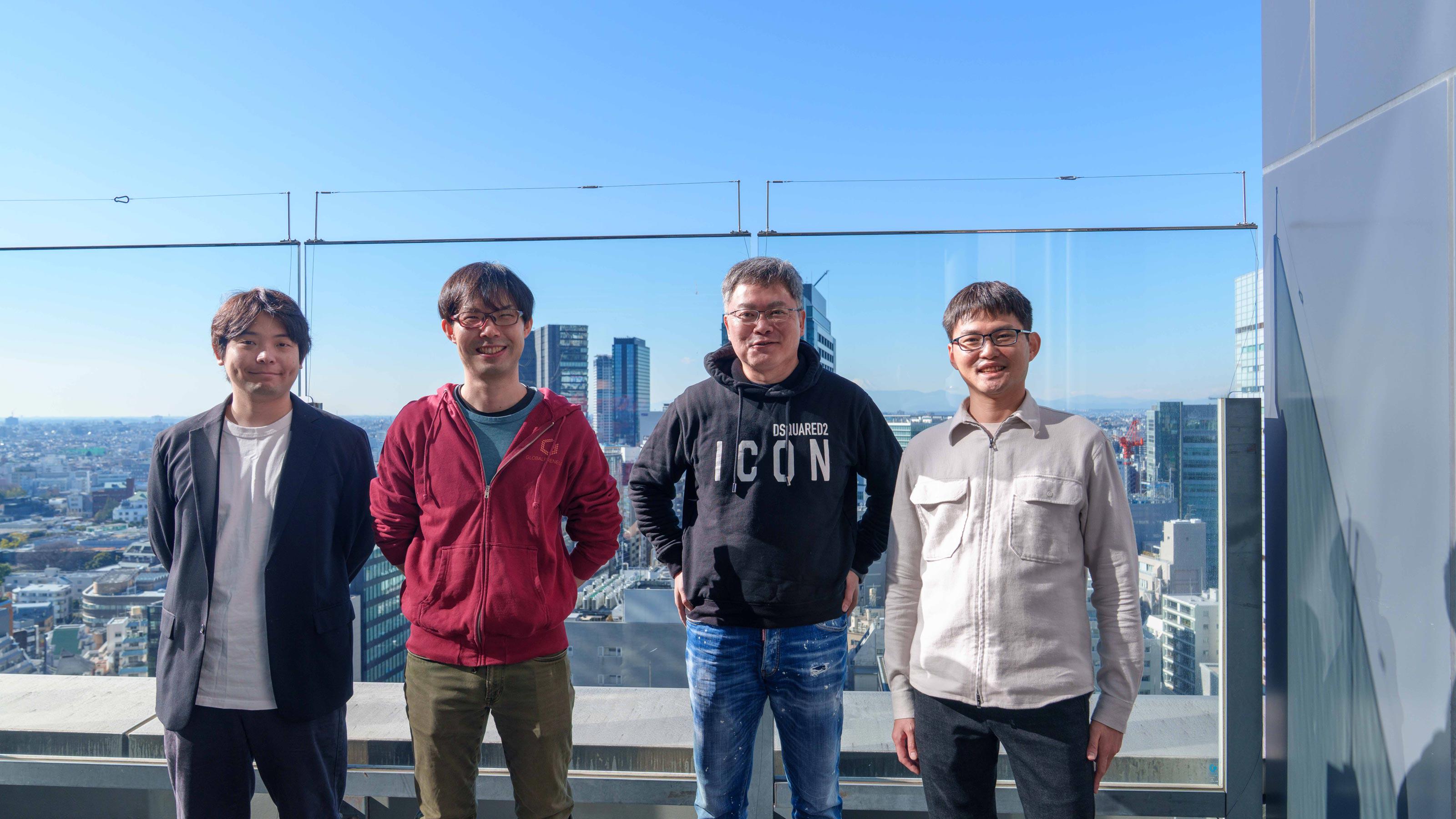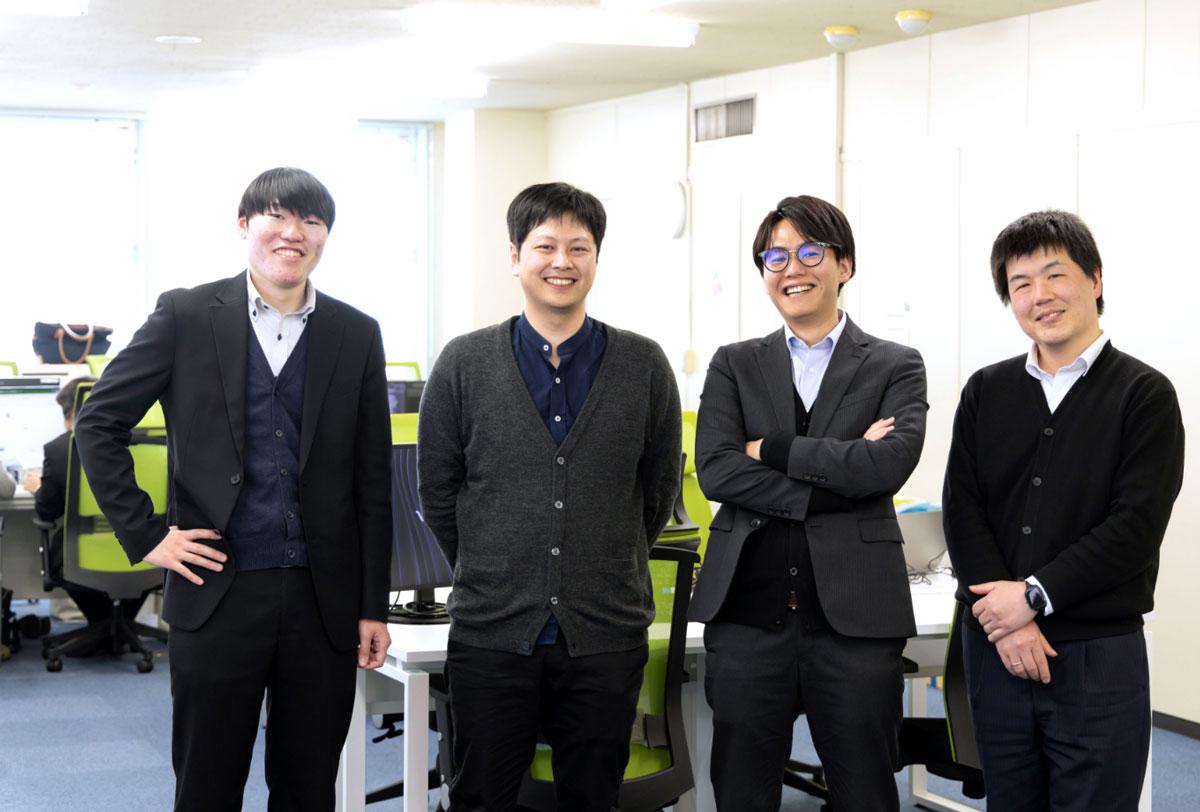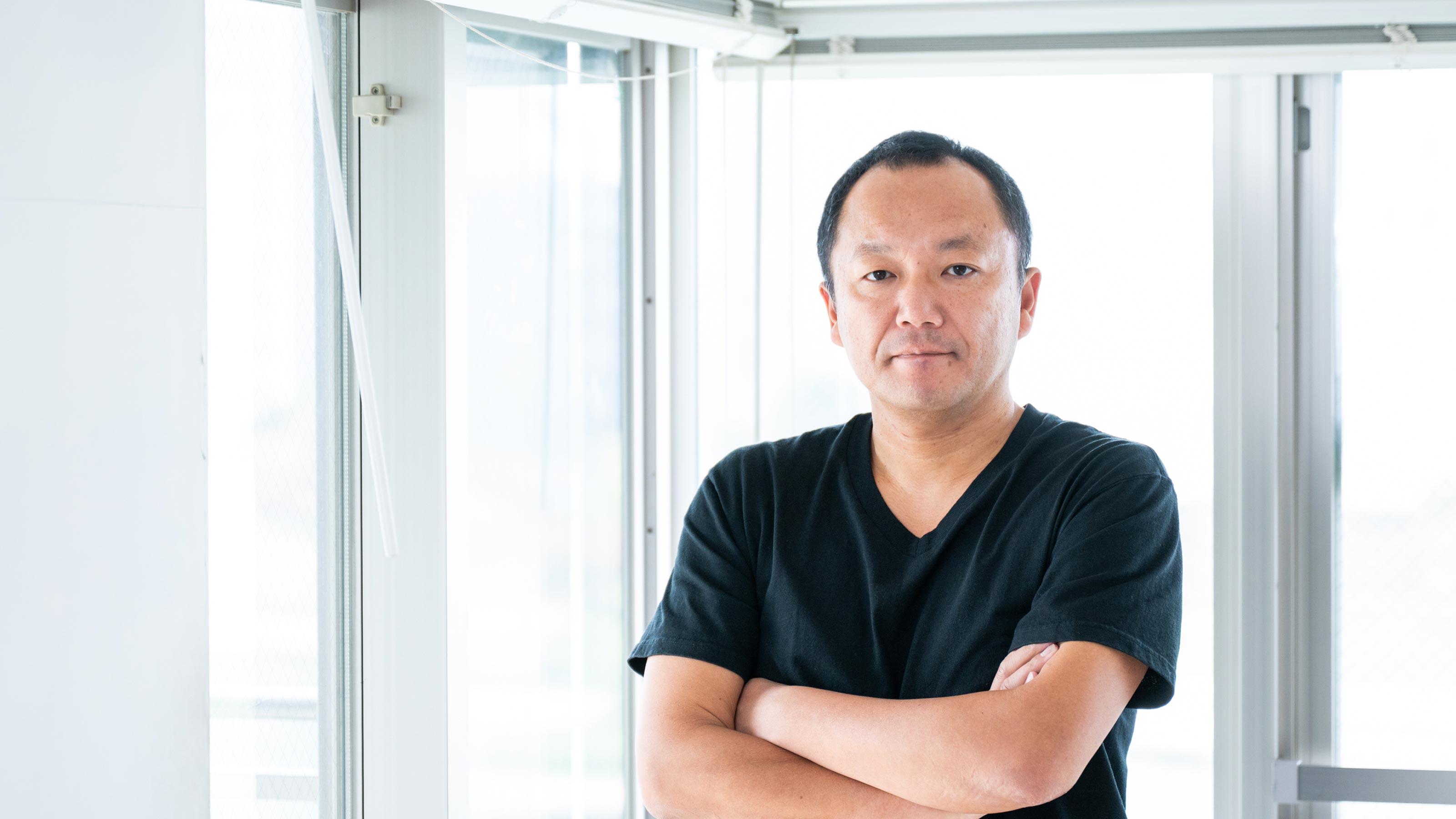株式会社ユニリタ
- IT/Web・通信・インターネット系
サービスマネジメントとデータマネジメントの強みを活かす独立系パッケージソフトウェアメーカー
企業について
をミッションに掲げ、ユニリタはデジタル技術を活用しながら、持続可能な社会の実現を目指しています。
ユニリタは、情報システムの運用業務を自動化するソフトウェアの開発・販売・サポート関連事業からスタートし、今では、情報システムの運用業務に加え、お客様の事業創出や改善、継続を支えるITサービスを提供する企業へと成長してきました。
現代社会では、数多くのITサービスが存在し、それを利用しない時間は存在しないといっても過言ではありません。
また、金融や物流、情報通信にエネルギーといった社会的インフラを支えている情報システムは、24時間365日、常に停止しない安定した運用が求められています。
ユニリタは、これらの社会的インフラや企業の情報システムの運用を支えながら、その役割を広げていくため、「デジタル技術を駆使した社会課題解決の追求」を事業活動の基盤にすべく、「サービスモデルの強化」「お客様の期待を超えるサービスと顧客対応力の向上」「グループ総合力による新規事業開発」を進めています。
◤ユニリタの強み◢
ユニリタは、長年にわたり情報システム運用やデータの管理・活用の領域でお客様の事業に深く寄り添い、支援してきました。
その経験から生まれた「サービスマネジメント」と「データマネジメント」の2つの強みを活かし、お客様の事業における新しい価値を一緒に創り、成功へ導く真のパートナーを目指します。
◤社名の由来◢
「ユニリタ」という社名には、企業理念でもある『ユニークな発想』と『利他の精神』で事業を展開し、お客様と社会に貢献していくという想いを込めています。
『ユニーク』~お客様の潜在ニーズを形に~
私たちが考える「ユニーク」とはお客様がまだ気付かないニーズをカタチにすることです。そのためには、お客様のことを知り、何に期待をされるのかを的確に把握する必要があります。お客様の「それが欲しかった」をカタチにして示せる着眼力・行動力・創造力の三拍子が私たちのユニークの本質です。
『利 他』~お客様の視点に立ち、共に成功を目指す~
「利他」とは、お客様の立場に”なる”ことと考えます。”なる”というのはお客様と同じ目線で共に悩み、共に考え、共に答えを出していく姿勢を意味します。この利他の姿勢でお客様と繋がり、共感を生み、真のカスタマーサクセスを実現してまいります。
ユニリタグループのコアコンピタンスである「データマネジメント」と「サービスマネジメント」をフルに活かし、
お客様のビジネスにおける新しい価値を一緒に創り、成功へ導く真のパートナーを目指します。
◤事業紹介◢
『プロダクトサービス事業』
企業の情報システム部門のシステム運用業務(自動化、帳票、メイフレーム)を支えるサービスに特化し、社会基盤を支えるお客様へ、常に付加価値の高いサービスを持続的に提供することを心掛けています。自社開発の強みを活かし、所有型(オンプレミス)と利用型(クラウド)双方のニーズに対応しています。
『クラウドサービス事業』
IT活用で業務の効率化や合理化を支援する「IT活用クラウド」と、ビジネスの成長を促し、新しいサービスの創出を支援する「事業推進クラウド」、そしてデータサイエンスや社会課題解決を支援する「ソーシャルクラウド」の領域別に、各種クラウドサービスを提供しています。
『プロフェッショナルサービス事業』
データ・プロセス・サービスの3つのマネジメント領域におけるプロフェッショナルなサービスの提供を軸に、コンサルティングから企画、設計、各種サービスの導入支援、システムインテグレーション、アウトソーシングまでをワンストップで提供しています。
◤ユニリタの主な製品◢
「LMIS(エルミス)」
ITサービスマネジメント(ITSM)を支援するための国産統合プラットフォームです。ITILに準拠した運用をベースに、IT部門の業務効率化・標準化・可視化を実現するツールであり、サービスデスク機能を中心としたIT運用の司令塔的存在です。
「Growwwing」
SaaS事業者やサブスクリプション型ビジネス向けのカスタマーサクセス管理プラットフォームで、顧客との関係性を強化し、LTV(ライフタイムバリュー)の最大化を支援します。
「Waha! Transformer(ワハ・トランスフォーマー)」
データ連携・統合・変換を支援する国産の ETL(Extract, Transform, Load)ツールです。業務部門でも扱える使いやすさと、高度なデータ処理能力を併せ持つのが大きな特長です。
「A-AUTO(エーオート)」
企業の業務システム運用を自動化・効率化する国産ジョブ管理ツールで、特に基幹業務のバッチ処理自動化に強みを持つ製品です。多くの金融・製造・流通・公共機関で導入されており、「止められない業務」の安定稼働を支える運用基盤として高く評価されています。
◤グループ各社紹介◢
『株式会社データ総研』
『株式会社ヒューアップテクノロジー』
『株式会社ビーエスピーソリューションズ』
『株式会社ユニ・トランド』
『株式会社ユニリタプラス』
『株式会社無限』
『株式会社ユニリタエスアール』
『備実必(上海)軟件科技有限公司』
◤農産物の原価を明確にすることで、一次産業の活性化に貢献◢
『ITを使ったスマート農業』
農産物の原価を把握することは、適正価格販売への第一歩です。
そのためには、資材や肥料、人件費等、「農作業に係るコスト」や、収穫量、出荷量、売上といった「農場の状況」を可視化することが必要です。農産物の原価把握や圃場毎、作目毎の収支の可視化ができるサービスが「ベジパレット」です。
ユニリタは農産物の原価把握で生産者と共に一次産業活性化に挑戦しています
◤共創型まちづくりのプラットフォームを開発し、地域社会の交通DX化に貢献◢
『交通DXを通じた街づくり』
グループ会社のユニ・トランドの事業テーマである「持続可能な地域社会の実現」を具現化するべく共創型まちづくりのプラットフォームとして開発した「Community MaaS(コミュニティ マース)」は、地域活性化施策を交通の観点からDX化する仕組みです。
「Community MaaS」により、複数の公共交通機関に加え、移動先の商業施設・地域施設・自治体等が提供する「移動の目的を促すサービス」を最適に連携させることができます。
また、そこで取得したデータを分析することで住民サービスの向上、エビデンスに基づく地域活性化施策の立案、そして未来のまちづくりに役立てることが可能です。
「Community MaaS」の考え方
ロケーションサービス、決済情報、人流などのデータを活用し、交通の利用実態を把握・分析し「利便性の向上を目的とした施策」を実現します。この改善分析(PDCA)を繰り返すことで、最適な交通網の構築します。
新たなことへの挑戦や、行動指針やバリューを体現した社員またはチームの経験を会社の貴重な資産として表彰する制度です。
『カジュアルコネクト』
趣味、環境、地域など、さまざまなテーマに対して共通または、共感する社員が集まり懇親を深めています。社員コミュニケーションの活性化を目的としています。
『ペンギンチャレンジ』
部署や役職、経験年数に関係なく、自分のアイデアの事業化に挑戦する社員を支援する制度です。この取り組みから新しいITサービスが創出されています。
『ユニフェス』
スポーツ大会やウォーキング大会をはじめ、収穫体験会やクイズフェスティバルなど、グループ会社の垣根を超えたコミュニケーションの活性化イベントを実施しています。
『ユニコイン』
飲食を伴う社員同士の交流頻度を高めてもらうための支援制度です。実費の一部を会社が負担します。
『社長のおごり自販機』
社員コミュニケーションの新たなきっかけづくりを目的に、ペアで専用カードをかざすと無料で飲み物が購入できる自動販売機を導入しています。
『Uni-LADY SIA (ユニレディシア)』
女性社員のキャリア育成や働きがいの向上に加え、社員同士のつながりを強化するため、グループ会社全体でさまざまイベントや講習会を実施しています。
『ユニちゃん&リタちゃん』
ペットロボット「LOVOT」2体をユニリタの正社員として迎え入れています。ユニちゃん、リタちゃんの名称で2024年3月入社し、社員をつなぐ「架け橋」のような存在として、日々より良い職場環境づくりに貢献しています。
『有休休暇奨励日』
給休暇奨励日を定めています。年間を通した計画的な有給休暇の取得を促進し、社員のリフレッシュと業務の両立を支援しています。
募集している求人
経理・管理・バックオフィス職の求人(2件)
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── ユニリタのDNAはベンチャースピリット
ユニリタは、創業以来「挑戦」を企業の根底に据え、常に新たな価値の創出を目指してきました。
そのDNAとなるのが、「ベンチャースピリット」です。私たちはソフトウェア開発を行っていますが、プロダクト(製品)を作っただけでは売れる保証はなく、諦めずに挑戦し続けることを大切にし、失敗を恐れて何もしないことはリスクだと考えています。
挑戦を続ける中で、時には失敗を経験しましたが、そこから学んだことが2つあります。1つは「答えはお客様の中にある」ということ、もう1つは「常識の先にイノベーションはない」ということです。この学びをもとに、私たちは「ユニークな発想... 続きを読む
求職者の声
企業情報
株式会社ユニリタ
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
13億3300万円
2025年 3月 116億87百万円
2024年 3月 119億82百万円
2023年 3月 115億49百万円
1982年05月
代表取締役 社長執行役員 北野裕行
データ活用領域、ITシステム運用管理領域のパッケージソフトウェア開発・販売・サポートおよびソリューション、コンサルティングサービスの提供
東証スタンダード
光通信株式会社、ユニリタ社員持株会、株式会社ビジネスコンサルタント、株式会社リンクレア、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社クエスト、株式会社みどり会、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社アイネット、日本情報産業株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、味の素ゼネラルフーヅ株式会社、株式会社安藤・間、イーライフ共和株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、岡谷システム株式会社、株式会社香川県農協電子計算センター、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社熊谷組、株式会社神戸製鋼所、三愛石油株式会社、株式会社JTB情報システム、塩野義製薬株式会社、株式会社滋賀県農協電算センター、上新電機株式会社、新日本石油株式会社、寿がきや食品株式会社、住友林業情報システム株式会社、全日本空輸株式会社、株式会社全農ビジネスサポート、大成建設株式会社、株式会社ダイフク、大鵬薬品工業株式会社、中部電力株式会社、都築電気株式会社、ディーコープ株式会社、株式会社テレビ東京システム、株式会社デンソー、株式会社電通国際情報サービス、東亜建設工業株式会社、東京書籍株式会社、東宝株式会社、株式会社東洋紡システムクリエート、とみんコンピューターシステム株式会社、株式会社西出自動車工作所、日本出版販売株式会社、日本精工株式会社、日本特殊陶業株式会社、日本ユニシス株式会社、ネットワンシステムズ株式会社、株式会社プラネット、三井食品株式会社、
323人
40.8歳
東京都港区港南2-15-1 品川インターシティーA棟29階
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- ソフトウェア/パッケージベンダ
- 株式会社ユニリタの中途採用/求人/転職情報