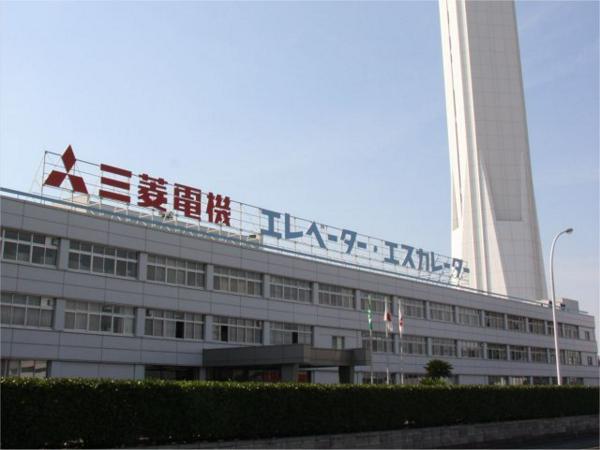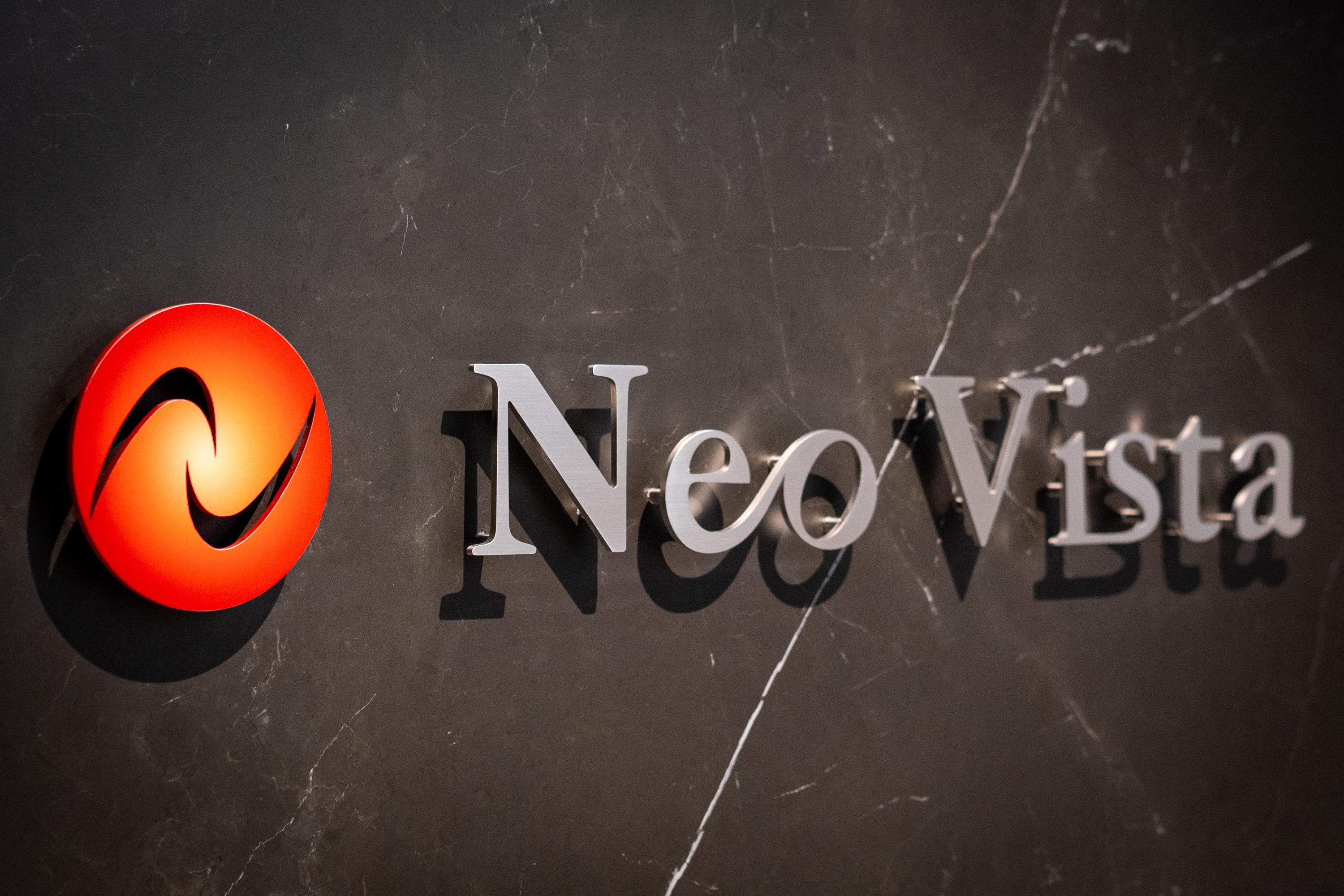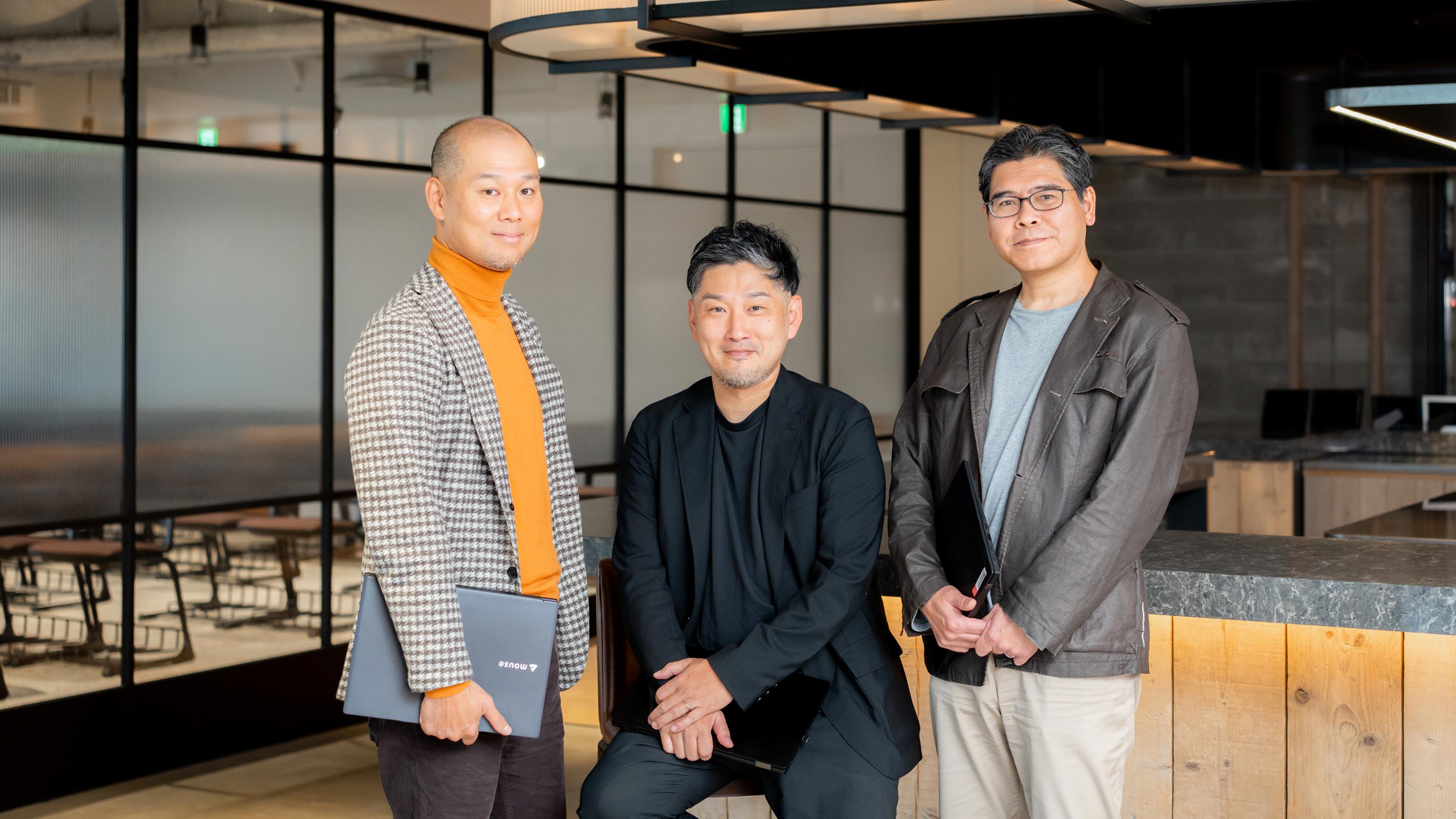株式会社ガウス
- IT/Web・通信・インターネット系
多業種のソフトウェア開発×総合電機メーカーのビルエンジニアリングのシナジー効果で成長中!
企業について
同社が設立されたきっかけは、初代や先代の社長を中心としたエンジニア有志が、自己研鑽と視野の拡大を目的に開催した勉強会に遡る。学校会計システムを研究テーマとして取り上げ、学校会計の第一人者である先生や、女子大の顧問会計士、学校の先生等を交えて意見交換を行い、研究の成果として教務・学務システムを開発した。そのシステムをいくつかの学校法人に展開したところ、非常に高い評価を獲得し、学校法人システムに大きな可能性を感じたことから、本格的に事業化することを決意して会社を設立したという。
設立当時はまだ世の中にPC(個人用のコンピュータ)はなく、学校のバックヤード業務もアナログが基本だった。学校法人システムの分野においては、パイオニア的な存在といえる。設立以降は、学校向けに会計・学籍・教職員管理・入試・図書等の事務システムを軸に展開し、さらに、小売の物流・店舗システムや商社の在庫管理等、様々な業界のソフトウェア開発を手掛けながら事業の裾野を拡大してきた。
総合電機メーカーグループが資本参加した1989(平成元)年からは、グループが製品・サービスを提供するビルのエンジニアリング(セキュリティシステム・管理システム・省エネシステム等の初期提案・設計・製造・保守・製品プロモーション)を手掛け、ソフトウェア開発事業とビルエンジニアリング事業、及び両事業のシナジー効果による統合ソリューション事業を展開する現在の原型がつくられた。
同社の特徴・強みは、変幻自在の業務形態だ。システム業務の川上から川下まで一貫して手掛け、「受注開発」「自社開発」「顧客支援」といった多種多様な業務形態を兼ねている。100名規模の組織でありながら、ソフトウェア開発ができて、総合電機メーカー品質のエンジニアリングも対応できるシステム会社はそう多くはないだろう。
現在の売上比率は、総合電機メーカーグループ関連が約45%を占め、残る55%はSES関連・学校関連・流通関連等で占められている。学校分野のスペシャリストとしてスタートした同社は、今では総合システムソリューション企業として変貌を遂げている。
例えば、同社が展開するソリューション製品の一つに、ビル管理システムと連動した出退勤時刻管理クラウドサービス『りれとる』が挙げられる。今後はエンドユーザーの要望を取り入れながら、機能のバリエーションを増やす提案を積極的に行い、自社製品の開発および総合電機メーカーグループの販売網を使った外販を強化する。これを実現するためには、ソフトウェア開発とエンジニアリングのさらなる結びつき強化が欠かせない。
また、同社が設立当初から手掛ける学校法人分野のシステム開発も、改めてテコ入れするという。IT活用が遅れている学校法人をはじめ、福祉・介護施設やカルチャーセンター等、管理スキームが近い文教系に視野を広げてアプローチする計画だ。
こうした事業展開のエンジンになるのは、言うまでもなく人材の力である。同社では現在、ソフトウェア開発とエンジニアリングの結びつきを担う中堅エンジニアの拡充を注力ポイントとして挙げている。牛山氏は同社で活躍できる人物像について、次のように述べている。
「まず何か一つを突き詰めるというよりも、幅広い分野に携わってみたいと考えている人の方が、多方面にチャレンジしようとする当社には適していると思います。PC系・Web系・スマートフォンやタブレット・クラウド・インフラ等、手を挙げれば新しい分野にもチャレンジできる機会が豊富にあります。また、希望すれば、フィールドをソフトウェア開発から、総合電機メーカーグループのエンジニアリングに移すことも可能です」(牛山氏)
同社は設立以降、エンドユーザーの業務に寄り添ったシステム開発事業で成長してきた。
「ヒューマンスキルや経営・ビジネス・会計等の強みを活かし、エンドユーザー等、多くの人々とコミュニケーションを取りながら、ものづくりがしたい方にも良い環境ではないでしょうか。当社は直取引が大部分を占めているので、“誰のためにシステムをつくっているのか”というジレンマは一切ないはずです」(牛山氏)
社内イベントも盛んな同社では、あらゆる部署の社員・得意先が一緒になって行う「釣りイベント」が恒例行事になっているそうだ。年に1回は品川の公園でBBQパーティを開いており、家族ぐるみで楽しんでいる。色々な人と交流・コミュニケーションを取るのが好きな人であれば、中途入社であってもすぐに仲間の輪に入っていけるはずだ。
さらに驚くべきことに、過去10年間の新卒社員の3年定着率は90%を超えているとか。思ったことは気兼ねなく言い合い、困りごとや悩みごとを気軽に相談できる人間関係が功を奏したのだろう。
ワークライフバランスを確立できる就労環境も魅力だ。有給休暇の取得率は非常に高く、残業も平均すれば月20時間を切っている。女性社員は全体の1割を占め、産休・育休を取得し、復帰後は時短勤務で働いている女性エンジニアも数人いる。一方、男性社員の育休取得実績もある。総合電機メーカーグループの一員として、コンプライアンス遵守や、時代が求める働き方に敏感であることも、一人ひとりのキャリア設計に合わせ、柔軟に働き方を実現できる要因として挙げられるだろう。
多様な働き方ができる理由の一つとして、常駐開発よりも、圧倒的に自社内開発の比率が高いことが挙げられる。なぜなら、顧客の事情に合わせがちな常駐開発と比べれば、自社内開発は人員体制・タスク・スケジュールも格段に柔軟性を持って組み立てられるからだ。
仕事と家庭のバランスを取りながら働きたいエンジニアにとっては絶好の環境。さらには多彩なキャリアを描けるチャンスがあることから、長期スパンで自分の将来像を描ける会社だと言っていいだろう。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)
PR
すべて見る企業情報
株式会社ガウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
9900万円
2024年 3月 8.2億円
2023年 3月 8.0億円
2022年 3月 7.5億円
1978年12月
代表取締役 牛山正弘
コンサルティングソリューション
・情報システムに関するコンサルティングサービス
・ネットワークに関するコンサルティングサービス
・サーバー等機器に関するコンサルティングサービス
・運用に関するコンサルティングサービス
パッケージソリューション
・学校総合事務システム
会計システム、管財システム、入試システム
学籍システム、図書システム、人事・給与システム
・指紋認証・パスワード管理システム
ビル管理ソリューション
・ビル管理システム、セキュリティシステム
・テナント課金システム、ビル内監視・制御システム
・エレベータ監視・制御システム、マンション管理システム
流通・小売ソリューション
・スマホ・タブレットによる買物支援システム
・スーパーマーケット新店舗開発支援システム
・販売在庫管理システム
・会計システム
金融ソリューション
・クレジットカード決済システム
・保険会社向けシステム開発
・証券会社向けシステム開発
・銀行向けシステム開発
官公庁ソリューション
・人事管理システム
・健康情報・福祉情報関連システム
非上場
亀山製絲株式会社 三菱電機ビルソリューションズ株式会社
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 三菱電機株式会社 三菱電機グループ各社 学校法人 ソフトウェア開発会社
100人
41.7歳
東京都千代田区二番町4番地3 二番町カシュービル2F
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- ITコンサルティング
- 株式会社ガウスの中途採用/求人/転職情報