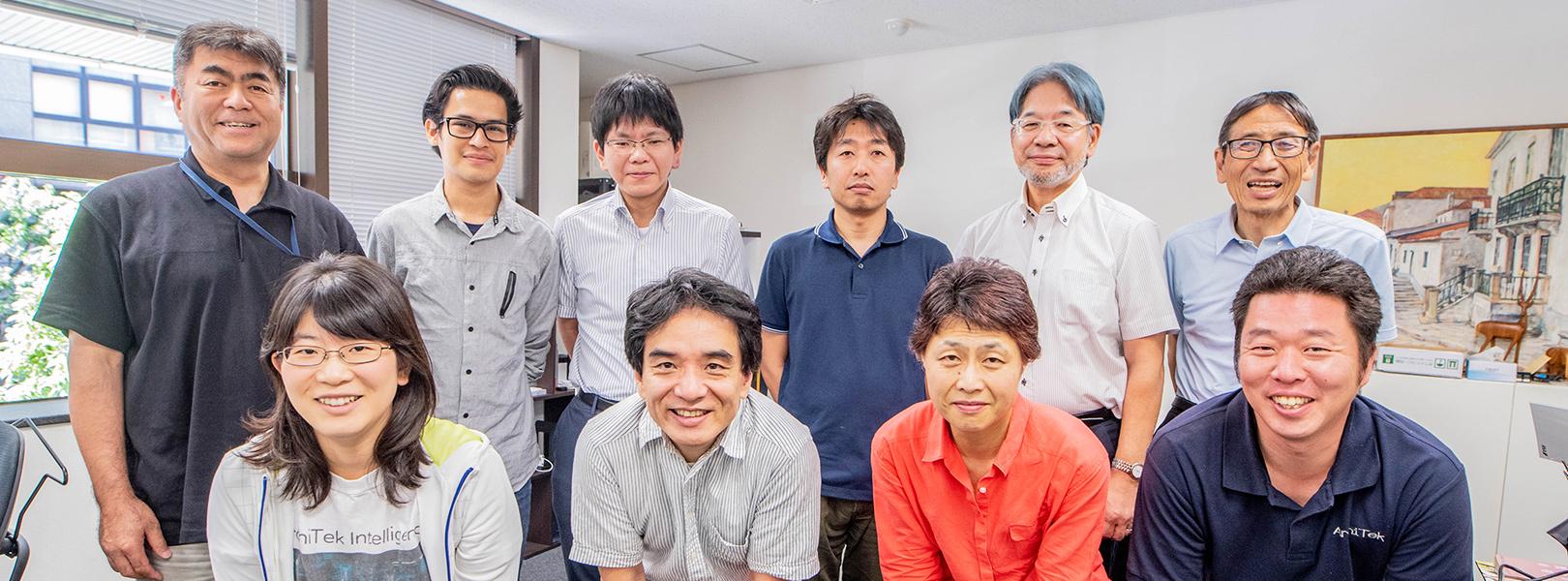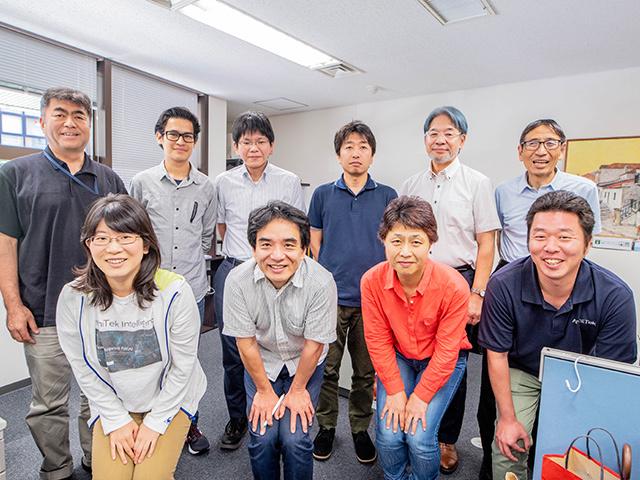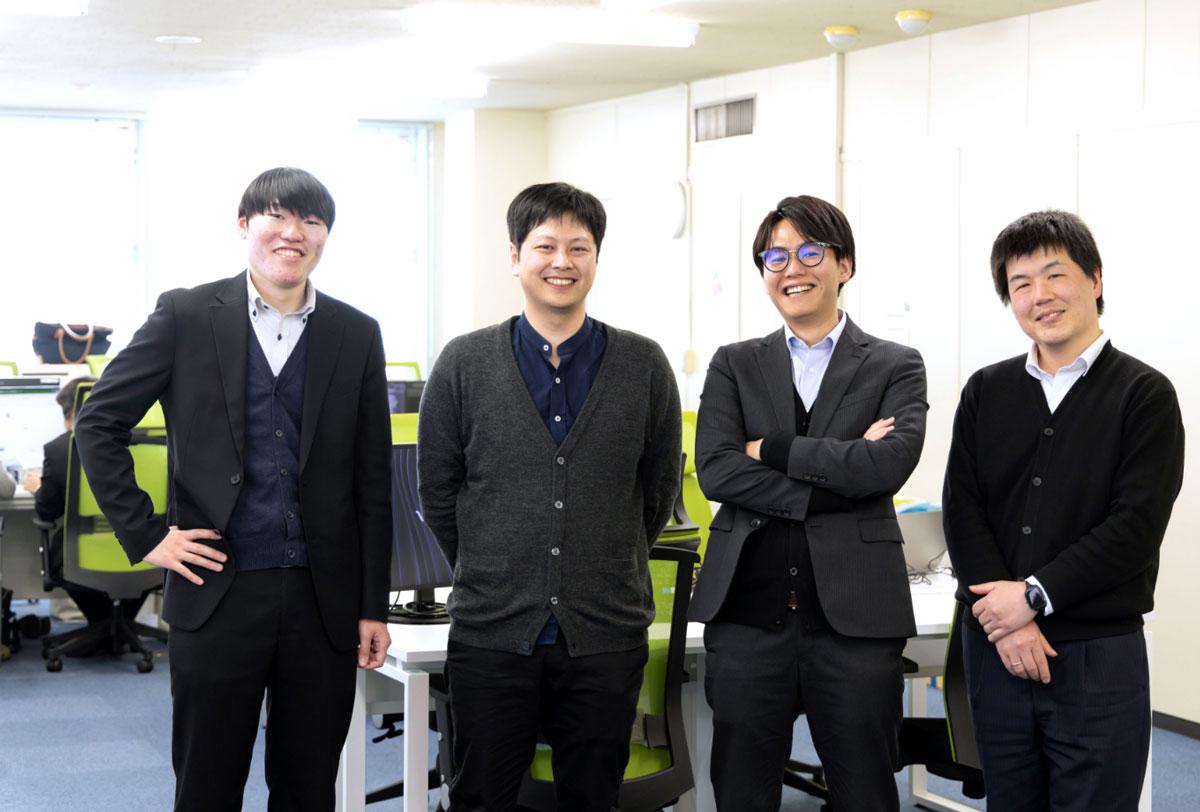ArchiTek株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
独自アーキテクチャによる日本発半導体を世界に発信するベンチャー企業
上場を目指す
自社サービス製品あり
グローバルに活動
企業について
本格的なIoT時代に不可欠な世界初のエッジ・プロセッサを開発
我々の身近にある、あらゆるものがインターネットに接続されるIoT。しかしその実現には、データ処理にこれまでにない程のスピーディさと省電力性が求められるため、現在主流のクラウド・コンピューティングでは対応することが出来ないと言われている。今後本格的なIoT時代を迎えるにあたって期待されるのは、IoTデバイスが生成するデータを、デバイス自体またはデバイス付近のローカルサーバーで処理するエッジ・コンピューティングだ。
そのエッジ・コンピューティング時代の到来を視野に、エッジ・デバイスの頭脳とも言うべき半導体回路『aIPE(ArchiTek Intelligence Pixel Engine)』を独自アーキテクチャに基づいて開発しているのがArchiTek株式会社(アーキテック)である。代表取締役・高田周一氏をはじめ、大手電機メーカーや半導体メーカー出身の半導体技術者らで構成されたベンチャー企業だ。
『aIPE』は、仮想エンジン技術を使用して革新的なソフトウェアの柔軟性と、低消費電力や低レイテンシのために最適化されたカスタムハードウェアを組み合わせた、プログラマブル、画像処理、AI専用のエンジンである。デバイスのイメージセンサーと繋ぐことで、デバイス側で画像を解析し、画像に映るモノの種類や数、モノとの距離等を判断して処理することを可能とする。自動車の自動運転やドローン、介護施設や独居高齢者宅における見守り・ヘルスケア、ファクトリーオートメーション、物流等、我々の生活におけるあらゆる用途が見込まれている。
現在、これらの用途で用いられている半導体回路はGPU(Graphics Processing Unit)やCPU(Central Processing Unit)、またはある用途に特化した専用LSIである。ただし、本格的なIoT時代に向けてはそれぞれに課題が存在している。GPUとCPUは回路が大規模であるため、大量のデータを処理することには長けているものの、導入コストが高い上に消費電力が大きい。特にGPUはサーバー側でビッグデータを高速で処理するため、電力消費量の大きさがネックとなっている。一方、専用LSIは、用途を限定することで消費電力とコストを抑えてはいるものの、限定されているが故に柔軟性がない。環境が変わればLSIも作り直す必要がある。
そういった既存のソリューションが持つ課題を解決するのが、あらゆるエッジ・デバイスに組み込まれる世界初のエッジ・プロセッサ『aIPE』だ。GPUやCPUよりもデバイスのサイズは小さく、コストや消費電力が低い。FPGAを使ったシミュレーションでは、世界トップメーカー製のGPUとの比較で、コスト1/10、消費電力1/20、処理スピード2倍から10倍と圧倒的な数値を得ている。電気自動車の自動運転に不可欠なSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)も、現在は高電力を使うためサーバー側で処理しているが、エッジ側での処理が可能となる。
同時に専用LSIにはない柔軟性も備えている。小さな部品を動的に組み替えて様々なアルゴリズムに柔軟に対応するため、アプリケーションを自由にプログラムすることが可能だ。さらに複数のアルゴリズムを同時に実行するため、画像の生データをリアルタイムに加工することが出来る。高齢者の見守り等ではカメラで撮影した生の画像を送るのではなく、リアルタイムで抽象化したデータとして送ることが出来るためセキュリティを確保することも可能だ。
そのエッジ・コンピューティング時代の到来を視野に、エッジ・デバイスの頭脳とも言うべき半導体回路『aIPE(ArchiTek Intelligence Pixel Engine)』を独自アーキテクチャに基づいて開発しているのがArchiTek株式会社(アーキテック)である。代表取締役・高田周一氏をはじめ、大手電機メーカーや半導体メーカー出身の半導体技術者らで構成されたベンチャー企業だ。
『aIPE』は、仮想エンジン技術を使用して革新的なソフトウェアの柔軟性と、低消費電力や低レイテンシのために最適化されたカスタムハードウェアを組み合わせた、プログラマブル、画像処理、AI専用のエンジンである。デバイスのイメージセンサーと繋ぐことで、デバイス側で画像を解析し、画像に映るモノの種類や数、モノとの距離等を判断して処理することを可能とする。自動車の自動運転やドローン、介護施設や独居高齢者宅における見守り・ヘルスケア、ファクトリーオートメーション、物流等、我々の生活におけるあらゆる用途が見込まれている。
現在、これらの用途で用いられている半導体回路はGPU(Graphics Processing Unit)やCPU(Central Processing Unit)、またはある用途に特化した専用LSIである。ただし、本格的なIoT時代に向けてはそれぞれに課題が存在している。GPUとCPUは回路が大規模であるため、大量のデータを処理することには長けているものの、導入コストが高い上に消費電力が大きい。特にGPUはサーバー側でビッグデータを高速で処理するため、電力消費量の大きさがネックとなっている。一方、専用LSIは、用途を限定することで消費電力とコストを抑えてはいるものの、限定されているが故に柔軟性がない。環境が変わればLSIも作り直す必要がある。
そういった既存のソリューションが持つ課題を解決するのが、あらゆるエッジ・デバイスに組み込まれる世界初のエッジ・プロセッサ『aIPE』だ。GPUやCPUよりもデバイスのサイズは小さく、コストや消費電力が低い。FPGAを使ったシミュレーションでは、世界トップメーカー製のGPUとの比較で、コスト1/10、消費電力1/20、処理スピード2倍から10倍と圧倒的な数値を得ている。電気自動車の自動運転に不可欠なSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)も、現在は高電力を使うためサーバー側で処理しているが、エッジ側での処理が可能となる。
同時に専用LSIにはない柔軟性も備えている。小さな部品を動的に組み替えて様々なアルゴリズムに柔軟に対応するため、アプリケーションを自由にプログラムすることが可能だ。さらに複数のアルゴリズムを同時に実行するため、画像の生データをリアルタイムに加工することが出来る。高齢者の見守り等ではカメラで撮影した生の画像を送るのではなく、リアルタイムで抽象化したデータとして送ることが出来るためセキュリティを確保することも可能だ。
世界に先駆けた独自のアーキテクチャで業界に価格破壊を起こす
『aIPE』のようにAIと画像処理をコンパクトかつ低消費電力で行う半導体回路は、同社の他にはまだ開発例がない。世界に先駆けてArchiTek社が独自に開発しているデバイスなのである。その革新性や技術力の高さは各所で認められており、2018年には国立研究開発法人の委託事業に採択。現在、他業種企業との3社共同で「進化型・低消費電力AIエッジLSIの研究開発」に取り組み、2020年明けには試作LSIをリリースする予定だ。
また国立研究開発法人の採択プロジェクトとは別に、独自開発によって1個あたりワンコイン相当の超低価格水準を目標とし、超低消費電力、極小サイズのLSI開発にも取り組む。こちらは2020年夏のサンプルリリースを目指しており、実用化されればIoT向けLSIに価格破壊を起こし、世界中のエッジデバイスに同社のLSIが組み込まれることも夢ではなくなり、業界地図も大きく塗り替えられることとなる。
同社は2011年9月、高田氏が創業した会社だ。高田氏は1989年、大手電機メーカーに入社。R&D部門で、家電製品やゲーム機器、携帯電話等、様々なデジタル機器の画像を扱うための回路設計に携わっていた。その中で大企業故に果たすことが困難な技術者としての思いを実現するために独立を決意。以来、“世界のより良いくらしと社会の発展に貢献する”“破壊と創造”といったビジョンのもと、独自に設計する論理回路を販売するIPビジネスを志向し続けてきた。事業を継続するため受託に移行した時期もあったが、2015年、公益財団法人の助成金交付プロジェクトに選定された頃から本来の目的に向けた活動に集中できる環境が整い始めた。
2017年1月には国立研究開発法人の「研究開発型ベンチャー支援事業 」に採択、さらに2018年10月には同委託事業に採択され現在を迎えている。この間、技術者だけではなく、金融機関でIPO支援等に従事してきた取締役CFO・藤中達也氏、高田氏と同じ電機メーカ出身の取締役CMO・黒田剛毅氏等を迎え入れ、資金調達やマーケティング等、ビジネスサイドの体制も整備。ベンチャーキャピタルからの出資を受け、2018年3月、第2創業と位置付けて採用活動にも注力する等、本格的な事業展開をスタートさせるに至ったのである。
『aIPE』が正式にリリースされれば、様々なデバイスに組み込まれ世界に広がっていくことになる。シリコンバレーに常駐する外部技術顧問等のネットワークを使って世界中に販売していく計画もある。だが、それに以上に同社が注目しているのが、『aIPE』の上で動くソフトウェアの開発だ。
「チップ価格を100として、ソフトウェア価格が30の水準にしたとしても、サブスクリプション型なら利益の上積みが見込めます。『aIPE』を水のように世界中に広め、ソフトウェア開発で一気に成長したいと考えています」(高田氏)。
また国立研究開発法人の採択プロジェクトとは別に、独自開発によって1個あたりワンコイン相当の超低価格水準を目標とし、超低消費電力、極小サイズのLSI開発にも取り組む。こちらは2020年夏のサンプルリリースを目指しており、実用化されればIoT向けLSIに価格破壊を起こし、世界中のエッジデバイスに同社のLSIが組み込まれることも夢ではなくなり、業界地図も大きく塗り替えられることとなる。
同社は2011年9月、高田氏が創業した会社だ。高田氏は1989年、大手電機メーカーに入社。R&D部門で、家電製品やゲーム機器、携帯電話等、様々なデジタル機器の画像を扱うための回路設計に携わっていた。その中で大企業故に果たすことが困難な技術者としての思いを実現するために独立を決意。以来、“世界のより良いくらしと社会の発展に貢献する”“破壊と創造”といったビジョンのもと、独自に設計する論理回路を販売するIPビジネスを志向し続けてきた。事業を継続するため受託に移行した時期もあったが、2015年、公益財団法人の助成金交付プロジェクトに選定された頃から本来の目的に向けた活動に集中できる環境が整い始めた。
2017年1月には国立研究開発法人の「研究開発型ベンチャー支援事業 」に採択、さらに2018年10月には同委託事業に採択され現在を迎えている。この間、技術者だけではなく、金融機関でIPO支援等に従事してきた取締役CFO・藤中達也氏、高田氏と同じ電機メーカ出身の取締役CMO・黒田剛毅氏等を迎え入れ、資金調達やマーケティング等、ビジネスサイドの体制も整備。ベンチャーキャピタルからの出資を受け、2018年3月、第2創業と位置付けて採用活動にも注力する等、本格的な事業展開をスタートさせるに至ったのである。
『aIPE』が正式にリリースされれば、様々なデバイスに組み込まれ世界に広がっていくことになる。シリコンバレーに常駐する外部技術顧問等のネットワークを使って世界中に販売していく計画もある。だが、それに以上に同社が注目しているのが、『aIPE』の上で動くソフトウェアの開発だ。
「チップ価格を100として、ソフトウェア価格が30の水準にしたとしても、サブスクリプション型なら利益の上積みが見込めます。『aIPE』を水のように世界中に広め、ソフトウェア開発で一気に成長したいと考えています」(高田氏)。
“破壊と創造”を共有する技術者が結集し日本発半導体を世界に発信
本格的なビジネス展開を控える現在の課題は、ソフトウェアエンジニアの確保だ。ハードウェアエンジニアは、家電メーカーや半導体メーカーで経験を積んだベテランと中堅が「日本発の半導体を世界に発信したい」という想いを持って集まっている。社員数14名(2019年9月現在)のうち、12名が高田氏を含むエンジニアだが、2/3がハードウェア技術者だ。
「ハードウェアのメリットを引き出すにはソフトウェアが重要です。ソフトウェアの分野は多様化されているので、ハードウェアエンジニアに対して3倍か4倍ぐらいのリソースが必要です。コンパイラーエンジニアを含めて、ソフトウェアエンジニアの層を厚くしたいと考えています」(藤中氏)。
特に同社が求めているのは、ミドルウェアやデバイスと直接やりとりするドライバの開発を担うエンジニアだ。組込み、IoT、AI等の、ハードウェアの知識も併せ持ったエンジニアだ。
「特に弊社の『aIPE』は独自のアーキテクチャですので、その仕組みを理解できる方が必要です。アーキテクチャに見識があり、ないものを作っていくことに対して積極的に取り組めるチャレンジャブルな方に期待しています。また、性能が良いとされるものは、シンプルで美しいアーキテクチャを持っています。そういった技術を突き詰めたい、またはそれが出来る技術者を求めています」(黒田氏)。
ハードウェアエンジニアを含め、同社には個々に尖ったスキルを持った技術者が集まる。高田氏が掲げる“破壊と創造”というスローガンを共有し、世の中にない、新しいものを生み出すことに価値を見いだすエンジニア集団である。ソフトウェアのエンジニアも、個性的なバックボーンを持ったエンジニアが集まる。台湾出身で言語処理系のスペシャリスト、ホンジュラスから日本の技術を学びに来ている若いエンジニア等、国際色も豊かだ。そういったエンジニアがそれぞれの役割を自発的に果たし、研鑽し合いながら、独自の技術で世界に打って出ようとしている。今ならまだその一員として世界を変える瞬間に立ち会えるチャンスが残されている。それが今、同社に参画する最大の魅力だろう。
拠点は大阪本社と東京支店の2拠点だが、リモートワークも可能な制度が整っており、実績もある。他には、フレックス制を採用する等、エンジニアが働きやすいよう柔軟な制度を取り入れ、「日本発の半導体を世界に発信する」という目標に集中して取り組める環境を整えている。同社に関わる人々と同じ想い、価値観を共有出来るエンジニアなら、年齢、性別、国籍等に関わらず活躍できることだろう。
「ハードウェアのメリットを引き出すにはソフトウェアが重要です。ソフトウェアの分野は多様化されているので、ハードウェアエンジニアに対して3倍か4倍ぐらいのリソースが必要です。コンパイラーエンジニアを含めて、ソフトウェアエンジニアの層を厚くしたいと考えています」(藤中氏)。
特に同社が求めているのは、ミドルウェアやデバイスと直接やりとりするドライバの開発を担うエンジニアだ。組込み、IoT、AI等の、ハードウェアの知識も併せ持ったエンジニアだ。
「特に弊社の『aIPE』は独自のアーキテクチャですので、その仕組みを理解できる方が必要です。アーキテクチャに見識があり、ないものを作っていくことに対して積極的に取り組めるチャレンジャブルな方に期待しています。また、性能が良いとされるものは、シンプルで美しいアーキテクチャを持っています。そういった技術を突き詰めたい、またはそれが出来る技術者を求めています」(黒田氏)。
ハードウェアエンジニアを含め、同社には個々に尖ったスキルを持った技術者が集まる。高田氏が掲げる“破壊と創造”というスローガンを共有し、世の中にない、新しいものを生み出すことに価値を見いだすエンジニア集団である。ソフトウェアのエンジニアも、個性的なバックボーンを持ったエンジニアが集まる。台湾出身で言語処理系のスペシャリスト、ホンジュラスから日本の技術を学びに来ている若いエンジニア等、国際色も豊かだ。そういったエンジニアがそれぞれの役割を自発的に果たし、研鑽し合いながら、独自の技術で世界に打って出ようとしている。今ならまだその一員として世界を変える瞬間に立ち会えるチャンスが残されている。それが今、同社に参画する最大の魅力だろう。
拠点は大阪本社と東京支店の2拠点だが、リモートワークも可能な制度が整っており、実績もある。他には、フレックス制を採用する等、エンジニアが働きやすいよう柔軟な制度を取り入れ、「日本発の半導体を世界に発信する」という目標に集中して取り組める環境を整えている。同社に関わる人々と同じ想い、価値観を共有出来るエンジニアなら、年齢、性別、国籍等に関わらず活躍できることだろう。
PR
すべて見るインタビュー

── 目指している企業像をお話し下さい。
人に、安心安全を与えるということは非常に大切だと考えています。ただ、軍事利用や犯罪等に利用される危険もある技術ではありますので、そのリスクは常に考えておかなければいけません。
その考え方の背景にあるのは、前職時代に教え込まれた水道経営の考え方です。私は電機メーカーに入った人間ですので、その頃に学んだことは受け継ぎたいと思っています。開発中のチップはそれに近いところがあります。安心安全を与えるチップを、世の中にタダに近い価格で売っていくことで、世の中に貢献していきたいと考えています。
目の前の利益だけを追い求めてしまうといずれ破綻してしまいます... 続きを読む
社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
会社名
ArchiTek株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
IT/Web・通信・インターネット系 > IoT・M2M・ロボット
IT/Web・通信・インターネット系 > その他IT/Web・通信・インターネット系
企業の特徴
上場を目指す、自社サービス製品あり、グローバルに活動資本金
1億円
設立年月
2011年09月
代表者氏名
代表取締役CTO 高田 周一
事業内容
アーキテクチャやアルゴリズムの開発およびそれらをFPGA/LSI/ソフトウェアへ実装する研究開発メーカー
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
高田周一および役職員。 未来創生ファンド(トヨタ自動車、三井住友銀行、スパークス・グループ、トヨタG企業他) テックアクセルベンチャーズ(オムロン、リコー、SMBCベンチャーキャピタル、INCJ 他) NTTドコモベンチャーズ(NTT本体を始めとしたNTTグループのファンドからの出資) 三菱UFJキャピタル・池田泉州キャピタル
主要取引先
株式会社ソシオネクスト、株式会社豊田自動織機、XILINX Inc.等
従業員数
14人
本社住所
大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番29号
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- ソフトウェア/パッケージベンダ
- ArchiTek株式会社の中途採用/求人/転職情報