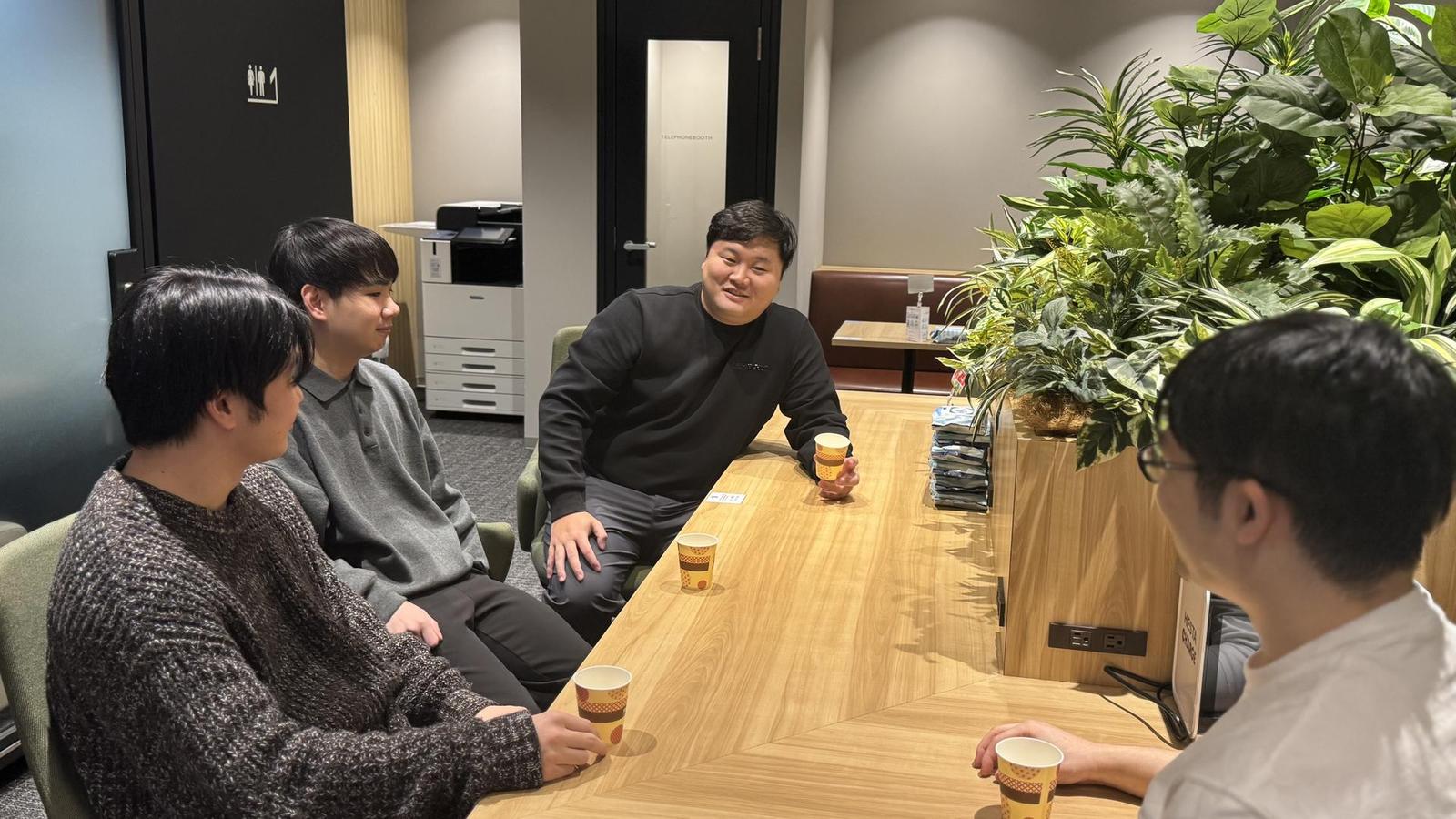VPoE 眞野(左)
開発部門管掌役員 吉田(右)
VPoE 眞野(左)
開発部門管掌役員 吉田(右)簡単な経歴とそれぞれの役割
開発部門管掌役員:吉田 コベルコソフト神戸(現:コベルコソフトサービス)に入社し、業務システム開発に従事。 その後、ITベンチャーの海外拠点において開発業務を経験。2004年にイノシス研究所に入社、複数プラットフォームのアプリ開発を牽引。2006年7月にレコモットに参画し、2020年6月にデベロップメント部並びにプロダクト管理部の管掌取締役に就任。現在は開発責任者として、会社のプロダクト開発を牽引。 VPoE:眞野 SI企業に入社し、業務系システム開発に従事。その後、ITベンチャー企業にてiOS、Androidアプリ開発を経験し、いくつかベンチャー企業でサービスの立ち上げや、開発部門の責任者を経て、2021年1月にレコモットに参画。VPoEとしてエンジニア組織全体の採用・育成・マネジメントを担当。
2人から見たレコモットの開発組織の特徴
吉田:サービス全体を俯瞰して見られるフルスタック思考の開発組織です。チーム構成はあるものの、比較的自由度の高いチーム体制です。弊社のサービスにmoconaviというものがありますが、基本的にはmoconaviを主軸に機能要件を追加し、サービスの拡充を図っています。そのため、どこか特定の分野にだけに特化しているというよりも、複数のチームを横断して様々なジャンルを手がけてもらうことが多いです。 最初はフロントエンドをやっていた方が、途中からバックエンドもやりたいということでチームを組み換えたり、iOSだけ出来るということで入社された方が、Androidにも挑戦してみたりといったこともよくあります。どこかのプラットフォームで得た知識というのは、他の分野でも必ず活かせます。それに、その方が自分自身の経験値や視野も広がるかと思います。 眞野:既存メンバーはもちろん、最近採用した若手メンバー含めて、成長意欲の高い方々が集まっている印象です。有志で技術的な勉強会を催すこともあって、最近だと「AtCoder」という世界でも有数の競技プログラミングに出場しようということで、6名ほどが集まって勉強しています。決して私たちが強制した訳ではないのですが、自然とそうなる空気感が組織全体としてあるように感じます。
面接の際に重視して見ているポイント
吉田:技術に興味があって、きちんと自分で勉強しているのかという点は重視して見ているポイントです。経験の有無というよりは、知りたい!という知的好奇心に満ち溢れている人です。私自身がどちらかというとそういうタイプのため、面接の場面で似た性質を持つ方にお会いすると、非常に嬉しくてどんどん深堀りして聞いてしまいます。どういったことに興味・関心があるのか、普段どんな本を読まれているかなどは気になる部分です。 眞野:技術的なスキルももちろん重要ですが、自分がどうなりたいのか、エンジニアとしてどうやって行きたいのかを、きちんと考えられているかどうか知りたいです。最近はエンジニアをやりたいと言われる方が非常に多いです。けれど、その想いだけではなくて具体的な行動に移せているか。つまり、想いと行動が一致しているかどうかは重視して見ているポイントです。
今後どんな開発組織を目指しているか
吉田:レコモットが掲げるValues(バリューズ)※にもありますが、変化を愉しみながら、新たなことにもチャレンジしていくことができる 開発組織を作っていきたいです。セールスチームや顧客からの要望にただ答えるだけの受け身の組織ではなく、メンバー自らが意思を持って、積極的なアプローチでプロダクト開発に携わっていく。そうした中で、自らも成長することができるような組織にしていきたいです。 もう1つは、思ったことを躊躇なく言い合える心理的安全性のある組織です。「ちょっとこのコードおかしくないですか?」や「ここを直してみましょうよ」とか、発言してくれた人が居心地がいいと感じてくれる環境でありたいです。 眞野:吉田からもありましたが、言われたものをただ淡々と作るのではなくて、メンバーが自分で考え、自分ならではの答えを見出しながら開発に打ち込める組織でありたいです。セールスチームや顧客の要望を聞き入れ反映する必要があるため、エンジニア組織はどうしても受け身の姿勢になってしまいがちです。 しかしながら、エンジニアは本来自分たちの手で”ものづくり”が出来る人材です。相手の要望の内側にある意図をしっかりと理解した上で、「顧客にとって一体何がいいのか?」そんなところを思考しながら、プロダクトを作れる組織でありたいです。
入社後の教育プログラムについて
眞野:近年、組織の拡大に伴い採用・育成を強化しています。若手エンジニアなどが入社した場合は、先程申し上げたメンター制度を活用しながらプロダクトや業務理解を深めて頂いております。現場からは、作業に行き詰まった際にすぐに相談できる存在がいることは安心感につながるといった声を耳にします。組織全体に対する信頼度も、上がってきているように感じています。 メンター制度以外でも、各チームでの1on1や、私による月1のMTGを行っています。他には、業務に関連する書籍は会社負担で購入できたり、「サポトラ(Support for your try)」と呼ばれる資格取得支援制度もあります。