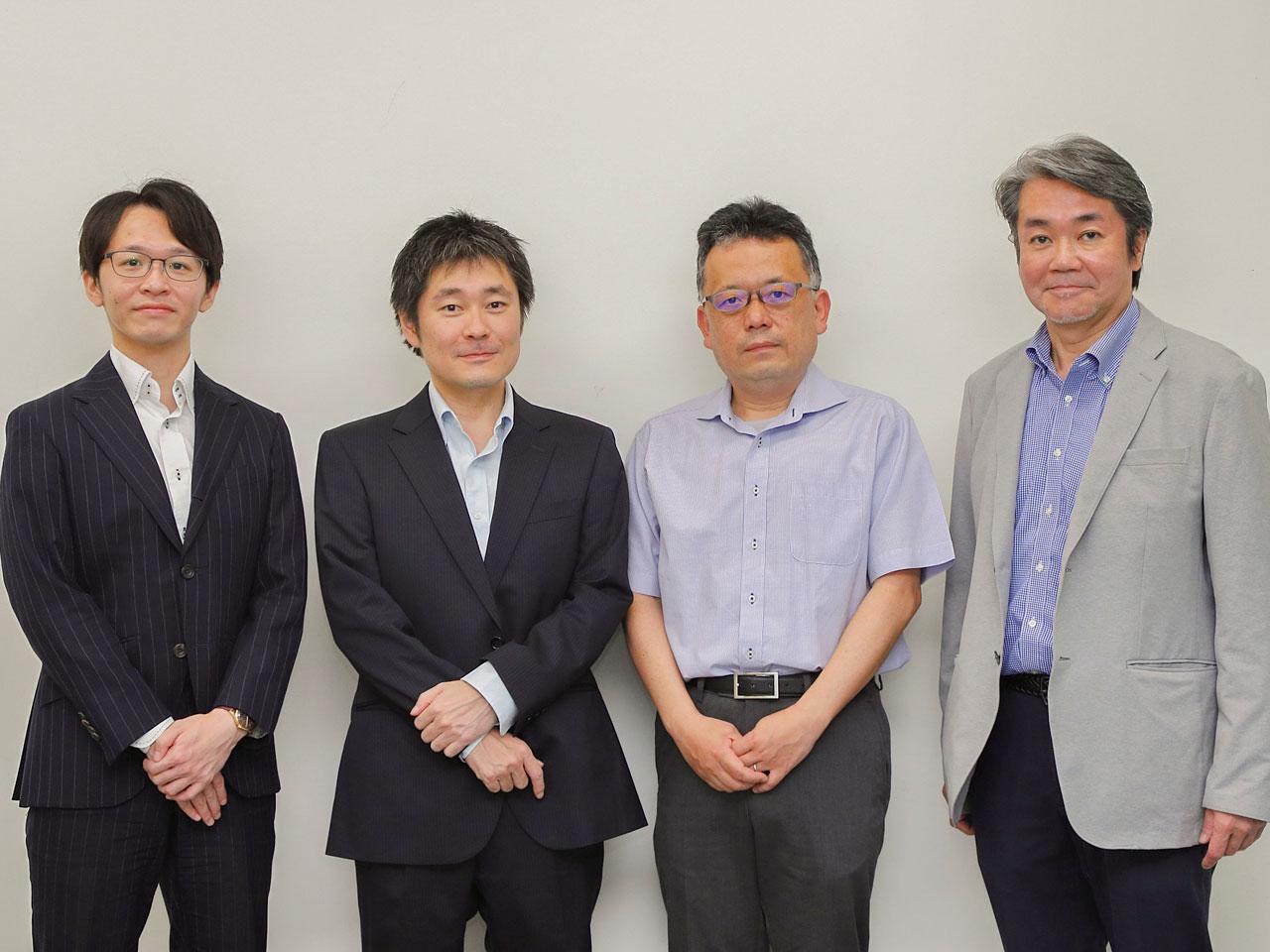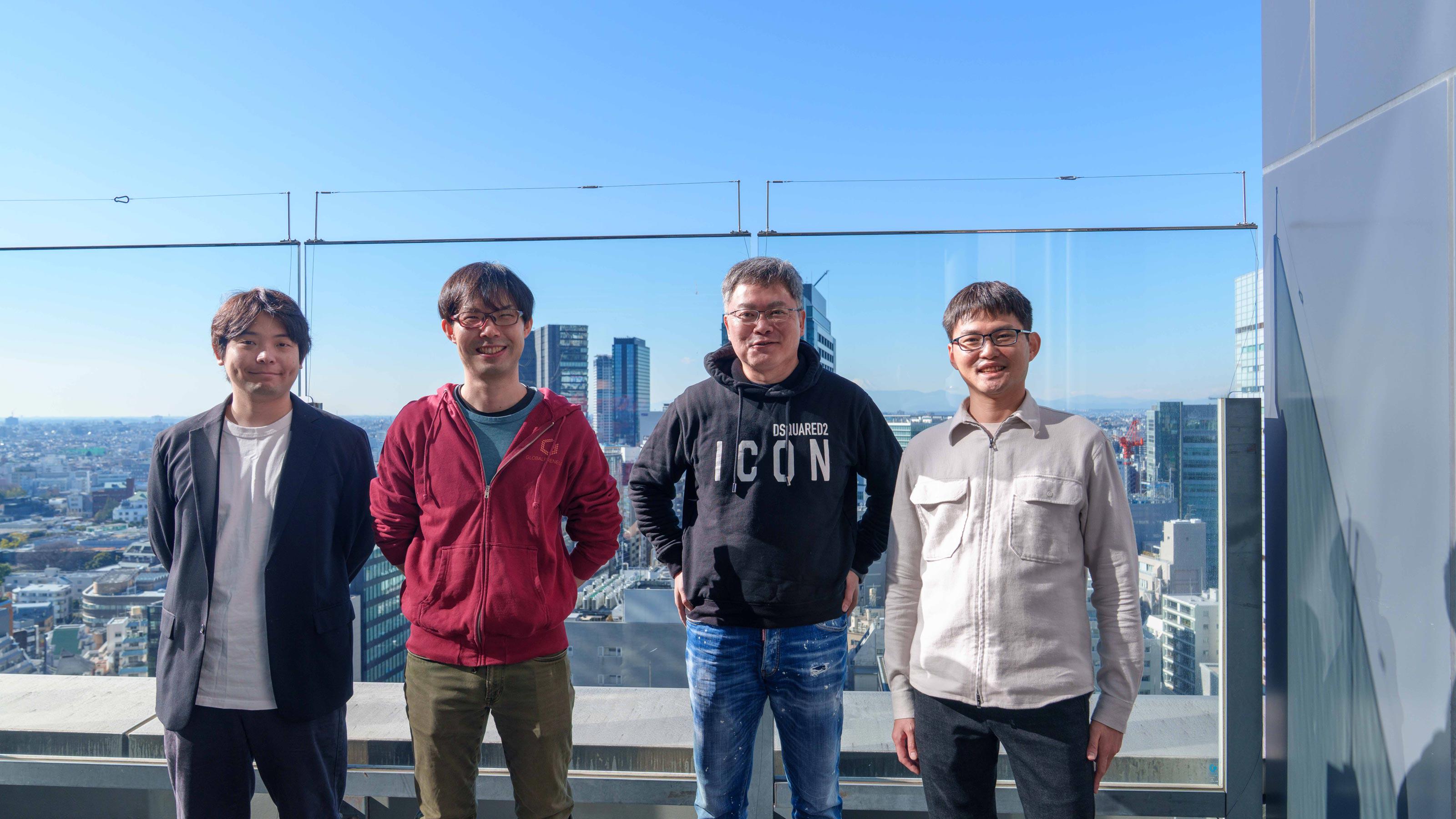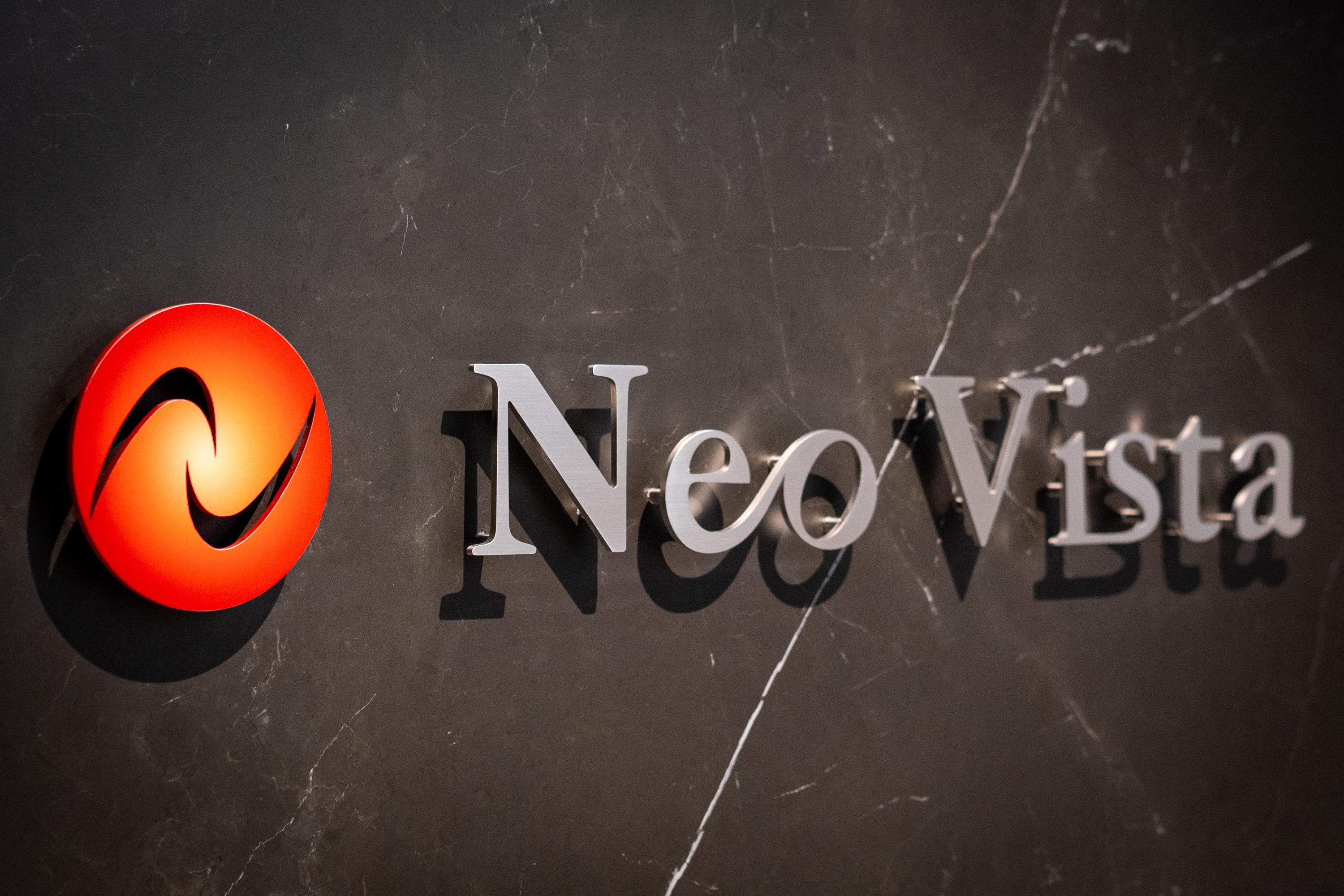株式会社テリロジー
- IT/Web・通信・インターネット系
- 商社(卸売)・流通・小売り系
最新&ニッチ製品に強く、自社開発も行うITセキュリティ専門商社
自社サービス製品あり
カジュアル面談歓迎
企業について
国家事業におけるネットワークセキュリティベンダーに選ばれる信頼性と技術力
ITセキュリティの専門商社の、株式会社テリロジー。同社は、海外ハードウェア・ソフトウェア製品の輸入販売、および自社ソフトウェア製品の開発・販売を手掛けている企業で、グループ親会社は東証スタンダード上場である。
同社の事業領域は、主力のネットワーク部門とセキュリティ部門に加え、モニタリング部門、ソリューションサービス部門からなる。総じて15ほどの主要製品を販売すると共に、導入後の保守運用まで一貫して手掛ける。売上比率は、製品販売約60%、保守運用約40%。各事業部門の主要取扱製品は次のものがある。
●ネットワーク部門
Infoblox:米Infoblox社によるDNS、DHCPサービス、IPアドレス管理を高度なセキュリティと共に提供する製品。
Radware:米Radware社による、DoS/DDoS対策、WAF、Bot対策製品。
●セキュリティ部門
Nozomi Networks Guardian :米Nozomi Networks 社のOT/IoTセキュリティ&可視化ソリューション。
TippingPoint:TREND MICRO社の、チューニングレスを実現するIPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防止システム)。
●モニタリング部門
CloudTriage:自社開発製品。様々なクラウドサービスのパフォーマンスを可視化し、体感品質等の問題の原因を追究するための運用監視クラウドサービス。
THX:子会社のテリロジーワークスの独自開発による、スレット(脅威)ハンティング・ソリューション。
●ソリューションサービス部門
みえる通訳:子会社のテリロジーサービスウェアの開発による、多言語映像通訳サービス。
Zoom:米Zoom Video Communications社によるWeb会議サービス。
同社の強みは、以下の通り。
①目利き力と市場対応力
同社では、大手商社等が取り扱わないシリコンバレーやイスラエルのベンチャーがリリースしている製品の先進性や機能性を評価し、日本市場にいち早く紹介していることが特徴。大手が扱わないのは、ベンチャーには事業継続等のリスクがあるためで、同社はこのリスクを積極的に取り、共に製品を育成するスタンスで臨んでいる。
②ソリューションラインアップ
ネットワークに不可欠な基礎的な製品から、多様なセキュリティーのニーズに応える製品、さらには自社開発のRPA『EzAvater』まで、幅広いラインアップを用意。
③サービス提供の多様性
ソフトウェア製品は、OracleやAWSのクラウドとセットにしたサブスクリプション型やオンプレミスのアプライアンス型等、顧客のニーズに応じた形態で提供。また導入後の保守運用まで一貫して提供している。他社から購入した取扱製品の保守運用を要請されることもあるほど、運用技術の高さも評価されている。
④実績に裏打ちされた技術力
自社独自製品を開発できる技術力を備えている。製品に的確なチューニングを施すのはもちろん、顧客ニーズに応じて異なるメーカーの製品同士を接続して提供したり、必要に応じ独自にシステムを開発することも行う。
⑤グローバル対応力
創業から33年間にわたってアメリカやイスラエルの企業とビジネスを推進してきたネットワーク力と、ベトナムの政府認定セキュリティオペレーションセンター会社であるVNCS Global社に出資し足場を築いている。
このような強みが大手企業や官公庁を主体とする顧客から評価され、2017年度より5期連続で増収増益を果たしている。
また、国家事業におけるネットワークセキュリティを支える存在に選ばれていることは、同社の信頼性や技術力の高さを雄弁に物語っている。
同社の事業領域は、主力のネットワーク部門とセキュリティ部門に加え、モニタリング部門、ソリューションサービス部門からなる。総じて15ほどの主要製品を販売すると共に、導入後の保守運用まで一貫して手掛ける。売上比率は、製品販売約60%、保守運用約40%。各事業部門の主要取扱製品は次のものがある。
●ネットワーク部門
Infoblox:米Infoblox社によるDNS、DHCPサービス、IPアドレス管理を高度なセキュリティと共に提供する製品。
Radware:米Radware社による、DoS/DDoS対策、WAF、Bot対策製品。
●セキュリティ部門
Nozomi Networks Guardian :米Nozomi Networks 社のOT/IoTセキュリティ&可視化ソリューション。
TippingPoint:TREND MICRO社の、チューニングレスを実現するIPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防止システム)。
●モニタリング部門
CloudTriage:自社開発製品。様々なクラウドサービスのパフォーマンスを可視化し、体感品質等の問題の原因を追究するための運用監視クラウドサービス。
THX:子会社のテリロジーワークスの独自開発による、スレット(脅威)ハンティング・ソリューション。
●ソリューションサービス部門
みえる通訳:子会社のテリロジーサービスウェアの開発による、多言語映像通訳サービス。
Zoom:米Zoom Video Communications社によるWeb会議サービス。
同社の強みは、以下の通り。
①目利き力と市場対応力
同社では、大手商社等が取り扱わないシリコンバレーやイスラエルのベンチャーがリリースしている製品の先進性や機能性を評価し、日本市場にいち早く紹介していることが特徴。大手が扱わないのは、ベンチャーには事業継続等のリスクがあるためで、同社はこのリスクを積極的に取り、共に製品を育成するスタンスで臨んでいる。
②ソリューションラインアップ
ネットワークに不可欠な基礎的な製品から、多様なセキュリティーのニーズに応える製品、さらには自社開発のRPA『EzAvater』まで、幅広いラインアップを用意。
③サービス提供の多様性
ソフトウェア製品は、OracleやAWSのクラウドとセットにしたサブスクリプション型やオンプレミスのアプライアンス型等、顧客のニーズに応じた形態で提供。また導入後の保守運用まで一貫して提供している。他社から購入した取扱製品の保守運用を要請されることもあるほど、運用技術の高さも評価されている。
④実績に裏打ちされた技術力
自社独自製品を開発できる技術力を備えている。製品に的確なチューニングを施すのはもちろん、顧客ニーズに応じて異なるメーカーの製品同士を接続して提供したり、必要に応じ独自にシステムを開発することも行う。
⑤グローバル対応力
創業から33年間にわたってアメリカやイスラエルの企業とビジネスを推進してきたネットワーク力と、ベトナムの政府認定セキュリティオペレーションセンター会社であるVNCS Global社に出資し足場を築いている。
このような強みが大手企業や官公庁を主体とする顧客から評価され、2017年度より5期連続で増収増益を果たしている。
また、国家事業におけるネットワークセキュリティを支える存在に選ばれていることは、同社の信頼性や技術力の高さを雄弁に物語っている。
グループ企業の拡大・連携強化による成長戦略
同社の設立は、1989(平成元)年。代表取締役会長の津吹憲男氏と代表取締役社長の阿部昭彦氏は、共にエレクトロニクス系技術商社から総合商社系情報通信・ネットワーク企業にヘッドハンティングされた。共に要職を務めたが、親会社から来た現場を知らない経営幹部が大きな権限を持ち、自由度が非常に少ない環境にあったという。そこで、社員がやりたいことを自由にできる環境をつくろうとスピンアウトし、同社をスタートさせた。
その当初から、誰もが知っている各領域のNo.1ベンダーではなく、より有利な条件で扱える二番手以降やベンチャーの高品質製品を見出してきた。例えば、同社はスタート当初はルーターやスイッチ等のネットワーク機器を主に扱ったが、ベンダーはCiscoではなくNortelやAVAYAを選択するといったように。
ブレイクしたのは、インターネット黎明期にSIEMENSのPPPoEを扱い、70%ほどのシェアを占めたこと。これで事業基盤を築き、2004年にJASDAQ市場に上場を果たした。
その後、ブロードバンド、携帯電話、クラウド、スマートフォンといった技術進化に合わせて取扱製品を徐々に拡大に、今日に至る。
この間、主要顧客として通信キャリア、電力会社、エレクトロニクスや自動車、化学、重機等のメーカー、メガバンクや証券会社等の金融機関、政府系研究機関、大学、官公庁等300社以上、そのほぼ9割と直取引している。
また、グループ会社もCTI(サイバー脅威インテリジェンス)と脅威ハンティング領域のパイオニアであり、現在もフロントランナーとして官公庁を主要顧客とするテリロジーワークスや、ベトナムのVNCS Global社等、5社を擁している。
今後の成長戦略は、大きく次の三つを掲げている。
①グループ連携によるストック型事業モデルへの強化
クラウドセキュリティ事業に挑戦すると共に、ビジネス・システム・アウトソーシング事業を拡大。
②グループ・ポートフォリオ事業のさらなる拡大・強化
主要事業領域のトップラインの拡大と共に、グループ事業シナジー追求を強化。さらに積極的なM&Aでダイナミックにグループ事業を拡大する
③グローバルな事業展開
VNCS Global社を基盤とするアジア事業戦略展開の強化と、米国およびイスラエルとの連携をさらに強化する
こうした戦略で、2021年3月期の連結売上高47億円から、2024年3月期に74億円(157.4%増)を目指す。
その当初から、誰もが知っている各領域のNo.1ベンダーではなく、より有利な条件で扱える二番手以降やベンチャーの高品質製品を見出してきた。例えば、同社はスタート当初はルーターやスイッチ等のネットワーク機器を主に扱ったが、ベンダーはCiscoではなくNortelやAVAYAを選択するといったように。
ブレイクしたのは、インターネット黎明期にSIEMENSのPPPoEを扱い、70%ほどのシェアを占めたこと。これで事業基盤を築き、2004年にJASDAQ市場に上場を果たした。
その後、ブロードバンド、携帯電話、クラウド、スマートフォンといった技術進化に合わせて取扱製品を徐々に拡大に、今日に至る。
この間、主要顧客として通信キャリア、電力会社、エレクトロニクスや自動車、化学、重機等のメーカー、メガバンクや証券会社等の金融機関、政府系研究機関、大学、官公庁等300社以上、そのほぼ9割と直取引している。
また、グループ会社もCTI(サイバー脅威インテリジェンス)と脅威ハンティング領域のパイオニアであり、現在もフロントランナーとして官公庁を主要顧客とするテリロジーワークスや、ベトナムのVNCS Global社等、5社を擁している。
今後の成長戦略は、大きく次の三つを掲げている。
①グループ連携によるストック型事業モデルへの強化
クラウドセキュリティ事業に挑戦すると共に、ビジネス・システム・アウトソーシング事業を拡大。
②グループ・ポートフォリオ事業のさらなる拡大・強化
主要事業領域のトップラインの拡大と共に、グループ事業シナジー追求を強化。さらに積極的なM&Aでダイナミックにグループ事業を拡大する
③グローバルな事業展開
VNCS Global社を基盤とするアジア事業戦略展開の強化と、米国およびイスラエルとの連携をさらに強化する
こうした戦略で、2021年3月期の連結売上高47億円から、2024年3月期に74億円(157.4%増)を目指す。
“No.1 in Quality”を掲げ、人材育成に力を入れる
2023年4月現在、同社の社員数は83名(グループ全体では約240名)。グループ全体を束ねるスローガンとして“No.1 in Quality”を掲げている。
「お客様に提供する技術やサービス等の品質をNo.1にするために、社員一人ひとりが常にプロ意識を持ち、仕事や事業の質を高めていこうということです」と経営管理部総務・人事グループのグループマネージャーを務める星野智氏は説明する。
目指す集団像は、「自由な発想力、着実な行動力、そして実現力を保有するプロフェッショナルなイノベーション力溢れる企業集団」。これを実現させるために、人事評価ではMBOによる考課を導入し、新たなことへのチャレンジ等を定性評価指標に取り入れている。
また、外部のe-ラーニングシステムを導入し、人事考課において半期ごとに1講座の履修を必須としている。「自己研鑽のため受講は無制限」と星野氏は話す。
さらに、トップレベルの技術力を持つ役員が膝詰めで教える「Tech寺子屋」を開講。
そのほか、各メンバーの担当領域に関する外部セミナー受講や、ベンダー系の資格取得等は会社が奨励金を支給する等してバックアップしている。
なお、人事評価で2年連続で全体の40%以上となる「B+」評価を受けると、自動的に昇格・昇給対象者として人事委員会に推薦される。努力目標が“見える化”されていると言える。
社内の情報共有や交流の機会としては、四半期ごとのキックオフミーティングおよび懇親会(コロナ禍では中断)のほか、社員の互助会と会社が負担する忘年会等が行われている。なお、技術部門では独自に在籍確認機能付きチャットを独自開発して活用も。
「社風としては、社長以下社員は同じフロアで仕事をし、フリーアドレスにつき役員と隣同士になるといったことも少なくないことから、経営との距離感がないアットホームさがあります。社長が新人に気安く声を掛けることもよくありますね」(星野氏)。
そんな同社が求める人材像は、チャレンジングで何事もセルフスタートできるタイプ。
「当社は創業34年でありながら、グループ事業経営の拡大もあり、テリロジーグループとしては中期経営計画において毎年10%の成長を掲げています。現在は第二の創業期のような雰囲気ですので、入社いただける方には、ぜひ、そのテリロジーグループ第二創業期のコアメンバーになっていただきたいと思います」と星野氏は呼び掛ける。
「お客様に提供する技術やサービス等の品質をNo.1にするために、社員一人ひとりが常にプロ意識を持ち、仕事や事業の質を高めていこうということです」と経営管理部総務・人事グループのグループマネージャーを務める星野智氏は説明する。
目指す集団像は、「自由な発想力、着実な行動力、そして実現力を保有するプロフェッショナルなイノベーション力溢れる企業集団」。これを実現させるために、人事評価ではMBOによる考課を導入し、新たなことへのチャレンジ等を定性評価指標に取り入れている。
また、外部のe-ラーニングシステムを導入し、人事考課において半期ごとに1講座の履修を必須としている。「自己研鑽のため受講は無制限」と星野氏は話す。
さらに、トップレベルの技術力を持つ役員が膝詰めで教える「Tech寺子屋」を開講。
そのほか、各メンバーの担当領域に関する外部セミナー受講や、ベンダー系の資格取得等は会社が奨励金を支給する等してバックアップしている。
なお、人事評価で2年連続で全体の40%以上となる「B+」評価を受けると、自動的に昇格・昇給対象者として人事委員会に推薦される。努力目標が“見える化”されていると言える。
社内の情報共有や交流の機会としては、四半期ごとのキックオフミーティングおよび懇親会(コロナ禍では中断)のほか、社員の互助会と会社が負担する忘年会等が行われている。なお、技術部門では独自に在籍確認機能付きチャットを独自開発して活用も。
「社風としては、社長以下社員は同じフロアで仕事をし、フリーアドレスにつき役員と隣同士になるといったことも少なくないことから、経営との距離感がないアットホームさがあります。社長が新人に気安く声を掛けることもよくありますね」(星野氏)。
そんな同社が求める人材像は、チャレンジングで何事もセルフスタートできるタイプ。
「当社は創業34年でありながら、グループ事業経営の拡大もあり、テリロジーグループとしては中期経営計画において毎年10%の成長を掲げています。現在は第二の創業期のような雰囲気ですので、入社いただける方には、ぜひ、そのテリロジーグループ第二創業期のコアメンバーになっていただきたいと思います」と星野氏は呼び掛ける。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── 技術統括部のミッションと、部や会社全体をどのようにしていきたいとお考えですか?
技術統括部のミッションは、大きく二つあります。一つは新製品や新技術への移行で、もう一つは、IT製品の輸入販売という既存のビジネスの生産性をより高めていくDXです。つまり、“攻め”と“守り”のトランスフォーメーションと言えます。
今後のビジョンとしては、次のようなことを考えています。
ITの世界には、ロシアのウクライナ侵攻でも明らかとなったサイバー戦争によるセキュリティニーズのさらなる高度化や、サブスクリプションモデルの台頭といったパラダイム変革が起きています。そうした中、創業三十有余年経つ当社の一部には、エスタブリッシュメントの意識が芽生えている... 続きを読む
企業情報
会社名
株式会社テリロジー
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
商社(卸売)・流通・小売り系 > 総合商社・専門商社
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、自社サービス製品あり資本金
5,000万円
売上(3年分)
2022年 3月 3,195百万円
2021年 3月 3,949百万円
2020年 3月 3,408百万円
設立年月
1989年07月
代表者氏名
代表取締役社長 鈴木 達
事業内容
■海外ハードウェア、ソフトウェア製品の輸入販売
■ネットワーク関連製品の販売
■エンドユーザへのシステムコンサルティングと構築・教育
■ネットワーク構築・工事
■ネットワーク関連製品の保守サービス
■アプリケーションソフトウェアの開発
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
・役員 ・社員持株会 (2021年3月31日現在)
主要取引先
通信事業者・大手企業など300社以上
従業員数
76人
平均年齢
37.4歳
本社住所
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5ヒューリック九段ビル4F
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社テリロジーに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- ソフトウェア/パッケージベンダ
- 株式会社テリロジーの中途採用/求人/転職情報