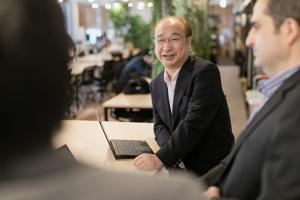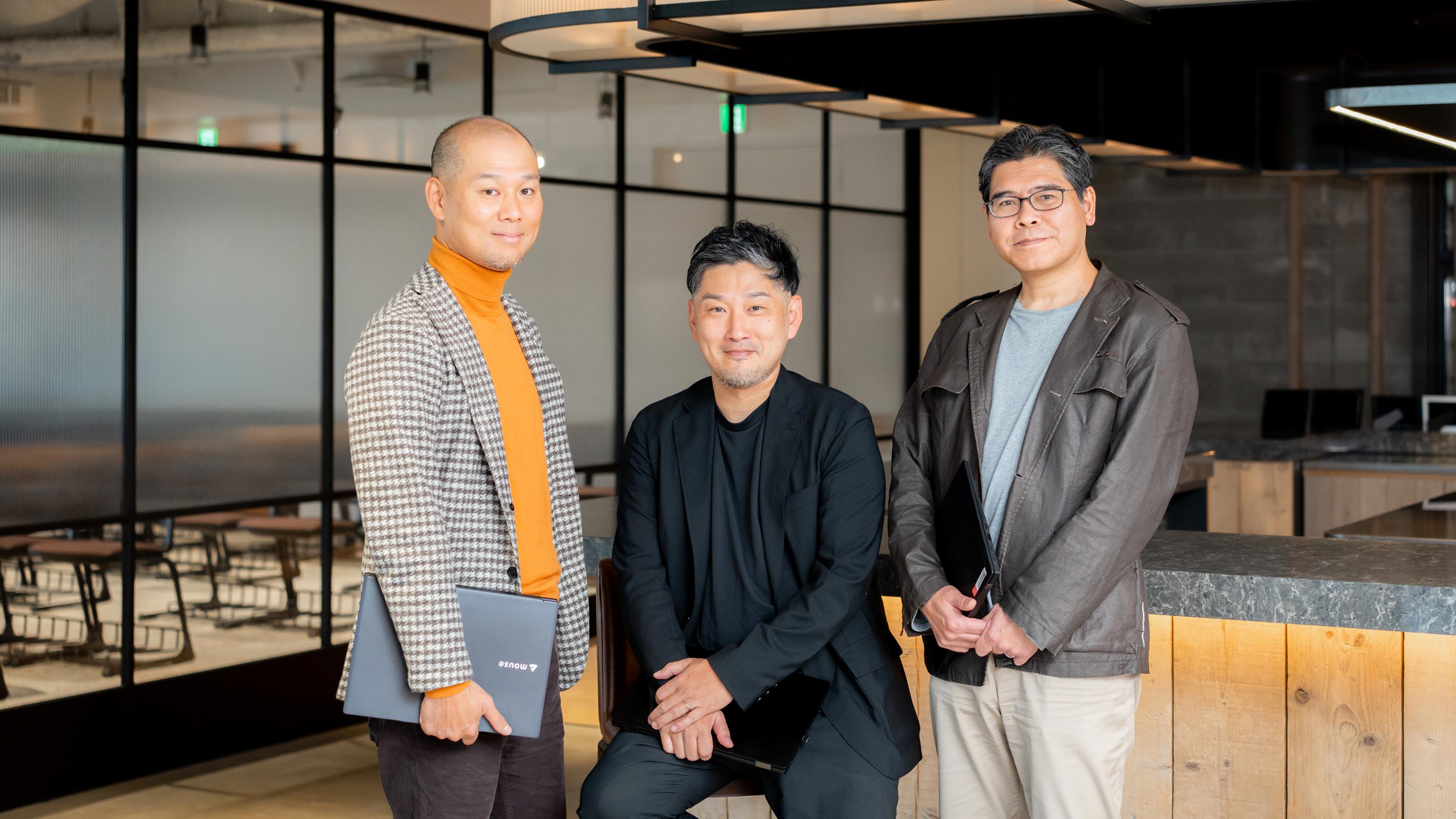ストックマーク株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
“攻めのDX”文化を醸成する、自然言語処理に特化したAIスタートアップ 一緒に事業を成功に導く仲間を募集しています!
企業について
ストックマークは、「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」というミッションを掲げ、2016年に設立した自然言語処理AI×SaaSのスタートアップです。
我々は日本企業の世界における国際競争力の低下という課題に向き合っています。多くの日本の大企業では国際的な競争力を高めるため、新規事業開発やイノベーション創出を進めていますが、テクノロジーの発展や市場の複雑化、顧客ニーズの多様化により情報が整理できず、思うように新規事業開発が進んでいないケースが多く見られます。
そこで、日英中の3.5万サイトもの膨大な情報網から自然言語処理を活用して、ニュース/ IR / 特許 / 論文 / 社内資料を解析。解析された情報を最適な形でお届けし、次世代のイノベーション創出&アイデア創出の仕組みを提供することで、新たなビジネスチャンスを発掘する支援を行っております。
具体的には
・AIが毎日必要なニュース情報をレコメンドし、新規事業創出のアイディエーションを助ける「Anews」
・AIを使ってオープンデータから業界のトレンドや市場構造を分析する「Astrategy」
という2つのSaaSプロダクトを通じて、「お客様の企業で新しい事業や顧客価値を継続的に生み出せる状態」を目指しております。
2022年8月にシリーズCで11億の資金調達完了。
2024年2月には、経済産業省およびNEDOが推進する「GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)プロジェクト」に採択され、1000億パラメーターの自社LLM開発に着手し始めました!
従業員も100名規模になり、更なる成長を目指すために人員を募集しております!
新しいことを始めようとする場合、まず行われるのは市場動向等の情報収集であろう。しかし、*デロイトトーマツの調査によると、「顧客との情報共有・対話」や「社員間での情報共有」「定期的な調査研究」等、“既存の延長”での情報源が大半を占め、「ビジネスプランコンテスト」「オフィシャルな自由時間設定」「体系的なアイデア創出フレームワーク」等の“既存の枠組みを超える”アイデア創出方法が取られているケースが極めて少ないことが分かる。つまり、アイデア発掘・共有の仕組みがアップデートされていないのだ。
一方、情報量は増加の一途で必要な情報を探り当てることは困難な環境にある。一般生活者向けにSEOされている検索エンジンではビジネス情報のみを抽出するには適さず、コンサルティング会社等の外部への調査委託は高額で使いづらいといった問題がある。会社員は1日当たり1.6時間情報収集を行うものの、75%の人がストレスを感じているという*ITmediaの調査もある。
では、どんな情報が必要なのか。
例えば、アメリカのショッピングサイトを手掛ける会社のようにデジタル技術で業界の在り方を変えてしまうディスラプターが様々な業界に出現している今、定量情報や業界特化情報、マスメディアによる情報では限界がある。定性情報、業界越境情報、マイクロメディアによる情報が不可欠なのだ。こうした情報の点と点を組み合わせ、自社のコンピテンシーやケイパビリティに照らし合わせてビジネスアイデアを抽出する必要がある。
現在、三菱商事、みずほ銀行、日立製作所、サントリー、JTB、ソフトバンク、リクルートホールディングスといった大手企業を中心に、事業部門向けの『A news』有償サービスは累計約250社、企画・戦略部門向け『A strategy』有償サービスは累計約50社に導入されている(2022年1月現在)。
「今後は、構造化されたオープンデータに社内データを統合して、AIが自動的に新規事業の企画書を作成し、人間は意思決定を行うだけ、という次元を目指してプロダクトのバリューアップを目指していきます」と代表取締役CEOの林達氏は意気込む。
*IPA「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方の関する調査」
*デジタル・デロイトトーマツ「日本企業のイノベーション実態調査(2013年)」
*ITmedia「会社は「調べもの」にいくら払っている? 1日当たり1057億円」
「文学部出身の私はエンジニアではなかったので、大学時代の友人であるエンジニアの有馬幸介(現・CTO)に声を掛け、2016年11月に二人で当社を創業しました」(林氏)。
有馬氏は大学・大学院時代に機械学習を用いたテキストデータ解析や分散環境における行列演算アルゴリズムによるビッグデータ処理を研究し、修了後は鉄鋼メーカーグループ会社のSIerに入社して大規模プロジェクトを主導する等、活躍していた人材。
両名は、まずコンシューマ向けに自らがストックしている情報を解析して意味付けを行う真のキュレーションサービス「ストックマーク」をリリースする。
その半年後、ある企業から『Aconnect』の元となるニーズが寄せられたことを機に、BtoBにピボットした。
そんな同社では、大学の生産技術研究所特任准教授として統計学・機械学習研究に従事していた博士や、複数の研究所で自然言語処理やAI等の主任研究員等を務めた研究者がR&D Managerに就任。自然言語処理技術における日本をリードする存在として、大学との共同研究や技術書の出版、メディアへの掲載を通じて影響力を発揮している。
2024年4月現在、約100名の優秀な人材が集まっている同社は、①CxOによるマネジメント層、②リーダー層、③メンバー層の3階層によるフラットな組織を構築。トップダウンによる方針やミッション等の情報の下達だけでなく、エンジニアや営業等、各ユニットリーダーの連携で横串を刺すと共に、各現場からのボトムアップ型の情報発信を重層化させ、社内に情報を行き渡らせている。
働き方も、オフィスやリモートの選択は個人の自由裁量に任されている。
そんな同社の求める人材像について、林氏は次のように言う。
「コアバリューとして、イノベーションに不可欠な“早く失敗すること”を促すチャレンジマインド、謙虚に学ぶ姿勢、未来構想力、アジリティ、チーム志向、自律と責任意識、オープンで誠実なコミュニケーション、多様性の尊重、仕組化できる能力等を挙げています。これらのうち、数個は光るものを持っている方に来ていただきたいと願っています」
今、日本が最も必要としているイノベーション。これを生む真のDXを推進する同社の仕事ほど、やりがいに満ちたものもないだろう。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(11件)
営業職の求人(7件)
企画・マーケティング職の求人(4件)
経営・CxO職の求人(2件)
専門職(金融/不動産/コンサルタント/士業)の求人(2件)
クリエイティブ職(Web)の求人(1件)
PR
すべて見る社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
ストックマーク株式会社
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
2016年11月
代表取締役 林 達
【会社概要】
ストックマークは、「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」というミッションを掲げ、2016年に設立した自然言語処理AI×SaaSのスタートアップです。
我々は日本企業の世界における国際競争力の低下という課題に向き合っています。多くの日本の大企業では国際的な競争力を高めるため、新規事業開発やイノベーション創出を進めていますが、テクノロジーの発展や市場の複雑化、顧客ニーズの多様化により情報が整理できず、思うように新規事業開発が進んでいないケースが多く見られます。
そこで、日英中の3.5万サイトもの膨大な情報網から自然言語処理を活用して、ニュース/ IR / 特許 / 論文 / 社内資料を解析。解析された情報を最適な形でお届けし、次世代のイノベーション創出&アイデア創出の仕組みを提供することで、新たなビジネスチャンスを発掘する支援を行っております。
具体的には
・AIが毎日必要なニュース情報をレコメンドし、新規事業創出のアイディエーションを助ける「Anews」
・AIを使ってオープンデータから業界のトレンドや市場構造を分析する「Astrategy」
という2つのSaaSプロダクトを通じて、「お客様の企業で新しい事業や顧客価値を継続的に生み出せる状態」を目指しております。
2022年8月にシリーズCで11億の資金調達完了。
2024年2月には、経済産業省およびNEDOが推進する「GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)プロジェクト」に採択され、1000億パラメーターの自社LLM開発に着手し始めました!
従業員も100名規模になり、更なる成長を目指すために人員を募集しております!
非上場
ポラリス・キャピタル・グループ
アサヒグループ食品、出光興産、沖電気工業、かんぽ生命、サッポロビール、サントリーホールディングス、Zacros、藤森工業、日本サムスン、JTBベネフィット、昭和電工、スズキ、住友商事、住友生命保険、セブン銀行、ソフトバンク、損保ジャパン日本興和ひまわり生命、大日本住友製薬、中外製薬、千代田化工建設、帝人、TIS、TOTO、凸版印刷、豊田通商、トヨタテクニカルディベロップメント、日華化学、日鉄ソリューションズ、日本ガイシ、日立製作所、パナソニック、みずほ銀行、三菱商事、三菱UFJ銀行、村田製作所、LIXIL、ロイヤルホールディングス、WOWOW
150人
35.1歳
東京都港区南青山一丁目12番3号
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- ストックマーク株式会社の中途採用/求人/転職情報