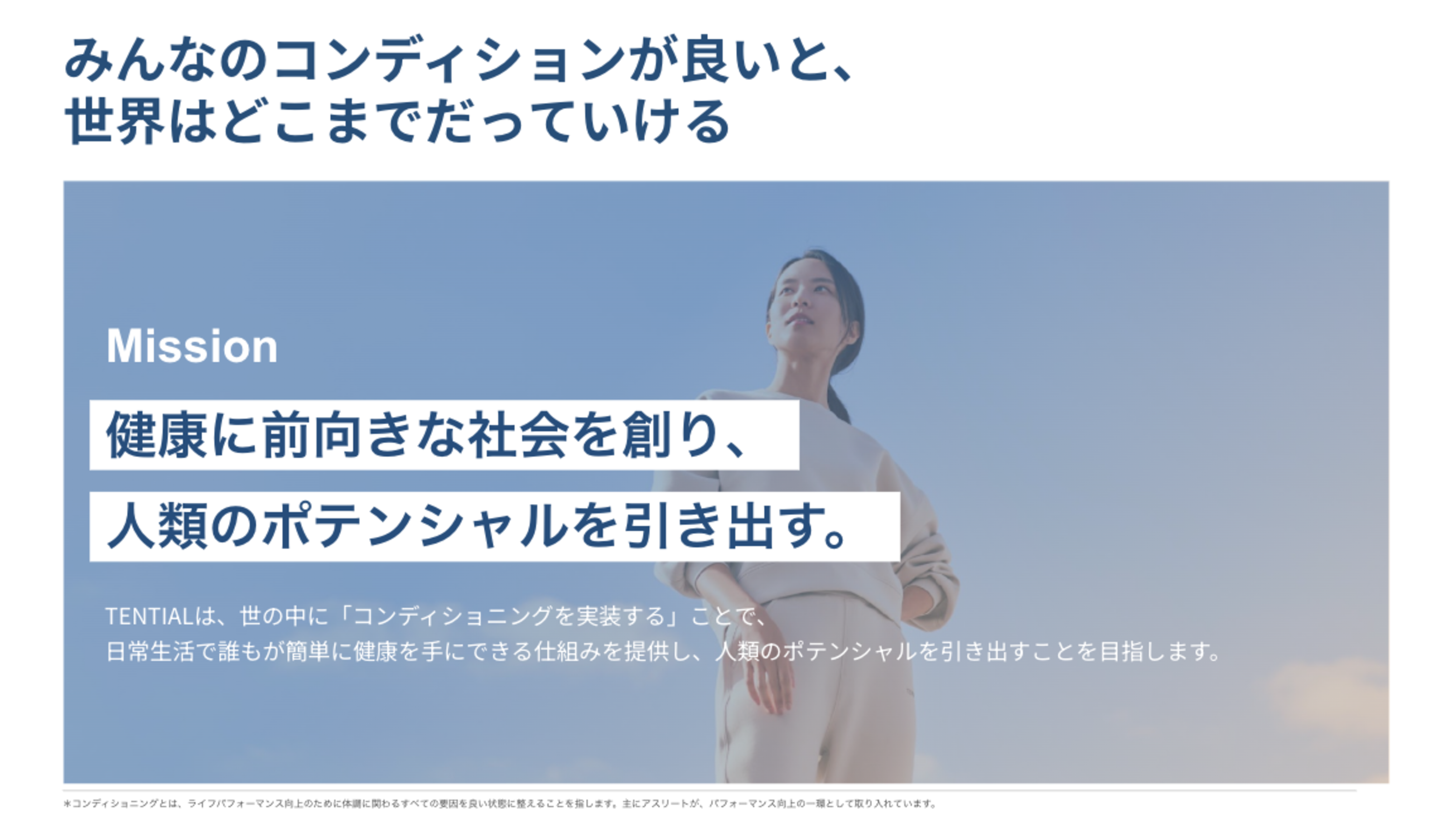株式会社TOAI
- サービス系
業界トップクラスの『ジャンカラ』がカラオケをデジタルの力で変える。
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
企業について
カラオケボックス業界に先駆け、非対面非接触受付アプリ『すぐカラ』をリリース
1970年前後、高度経済成長期の日本で生まれたカラオケは、現在、国内のみならず、J-POPが人気のアジア圏、または北米などにも広がり、世界中で親しまれるレクリエーションにまで発展している。発祥当時はスナックや宴会場などアルコールをたしなむ場で楽しまれる、いわば大人の遊びだったカラオケが、ファミリー層や未成年層にまで親しまれる娯楽へと変化し、幅広い人々に親しまれる一大産業にまで発展していった背景には、カラオケ機器メーカーやカラオケボックスチェーンなど、業界の人々による様々な創意工夫がある。
京都市に本社を構える株式会社TOAIも、カラオケ文化の発展に大きく寄与してきた企業の一社だ。1990年に創業の地である京都市に『ジャンボカラオケ広場(ジャンカラ)』1号店をオープンして以来、数々の新機軸を打ち出してきた。今では当たり前の歌い放題、飲み放題というサービスは、同社がカラオケボックス事業に参入した当初から打ち出したものである。一曲ごとに課金される料金システムが一般的な時代だ。料金の明朗化と価格破壊は、ユーザーの賛同を得て同社が躍進する要因となっただけではなく、カラオケのシーン拡大、ユーザー層拡大に寄与したことは疑いの余地はない。
その後も、地域最安値、飲食物の持ち込みOK、利用シーンに合わせて選べるコンセプトルームなど、他社にはないサービスを次々に打ち出しながら、西日本最大級のカラオケチェーンへと成長。店舗数は京阪神を中心に180店舗(2023年6月現在)、年間集客数は2000万人を超えるほどの知名度と人気を誇る。
そんな同社が近年、注力しているのがデジタルトランスフォーメーション(DX)だ。例えば『すぐカラ』というアプリで予約をして、非対面非接触で受付し、直接部屋に入ってカラオケを楽しむことが出来る。退室精算も同様にアプリを使ってすることが可能だ。
同サービスは、日本国内で新型コロナウィルス感染症の拡大が始まる以前の2019年10月にリリースし全店導入されている。カラオケボックス業界としては先駆的な事例である。つまり、この動きはコロナ禍によって一気に加速したDXの波とは別の文脈で実現したサービスである。
背景には代表取締役・東原元規氏が2015年に代表就任後掲げてきた“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”という2つのビジョンがある。
京都市に本社を構える株式会社TOAIも、カラオケ文化の発展に大きく寄与してきた企業の一社だ。1990年に創業の地である京都市に『ジャンボカラオケ広場(ジャンカラ)』1号店をオープンして以来、数々の新機軸を打ち出してきた。今では当たり前の歌い放題、飲み放題というサービスは、同社がカラオケボックス事業に参入した当初から打ち出したものである。一曲ごとに課金される料金システムが一般的な時代だ。料金の明朗化と価格破壊は、ユーザーの賛同を得て同社が躍進する要因となっただけではなく、カラオケのシーン拡大、ユーザー層拡大に寄与したことは疑いの余地はない。
その後も、地域最安値、飲食物の持ち込みOK、利用シーンに合わせて選べるコンセプトルームなど、他社にはないサービスを次々に打ち出しながら、西日本最大級のカラオケチェーンへと成長。店舗数は京阪神を中心に180店舗(2023年6月現在)、年間集客数は2000万人を超えるほどの知名度と人気を誇る。
そんな同社が近年、注力しているのがデジタルトランスフォーメーション(DX)だ。例えば『すぐカラ』というアプリで予約をして、非対面非接触で受付し、直接部屋に入ってカラオケを楽しむことが出来る。退室精算も同様にアプリを使ってすることが可能だ。
同サービスは、日本国内で新型コロナウィルス感染症の拡大が始まる以前の2019年10月にリリースし全店導入されている。カラオケボックス業界としては先駆的な事例である。つまり、この動きはコロナ禍によって一気に加速したDXの波とは別の文脈で実現したサービスである。
背景には代表取締役・東原元規氏が2015年に代表就任後掲げてきた“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”という2つのビジョンがある。
テクノロジーでカラオケを再定義。OMOのビジネスモデル確立を目指す
「“カラオケ体験を10倍にする”ための観点は大きく2つある。マイナスをゼロにすることと、プラスをさらにプラスにすること。マイナスをゼロにするとは、カラオケの本来の目的である“歌う”こと以外の煩わしさや不便さをなくしていくこと。現在はカラオケ利用前後の過程である“入退室の手続”を自動化させただけだが、今後は入室後の照明や機器類の設定、スマホの音楽アプリと連動させた自動選曲など、定型化された行動は全て自動化するといったことも考えられる」
プラスをさらにプラスにするというのは、カラオケボックスの中にある、“歌う”という行為の周辺にある、飲食やコミュニケーションを始めとする様々な体験を増幅させること。例えば、よく歌う曲の傾向に合わせたおすすめ商品のレコメンドとショッピング、カラオケをしている最中の体温の変化に応じたコンテンツ提供、来店目的に応じた五感に訴える演出効果などが考えられる。
また、“カラオケの再定義”をより具体的に表現すると、“カラオケボックスというインフラが担う機能や価値を設定し直す”ということになる。すでにカフェやコワーキングスペースのような使い方も一般的になりつつある。
「『ジャンカラ』の、駅前立地、ほぼ24時間営業、個室といった特性を活かした付加価値をいかに生み出せるか。仕事帰りにちょっと立ち寄って荷物を受け取る、ドリンクをボトルに詰めて持ち帰るなど、生活インフラの1つとして新たな価値を提供していきたい」
企業とのコラボレーションも可能だ。すでに実験的な試みとして、ある飲料メーカーと提携し、アルコールやソフトドリンク100種類以上を飲み放題で提供中だ。これをより発展させれば、メーカーのテストマーケティングにも活用することが出来る。部屋の利用料を含めて全て無料にする代わりに、動体検知などによって滞在中のデータを収集し、そのデータを商品開発に活用してもらうなど、様々な可能性を探っている。
さらに“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”といったビジョンの実現と並行して、事業の2本目の柱を育てる試みもスタートしている。これまでTOAIグループとして、フィットネス事業、温浴事業、レストラン事業、コワーキングスペース事業などを手がけているが、現在重点を置くのは、カラオケの隣接サービスの立ち上げと育成である。すでに『ジャンカラ』の店内機器や人材を活用したデリバリー専門のバーチャルレストラン(ゴーストキッチン事業)をスタートさせているが、今後もカラオケ事業の資産を活かした周辺事業への積極的参入を計画中である。
このようなビジョンを達成するためにはテクノロジーの活用は不可欠であり、オンラインとオフラインを繋ぎ込んでいくOMO(Online Merges with Offline)のビジネスモデルの確立は、現体制への移行後、重要課題として掲げ続けてきたテーマである。2020年に発生した新型コロナウィルス感染症拡大は、その動きに拍車をかけている。
「コロナがなければ5年、10年というスパンで進行したはずのイノベーションを、一気に形にしていかなければいけません。それを進めていくためにIT系、デジタル系、クリエイティブ系の人材の採用が緊急の課題となっています」
プラスをさらにプラスにするというのは、カラオケボックスの中にある、“歌う”という行為の周辺にある、飲食やコミュニケーションを始めとする様々な体験を増幅させること。例えば、よく歌う曲の傾向に合わせたおすすめ商品のレコメンドとショッピング、カラオケをしている最中の体温の変化に応じたコンテンツ提供、来店目的に応じた五感に訴える演出効果などが考えられる。
また、“カラオケの再定義”をより具体的に表現すると、“カラオケボックスというインフラが担う機能や価値を設定し直す”ということになる。すでにカフェやコワーキングスペースのような使い方も一般的になりつつある。
「『ジャンカラ』の、駅前立地、ほぼ24時間営業、個室といった特性を活かした付加価値をいかに生み出せるか。仕事帰りにちょっと立ち寄って荷物を受け取る、ドリンクをボトルに詰めて持ち帰るなど、生活インフラの1つとして新たな価値を提供していきたい」
企業とのコラボレーションも可能だ。すでに実験的な試みとして、ある飲料メーカーと提携し、アルコールやソフトドリンク100種類以上を飲み放題で提供中だ。これをより発展させれば、メーカーのテストマーケティングにも活用することが出来る。部屋の利用料を含めて全て無料にする代わりに、動体検知などによって滞在中のデータを収集し、そのデータを商品開発に活用してもらうなど、様々な可能性を探っている。
さらに“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”といったビジョンの実現と並行して、事業の2本目の柱を育てる試みもスタートしている。これまでTOAIグループとして、フィットネス事業、温浴事業、レストラン事業、コワーキングスペース事業などを手がけているが、現在重点を置くのは、カラオケの隣接サービスの立ち上げと育成である。すでに『ジャンカラ』の店内機器や人材を活用したデリバリー専門のバーチャルレストラン(ゴーストキッチン事業)をスタートさせているが、今後もカラオケ事業の資産を活かした周辺事業への積極的参入を計画中である。
このようなビジョンを達成するためにはテクノロジーの活用は不可欠であり、オンラインとオフラインを繋ぎ込んでいくOMO(Online Merges with Offline)のビジネスモデルの確立は、現体制への移行後、重要課題として掲げ続けてきたテーマである。2020年に発生した新型コロナウィルス感染症拡大は、その動きに拍車をかけている。
「コロナがなければ5年、10年というスパンで進行したはずのイノベーションを、一気に形にしていかなければいけません。それを進めていくためにIT系、デジタル系、クリエイティブ系の人材の採用が緊急の課題となっています」
IT、デジタル、クリエイティブの部門強化で新しい顧客体験を創出
今後、“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”といった命題を実現していくには、多様な専門スキルを持った技術者やクリエイター、マーケッターが必要とされる。社内SEやWEBエンジニアは、現状ではベンダーコントロールがメインだが、将来的には内製化も推し進めたい考えである。そのため各領域において、現場を担う若手から課長レベルのスキルを持ったミドル層、さらに部門責任者層まで、幅広い層の人材を積極的に採用していく計画である。
「求める人物像は職種によって変わりますが、会社全体の雰囲気としては、チャレンジを歓迎する社風です。お客様本位の視点を持ち、既存のやり方を疑い、新たな価値を創造していけるような人材を求めています」(人事責任者)
TOAIは経営理念に“笑顔のために”を掲げ、“笑顔あふれる社会作り”を目指した事業展開を行っている。その理念を実現していくための行動指針として、顧客の笑顔のために何が正しいかを個々が考え行動することを最上位概念に掲げる。そのためのキーワードは、“挑戦”“ワイルド”“スピード”である。同社は1986年6月に創業され30年以上の歴史を重ねてきた会社だが、こういった理念と行動指針のもと、一貫してチャレンジと改革改善を重ねてきた。現在進行する“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”もそういった文脈を引き継ぐものだ。
同社の社員は店舗スタッフも合わせると400名以上。そのうち本部勤務はおよそ120名だ。組織的な特徴としては、社員の約9割が中途採用であることと、本部のマネジメント層に店舗出身者が多いことである。そのため多様性を受け入れる下地がある一方で、横の繋がりが強くセクショナリズムが生じにくいという特性がある。全社横断で、1つの方向性、価値観を共有しながら理念の追求に集中することが出来る環境だ。
「みんな非常に協力的な社風ですし、お客様に楽しんでいただきたいという信念、目的を持って動く限り、行動を阻害されることはありません。こんなことがやりたいけど、今の環境では制約があって出来ないという方には適した会社です」(人事責任者)
カラオケ業界に限らず、対面によるサービスを提供する企業の多くが苦境に立たされる中、次代を見据えた変革への取り組みができることは、TOAIの経営基盤が盤石であることを示している。これまでにない素晴らしい顧客体験を生み出す当事者になれるチャンス。それが現在のTOAIに参画する最大の魅力である。
「求める人物像は職種によって変わりますが、会社全体の雰囲気としては、チャレンジを歓迎する社風です。お客様本位の視点を持ち、既存のやり方を疑い、新たな価値を創造していけるような人材を求めています」(人事責任者)
TOAIは経営理念に“笑顔のために”を掲げ、“笑顔あふれる社会作り”を目指した事業展開を行っている。その理念を実現していくための行動指針として、顧客の笑顔のために何が正しいかを個々が考え行動することを最上位概念に掲げる。そのためのキーワードは、“挑戦”“ワイルド”“スピード”である。同社は1986年6月に創業され30年以上の歴史を重ねてきた会社だが、こういった理念と行動指針のもと、一貫してチャレンジと改革改善を重ねてきた。現在進行する“カラオケ体験を10倍にする”“カラオケの再定義”もそういった文脈を引き継ぐものだ。
同社の社員は店舗スタッフも合わせると400名以上。そのうち本部勤務はおよそ120名だ。組織的な特徴としては、社員の約9割が中途採用であることと、本部のマネジメント層に店舗出身者が多いことである。そのため多様性を受け入れる下地がある一方で、横の繋がりが強くセクショナリズムが生じにくいという特性がある。全社横断で、1つの方向性、価値観を共有しながら理念の追求に集中することが出来る環境だ。
「みんな非常に協力的な社風ですし、お客様に楽しんでいただきたいという信念、目的を持って動く限り、行動を阻害されることはありません。こんなことがやりたいけど、今の環境では制約があって出来ないという方には適した会社です」(人事責任者)
カラオケ業界に限らず、対面によるサービスを提供する企業の多くが苦境に立たされる中、次代を見据えた変革への取り組みができることは、TOAIの経営基盤が盤石であることを示している。これまでにない素晴らしい顧客体験を生み出す当事者になれるチャンス。それが現在のTOAIに参画する最大の魅力である。
募集している求人
経理・管理・バックオフィス職の求人(2件)
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)
経営・CxO職の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── デジタル戦略部立ち上げに携わった経緯をお話し下さい。
私がTOAIに入社した理由は、以前から親しんでいた『ジャンカラ』を運営している会社が節目を迎えていて、データ分析やデジタル化といった領域に、まさにこれから力を入れていこうとしているタイミングだったことに惹かれたからです。何か起こるかわからない不確実性が魅力的でした。
デジタル戦略部の立ち上げに関わったのは、あくまでも結果です。新しい体験を作って行くという課題に向けて何をすべきかを考えている中で、デジタル専門の部署が必要だという話になりデジタル戦略部が生まれました。
デジタル戦略部の責任範囲は、お客様との接点におけるデジタル領域全般です。独自の... 続きを読む
企業情報
会社名
株式会社TOAI
業界
サービス系 > 飲食・旅行・レジャー・アミューズメント
サービス系 > その他サービス系
企業の特徴
自社サービス製品あり、シェアトップクラス資本金
40,000,000円
設立年月
1986年06月
代表者氏名
代表取締役 東原 元規
事業内容
カラオケ『ジャンボカラオケ広場(ジャンカラ)』のチェーン展開(カラオケルームの運営)
株式公開(証券取引所)
非上場
従業員数
6356人
平均年齢
35.2歳
本社住所
〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 烏丸ビル5階
この企業と同じ業界の企業
この求人の募集は終了しました。株式会社TOAIは、他にも求人を募集しているので、 ぜひチェックしてみてください。
この求人の募集は終了しました。株式会社TOAIは、他にも求人を募集しているので、ぜひチェックしてみてください。
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- サービス系
- 飲食・旅行・レジャー・アミューズメント
- 株式会社TOAIの中途採用/求人/転職情報