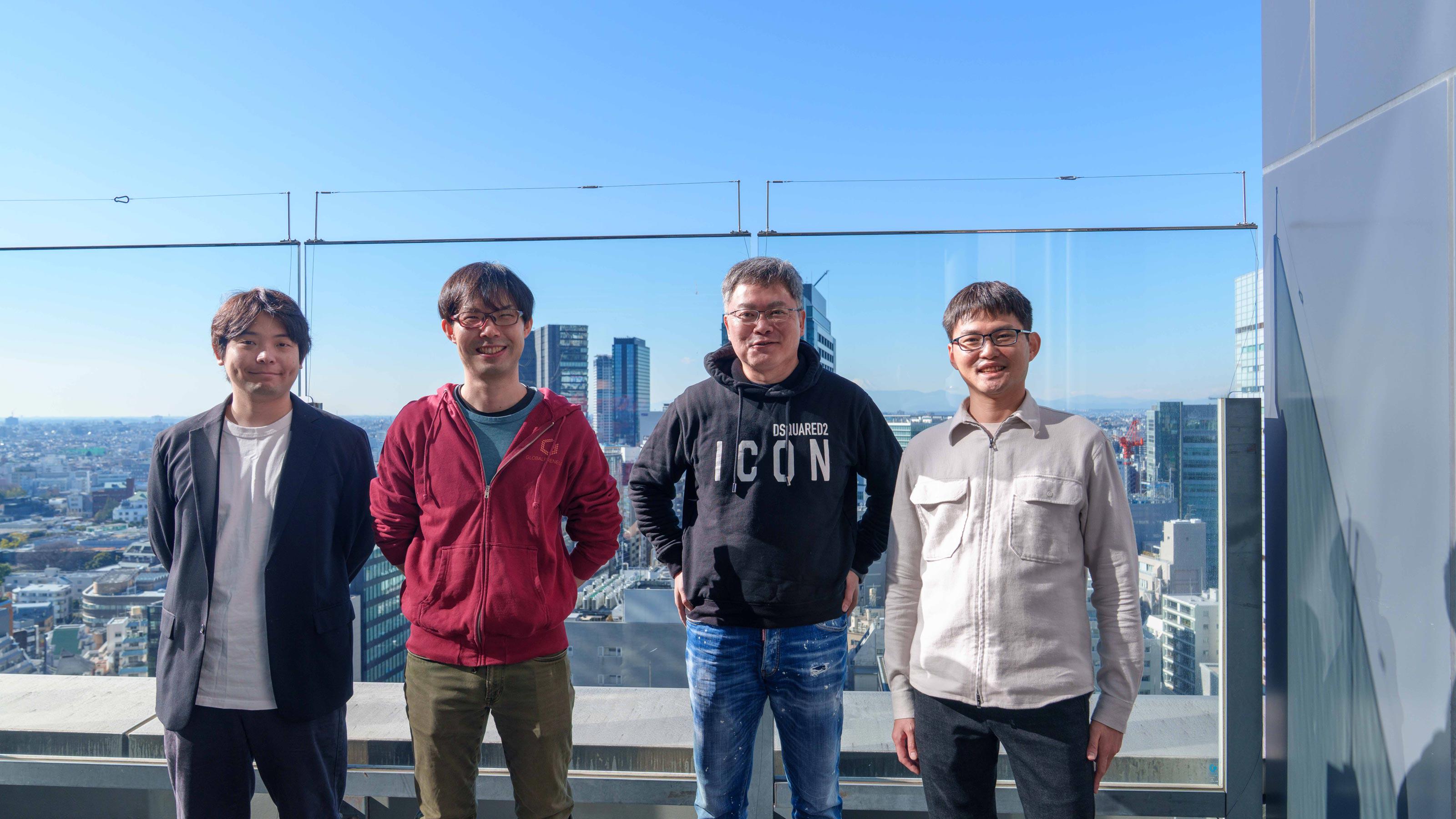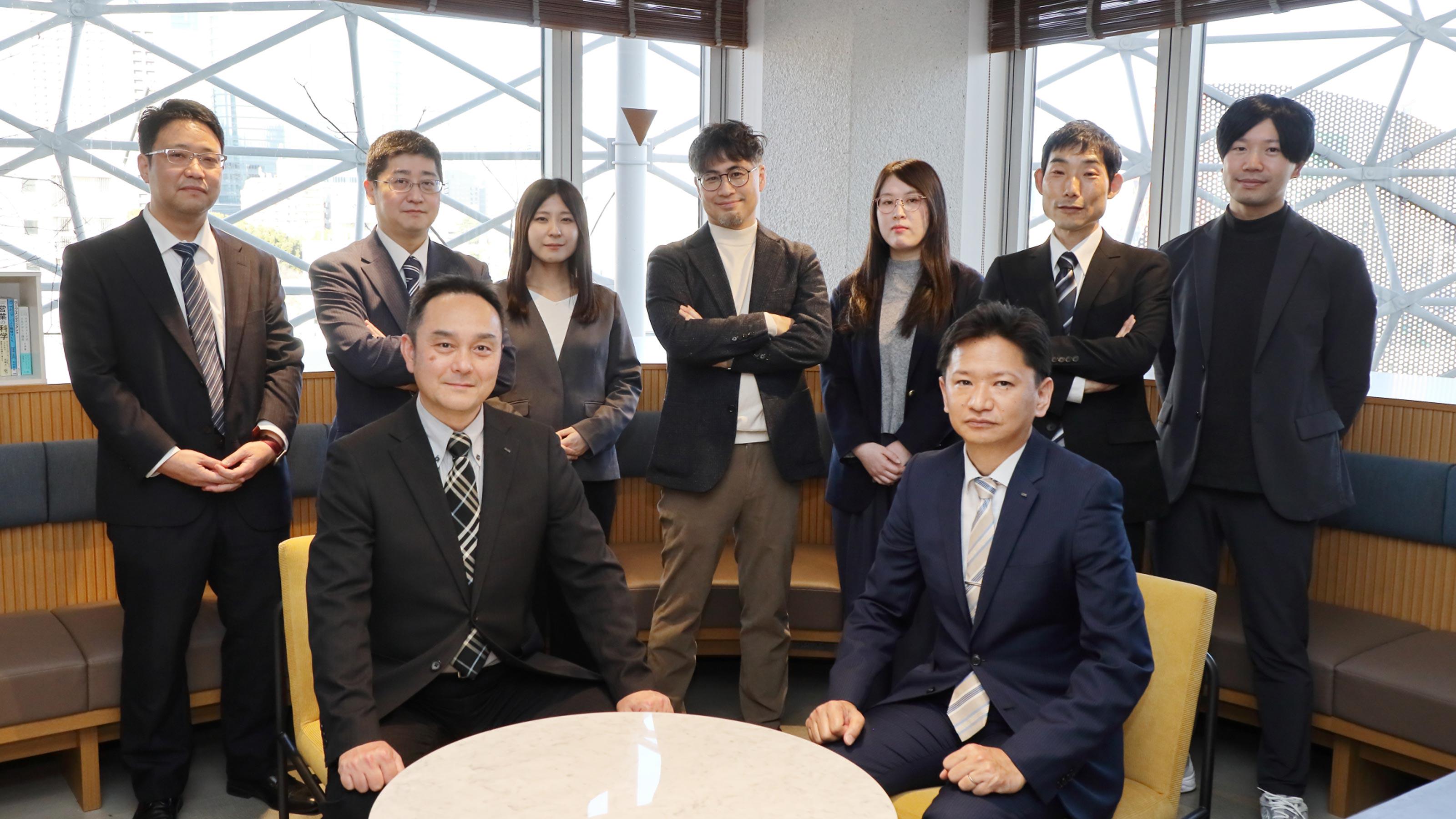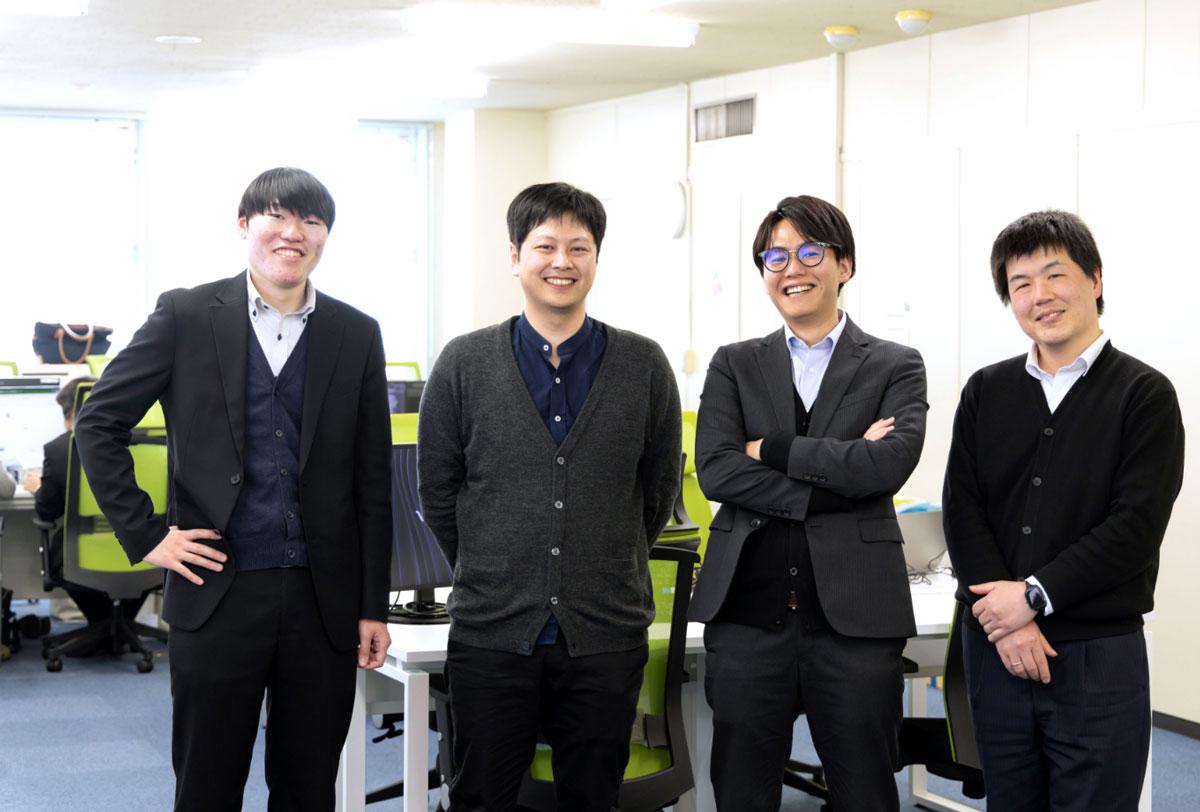株式会社アテック
- IT/Web・通信・インターネット系
全完成車メーカー・Tier1企業と取引。車に関わる最新技術に触れられるテック企業
企業について
手掛けている領域は、自動車分野が8割ほどを占める。内容としては、パワートレインやモーター、ブレーキ、エアコン、メーター、HVインバーター等、あらゆるパーツに及ぶ。残りの2割は、デジタル家電やプラント、ロボット、工作機械、航空機等。顧客には、国内の完成車メーカーおよび、そのTier1と呼ばれる大手パーツメーカーを網羅しているほか、大手の電機/機械メーカー、SIerが顔を揃える。
業務形態としては、派遣が60%、請負・受託が40%。「いずれは、請負・受託が60%、派遣40%と逆転させることを目指している」と取締役執行役員コア事業推進本部長の髙野雅史氏は言う。
同社は受託業務を行うための技術センターを擁しているが、そこでは電子回路等の評価を行うTier1メーカーと同じ設備を設けて当該業務を受託。設計から評価までウィングを広げている。
さらに同社の強みとして挙げられるのは、車載電子制御ユニット用の共通標準ソフトウェアアーキテクチャを策定・確立する自動車業界のグローバル開発パートナーシップである「AUTOSAR:Automotive Open System ARchitecture」のアソシエイトパートナーであること。全世界130社強・国内20社強が認められているが、同社のような業態の企業としては稀有の存在だ。
ヨーロッパ発の「AUTOSAR」は、安全性や拡張性、可用性等を満たすアーキテクチャとして、特に欧米で発売される車の開発には不可欠のもの。このアーキテクチャを活用することで開発工数を削減でき、それだけエラーを無くすことができる。しかし、技術的に高度で、資料等あらゆる表記が英語とハードルが高い。同社は2017年から本格的に取り組みを開始し、このほど「AUTOSAR」のBSW(Basic Soft Ware)の最大手であるドイツのベクター・インフォマティック社と、主にコンフィグレーション(設定)業務を受託するパートナー契約を締結した。2021年7月からサービスを開始し、当該業務においてのシェア率はトップレベルの地位にある。
「今後、自動運転が進展すると、さらなる安全性追求のため『AUTOSAR』はますます重視されると考えられます。このコンフィグレーションにはコンサルティング業務的な色彩が強く、アウトソーシング業を手掛ける当社にとっては新機軸となります。そこで、『AUTOSAR事業部』を設立し、本腰を入れて取り組んでおります」と髙野氏は意気込む。
スタート当初は工作機械や設備、遊技機等の機械設計から始め、徐々に領域を拡大。設備に付けるセンサーも手掛ける必要性から、電子回路やソフトウェアにも領域を広げていった。
10年後の1999年にトヨタ自動車と取引を開始し、自動車領域が主力となる。2000年から早くも燃料電池車の開発に関わる等、最先端領域を手掛け始め、現在までFCV、HV、PHVおよび関連インフラ、設備の開発に数多く携わる。
「トヨタさんがFCVの『MIRAI』の発売計画を1年前倒して2014年12月に発売しましたが、そこにも総力を挙げて全面的に関わりました」と髙野氏。
2009年には共和技術センターを建て、受託業務を本格化。翌2010年に“トータルエンジニアリングカンパニーの確立”をスローガンに、より広範な業務領域の受託を目指し始める。そして2016年、社員数1,000名を超える規模に発展した。
目標は、“オンリーワンのアウトソーシング企業”になること。その内容について、髙野氏は次のように説明する。
「アウトソーシング事業は、“単価×工数”の世界です。しかし、そこに縛られることなく、付加価値を発揮して“オンリーワン”の存在になることを目指したい。『AUTOSAR事業部』によるコンサルティングサービスは、その象徴的な存在になると考えています」
まず、上司の評価や顧客アンケートを基に1年単位で目標を設定する目標管理制度を導入。その達成を支援するために、初級・中級に分けて行う技術研修やマネジメント研修はもちろん、コミュニケーション力やプレゼン力、論理的思考力、ビジネスマナー等の人間力向上研修、品質管理や機密管理、安全衛生等の意識向上研修にも重きを置いている。名古屋市内に構える6階建ての本社ビルの1フロアを研修専用に割き、ソフトウェア設計開発、電子回路設計、機械設計のそれぞれにおいて専任講師を常駐させるという力の入れようだ。
経験豊富なエンジニアである専任講師は、主に基本的な技術と人間力向上、意識向上を受け持ち、最新技術に関しては現場で活躍しているエンジニアが挙手制で吸収したての知識やスキルを教えるカリキュラムを設けている。
「こうしたOff-JTの研修教材のほとんどは、社員の手づくりです。現場のエンジニアが一番知りたいことを知っている先輩社員が後輩社員のために作成して教えるという“順送り”の文化が根付いているのです」と髙野氏。
資格取得も、基本情報技術者・応用情報技術者や電気通信主任技術者等の技術系だけでなく、「AUTOSAR」を扱う上で不可欠の語学力を高めるTOEIC等まで幅広く対応し、対策講座や取得費用の負担、取得時の一時金支給で支援している。
また、各現場に分散している社員の求心力や一体感を高めるべく、5年ごとに全社社員旅行を実施。前回は、社員の家族も招いて
大阪のテーマパークを貸し切って休日を楽しんだ。また、毎年9月の期初には拠点ごとに社員を集めて経営方針説明会および懇親会を行っている。
社員を大切に考えている中島氏は、時に同社の拠点にあるリラックススペースに併設されたキッチンで料理をつくり、集まった社員に振る舞うという。こうしたアットホームさも、同社の魅力といえるだろう。「社員の声を積極的に吸収するフラットさがあり、『AUTOSAR』の事業化も社員の発案で決定した」と髙野氏。
そんな同社の求める人材像について、髙野氏は次のように期待を寄せる。
「お客様からは、責任感の強さや着実に業務をこなす姿勢を高く評価いただいています。半面、主体的に切り拓いて行くような動きをもっとしてほしいと要望されています。これから受託や請負業務を増やしていく上で、まさしくそういったプロアクティブな姿勢は重要です。チームワークは大事にする一方、フロンティア精神のある方に来ていただきたいと願っています」
募集している求人
エンジニア・技術職(電気/電子/機械/半導体)の求人(34件)
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(21件)
サービス職(人材/店舗/医療)の求人(1件)
アシスタント・事務職・オフィスワークの求人(1件)
営業職の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── 御社で働くやりがいや魅力を教えてください
「これからの技術」を学ぶ、とてもやりがいを感じる仕事
AUTOSAR自体が難易度が高かったり、活用するためのAUTOSAR対応ツールを扱える技術者が日本に少ない中、お客様へ知識を伝えることや、トラブルシューティングをした際にお礼を言われたときなど、とてもやりがいを感じる仕事です。また、AUTOSARを扱っていく中では「これからの技術」を学ぶ機会がたくさんあり、それが私としては仕事に対するモチベーションになってます。
また私たちがAUTOSAR事業を推進していく上で取得を目指すCEP(Vector Certified Embedded Professi... 続きを読む
求職者の声
企業情報
株式会社アテック
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
9000万円
1988年04月
代表取締役社長 立花 徹
制御ソフトウェア開発・機械設計・電子設計・電気設計・通信及びネットワーク構築、 技術系全般におけるアウトソーシング事業
■AUTOSAR事業
BSWトータルコーディネートサービス・導入支援サービス・先行開発支援サービス
○設計開発請負事業
○労働者派遣事業
労働者派遣事業許可番号 派 23-010037
○有料職業紹介事業
有料職業紹介事業労働大臣許可 23- ユ-010030
株式会社アイシン/アイシン・ソフトウェア株式会社//いすゞ自動車株式会社/ウーブン・バイ・トヨタ株式会社/川崎重工業株式会社/株式会社SUBARU/SUBARUテクノ株式会社/ダイハツ工業株式会社/株式会社デンソー/株式会社デンソーウェーブ/デンソーテクノ株式会社/株式会社デンソーテン/株式会社デンソーワイパシステムズ/豊田合成株式会社/トヨタ自動車株式会社/トヨタ自動車九州株式会社/トヨタ自動車東日本株式会社/トヨタ自動車株式会社東富士研究所/株式会社豊田自動織機/トヨタ車体株式会社/トヨタ紡織株式会社/株式会社日産オートモーティブテクノロジー/日産自動車株式会社/日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社/パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社/日立Astemo株式会社/株式会社日立製作所/株式会社日立ソリューションズ/日野自動車株式会社/ブラザー工業株式会社/ベクター・ジャパン株式会社/本田技研工業株式会社/株式会社ホンダテクノフォート/マツダ株式会社/三菱電機株式会社/三菱電機エンジニアリング株式会社/三菱電機ソフトウエア株式会社 他多数
1264人
【本社】 愛知県名古屋市東区葵三丁目24番4号 【拠点】 ・東京営業所:東京都港区 ・横浜営業所:神奈川県横浜市 ・宇都宮営業所:栃木県宇都宮市 ・豊田営業所:愛知県豊田市 ・大阪営業所:大阪府大阪市 ・広島営業所:広島県広島市 ・共和技術センター:愛知県大府市
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社アテックの中途採用/求人/転職情報