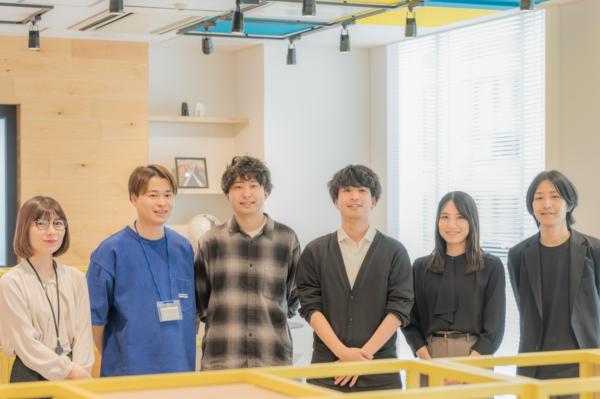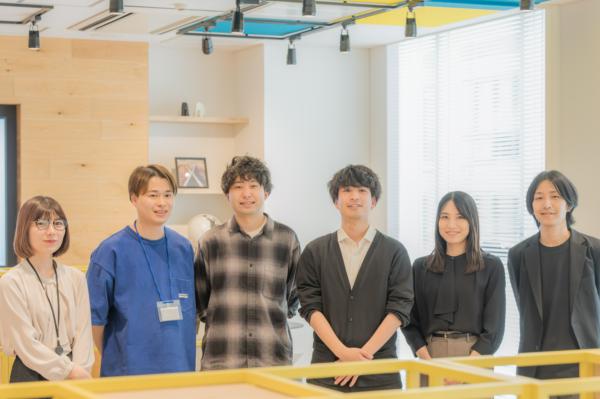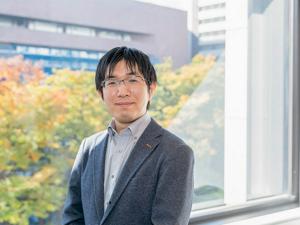株式会社ワンズパワー
- IT/Web・通信・インターネット系
金融業界のインフラ構築に強み。社員のやりたいことをかなえる会社。
残業少なめ
企業について
高度な堅牢性や厳重な安全性が求められる金融業界のインフラが得意。独自サービスも
株式会社ワンズパワーは、東証上場企業であるランサーズ株式会社のグループ企業として新たなスタートを切りました。インフラ構築や業務システム開発において、“超上流”の要件定義やコンサルテーションから、設計・開発・保守運用までをトータルに手がけるITのマルチプレーヤーです。
最大の強みは、高度な堅牢性が求められる金融業界のインフラ構築です。大手SIer等と連携し、エンドユーザー直下のプロジェクトで実績を積んできました。
近年はAIソリューションにも注力。決済サービスへのブロックチェーン活用、不正検知へのRAPID機械学習、審査業務への異種混合学習技術、窓口業務へのチャットボット導入など、先端技術を駆使した開発を推進しています。
一方、受託開発や自社サービスも拡大中です。コロナ禍以降の「リモートで働きたい」というエンジニアの声に応えるべく、建設業界向け工程管理システム等の受託開発を強化。また自社開発分野では、クラウド黎明期より、CMS不要で高機能サイトを運用できる「ReWebホスティングサービス」や「クラウド支援」をいち早く手掛けるなど、時代に先駆けた取り組みで技術的知見を蓄積してきました。
「これらは全て、金融機関の厳しい基準で培った技術知見がベースです。ランサーズグループの一員となったことで、今後はフリーランス支援や新しい働き方の提案など、より広い視野で社会に貢献できると確信しています」と、ゼネラルマネージャーの小林雄一氏は語ります。
最大の強みは、高度な堅牢性が求められる金融業界のインフラ構築です。大手SIer等と連携し、エンドユーザー直下のプロジェクトで実績を積んできました。
近年はAIソリューションにも注力。決済サービスへのブロックチェーン活用、不正検知へのRAPID機械学習、審査業務への異種混合学習技術、窓口業務へのチャットボット導入など、先端技術を駆使した開発を推進しています。
一方、受託開発や自社サービスも拡大中です。コロナ禍以降の「リモートで働きたい」というエンジニアの声に応えるべく、建設業界向け工程管理システム等の受託開発を強化。また自社開発分野では、クラウド黎明期より、CMS不要で高機能サイトを運用できる「ReWebホスティングサービス」や「クラウド支援」をいち早く手掛けるなど、時代に先駆けた取り組みで技術的知見を蓄積してきました。
「これらは全て、金融機関の厳しい基準で培った技術知見がベースです。ランサーズグループの一員となったことで、今後はフリーランス支援や新しい働き方の提案など、より広い視野で社会に貢献できると確信しています」と、ゼネラルマネージャーの小林雄一氏は語ります。
SESと受託開発を経営の2本柱に。システム開発以外の事業も視野に
同社の創業は、2008年10月。大手ICTベンダーの業務を手がけるシステム開発会社を経て、フリーランスのエンジニアとして活動していた小林氏が、SIerと直取引を始めるに当たって設立した。
「当初は自分一人で頑張るつもりだったので、『One’s Power』という社名にしました。ポリシーとしたのは、飽くなき探求心を持って新しい技術を吸収し続け、常にベストなアウトプットを生み出すこと。それと、自分の技術を提供することで、世の中のネット環境をより安全なものにしていくことも意識しました」と小林氏は言う。
そんな姿勢が認められ、セキュリティが重視される金融業界のプロジェクト案件を依頼されるようになり、メンバーを増やしていく。
「今も、メンバーに対しては『新しい技術や知識を貪欲に吸収する努力を忘れないでほしい』と常に話しています。我々はサービス業であり、お客様に喜ばれることがすべて。お客様から言われたことだけに唯々諾々と従うのではなく、吸収した技術や知識でよりよい改善策やお客様が気づかない問題点を提案・指摘してほしいと要望しています。そんな意識がカルチャーとして定着してきましたね」(小林氏)
今後のビジョンとしては、短期的には受託案件を増やしてSESとの二本柱にすること。その先に、アイデアやチャンスがあれば、自社サービスづくりにも着手する。そして、「中長期的には、システム開発以外のビジネスにももっと取り組んでいきたい」と小林氏。
同社はすでに「ART INCUBATOR」事業をスタートさせている。これは、イミテーションではなく作家の本物の作品を企業などにレンタルするサービス。作品は同社がセレクトし、額装して2カ月ごとに入れ替えるというものだ。
「当社は、メンバーがやりたいことの実現を大きな方針に掲げています。そこで、あるメンバーから『小林さんは何がやりたいの?』と問われたことを機に、このサービスを考えました。当社はこれまで、“企業とエンジニア”“新技術とクライアント”といったマッチングに取り組んできました。そこで、私が関心のある“アート作品”を企業にマッチングすることを思いついたわけです」と小林氏は説明する。
こうした幅の広さや柔軟性が、同社の一つの魅力といえるかもしれない。
「当初は自分一人で頑張るつもりだったので、『One’s Power』という社名にしました。ポリシーとしたのは、飽くなき探求心を持って新しい技術を吸収し続け、常にベストなアウトプットを生み出すこと。それと、自分の技術を提供することで、世の中のネット環境をより安全なものにしていくことも意識しました」と小林氏は言う。
そんな姿勢が認められ、セキュリティが重視される金融業界のプロジェクト案件を依頼されるようになり、メンバーを増やしていく。
「今も、メンバーに対しては『新しい技術や知識を貪欲に吸収する努力を忘れないでほしい』と常に話しています。我々はサービス業であり、お客様に喜ばれることがすべて。お客様から言われたことだけに唯々諾々と従うのではなく、吸収した技術や知識でよりよい改善策やお客様が気づかない問題点を提案・指摘してほしいと要望しています。そんな意識がカルチャーとして定着してきましたね」(小林氏)
今後のビジョンとしては、短期的には受託案件を増やしてSESとの二本柱にすること。その先に、アイデアやチャンスがあれば、自社サービスづくりにも着手する。そして、「中長期的には、システム開発以外のビジネスにももっと取り組んでいきたい」と小林氏。
同社はすでに「ART INCUBATOR」事業をスタートさせている。これは、イミテーションではなく作家の本物の作品を企業などにレンタルするサービス。作品は同社がセレクトし、額装して2カ月ごとに入れ替えるというものだ。
「当社は、メンバーがやりたいことの実現を大きな方針に掲げています。そこで、あるメンバーから『小林さんは何がやりたいの?』と問われたことを機に、このサービスを考えました。当社はこれまで、“企業とエンジニア”“新技術とクライアント”といったマッチングに取り組んできました。そこで、私が関心のある“アート作品”を企業にマッチングすることを思いついたわけです」と小林氏は説明する。
こうした幅の広さや柔軟性が、同社の一つの魅力といえるかもしれない。
月1回の1 on 1でメンバーがやりたいことを確認
2023年5月現在、同社では20名の社員が業務に取り組んでいる。高度な技術力を身に着け自律できるエンジニア揃いで、顧客プロジェクト現場に関わるケースが多い。そうした事情もあって、毎月定例会を開いて各現場の状況などを共有しているほか、月1回のペースで全メンバーと1 on 1を行っている。
「自社オフィスならば毎日顔を合わせますから、月1回でも少ないくらいだと思います。状況確認や今後の課題だけでなく、プライベートの状況を聞いたり顔色を見て、心身のコンディションもチェックするようにしています」(小林氏)
そして、話し好きの小林氏は、1 on 1では現在の仕事のことだけでなく、メンバーがやりたいことを必ず聞くという。そこから、新規事業のアイデアを見つけるためだ。
「例えば、農業をやりたいというメンバーがいれば、必ず会社としてどう関われるかを考えます。このように、メンバーがやりたいことに対して極めてポジティブかつ柔軟な姿勢があると自負しています」
人材育成としては、「メンバーの学習に対する投資は厭わない」と小林氏は話す。また、日常的なメンバーによる業務報告の際、背景を含めて端的に説明するスキルや、より伝わりやすい話し方といったヒューマンスキルも意識的に指導しているという。このスキルがPMO業務に活かせていることはいうまでもない。
また、同社では国家資格キャリアコンサルタントの有資格者もおり、社員の単純なスキルアップにとどまらず、個々がどうなりたいか、どうありたいかを業務で扱い、若手もベテランも関係なく社員のキャリアアップをはかっている。
現在はまだ20名の組織であるが、「今後100名、200名となってもヒエラルキー型の組織をつくるつもりはない」と小林氏。志向しているのは、フラットなティール型組織だ。現場のエンジニアの中で、リーダー志向や能力のある者が一定のサイズのチームをまとめる“役割”を担う程度の管理形態である。
「課長や部長といった管理職と現場の作業者を明確に分けるような組織は、日本的ではないとの思いがあります。あくまでもプレーヤーが主体のチームとして、全員が協調して一つのミッションに向かうといったイメージです」(小林氏)
メンバー同士の親睦を深める機会としては、コロナ以前は毎年、全員でスノーボードを楽しむといったイベントを行っていた。「メンバーの要請もあり、コロナが落ち着いたら再開したい」と小林氏。
そんな同社が求める人材像として、小林氏は次のように話す。
「明確なテーマがなくても、何かやりたいという思いがある人。そういう思いさえあれば、やりたいことを見つける手助けができます。当社は、何かやりたいと思っている人たちの集団なので、入社すれば一斉に『何をやりたいの?』と聞かれるでしょう(笑)。それにポジティブに応えられれば、当社に馴染めると思います」
「自社オフィスならば毎日顔を合わせますから、月1回でも少ないくらいだと思います。状況確認や今後の課題だけでなく、プライベートの状況を聞いたり顔色を見て、心身のコンディションもチェックするようにしています」(小林氏)
そして、話し好きの小林氏は、1 on 1では現在の仕事のことだけでなく、メンバーがやりたいことを必ず聞くという。そこから、新規事業のアイデアを見つけるためだ。
「例えば、農業をやりたいというメンバーがいれば、必ず会社としてどう関われるかを考えます。このように、メンバーがやりたいことに対して極めてポジティブかつ柔軟な姿勢があると自負しています」
人材育成としては、「メンバーの学習に対する投資は厭わない」と小林氏は話す。また、日常的なメンバーによる業務報告の際、背景を含めて端的に説明するスキルや、より伝わりやすい話し方といったヒューマンスキルも意識的に指導しているという。このスキルがPMO業務に活かせていることはいうまでもない。
また、同社では国家資格キャリアコンサルタントの有資格者もおり、社員の単純なスキルアップにとどまらず、個々がどうなりたいか、どうありたいかを業務で扱い、若手もベテランも関係なく社員のキャリアアップをはかっている。
現在はまだ20名の組織であるが、「今後100名、200名となってもヒエラルキー型の組織をつくるつもりはない」と小林氏。志向しているのは、フラットなティール型組織だ。現場のエンジニアの中で、リーダー志向や能力のある者が一定のサイズのチームをまとめる“役割”を担う程度の管理形態である。
「課長や部長といった管理職と現場の作業者を明確に分けるような組織は、日本的ではないとの思いがあります。あくまでもプレーヤーが主体のチームとして、全員が協調して一つのミッションに向かうといったイメージです」(小林氏)
メンバー同士の親睦を深める機会としては、コロナ以前は毎年、全員でスノーボードを楽しむといったイベントを行っていた。「メンバーの要請もあり、コロナが落ち着いたら再開したい」と小林氏。
そんな同社が求める人材像として、小林氏は次のように話す。
「明確なテーマがなくても、何かやりたいという思いがある人。そういう思いさえあれば、やりたいことを見つける手助けができます。当社は、何かやりたいと思っている人たちの集団なので、入社すれば一斉に『何をやりたいの?』と聞かれるでしょう(笑)。それにポジティブに応えられれば、当社に馴染めると思います」
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(15件)
すべて見る
企画・マーケティング職の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── 会社を設立して実現できたこととは?
会社経営者として、会社間のトラブルやその解決に取り組むなど、従業員やフリーランスの立場では経験できなかったことを経験できました。
また、会社としては、大手SIerや有名SIerと取引口座を開設できたことが大きかったと思います。普通、フリーランスが会社を設立したぐらいで取引できるような相手ではありませんが、その会社の方々がいろいろ考慮して動いてくれたおかげです。そんな恩も感じることができていますね。
このように、自分一人では力が及ばず、いろいろな人に助けてもらうことで前に進められることを経験しています。こうした経験を通じて、人として成長できたのではない... 続きを読む
社員の声
すべて見る企業情報
会社名
株式会社ワンズパワー
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
企業の特徴
残業少なめ資本金
1250万円
設立年月
2008年10月
代表者氏名
代表取締役 後藤 信彦
事業内容
■システムインフラの企画、設計、構築、メンテナンス
■金融系アプリケーション設計、開発
■プロジェクトマネジメント業務
■クラウド環境への導入提案、設計、構築、移行
■ホームページの企画、作成
■アートインキュベータ事業
■労働派遣事業(派13-305642)
株式公開(証券取引所)
主要取引先
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ シンプレクス株式会社 他
従業員数
20人
本社住所
東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町 1310号室
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社ワンズパワーに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社ワンズパワーの中途採用/求人/転職情報