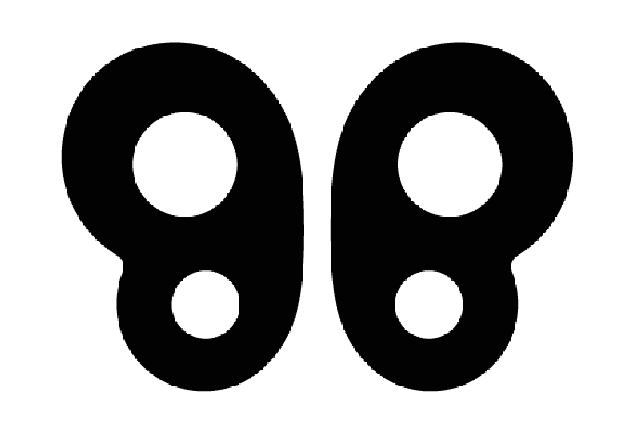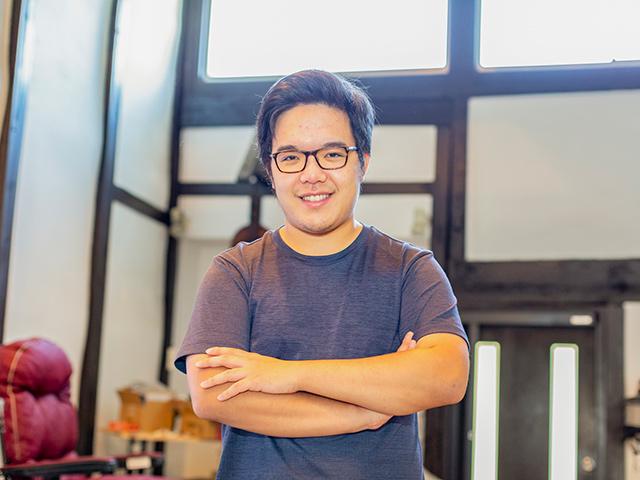BonBon株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
- サービス系
"Gamify Medicine"をコンセプトに 「あたらしい医療」を生み出す
上場を目指す
自社サービス製品あり
企業について
"Gamify Medicine"を実現する3つの柱
BonBon株式会社は"Gamify Medicine"をコンセプトに「あたらしい医療」の実現を目指す、京都発のスタートアップ企業だ。
エンジニアも、デザイナーも、教育者も 誰もが「あたらしい医療者」に
医療は「つらい」「痛い」「苦い」「めんどくさい」など、ネガティブなイメージや心理的ハードルがつきまとうものでもある。また、医療従事者の世界においても臨床・研究・教育の中では教育にあまり着目されてこなかった歴史もある。
莊子氏は「患者もまた自分自身の専門家であり、医療におけるプレイヤーである」という考えがあり、医療にかかる心理的ハードルを直感・論理双方の側面から下げていく必要があると考えている。
そのような「あたらしい医療」を実装する上では、医師だけが医療社なのではなく、エンジニアもデザイナーも全ての人が「あたらしい医療者」になり得ると考えている。
「世の中では、『人かAIか』『患者か医療者か』など、多くの『か』の議論があります。しかし、私はこの『か』を『と』に変えてこそ、あたらしい解決策が生まれると思うのです。これからは、エンジニアやデザイナーが“薬”を作れる時代です。既存の医療者とは違った視点でアプローチするからこそ、解決できる問題や、治せる病気があると思います。エンジニアやデザイナーとしての技術と経験を使い、医療の世界で是非活躍してほしいです。私達は、既存の医療では盲点になりがちな境界領域や辺境領域にある問題を解決したいと考えています。医療機関と医療機関が、オンラインでスムーズに繋がるように。多職種の集合体である私達が医療を支える『あたらしい医療者』となって、『あたらしい医療』をつくり出していきたいと思います」(荘子氏)
莊子氏は「患者もまた自分自身の専門家であり、医療におけるプレイヤーである」という考えがあり、医療にかかる心理的ハードルを直感・論理双方の側面から下げていく必要があると考えている。
そのような「あたらしい医療」を実装する上では、医師だけが医療社なのではなく、エンジニアもデザイナーも全ての人が「あたらしい医療者」になり得ると考えている。
「世の中では、『人かAIか』『患者か医療者か』など、多くの『か』の議論があります。しかし、私はこの『か』を『と』に変えてこそ、あたらしい解決策が生まれると思うのです。これからは、エンジニアやデザイナーが“薬”を作れる時代です。既存の医療者とは違った視点でアプローチするからこそ、解決できる問題や、治せる病気があると思います。エンジニアやデザイナーとしての技術と経験を使い、医療の世界で是非活躍してほしいです。私達は、既存の医療では盲点になりがちな境界領域や辺境領域にある問題を解決したいと考えています。医療機関と医療機関が、オンラインでスムーズに繋がるように。多職種の集合体である私達が医療を支える『あたらしい医療者』となって、『あたらしい医療』をつくり出していきたいと思います」(荘子氏)
多彩な領域の専門家が集まり 夢へ向かって邁進中
【なにをやっているのか】
医療業界においては難易度が高いと言われているアジャイル型開発に取り組むプレイヤーとして医療業界が抱えるさまざまな問題に向き合い、クライアントと共に協業しながら新しいプロダクトやサービスの開発を行っています。
BonBonでは、単なる受託形式とは異なりアジャイル型でプロジェクトを進めていくため、段階的に課題や業務に対する理解が深まり、正しい理解のもとで最適なプロダクト開発を行える環境を整えています。
病院やクリニック、大学研究機関や民間企業等の医療業界内のステークホルダーが持つ課題解決に加えて、業界外から医療分野に参入する際に「何をすればよいかわからない」といった参入障壁も一つ一つ紐解きながら、共に乗り越え、新たな価値をともに提案していきます。
医療業界においては難易度が高いと言われているアジャイル型開発に取り組むプレイヤーとして医療業界が抱えるさまざまな問題に向き合い、クライアントと共に協業しながら新しいプロダクトやサービスの開発を行っています。
BonBonでは、単なる受託形式とは異なりアジャイル型でプロジェクトを進めていくため、段階的に課題や業務に対する理解が深まり、正しい理解のもとで最適なプロダクト開発を行える環境を整えています。
病院やクリニック、大学研究機関や民間企業等の医療業界内のステークホルダーが持つ課題解決に加えて、業界外から医療分野に参入する際に「何をすればよいかわからない」といった参入障壁も一つ一つ紐解きながら、共に乗り越え、新たな価値をともに提案していきます。
求職者の声
企業情報
会社名
BonBon株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
サービス系 > 医療・福祉・介護サービス
企業の特徴
上場を目指す、自社サービス製品あり資本金
6,600万円
設立年月
2018年04月
代表者氏名
代表取締役 荘子 万能
事業内容
――感情と情報を結び、あたらしい医療をつくる――
BonBon株式会社は、多様な職種のスタッフ及び当社のネットワークの仲間たちとともに、より良い医療を目指して日々挑戦している、京都発の医療関連ソフトウェア開発スタートアップ企業です。
【事業内容】
▽ 医療関連ソフトウェア開発
▽ 医療関連業務支援
株式公開(証券取引所)
非上場
従業員数
12人
本社住所
京都府京都市中京区壬生上大竹町22
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- BonBon株式会社の中途採用/求人/転職情報