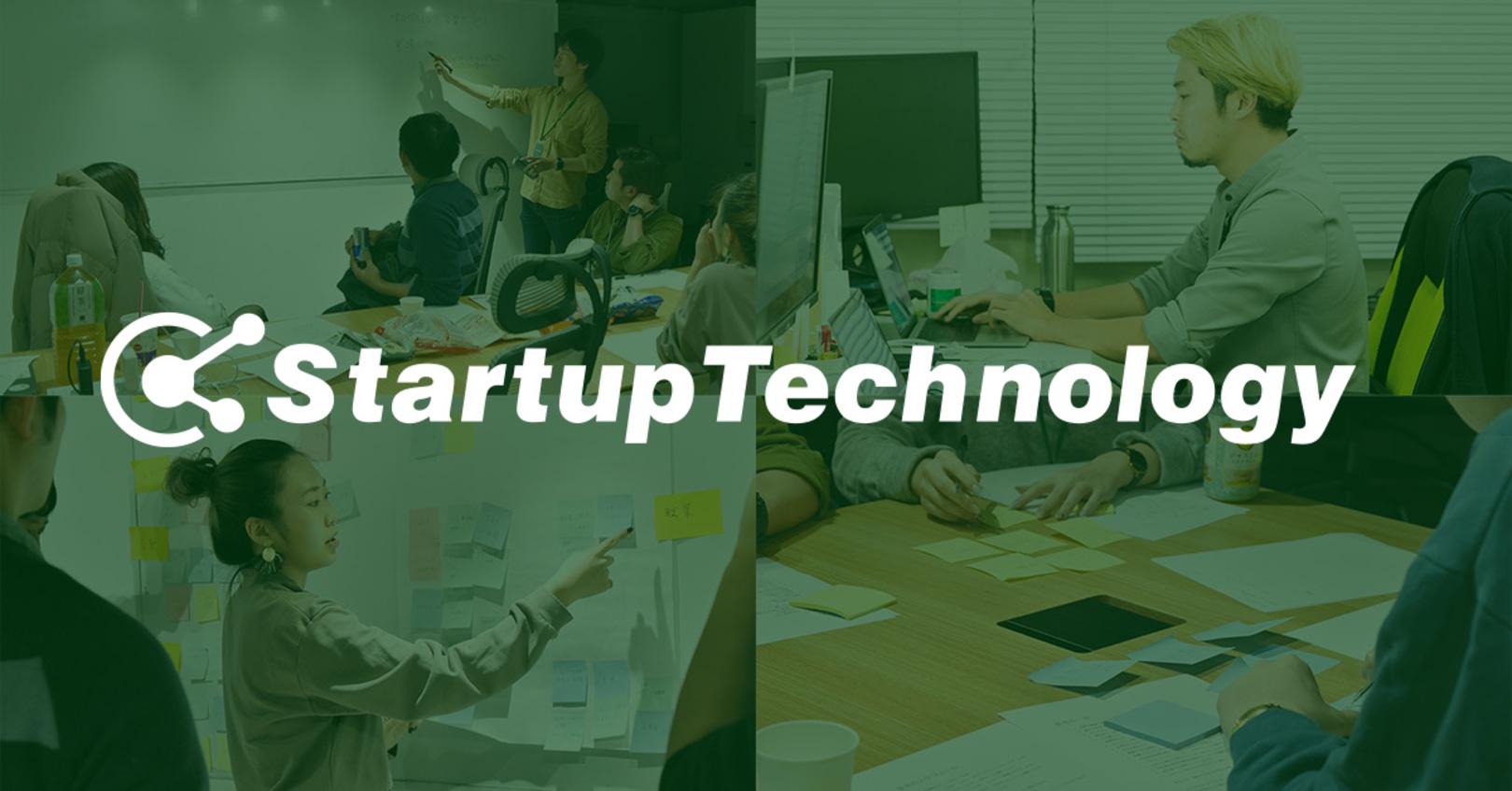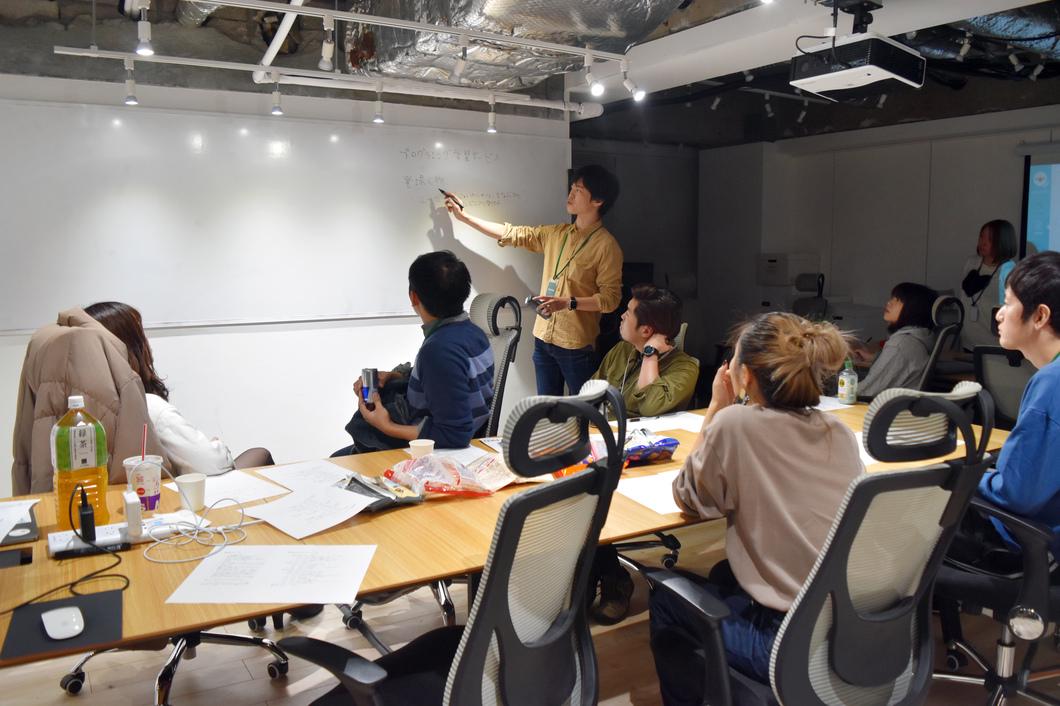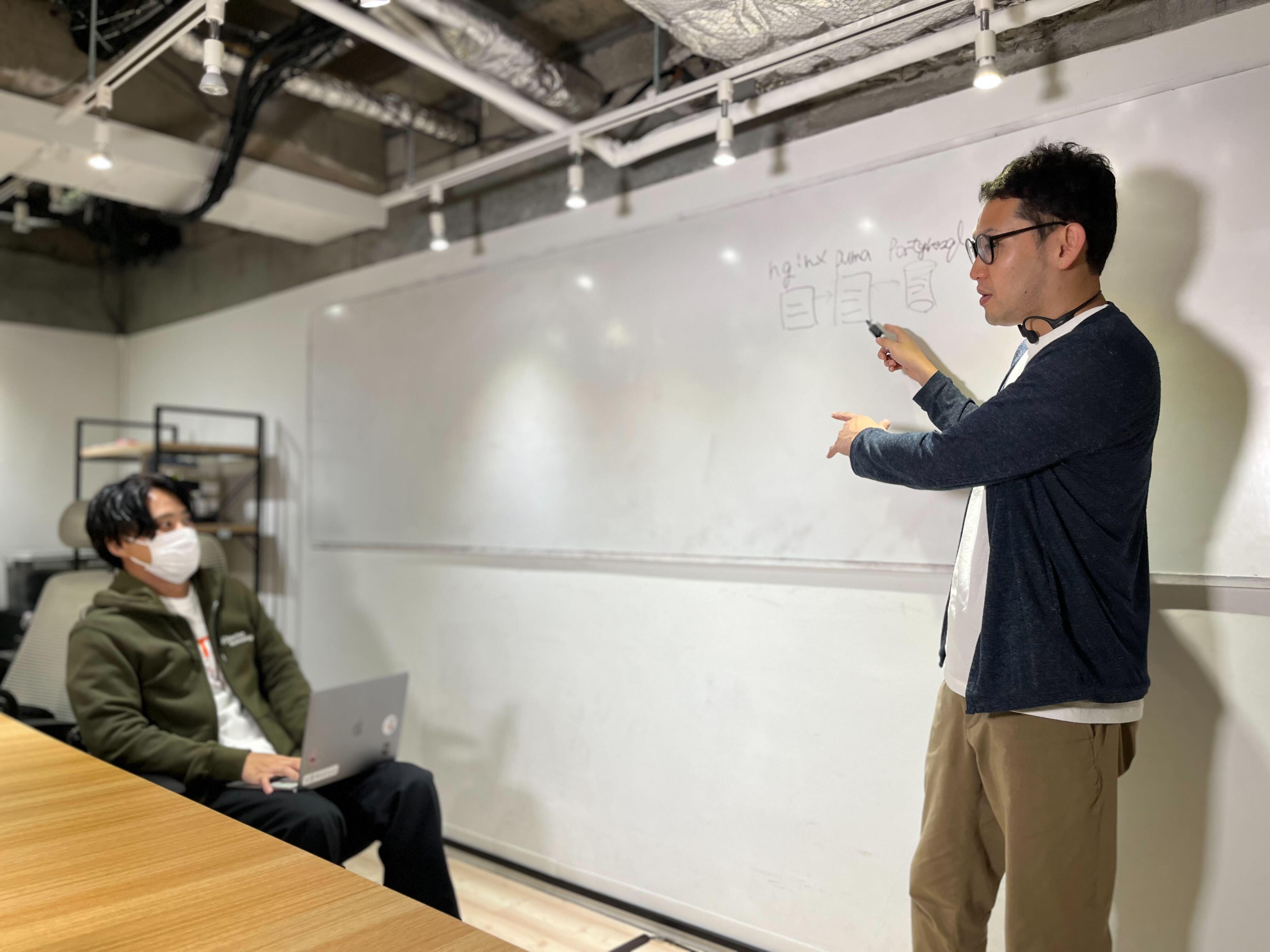株式会社スタートアップテクノロジー
- IT/Web・通信・インターネット系
- サービス系
超実践型エンジニア育成スクール「RUNTEQ」・Webサービスの開発
上場を目指す
自社サービス製品あり
残業少なめ
カジュアル面談歓迎
企業について
「開発力を増やす」ことで起業家に機会を与え、「開発内製化を実現する」ことで世の中に生む価値を増やす
株式会社スタートアップテクノロジーは、Webサービスの企画、開発、制作、運営やコンサルティングをおこなっている会社だ。「開発力を増やす」というミッションのもと、スタートアップ企業のWebサービスの新規開発を中心に、UI/UXデザインや、エンジニア教育事業を手がけている。設立は2014年10月で、東京都渋谷区宇田川町に本社を置く。
市場ではサービスの立ち上げに強みを持つ、Ruby on Rails専門のWebシステム開発会社として知られている。また、上場企業の技術部長やスタートアップのCTOを経験してきた菊本久寿氏が代表取締役を務めていることもあり、スタートアップ界隈での知名度も高い。菊本氏はSIerなどを経て、ngi group(現 ユナイテッド株式会社)の技術部部長時代はアドテク関連サービス立ち上げに関与。2012年からフリーランスとして独立し、「レンタルCTO」という肩書で、技術顧問として現在上場しているような名だたるスタートアップの開発支援を行ってきた。様々な環境で開発をする中で、起業家に寄り添ったWebサービス開発ができる会社が少なすぎるという課題を解決するため、スタートアップテクノロジーを設立している。
スタートアップテクノロジーの主な事業は、Webサービス開発、運用や、Webサービスのデザイン制作だ。得意とする業界はスタートアップ企業や大手企業の新規事業部門で、顧客にとって必要なシステムは何かを一緒に考えていくスタイルが特徴。Webサービスの新規開発プロジェクトでは、開発段階では何が正解か分からないので完成形も見えず、柔軟に変更を加えていかないとローンチ後のビジネススピードにもついていけないためだ。また、事業のマーケティングやUI/UXデザインまで社内で完結できる点も他社には無い強みとしている。
また、Webエンジニア教育事業も順調に拡大している。世の中に新しい価値を生み出そうとしている起業家に対して、「つくる」ことを通した貢献をおこなう。そして、世の中に価値を生み出せるつくれる人を見出し、「開発力を増やしていくこと」、開発内製化を実現することを通じて、社会に存在する価値の総量を高め、未来を担う子どもたちが安心して暮らせる仕組みを創造していく。
市場ではサービスの立ち上げに強みを持つ、Ruby on Rails専門のWebシステム開発会社として知られている。また、上場企業の技術部長やスタートアップのCTOを経験してきた菊本久寿氏が代表取締役を務めていることもあり、スタートアップ界隈での知名度も高い。菊本氏はSIerなどを経て、ngi group(現 ユナイテッド株式会社)の技術部部長時代はアドテク関連サービス立ち上げに関与。2012年からフリーランスとして独立し、「レンタルCTO」という肩書で、技術顧問として現在上場しているような名だたるスタートアップの開発支援を行ってきた。様々な環境で開発をする中で、起業家に寄り添ったWebサービス開発ができる会社が少なすぎるという課題を解決するため、スタートアップテクノロジーを設立している。
スタートアップテクノロジーの主な事業は、Webサービス開発、運用や、Webサービスのデザイン制作だ。得意とする業界はスタートアップ企業や大手企業の新規事業部門で、顧客にとって必要なシステムは何かを一緒に考えていくスタイルが特徴。Webサービスの新規開発プロジェクトでは、開発段階では何が正解か分からないので完成形も見えず、柔軟に変更を加えていかないとローンチ後のビジネススピードにもついていけないためだ。また、事業のマーケティングやUI/UXデザインまで社内で完結できる点も他社には無い強みとしている。
また、Webエンジニア教育事業も順調に拡大している。世の中に新しい価値を生み出そうとしている起業家に対して、「つくる」ことを通した貢献をおこなう。そして、世の中に価値を生み出せるつくれる人を見出し、「開発力を増やしていくこと」、開発内製化を実現することを通じて、社会に存在する価値の総量を高め、未来を担う子どもたちが安心して暮らせる仕組みを創造していく。
プロ集団としての専門性と、スクール運営による人材育成が特徴
スタートアップテクノロジーは、超実践型エンジニア育成スクール「RUNTEQ」の運営と Ruby on RailsによるWebサービス開発を手がける「開発部」から構成される。
ビジネスモデルの特徴としては、スタートアップや大手企業のWebサービス開発を月額型で受託している。一般的には請負と言われる納品型が業界の主流だが、Webサービス開発は技術やトレンドの移り変わりが早いため、高速に仮説検証ができる「アジャイル開発」を採用。月額型で開発にあたるため、結果として開発中の仕様変更や、方向性の変更にあわせて開発内容を柔軟に変更するなど、自社でサービスの開発と近い形で業務をおこなっている。
さらに、受託開発で培ったエンジニアの育成ロジックを活用し、エンジニアリングスクール「RUNTEQ」の運営も手がけている。講師は開発の現場に立つエンジニアが行うため、実際の開発現場のノウハウが身につく“超実践型”の講義内容が特徴。卒業生の転職支援もおこなっている。
職種別ではエンジニアは主にピッチコンテストで入賞するようなスタートアップのサービス開発や、大手企業の事業開発など、さまざまなプロジェクトのシステム開発に携わる。月額制のため納品型のように都度見積もりを取ることなく、顧客と直接関わりながら、チームメンバーとして自由度高く開発に集中できる。将来的には、エンジニアのマネジメントや教育だけでなく、これまでになかったエンジニア教育サービスなどの自社サービス開発でも活躍できる。
デザイナーは主にUIデザインやコーディングを担当する。「グラフィックデザインの経験しかない」という人でも、サポートを受けながらUIデザインに携わることができる。クライアントワークだけでなく自社開発のプロジェクトもあるため、ロゴ制作やフライヤーなど、活躍の場は幅広く用意されている。
ビジネスモデルの特徴としては、スタートアップや大手企業のWebサービス開発を月額型で受託している。一般的には請負と言われる納品型が業界の主流だが、Webサービス開発は技術やトレンドの移り変わりが早いため、高速に仮説検証ができる「アジャイル開発」を採用。月額型で開発にあたるため、結果として開発中の仕様変更や、方向性の変更にあわせて開発内容を柔軟に変更するなど、自社でサービスの開発と近い形で業務をおこなっている。
さらに、受託開発で培ったエンジニアの育成ロジックを活用し、エンジニアリングスクール「RUNTEQ」の運営も手がけている。講師は開発の現場に立つエンジニアが行うため、実際の開発現場のノウハウが身につく“超実践型”の講義内容が特徴。卒業生の転職支援もおこなっている。
職種別ではエンジニアは主にピッチコンテストで入賞するようなスタートアップのサービス開発や、大手企業の事業開発など、さまざまなプロジェクトのシステム開発に携わる。月額制のため納品型のように都度見積もりを取ることなく、顧客と直接関わりながら、チームメンバーとして自由度高く開発に集中できる。将来的には、エンジニアのマネジメントや教育だけでなく、これまでになかったエンジニア教育サービスなどの自社サービス開発でも活躍できる。
デザイナーは主にUIデザインやコーディングを担当する。「グラフィックデザインの経験しかない」という人でも、サポートを受けながらUIデザインに携わることができる。クライアントワークだけでなく自社開発のプロジェクトもあるため、ロゴ制作やフライヤーなど、活躍の場は幅広く用意されている。
混雑した電車とは無縁。リモート勤務中心、家事・育児との両立も可能
メンバーの平均年齢は35歳で、男女比はおおよそ5:5。マネージャー・部長級の管理職として活躍する女性もいる。また、子育て中の男性エンジニアも多く、複数人の子育てと仕事を両立させている女性スタッフも在籍する。40~60代のエンジニアも複数名在籍しており、柔軟な働き方ができるよう、勤務時間はコアタイムなしのフレックス制度を導入。子供の体調不良や行事、家族の介護などにも柔軟に対応できるようリモート勤務が中心だ。リモート勤務が中心ではあるが、コミュニケーションは多く、勉強会なども頻繁に行われている。
主な福利厚生は、PC購入支援制度(15万円)がある。BYOD(Bring your own device:私的デバイスの活用)で業務にあたるため、そのための費用補助をおこなっている。その他の社内制度としては、書籍購入補助、社内勉強会、社内飲み会、1on1(個別面談)、定例全社会議、開発合宿などがある。
仕事のアウトプットにはしっかりと責任をもって取り組み、顧客の課題解決を楽しめる人がフィットしているだろう。また、セルフマネジメントができること、物事を論理的に考えることができること、若手の育成に携わりたい、といった指向性も歓迎される。
エンジニア教育領域、Webサービスの開発とで成長するスタートアップテクノロジーで、一緒にチャレンジをしてくれる方からの応募を待っている。
主な福利厚生は、PC購入支援制度(15万円)がある。BYOD(Bring your own device:私的デバイスの活用)で業務にあたるため、そのための費用補助をおこなっている。その他の社内制度としては、書籍購入補助、社内勉強会、社内飲み会、1on1(個別面談)、定例全社会議、開発合宿などがある。
仕事のアウトプットにはしっかりと責任をもって取り組み、顧客の課題解決を楽しめる人がフィットしているだろう。また、セルフマネジメントができること、物事を論理的に考えることができること、若手の育成に携わりたい、といった指向性も歓迎される。
エンジニア教育領域、Webサービスの開発とで成長するスタートアップテクノロジーで、一緒にチャレンジをしてくれる方からの応募を待っている。
求職者の声
企業情報
会社名
株式会社スタートアップテクノロジー
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
サービス系 > 人材サービス(紹介/派遣/教育/研修)
IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場を目指す、自社サービス製品あり、残業少なめ資本金
77百万円
設立年月
2014年10月
代表者氏名
代表取締役 菊本 久寿
事業内容
「開発力を増やす」というミッション、「開発内製化を実現する」というビジョンのもと、スタートアップ企業や大手企業の新規Webサービス開発を中心に、UI/UXデザインや、エンジニア教育事業を手がけています。
・Webエンジニア教育事業
・月額制によるWebサービス開発
・Webサービス、スマートフォンアプリのUI / UXデザイン
株式公開(証券取引所)
従業員数
47人
平均年齢
33歳
本社住所
東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル 5階 B室
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社スタートアップテクノロジーの中途採用/求人/転職情報