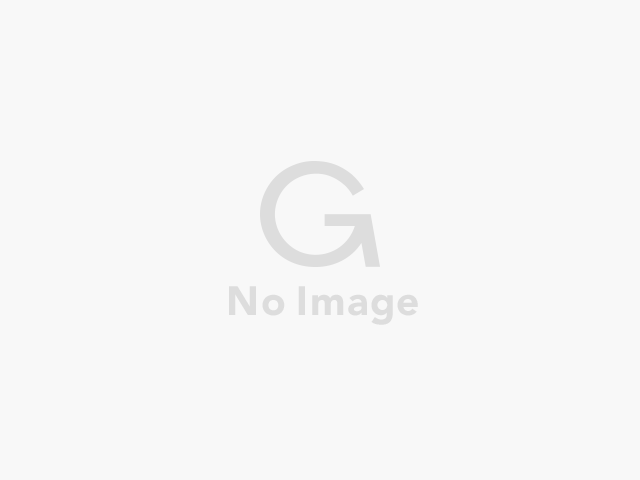STAGE株式会社
- その他
準備中
自社サービス製品あり
グローバルに活動
残業少なめ
企業情報
会社名
STAGE株式会社
業界
その他 > その他業界
企業の特徴
自社サービス製品あり、グローバルに活動、残業少なめ資本金
確認準備中
売上(3年分)
2017年 8月 8百万
2018年 8月 14百万
2019年 8月 180百万
設立年月
2022年02月
代表者氏名
反映中
事業内容
確認準備中
株式公開(証券取引所)
従業員数
47人
本社住所
確認準備中
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- その他
- その他業界
- STAGE株式会社の中途採用/求人/転職情報