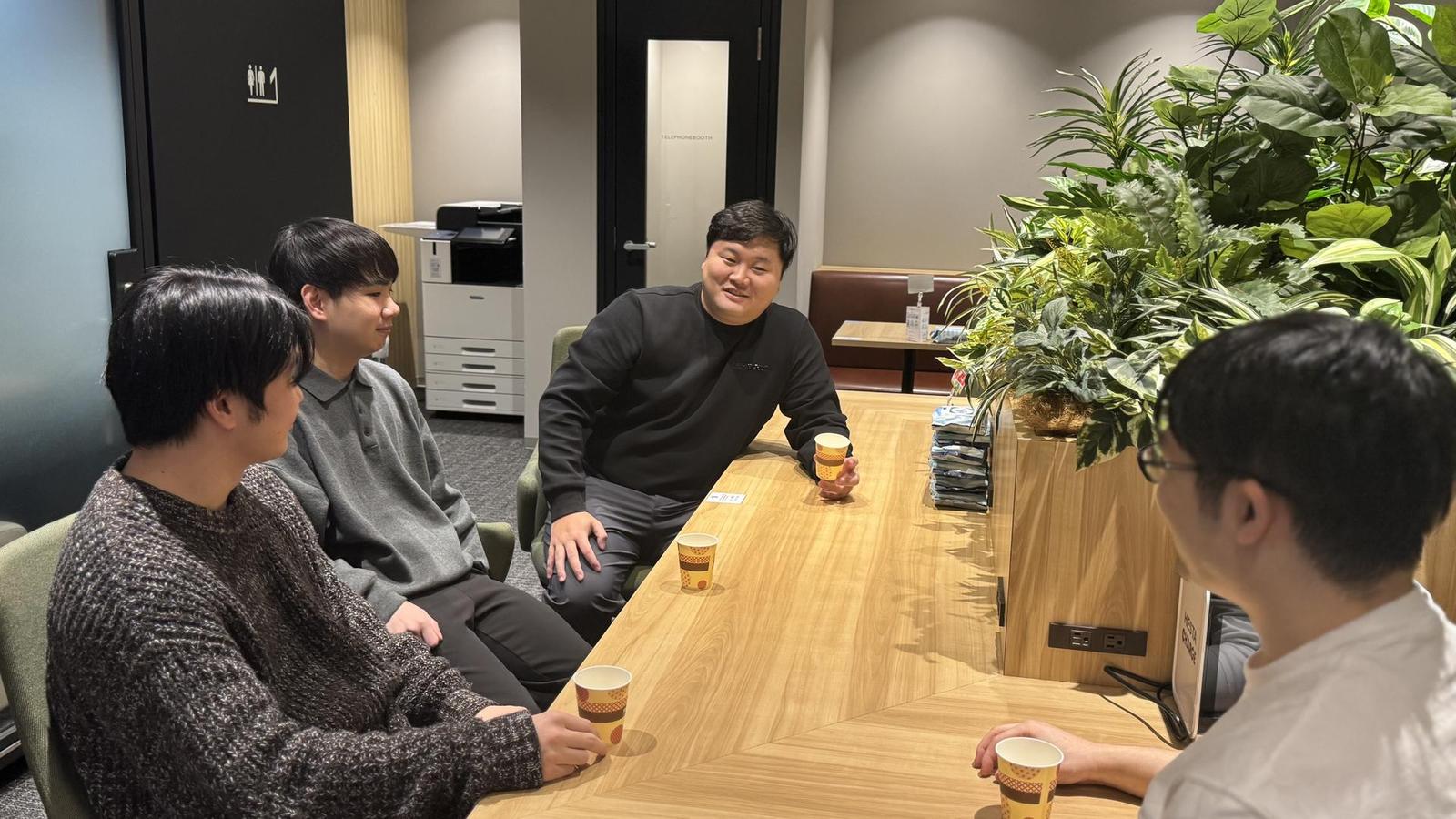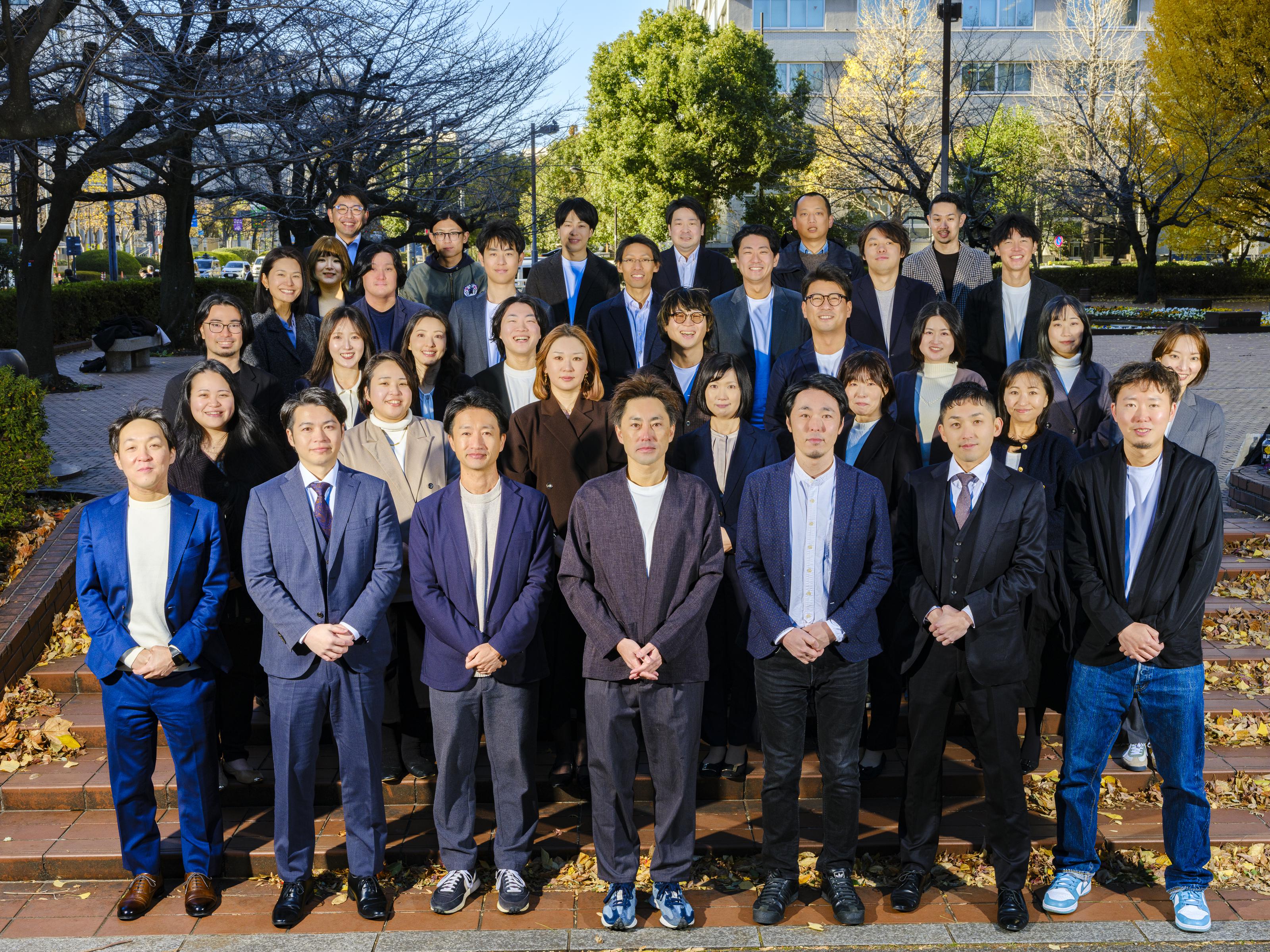弥生株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
- 金融・保険系
業界シェアNo.1のSaaS開発企業!! 中小企業向けの事業支援サービスで変革は止まらない
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
残業少なめ
カジュアル面談歓迎
企業について
27年連続売上実績ナンバーワンは挑戦と変革の証。クラウド版でもシェア1位を獲得
◆◇ユーザー数350万人超~業務ソフト領域において圧倒的なNo.1~◇◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
弥生株式会社は中小企業や個人事業主、起業家向けに、「弥生シリーズ」で知られる会計、確定申告、給与計算、顧客管理といった各種業務ソフトウェアを展開している会社です。シリーズは1987年の発売から約36年を数え、今や登録ユーザー数は350万人超。全国の主要販売店やネットショップによる業務ソフトの売上統計によれば、弥生シリーズの売上は27年連続ナンバーワン、2012年に順次リリースしているクラウド版も、市場調査では既にシェア50%を超え、ナンバーワンのポジションにあります。
◆◇保守的な会社と思いきや、実は非常に自由でチャレンジングな社風◇◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
弥生と言えば会計ソフト―というように、高い知名度があり、実績もありますが、逆にそのインパクトが強すぎる為、保守的な堅い会社というイメージも持たれてきました。でも実際は全く違います。時代から取り残されず、今のナンバーワンのシェアを維持しているのは、時代に合わせ、時代をリードしていち早く変化を続けてきたからです。
約36年前、スモールビジネス向けの会計ソフトというまったく新しいコンセプトの製品を出し、今日まで市場を切り拓き、牽引してきました。その強みは、誰でもすぐに使えること。知識がなくても使え、使い始めると圧倒的に業務が効率化する。そして、一度覚えたやり方は変えたくないというユーザーの要望に応えるべく、UXとUIを徹底して研究し、ユーザーに負荷をかけることなく、だが機能はどんどん進化させてきました。
これから中核になるのは、「弥生Next」という新サービスです。
「弥生Next」は、バックオフィス業務を自動化するだけでなく、会計データを可視化することにより、データを利活用できることが特長です。データをもとにAI分析をしたり、同業者との比較をおこなうなど、経営の意思決定を支援し業績向上につなげていきます。
私たちは、半歩先を見据えた価値提供を目指し、日本の中小企業を支え続けることで日本経済全体の活力向上に貢献していきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
弥生株式会社は中小企業や個人事業主、起業家向けに、「弥生シリーズ」で知られる会計、確定申告、給与計算、顧客管理といった各種業務ソフトウェアを展開している会社です。シリーズは1987年の発売から約36年を数え、今や登録ユーザー数は350万人超。全国の主要販売店やネットショップによる業務ソフトの売上統計によれば、弥生シリーズの売上は27年連続ナンバーワン、2012年に順次リリースしているクラウド版も、市場調査では既にシェア50%を超え、ナンバーワンのポジションにあります。
◆◇保守的な会社と思いきや、実は非常に自由でチャレンジングな社風◇◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
弥生と言えば会計ソフト―というように、高い知名度があり、実績もありますが、逆にそのインパクトが強すぎる為、保守的な堅い会社というイメージも持たれてきました。でも実際は全く違います。時代から取り残されず、今のナンバーワンのシェアを維持しているのは、時代に合わせ、時代をリードしていち早く変化を続けてきたからです。
約36年前、スモールビジネス向けの会計ソフトというまったく新しいコンセプトの製品を出し、今日まで市場を切り拓き、牽引してきました。その強みは、誰でもすぐに使えること。知識がなくても使え、使い始めると圧倒的に業務が効率化する。そして、一度覚えたやり方は変えたくないというユーザーの要望に応えるべく、UXとUIを徹底して研究し、ユーザーに負荷をかけることなく、だが機能はどんどん進化させてきました。
これから中核になるのは、「弥生Next」という新サービスです。
「弥生Next」は、バックオフィス業務を自動化するだけでなく、会計データを可視化することにより、データを利活用できることが特長です。データをもとにAI分析をしたり、同業者との比較をおこなうなど、経営の意思決定を支援し業績向上につなげていきます。
私たちは、半歩先を見据えた価値提供を目指し、日本の中小企業を支え続けることで日本経済全体の活力向上に貢献していきます。
中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。
私たちは日本の企業数の99.7%を占めている中小企業がは日本経済の起爆剤になりうると考えています。
さまざまな中小企業が元気になれば、そこで働く人びとの気持ちも未来も元気になる。それは、日本の経済が成長し、社会が元気になることにつながる。
弥生は、中小企業の活力を生み出すことで、日本の活力を生み出すことに貢献します。
さまざまな中小企業が元気になれば、そこで働く人びとの気持ちも未来も元気になる。それは、日本の経済が成長し、社会が元気になることにつながる。
弥生は、中小企業の活力を生み出すことで、日本の活力を生み出すことに貢献します。
テクノロジーと人材の力が弥生の強さの源泉。働きやすい環境も魅力
◆◇新技術をどんどん取り入れています!進化を続ける社風こそが弥生の強み◇◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
弥生がターゲットとする中小企業の領域は、極めて有望でユニークなマーケットでもあります。毎年20万社以上の起業があり、一方で一定の廃業もあります。常に新陳代謝があり、毎年、新たな市場が生まれ続けています。
起業というと成長志向のベンチャーをイメージしますが、それだけではなく、自分のやりたいことを自分のスタイルでやる、いわば身の丈に合った起業や個人事業主という選択も、働き方の多様化の一つとして今後どんどん広がるでしょう。スモールビジネスのあり方も変わり、それに合わせて弥生のサービスも進化を続けます。
中小企業各社や個人事業主の間では、未だに会計ソフトの普及率も低く、普及率はざっと3~4割。残りは会計事務所への全部委託や、Excelや手書きベース。マーケットとして、まだまだできることがあります。
弥生シリーズを支えるのは、テクノロジーであり、高い技術と能力と意欲を持つメンバー達です。キャリア採用を中心に体制を整えて来た弥生には、様々な経歴を持つ人材が集います。
社員に共通するのが、最初こそ「弥生=パッケージ=保守的」というイメージがあったものの、話を聞くうちにチャレンジングで、新たな技術にもどん欲に挑む姿勢に興味がわいたということ。
自社製品に誇りを持ち、リーディングカンパニーとして他の追随を許さない製品やサービス出し続け、今後も進化を続けていく、そんな気質にいい意味でイメージを覆され、入社してきます。
そんな意欲あふれる人材が集結し、安定した収益基盤や会社組織を土台に、言ってみれば地に足をつけながらも思い切った挑戦ができる稀有な環境が、弥生にはあります。その余裕が良き製品を生み出し、良きユーザーを集め、その声に耳を傾けてさらに良き製品に進化する。そんな好循環を生み出しています。
◆◇エンジニア離職率は3%程度。活き活きと働ける環境を構築中◇◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私たちは、社員の為に働きやすい環境を常に考えています。フレッシュな気持ちを保ち、組織を活性化するために、ジョブローテーションも行っています。また評価や個々人のキャリア設計に対してフォロー体制を整えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
弥生がターゲットとする中小企業の領域は、極めて有望でユニークなマーケットでもあります。毎年20万社以上の起業があり、一方で一定の廃業もあります。常に新陳代謝があり、毎年、新たな市場が生まれ続けています。
起業というと成長志向のベンチャーをイメージしますが、それだけではなく、自分のやりたいことを自分のスタイルでやる、いわば身の丈に合った起業や個人事業主という選択も、働き方の多様化の一つとして今後どんどん広がるでしょう。スモールビジネスのあり方も変わり、それに合わせて弥生のサービスも進化を続けます。
中小企業各社や個人事業主の間では、未だに会計ソフトの普及率も低く、普及率はざっと3~4割。残りは会計事務所への全部委託や、Excelや手書きベース。マーケットとして、まだまだできることがあります。
弥生シリーズを支えるのは、テクノロジーであり、高い技術と能力と意欲を持つメンバー達です。キャリア採用を中心に体制を整えて来た弥生には、様々な経歴を持つ人材が集います。
社員に共通するのが、最初こそ「弥生=パッケージ=保守的」というイメージがあったものの、話を聞くうちにチャレンジングで、新たな技術にもどん欲に挑む姿勢に興味がわいたということ。
自社製品に誇りを持ち、リーディングカンパニーとして他の追随を許さない製品やサービス出し続け、今後も進化を続けていく、そんな気質にいい意味でイメージを覆され、入社してきます。
そんな意欲あふれる人材が集結し、安定した収益基盤や会社組織を土台に、言ってみれば地に足をつけながらも思い切った挑戦ができる稀有な環境が、弥生にはあります。その余裕が良き製品を生み出し、良きユーザーを集め、その声に耳を傾けてさらに良き製品に進化する。そんな好循環を生み出しています。
◆◇エンジニア離職率は3%程度。活き活きと働ける環境を構築中◇◆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私たちは、社員の為に働きやすい環境を常に考えています。フレッシュな気持ちを保ち、組織を活性化するために、ジョブローテーションも行っています。また評価や個々人のキャリア設計に対してフォロー体制を整えています。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(17件)
すべて見る
クリエイティブ職(Web)の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── 恐れずチャレンジを推進していく ~新しいプロダクトを生み出すために~
2020年4月に、執行役員 開発本部長に就任しました。就任後は、開発本部の社員が働きやすく成果の出しやすい環境や制度を作っていくことを重点的に取り組んでいます。
現在、弊社では新規プロダクトをゼロから開発するというプロジェクトを進めています。今後デスクトップアプリからクラウドアプリへの移行も見据えたものになりますが、弊社が提供している既存プロダクトのように、多くのお客さまに利用していただいていて、かつ高いシェアを持つプロダクトを、新しくゼロから開発する機会というのは、なかなかありません。そういった意味では非常にやりがいのあるプロジェクトです。
... 続きを読む
求職者の声
企業情報
会社名
弥生株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
金融・保険系 > その他金融・保険系
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、自社サービス製品あり、シェアトップクラス、残業少なめ売上(3年分)
2024年 9月 287.8億円
2023年 9月 251.4億円
設立年月
1978年12月
代表者氏名
代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者 武藤 健一郎
事業内容
業務ソフトウェア(デスクトップアプリ、クラウドアプリ)および関連サービスの開発・販売・サポート
デスクトップ、クラウド製品ともにシェアNo.1を達成。
今後は、さらなるクラウド市場の拡大や中小企業向け業務支援サービスなど新規事業を仕掛けていきます。
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
KKRグループ
主要取引先
SB C&S株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 TD SYNNEX株式会社
従業員数
801人
平均年齢
39.5歳
本社住所
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 21F
この企業と同じ業界の企業
👋
弥生株式会社に興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 弥生株式会社の中途採用/求人/転職情報