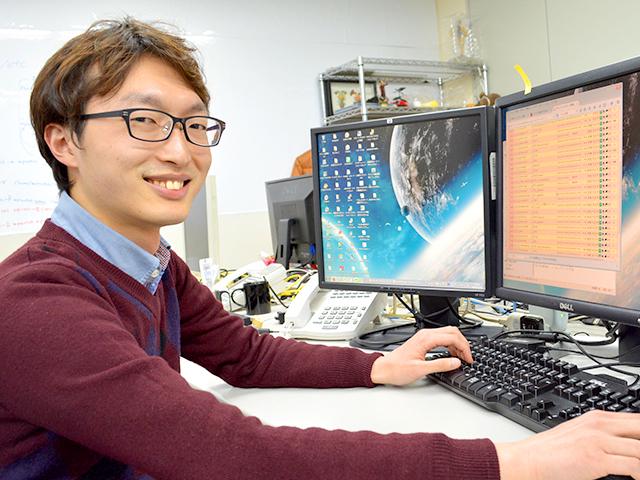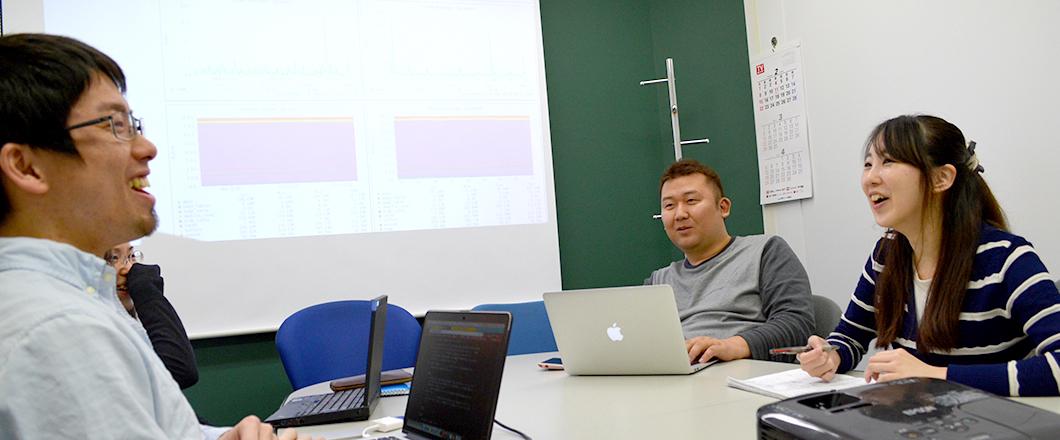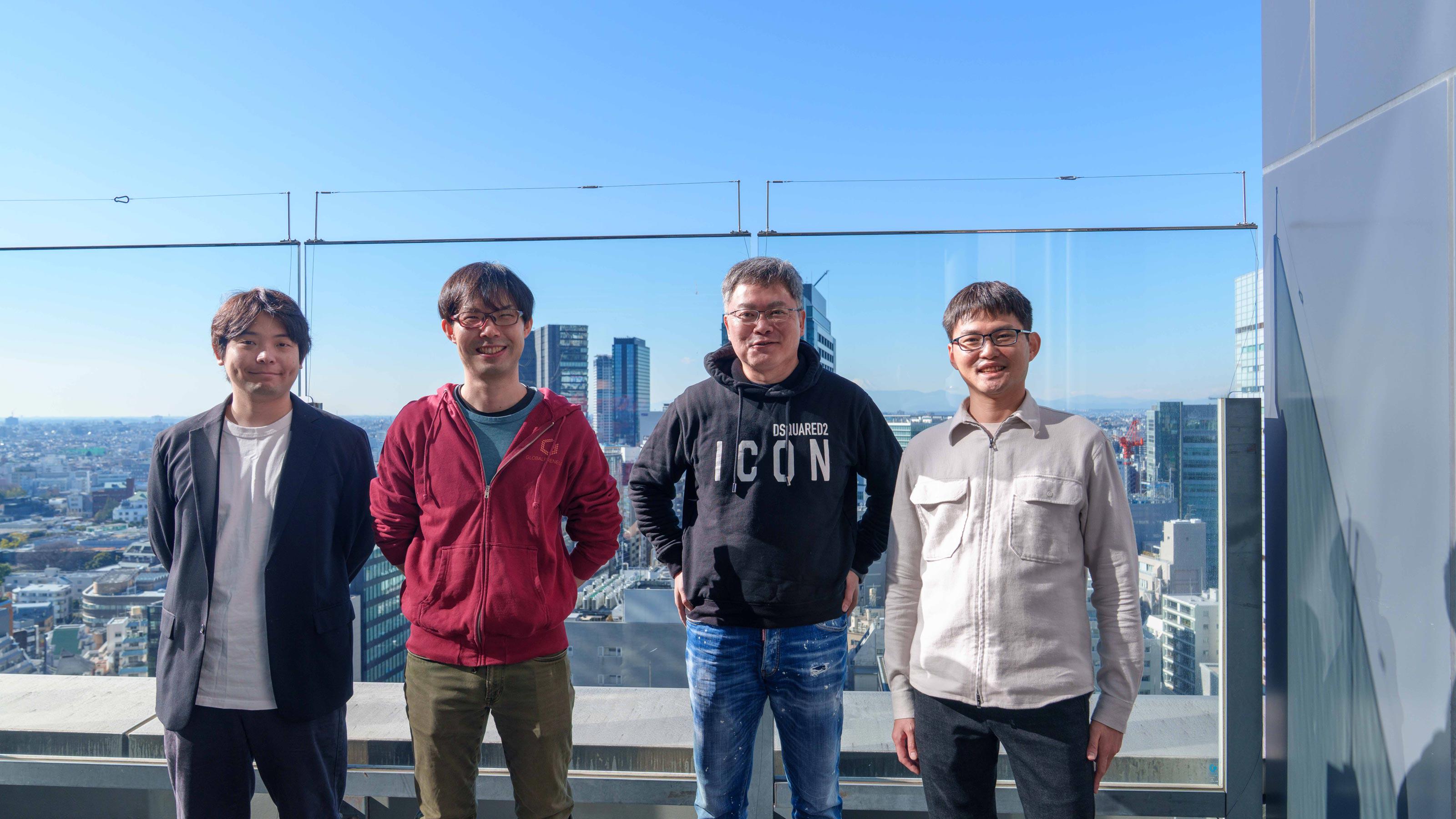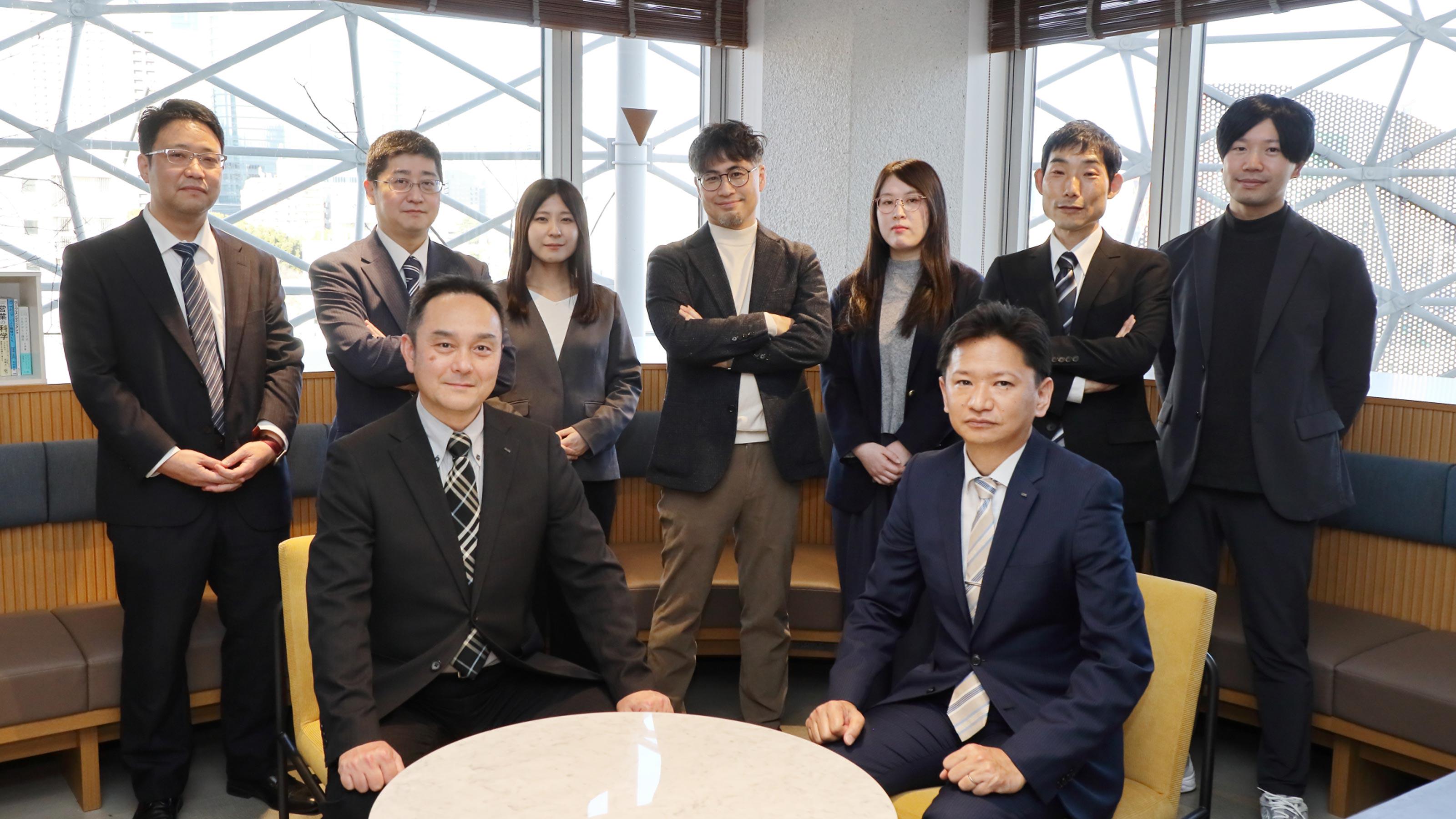株式会社マスターピース
- IT/Web・通信・インターネット系
システム開発・運用からインフラの構築・運用まで一貫して提供できる強み
自社サービス製品あり
企業について
200万本を売るヒットを飛ばしたゲーム『ザ・コンビニ』を手がける
自社およびOEMでのゲーム開発事業、諸システムの受託開発事業、MSP(企業が保有するサーバやネットワークの運用・監視・保守)およびクラウド環境を提供するインフラ事業を展開している、株式会社マスターピース。平均年齢が36歳という円熟の技術力と、システム開発、システム運用、インフラの構築・運用を一貫して提供できることが大きな強みだ。
同社は1992年、教育用ソフトウェア会社の役員を務めていた代表取締役の吉川裕治氏が“つくりたいものをつくる”ゲーム会社として設立した。96年には、Windows版シュミレーションゲーム『ザ・コンビニ~あの町を独占せよ~』をリリース。
「当時はWindows95が爆発的に普及し始めた時期で、経営シミュレーションゲームはまだまだ少なかったのです。バンドル的な売り方をするなどの工夫をしたり、プレイステーションやNINTENDO DSなどのプラットフォームにも展開し、200万本ほども売れるヒット作となりました」と常務取締役COOの坂口昌也氏は言う。その後、2007年までゲーム専業メーカーとして、『ザ・コンビニ』のシリーズ展開やソーシャルゲームの開発を手がけてきた。
2007年に、教育用ソフトウェア会社で吉川氏の部下であった坂口氏が参画する。坂口氏はそれまで別のシステム会社でネットワーク構築・運営事業やシステム開発事業の責任者を務めており、そのメンバーを率いて合流し新たにSI事業部を設立。現在の業態に大きく発展させた。現在の売上構成は、インフラ事業が55%、ゲームのOEM開発を含めたシステム開発事業が45%となっている。
「現在はSIや受託開発のニーズが非常に大きく、その対応で目一杯。エンジニアの増強が急務です」と坂口氏は明かす。
同社は1992年、教育用ソフトウェア会社の役員を務めていた代表取締役の吉川裕治氏が“つくりたいものをつくる”ゲーム会社として設立した。96年には、Windows版シュミレーションゲーム『ザ・コンビニ~あの町を独占せよ~』をリリース。
「当時はWindows95が爆発的に普及し始めた時期で、経営シミュレーションゲームはまだまだ少なかったのです。バンドル的な売り方をするなどの工夫をしたり、プレイステーションやNINTENDO DSなどのプラットフォームにも展開し、200万本ほども売れるヒット作となりました」と常務取締役COOの坂口昌也氏は言う。その後、2007年までゲーム専業メーカーとして、『ザ・コンビニ』のシリーズ展開やソーシャルゲームの開発を手がけてきた。
2007年に、教育用ソフトウェア会社で吉川氏の部下であった坂口氏が参画する。坂口氏はそれまで別のシステム会社でネットワーク構築・運営事業やシステム開発事業の責任者を務めており、そのメンバーを率いて合流し新たにSI事業部を設立。現在の業態に大きく発展させた。現在の売上構成は、インフラ事業が55%、ゲームのOEM開発を含めたシステム開発事業が45%となっている。
「現在はSIや受託開発のニーズが非常に大きく、その対応で目一杯。エンジニアの増強が急務です」と坂口氏は明かす。
自社ゲーム運用で蓄積した知見をMSPやクラウドサービスにフィードバックできる強み
そんな同社の強みは、まずは先述のとおりエンジニアのレベルの高さにある。そして、システムの受託開発においては、“妄想実現力”を標榜。
「『こんなのをつくりたい』という茫洋としたイメージを伺うだけで、具体的なシステムにインプリメントしていける設計力、開発力がある人材がそろっています。リードエンジニアは『ザ・コンビニ』を開発したベテランで、PCゲームやオンラインゲームから様々なシステムまで、マルチ言語でプログラミングできます」と坂口氏は強調する。
一方、SIチームのメンバーは、長らくネット広告配信システムのインフラを手がけてきた。
「広告配信は、システムダウンなどが許されないシビアな世界です。その中で育った人間がコアメンバーとして在籍していますので、高度な運用力を備えていると自負しています」と坂口氏は胸を張る。2012年からは、高い可用性が求められる、mobageなどで運営されるソーシャルゲームにインフラを提供し実績を積んでいる。
「ここでの強みは、当社の一貫性が挙げられます。mobageでは、当社も“イチオシ”として紹介されるようなオリジナルのゲームタイトルを運営していますが、その運用で蓄積した知見をMSPやクラウド事業にフィードバックして、常に最新のノウハウを導入することができます」(坂口氏)
「『こんなのをつくりたい』という茫洋としたイメージを伺うだけで、具体的なシステムにインプリメントしていける設計力、開発力がある人材がそろっています。リードエンジニアは『ザ・コンビニ』を開発したベテランで、PCゲームやオンラインゲームから様々なシステムまで、マルチ言語でプログラミングできます」と坂口氏は強調する。
一方、SIチームのメンバーは、長らくネット広告配信システムのインフラを手がけてきた。
「広告配信は、システムダウンなどが許されないシビアな世界です。その中で育った人間がコアメンバーとして在籍していますので、高度な運用力を備えていると自負しています」と坂口氏は胸を張る。2012年からは、高い可用性が求められる、mobageなどで運営されるソーシャルゲームにインフラを提供し実績を積んでいる。
「ここでの強みは、当社の一貫性が挙げられます。mobageでは、当社も“イチオシ”として紹介されるようなオリジナルのゲームタイトルを運営していますが、その運用で蓄積した知見をMSPやクラウド事業にフィードバックして、常に最新のノウハウを導入することができます」(坂口氏)
これまでの実績はユニークで多岐に渡る
こうした強みを発揮して、同社は次に挙げるような実績を残している。
まず、自社サービス開発。『ザ・コンビニ』のほか、『ザ・ファミレス』や『トラフィックコンフュージョン』などのPC・専用機ゲーム、デイリーアクティブユーザー15万以上の『親方!お祭りです!』などのソーシャルゲームが計10タイトルある。
「『トラフィックコンフュージョン』は、信号機メーカーとビジネスユースでアライアンスを申し込まれるほど、完成度の高さが評価されています」(坂口氏)
ネット上で情報収集やゲームをしながら新しい自分を発見していくコンテンツ『XIMA』、インフラエンジニアをサポートするASP型の管理ツール『NodeMaster』などのユニークな製品もある。
受託開発では、60万ダウンロードを突破した人気ネイティブゲームや、mixiランキングでトップを獲得したソーシャルゲームなどを手がけた。
また、「インターネットTVガイド」のUIから番組表生成バッチプログラムといった裏側のシステムまでを一貫して手がけたり、海外旅行保険の契約サイト、電子書籍配信システム、e-ラーニングシステムなど多彩な領域で実績を重ねている。
SI事業では、クラウドとホスティングをハイブリッドさせた環境を構築し、システムの特性や規模に最適なインフラを提案・設計している。例えば、マンガ/アニメの人気タイトルのソーシャルゲームのインフラでは、テレビ放映と連動したアクセスのピーク時の負荷に対応するため、プライベートクラウドとAWSのCDNを組み合わせたソリューションを構築した。
また、同社では機械監視のみからインフラエンジニアによる運用代行つきまで、4段階のシステム運用サービスメニューを用意。インフラの特性や規模に応じて、24時間365日、効率的な監視・運用を提供している。
「これらの分野はまだまだ発展させていく余地が広がっています。当面は目の前の市場にしっかり対応していきますが、一方で新しいことにもチャレンジしたいと思っています。世の中には、ゲーミフィケーションで市場化していける未開拓領域がたくさん残っています。そういったことにも積極的に取り組んでいきたいですね」と坂口氏は力を込める。
まず、自社サービス開発。『ザ・コンビニ』のほか、『ザ・ファミレス』や『トラフィックコンフュージョン』などのPC・専用機ゲーム、デイリーアクティブユーザー15万以上の『親方!お祭りです!』などのソーシャルゲームが計10タイトルある。
「『トラフィックコンフュージョン』は、信号機メーカーとビジネスユースでアライアンスを申し込まれるほど、完成度の高さが評価されています」(坂口氏)
ネット上で情報収集やゲームをしながら新しい自分を発見していくコンテンツ『XIMA』、インフラエンジニアをサポートするASP型の管理ツール『NodeMaster』などのユニークな製品もある。
受託開発では、60万ダウンロードを突破した人気ネイティブゲームや、mixiランキングでトップを獲得したソーシャルゲームなどを手がけた。
また、「インターネットTVガイド」のUIから番組表生成バッチプログラムといった裏側のシステムまでを一貫して手がけたり、海外旅行保険の契約サイト、電子書籍配信システム、e-ラーニングシステムなど多彩な領域で実績を重ねている。
SI事業では、クラウドとホスティングをハイブリッドさせた環境を構築し、システムの特性や規模に最適なインフラを提案・設計している。例えば、マンガ/アニメの人気タイトルのソーシャルゲームのインフラでは、テレビ放映と連動したアクセスのピーク時の負荷に対応するため、プライベートクラウドとAWSのCDNを組み合わせたソリューションを構築した。
また、同社では機械監視のみからインフラエンジニアによる運用代行つきまで、4段階のシステム運用サービスメニューを用意。インフラの特性や規模に応じて、24時間365日、効率的な監視・運用を提供している。
「これらの分野はまだまだ発展させていく余地が広がっています。当面は目の前の市場にしっかり対応していきますが、一方で新しいことにもチャレンジしたいと思っています。世の中には、ゲーミフィケーションで市場化していける未開拓領域がたくさん残っています。そういったことにも積極的に取り組んでいきたいですね」と坂口氏は力を込める。
“非アジャイル”が方針の堅実な開発スタイルの職人集団
社員数20名の同社の組織は、大きくSI事業部とシステム開発事業部に分かれる。前者はネットワークと営業、後者は企画、開発、デザイン、営業の各機能別セクションに分かれる。デザインだけ、運用だけという案件もあれば、企画・開発から運用まで包括的に手がけるものまで多様で、適宜タスクチームが組まれる。
「職人気質のメンバーが集まっているので、古風な雰囲気があるかもしれません。けれども、現場の上下関係はフラットで、入社したばかりの新人でも意見が言える雰囲気がありますね。逆に、どんどん意見を言ってもらわないと困る、というふうに考えています」と坂口氏。風土づくりでは、システム開発の現場では集中して取り組めるよう、パーテーションを立て、役員クラスでも必要以上に声をかけることも控えているという。
職人集団の開発スタイルとして特筆すべきは、“非アジャイル”という方針を取っていることだ。その理由を、坂口氏は次のように説明する。
「当初は、やはり100%の完成度で納品すべきと考えているからです。工期が決められているので、スピードの問題もありません。もちろん、完成後の必要な修正には柔軟に応じます。アジャイル開発を標榜している開発会社の中には、プランニングや設計をせず適当につくるところが少なくないように思います。当社はそうした姿勢をよしとはせず、しっかりつくり込みます。このため、個々のエンジニアが手触り感を持ちながら職人的に開発できる規模以上に組織を大きくするつもりはありません」
一方、インフラエンジニアのチームは、トラブルシューティングのために声を掛け合うことが多く、比較的にぎやかな雰囲気だという。
会社全体でも、毎日全員でランチを食べに行くなどのまとまり感がある。
同社が求める人材像は、まずは堅実に業務を遂行する人。そして、新しい技術に進んで取り組むような向上心のある人だ。
「いつまでも古くならない人であってほしいと思います」と坂口氏は期待を寄せる。
「職人気質のメンバーが集まっているので、古風な雰囲気があるかもしれません。けれども、現場の上下関係はフラットで、入社したばかりの新人でも意見が言える雰囲気がありますね。逆に、どんどん意見を言ってもらわないと困る、というふうに考えています」と坂口氏。風土づくりでは、システム開発の現場では集中して取り組めるよう、パーテーションを立て、役員クラスでも必要以上に声をかけることも控えているという。
職人集団の開発スタイルとして特筆すべきは、“非アジャイル”という方針を取っていることだ。その理由を、坂口氏は次のように説明する。
「当初は、やはり100%の完成度で納品すべきと考えているからです。工期が決められているので、スピードの問題もありません。もちろん、完成後の必要な修正には柔軟に応じます。アジャイル開発を標榜している開発会社の中には、プランニングや設計をせず適当につくるところが少なくないように思います。当社はそうした姿勢をよしとはせず、しっかりつくり込みます。このため、個々のエンジニアが手触り感を持ちながら職人的に開発できる規模以上に組織を大きくするつもりはありません」
一方、インフラエンジニアのチームは、トラブルシューティングのために声を掛け合うことが多く、比較的にぎやかな雰囲気だという。
会社全体でも、毎日全員でランチを食べに行くなどのまとまり感がある。
同社が求める人材像は、まずは堅実に業務を遂行する人。そして、新しい技術に進んで取り組むような向上心のある人だ。
「いつまでも古くならない人であってほしいと思います」と坂口氏は期待を寄せる。
企業情報
会社名
株式会社マスターピース
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
企業の特徴
自社サービス製品あり資本金
2100万円
設立年月
1992年02月
代表者氏名
吉川裕治
事業内容
システムインテグレーション/システム開発/ゲーム開発
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
ラインズ株式会社
主要取引先
(株)ネクソン/(株)サイバーエージェント/(株)サンケイリビング新聞社/(株)東京ニュース通信社/DeNA/GREE
従業員数
26人
平均年齢
36歳
本社住所
東京都新宿区百人町2-27-7 ハンドレッドサーカス イーストタワー5F
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社マスターピースに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社マスターピースの中途採用/求人/転職情報