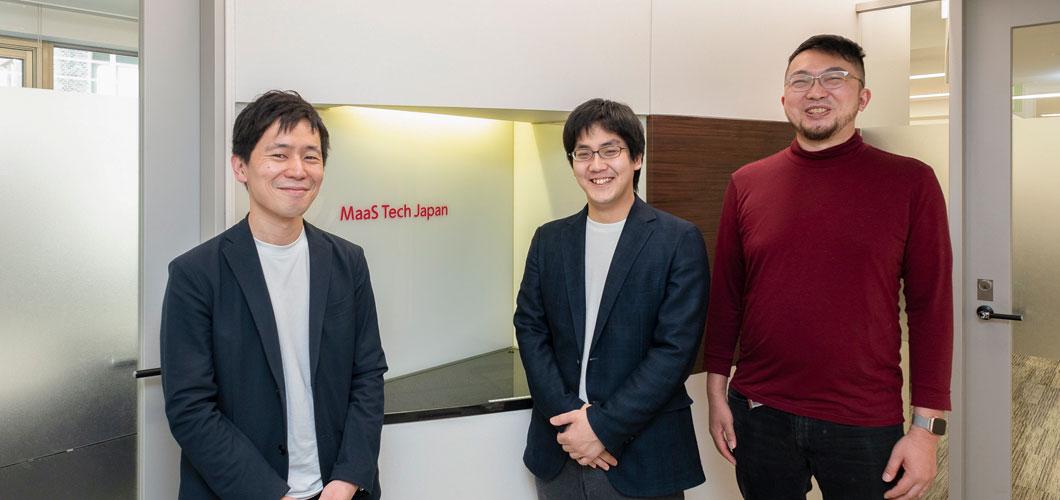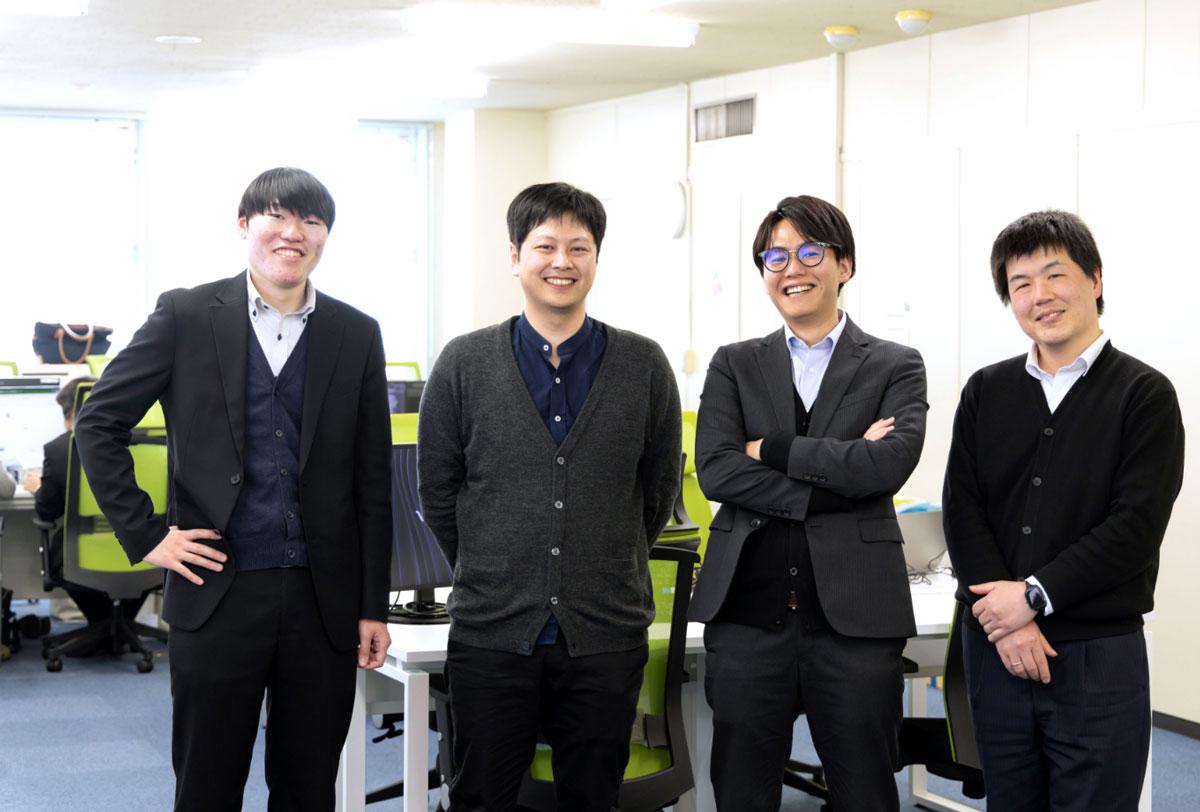株式会社MaaS Tech Japan
- IT/Web・通信・インターネット系
MaaSプロジェクト・自社プロダクトを通じ、「交通」から社会課題の解決に取り組む
上場を目指す
自社サービス製品あり
カジュアル面談歓迎
企業について
自治体や交通事業者のMaaSプロジェクトを支援、ニーズを顕在化
日本におけるMaaS(Mobility as a Service)のモデル構築およびMaaSを活用したプロダクトの開発に向けて、2018年に設立された株式会社MaaS Tech Japan。同社は「100年先の理想的な移動社会の基盤を構築する」をビジョンとして掲げ、理想的な移動社会の実現に向けて、プラットフォーム開発事業、コンサルティング事業を展開。MaaSに関する先進的な知見、コンサルティング実務~実装における豊富な経験を持ち、自治体や交通事業者、損保・コミュニケーションプラットフォームをはじめ各事業者のMaaSプロジェクトを支援している。
2021年4月には、移動情報統合データ基盤『TraISARE』(Transport Information Store with Aggregator, Receiver and Encoder:トレイザー)のβ版の開発が完了した。これは鉄道、バス、タクシー、飛行機等、事業者ごとに異なる形式やフォーマットで保持されている多様な交通データをシームレスに共有し、分析・予測することを可能にした移動情報統合データ基盤である。
同社は設立後の約3年間で、様々な自治体や事業者の交通課題解決に向けて、課題抽出~コンサルティング~技術実装を行ってきた。広島県「モビリティデータ連携基盤構築業務」では『TraISARE』が採択され、分析モデルの検討、MaaSデータの取得、分析ダッシュボードの開発が進んでいる。石川県加賀市とは、MaaSを活用した質の高い住民サービスの提供・スマートシティの実現を目指して連携協定を締結。MaaSアプリの提供から子育て世代への支援、高齢者の免許返納や医療機関へのアクセス向上といったアクションプランの推進に携わっている。さらに、大手町・丸の内・有楽町エリアの就業者・来街者に向けてイベント情報やモビリティ情報を一括で提供するアプリ「Oh MY Map!」において、MaaSデータ連携基盤『TraISARE』および評価・分析ダッシュボード(MaaSコントローラ)を提供し、エリア内の回遊性向上や都市活動・滞在促進するとともに、交通やエリアサービスの利用実態の把握・分析を行った。
このようなプロジェクトを通して、MaaSの社会的な認知が向上するとともに、自治体・事業者側における具体的なニーズが顕在化してきており、同社にとっては、各プロジェクトで蓄積されたナレッジと移動情報統合データ基盤『TraISARE』をもとに、いよいよ独自のプロダクトの開発・提供を行う素地が整ったと言える。
2021年4月には、移動情報統合データ基盤『TraISARE』(Transport Information Store with Aggregator, Receiver and Encoder:トレイザー)のβ版の開発が完了した。これは鉄道、バス、タクシー、飛行機等、事業者ごとに異なる形式やフォーマットで保持されている多様な交通データをシームレスに共有し、分析・予測することを可能にした移動情報統合データ基盤である。
同社は設立後の約3年間で、様々な自治体や事業者の交通課題解決に向けて、課題抽出~コンサルティング~技術実装を行ってきた。広島県「モビリティデータ連携基盤構築業務」では『TraISARE』が採択され、分析モデルの検討、MaaSデータの取得、分析ダッシュボードの開発が進んでいる。石川県加賀市とは、MaaSを活用した質の高い住民サービスの提供・スマートシティの実現を目指して連携協定を締結。MaaSアプリの提供から子育て世代への支援、高齢者の免許返納や医療機関へのアクセス向上といったアクションプランの推進に携わっている。さらに、大手町・丸の内・有楽町エリアの就業者・来街者に向けてイベント情報やモビリティ情報を一括で提供するアプリ「Oh MY Map!」において、MaaSデータ連携基盤『TraISARE』および評価・分析ダッシュボード(MaaSコントローラ)を提供し、エリア内の回遊性向上や都市活動・滞在促進するとともに、交通やエリアサービスの利用実態の把握・分析を行った。
このようなプロジェクトを通して、MaaSの社会的な認知が向上するとともに、自治体・事業者側における具体的なニーズが顕在化してきており、同社にとっては、各プロジェクトで蓄積されたナレッジと移動情報統合データ基盤『TraISARE』をもとに、いよいよ独自のプロダクトの開発・提供を行う素地が整ったと言える。
『TraISARE』を活かしたプロダクトの機能開発・展開に向けて、新体制に移行
前項で紹介したように、同社はこれまで先進的な自治体・事業者とコラボレートし、個別の自治体の要望にできるだけフィットする形でコンサルティング~MaaS実装を行ってきた。その実績が評価され、さらに多くの自治体からの引き合いが増えている。また、鉄道会社との実証実験、損害保険会社との新サービス・保険商品の共同開発、コミュニケーションプラットフォーム事業者とのデモアプリの開発・提供等、事業の幅も広がりを見せている。
そこで設立5年目を迎えた今年(2023年)、同社はプロダクト開発強化に乗り出した。今後は、これまでの取り組みを通じて得られた知見やマーケットニーズを踏まえ、より多くの自治体・エリアで活用できるようなプロダクトの機能開発を加速させる。自治体や事業者ごとのニーズに応えることの価値は変わらないが、同社のリソースは限られている。それが足枷とならないよう、横展開が可能なプロダクトの存在は不可欠だ。
このタイミングで取締役CSO/プロダクト開発統括としてジョインした清水宏之氏は、新たな組織づくりについてこう語る。
「これからは、プロダクトをベースに顧客の課題解決を実現するという新たな取り組みが求められます。そこで現在は、このプロダクトを提案する営業、全国にセールスパートナーを開拓して管理を行うパートナー営業、そしてプロダクトの継続的な利活用を実現するカスタマーサクセス等、新しいポジションで活躍する人材を集めていきたいですね」(清水氏)。
プロダクトの機能開発・展開には『TraISARE』が不可欠である。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成を受けて開発された『TraISARE』は、モビリティデータの「マルチモーダル統合」「リアルタイム活用」「リアルタイム活用」という諸機能において、日本で群を抜くデータ基盤だ。昨年は、この『TraISARE』のユースケースの一つとして、交通データ×人流データによる混雑情報ダッシュボード 『PeopleFlow』を限定公開し、注目を浴びた。
取締役CTOの渡邊徹志氏は、プロダクトの運用効率化の観点から、インフラエンジニアよりもさらにスキル範囲の広いSREを重要視している。プロダクトの展開において、データクレンジング・分析を行う体制強化は必要不可欠である。
「インフラ周りやデータのクレンジング・分析に携われる人材を集めてエンジニアリングリソースを適正化し、プロダクトの拡販、事業のスケールに備えておきたいと考えています」(渡邊氏)。
新たなプロダクト開発に向け、同社では新しい仲間を増やしている最中だ。では同社が求めている人材像とはどのようなものだろうか。
そこで設立5年目を迎えた今年(2023年)、同社はプロダクト開発強化に乗り出した。今後は、これまでの取り組みを通じて得られた知見やマーケットニーズを踏まえ、より多くの自治体・エリアで活用できるようなプロダクトの機能開発を加速させる。自治体や事業者ごとのニーズに応えることの価値は変わらないが、同社のリソースは限られている。それが足枷とならないよう、横展開が可能なプロダクトの存在は不可欠だ。
このタイミングで取締役CSO/プロダクト開発統括としてジョインした清水宏之氏は、新たな組織づくりについてこう語る。
「これからは、プロダクトをベースに顧客の課題解決を実現するという新たな取り組みが求められます。そこで現在は、このプロダクトを提案する営業、全国にセールスパートナーを開拓して管理を行うパートナー営業、そしてプロダクトの継続的な利活用を実現するカスタマーサクセス等、新しいポジションで活躍する人材を集めていきたいですね」(清水氏)。
プロダクトの機能開発・展開には『TraISARE』が不可欠である。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成を受けて開発された『TraISARE』は、モビリティデータの「マルチモーダル統合」「リアルタイム活用」「リアルタイム活用」という諸機能において、日本で群を抜くデータ基盤だ。昨年は、この『TraISARE』のユースケースの一つとして、交通データ×人流データによる混雑情報ダッシュボード 『PeopleFlow』を限定公開し、注目を浴びた。
取締役CTOの渡邊徹志氏は、プロダクトの運用効率化の観点から、インフラエンジニアよりもさらにスキル範囲の広いSREを重要視している。プロダクトの展開において、データクレンジング・分析を行う体制強化は必要不可欠である。
「インフラ周りやデータのクレンジング・分析に携われる人材を集めてエンジニアリングリソースを適正化し、プロダクトの拡販、事業のスケールに備えておきたいと考えています」(渡邊氏)。
新たなプロダクト開発に向け、同社では新しい仲間を増やしている最中だ。では同社が求めている人材像とはどのようなものだろうか。
行動規範『SPEC』をベースに、「交通」から新しいまちづくりに情熱を傾ける
同社ではこのたび、社員の行動規範『SPEC』を策定した。これは「Safety」「Performance」「Encourage」「Courtesy」の頭文字を取った言葉である。
共に社会課題の解決に取り組む自治体や交通事業者、そして様々な移動手段の利用者の間に、同社の社員は入っていく。それらステークホルダー一人ひとりと目線を合わせ、束ねていくには、相手から安心して(Safety)任せてもらえるような人間でなければならない。任せてもらったらスピーディーに効率良く仕事に取り組み(Performance)、ステークホルダーに「自分達の町も活気を取り戻せるかもしれない」という勇気を持ってもらう(Encourage)。ただし、その積み重ねで実績が増え、会社としての収益が向上したとしても決して慢心せず、礼儀正しく(Courtesy)謙虚であること。このようなストーリーが、行動規範『SPEC』には込められている。
社会課題を解決しようとする事業に共感し、行動規範に則って行動してもらえるかどうかを見極めるため、同社では採用に時間をかけている。そのプロセスを経て入社した人材は「社会課題の解決を通して何かを成し遂げたい」という思いで行動する。自らのスペシャリティから外れた仕事であっても、積極的に取り組んでいるとのことだ。
そのような前のめりな人材に対して、代表取締役CEOの日高洋祐氏は1on1で話し合い、一人ひとりの成長プランや、やりがいを感じる瞬間をヒアリング。その人材がなりたい姿に近づけるように、任せる仕事やポジションをデザインすることに心を砕いている。
一方で、同社ならではの風土として、「乗り物や移動が大好き」「まちづくりシミュレーションゲームに強い興味を持っている」という人材が集まっていることも見逃せない。ある地方都市のMaaSプロジェクトに関する議論でも、電車の時刻表やバスの路線図をかき集め、まるで子供のように目を輝かせて意見を交わす姿がよく見られるという。
「ある地域の課題を交通という切り口で解決するという情熱が必要」と話す清水氏、「プログラミングは手段に過ぎない、プログラミングを通して交通のエコシステムを確立させるという目的が重要」と話す渡邊氏の言葉からも、元々移動手段やまちづくりに強い関心を持っている人材が活躍できると言えそうだ。
同社は今後新しいプロダクトを通じて、日本の社会課題の解決にさらに深く関わっていくことになる。確かな知見を持った人材が、その深みに入り込んでいくことに期待したい。
共に社会課題の解決に取り組む自治体や交通事業者、そして様々な移動手段の利用者の間に、同社の社員は入っていく。それらステークホルダー一人ひとりと目線を合わせ、束ねていくには、相手から安心して(Safety)任せてもらえるような人間でなければならない。任せてもらったらスピーディーに効率良く仕事に取り組み(Performance)、ステークホルダーに「自分達の町も活気を取り戻せるかもしれない」という勇気を持ってもらう(Encourage)。ただし、その積み重ねで実績が増え、会社としての収益が向上したとしても決して慢心せず、礼儀正しく(Courtesy)謙虚であること。このようなストーリーが、行動規範『SPEC』には込められている。
社会課題を解決しようとする事業に共感し、行動規範に則って行動してもらえるかどうかを見極めるため、同社では採用に時間をかけている。そのプロセスを経て入社した人材は「社会課題の解決を通して何かを成し遂げたい」という思いで行動する。自らのスペシャリティから外れた仕事であっても、積極的に取り組んでいるとのことだ。
そのような前のめりな人材に対して、代表取締役CEOの日高洋祐氏は1on1で話し合い、一人ひとりの成長プランや、やりがいを感じる瞬間をヒアリング。その人材がなりたい姿に近づけるように、任せる仕事やポジションをデザインすることに心を砕いている。
一方で、同社ならではの風土として、「乗り物や移動が大好き」「まちづくりシミュレーションゲームに強い興味を持っている」という人材が集まっていることも見逃せない。ある地方都市のMaaSプロジェクトに関する議論でも、電車の時刻表やバスの路線図をかき集め、まるで子供のように目を輝かせて意見を交わす姿がよく見られるという。
「ある地域の課題を交通という切り口で解決するという情熱が必要」と話す清水氏、「プログラミングは手段に過ぎない、プログラミングを通して交通のエコシステムを確立させるという目的が重要」と話す渡邊氏の言葉からも、元々移動手段やまちづくりに強い関心を持っている人材が活躍できると言えそうだ。
同社は今後新しいプロダクトを通じて、日本の社会課題の解決にさらに深く関わっていくことになる。確かな知見を持った人材が、その深みに入り込んでいくことに期待したい。
PR
すべて見る企業情報
会社名
株式会社MaaS Tech Japan
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場を目指す、自社サービス製品あり資本金
1億9,750万円
設立年月
2018年11月
代表者氏名
代表取締役 日高 洋祐
事業内容
プラットフォーム開発事業
株式公開(証券取引所)
従業員数
20人
本社住所
東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社MaaS Tech Japanの中途採用/求人/転職情報