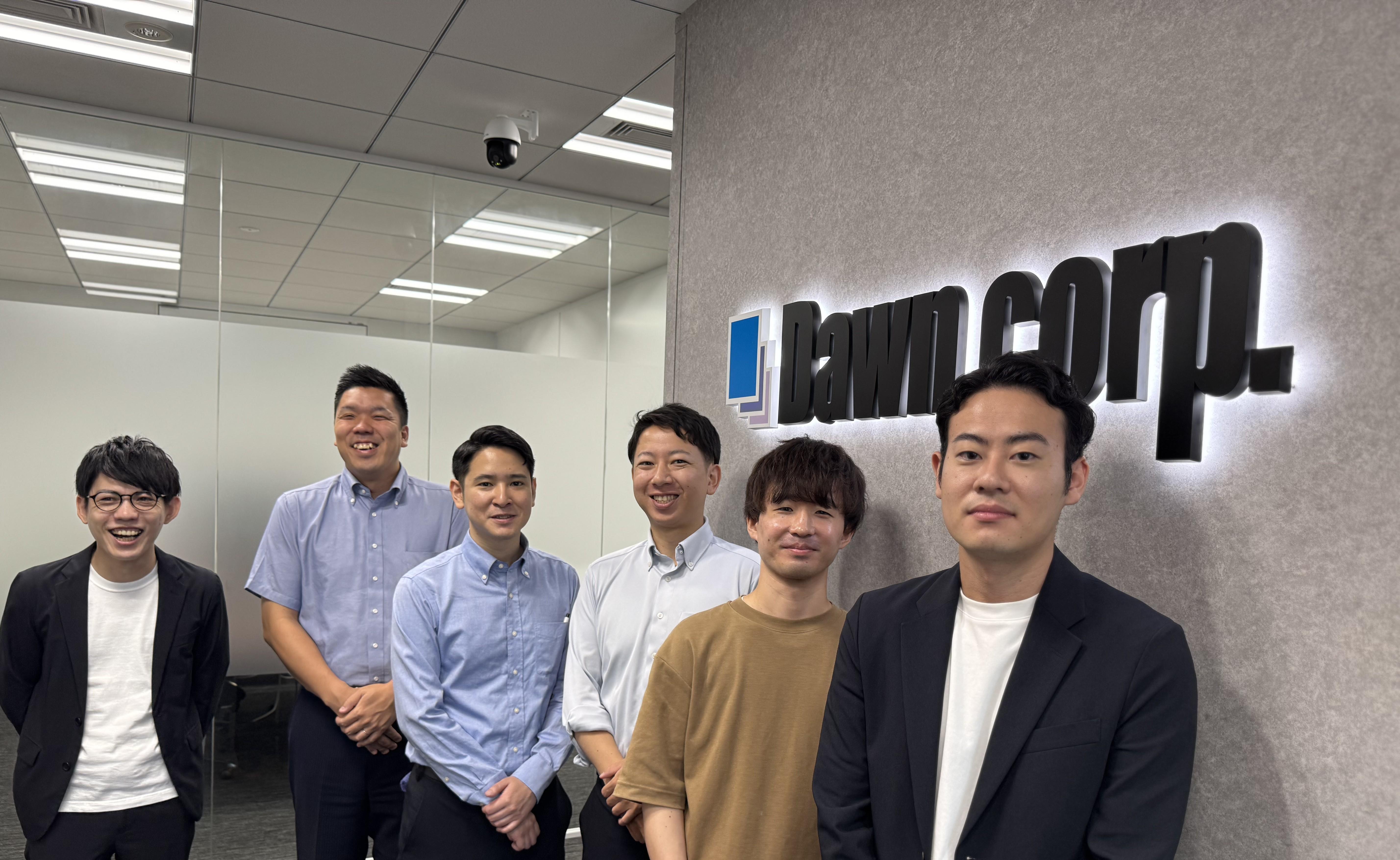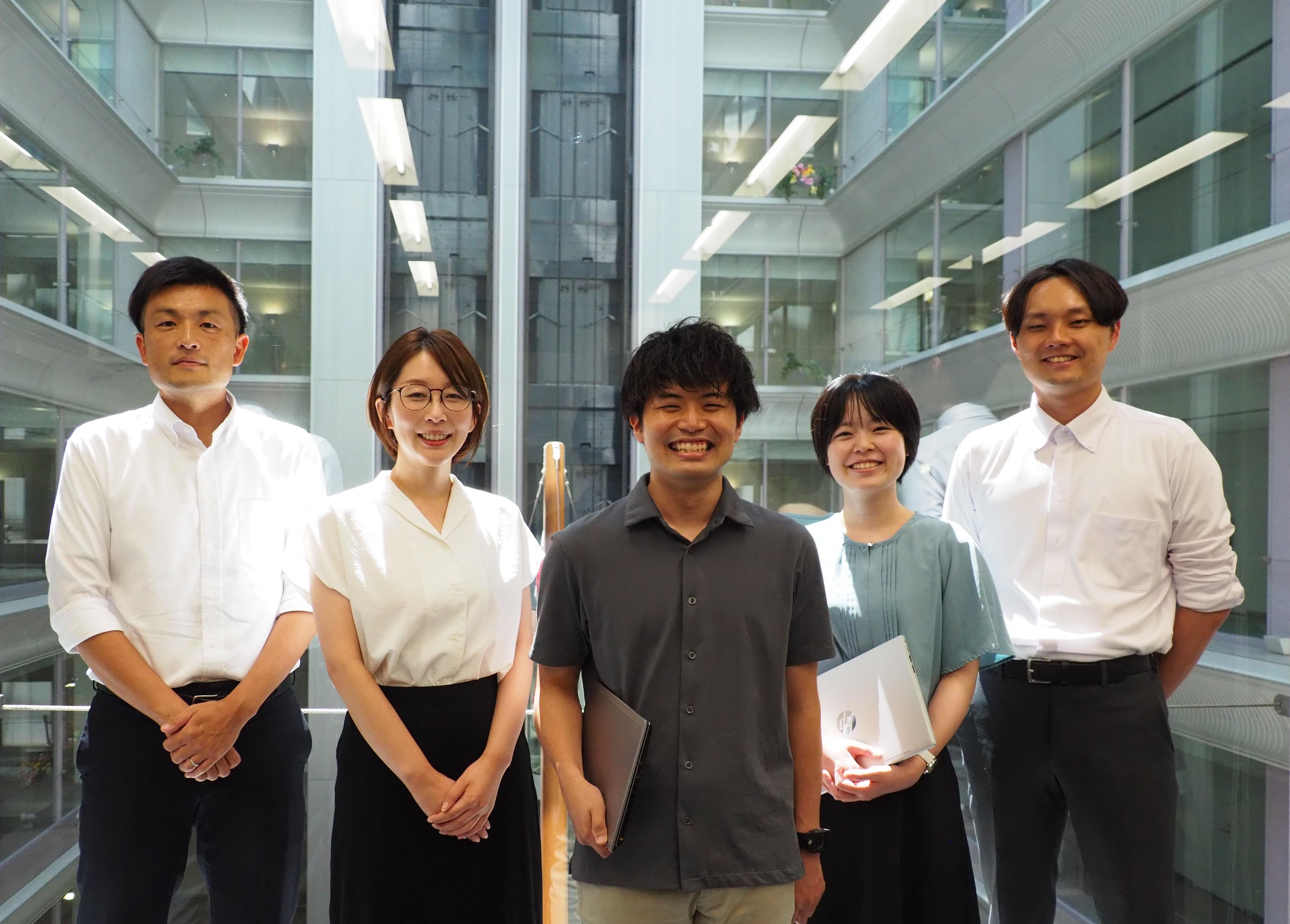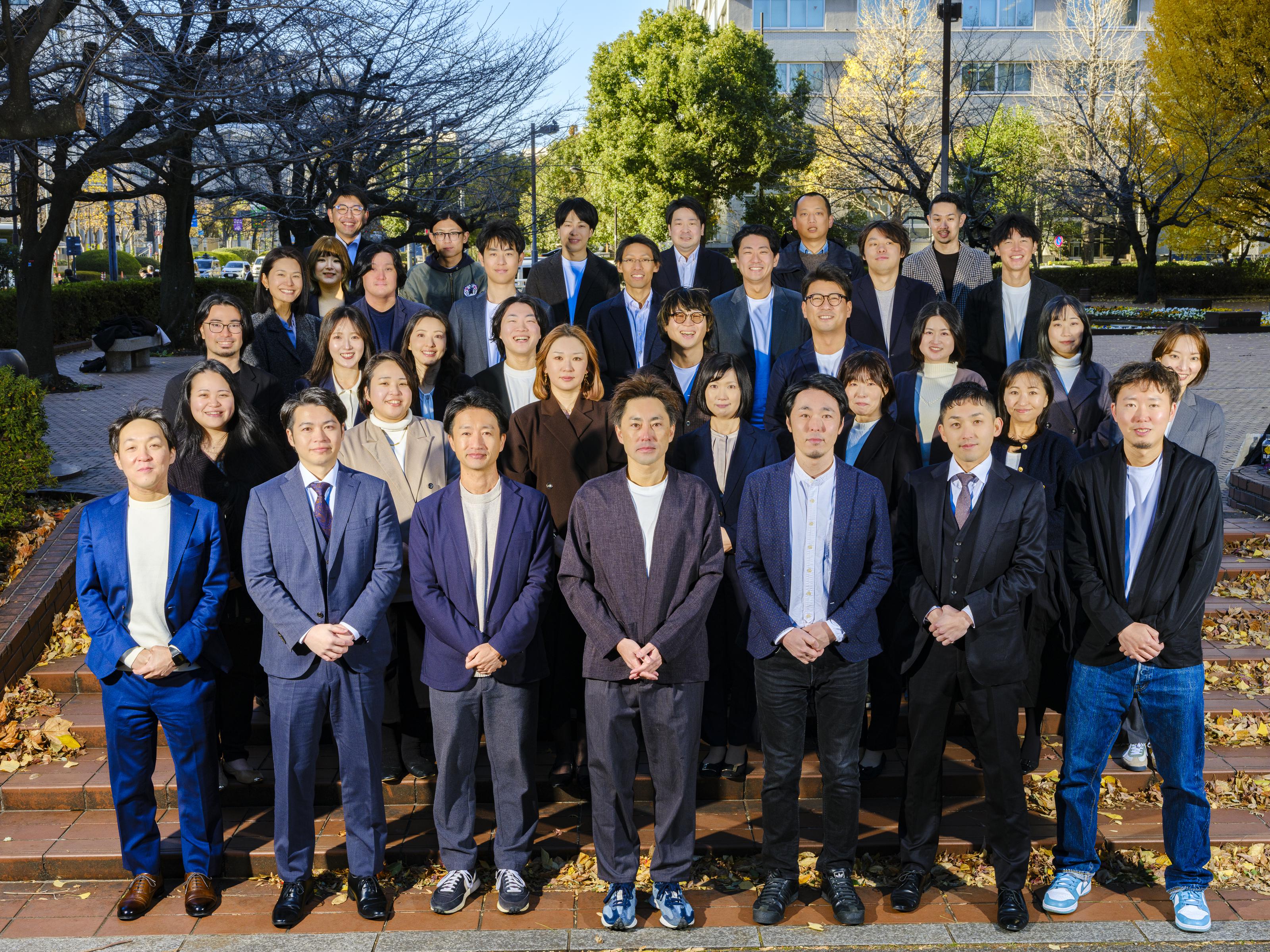株式会社ドーン
- IT/Web・通信・インターネット系
【東証スタンダード上場】GIS業界のリーディングカンパニー 社会の安心安全に貢献する次世代型クラウドサービスを開発
上場
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
カジュアル面談歓迎
企業について
ユーザーニーズを先取りするマーケット・インの開発力を強みに、クラウドサービス企業へシフト
株式会社ドーンは、警察、消防、自治体防災、社会インフラ保全といったシーンにおいて、空間情報技術を駆使した最新のクラウドソリューションを提供する企業だ。
祖業であるGIS(Geographic Information System:地理情報システム)事業で培った知見をベースに、近年は次世代の緊急通報サービスや防犯・防災関連のスマホアプリ等をリリース。社会の安全と安心に関わるシステムを次々と展開している。
現場のニーズに応える機能性と操作性が高い評価を得て、多くの引き合いが寄せられている。一方、良いものを実直に丁寧に創り上げていく姿勢を崩さないのが同社らしさ。堅調に歩みを進める風土の中で、腰を据えて研究開発に勤しむエンジニアを広く求める。
1991年に兵庫県神戸市で創業した同社は、阪神淡路大震災後に神戸市長田区復興支援GIS構築事業、神戸市地盤情報/震災被害解析GISシステムの開発を開始した。「社会の安心と安全を支えるシステム提供」という役割を意識するに至ったきっかけだ。
自社開発のGISミドルウェアが日本全国の公共分野で利用され、さらにユーザーからの高い性能評価により、GISリーディングカンパニーとして事業成長を遂げ、2002年には、NASDAQ JAPAN(現東証 JASDAQ)に上場を果たす。
近年では、強みである警察消防、自治体防災、社会インフラ保全の分野におけるニーズを先取りしたマーケット・インの開発力を発揮し、クラウドサービスを続々とリリース。SIによるフロービジネスから、ストック型のクラウドサービス企業へとシフトした。その結果8期連続過去最高売上、6期連続過去最高収益という好調な売上高で推移する。
サービスの詳細は後述するが、映像コミュニケーションを活用した現場からの通報システムは特に話題を呼んでいる。
同社は企画から提案、開発、運用まで、自社内で手掛ける一貫体制が特徴だ。営業・開発・支援部門が一体となって実現する「高性能・高機能・高付加価値」なサービス提供で、ニッチ領域のトップ企業として認知される。
情報通信技術仕様の標準化委員会でリーダー企業を務める発信力や、パートナー企業との強力な連携によるスピーディーな展開等、他社との差別化になるポイントは多い。
それゆえ価格競争に巻き込まれることなく、市場調査を入念に行い、ユーザーが必要とする機能をじっくりと作り込む研究開発が可能なのだ。
祖業であるGIS(Geographic Information System:地理情報システム)事業で培った知見をベースに、近年は次世代の緊急通報サービスや防犯・防災関連のスマホアプリ等をリリース。社会の安全と安心に関わるシステムを次々と展開している。
現場のニーズに応える機能性と操作性が高い評価を得て、多くの引き合いが寄せられている。一方、良いものを実直に丁寧に創り上げていく姿勢を崩さないのが同社らしさ。堅調に歩みを進める風土の中で、腰を据えて研究開発に勤しむエンジニアを広く求める。
1991年に兵庫県神戸市で創業した同社は、阪神淡路大震災後に神戸市長田区復興支援GIS構築事業、神戸市地盤情報/震災被害解析GISシステムの開発を開始した。「社会の安心と安全を支えるシステム提供」という役割を意識するに至ったきっかけだ。
自社開発のGISミドルウェアが日本全国の公共分野で利用され、さらにユーザーからの高い性能評価により、GISリーディングカンパニーとして事業成長を遂げ、2002年には、NASDAQ JAPAN(現東証 JASDAQ)に上場を果たす。
近年では、強みである警察消防、自治体防災、社会インフラ保全の分野におけるニーズを先取りしたマーケット・インの開発力を発揮し、クラウドサービスを続々とリリース。SIによるフロービジネスから、ストック型のクラウドサービス企業へとシフトした。その結果8期連続過去最高売上、6期連続過去最高収益という好調な売上高で推移する。
サービスの詳細は後述するが、映像コミュニケーションを活用した現場からの通報システムは特に話題を呼んでいる。
同社は企画から提案、開発、運用まで、自社内で手掛ける一貫体制が特徴だ。営業・開発・支援部門が一体となって実現する「高性能・高機能・高付加価値」なサービス提供で、ニッチ領域のトップ企業として認知される。
情報通信技術仕様の標準化委員会でリーダー企業を務める発信力や、パートナー企業との強力な連携によるスピーディーな展開等、他社との差別化になるポイントは多い。
それゆえ価格競争に巻き込まれることなく、市場調査を入念に行い、ユーザーが必要とする機能をじっくりと作り込む研究開発が可能なのだ。
収益性や成長性が異なる複数のサービスで事業ポートフォリオを構成し継続的な成長を目指す
同社が開発した『Live119 映像通報システム』は、全国の市町区村の消防署で採用が進む次世代119番通報システムだ。
一般市民である通報者がスマートフォンで119番通報をすると、『Live119』を導入する消防指令センターは発信者を確認。SMSでビデオ通話開始依頼のURLを通知する。通報者がURLをタップすると、『Live119』によるブラウザベースのサービスが起動して、ビデオ通話が可能になる。消防指令センターは音声による通報だけでは把握が難しい視覚的な情報をリアルタイムに収集して、火災や事故、救護対象者の状況を把握できる。現場に向かう消防隊等に正確に概要を伝えられるほか、通報者に対して応急手当方法等の動画送信や、効果的な口頭指導の支援が可能になるのだ。
取締役 品川真尚氏は「スマートフォンからの緊急通報が6割を超える現代に適した“119番の見える化ソリューション”です。これまでになかったシステムで、緊急通報の在り方を変えるのではないかと期待が寄せられています。全国の多数の消防で導入が検討されているほか、日本最大規模を誇る東京消防庁で2020年9月から試行運用が開始されました。2025年10月現在、210消防以上で導入されており、緊急通報のスタンダードになりつつあるくらい、それほどの勢いを帯びています」と力を込める。
専用アプリを事前にダウンロードする必要がなく、心理的な余裕がない緊急通報時にも簡単に操作できる配慮が特徴だ。
開発最高責任者の松波功二氏は「我々には、作りたいものを作るという自己満足な考えはありません。社会貢献への高い志は必ずしも持っていなくていいのですが、いいものを作って普及させようというプロフェッショナルな姿勢は大事。その結果が社会の安心安全に向かえばいいのです」と話す。
特定の開発手法や技術、思いに固執せず、利用側に立った柔軟な発想を求めたいという。
官公庁や自治体の防災対策拡大を鑑みて、防災クラウドシステム/アプリ等を含めた新たなサービス開発に積極的に取り組む。収益性や成長性が異なる複数のサービスで事業ポートフォリオを構成し、持続的な成長を目指す方針だ。
一般市民である通報者がスマートフォンで119番通報をすると、『Live119』を導入する消防指令センターは発信者を確認。SMSでビデオ通話開始依頼のURLを通知する。通報者がURLをタップすると、『Live119』によるブラウザベースのサービスが起動して、ビデオ通話が可能になる。消防指令センターは音声による通報だけでは把握が難しい視覚的な情報をリアルタイムに収集して、火災や事故、救護対象者の状況を把握できる。現場に向かう消防隊等に正確に概要を伝えられるほか、通報者に対して応急手当方法等の動画送信や、効果的な口頭指導の支援が可能になるのだ。
取締役 品川真尚氏は「スマートフォンからの緊急通報が6割を超える現代に適した“119番の見える化ソリューション”です。これまでになかったシステムで、緊急通報の在り方を変えるのではないかと期待が寄せられています。全国の多数の消防で導入が検討されているほか、日本最大規模を誇る東京消防庁で2020年9月から試行運用が開始されました。2025年10月現在、210消防以上で導入されており、緊急通報のスタンダードになりつつあるくらい、それほどの勢いを帯びています」と力を込める。
専用アプリを事前にダウンロードする必要がなく、心理的な余裕がない緊急通報時にも簡単に操作できる配慮が特徴だ。
開発最高責任者の松波功二氏は「我々には、作りたいものを作るという自己満足な考えはありません。社会貢献への高い志は必ずしも持っていなくていいのですが、いいものを作って普及させようというプロフェッショナルな姿勢は大事。その結果が社会の安心安全に向かえばいいのです」と話す。
特定の開発手法や技術、思いに固執せず、利用側に立った柔軟な発想を求めたいという。
官公庁や自治体の防災対策拡大を鑑みて、防災クラウドシステム/アプリ等を含めた新たなサービス開発に積極的に取り組む。収益性や成長性が異なる複数のサービスで事業ポートフォリオを構成し、持続的な成長を目指す方針だ。
ワイワイガヤガヤと意見交換する自由闊達な風土。安定性と柔軟性の両面を併せもつカルチャー。
主要顧客を官公庁とするクラウドサービスで、安定的かつ継続的な収益を見込めるストック型ビジネスへの移行に成功した同社。
堅固な財務基盤の下でじっくりと業務に取り組み、着実な成長を目指そうという意識を共有しているが、かといって、上場企業にありがちな堅苦しさはない。部門や役職を意識しない一体感の中、ワイワイガヤガヤと意見交換する自由闊達な雰囲気が特徴だ。
「当社は、大手の安定性とベンチャー企業の柔軟性という両面をいい塩梅に併せもっています。この風土はサービス開発にも活きています。大手SIerだと堅苦しいシステムになりがちだったり、デザインオフィスだと要件が分かっていなかったりがありますが、うちは公共サービスを理解しつつ“そうそう、これが欲しかったんだよね”というユーザーニーズをきっちり掴んだ開発ができる。この絶妙なバランス感覚が他社との圧倒的な差別化になっています」(品川氏)。
クラウド開発部で部長を務める近藤大機氏は、魅力の一つとして“エンジニアの居心地の良さ”を挙げる。
「とにかくできることの幅が広い。顧客と直接話をしながら企画・設計の上流から携わり、実際に手を動かして開発を行い、テストを経てリリースして、保守運用までできる。一人のエンジニアが一つの案件を丸ごと担当するスタイルです。そのため日々の研究や調査結果、アイデアを反映できる余地が多い。会社はいまだ成長過程で、自分自身の成長も共に実感できる環境です。派手さはないものの、じっくり腰を据えて開発に取り組みたいエンジニアにとっては最高の環境です。居心地が良くて離職率が少ないんですよ」
大手にありがちな、年数を経たら上流に行ってプログラムは書かないという風潮に対し、近藤氏は異論を唱える。
「当社には上流から下流まで全部できる面白さがあり、”IT職人“としてのスキルを伸ばせます。また直接契約が主体で、悪い評価も含めて率直な顧客の声が聴ける。発注者が別の顧客を紹介してくれることがあり、それは満足の証だと受けとめています。エンジニアとして嬉しさを感じるところですね」
地図情報を活用したシステム開発を行っているが、地図に関する知識は一切不要だという。
「当社は、様々な業界を経験したエンジニアが自由に発言し、活躍できる環境です。あなたの経験や考えを是非サービスづくりに活かしてください。また“世の中を変えるサービスを開発したい”という高い志を持った方も歓迎です。是非我々と一緒に成長しましょう」とは近藤氏からのメッセージだ。
同社だからこそ可能なモノづくりがある。魅力を感じたならば、是非コンタクトをとってほしい。
堅固な財務基盤の下でじっくりと業務に取り組み、着実な成長を目指そうという意識を共有しているが、かといって、上場企業にありがちな堅苦しさはない。部門や役職を意識しない一体感の中、ワイワイガヤガヤと意見交換する自由闊達な雰囲気が特徴だ。
「当社は、大手の安定性とベンチャー企業の柔軟性という両面をいい塩梅に併せもっています。この風土はサービス開発にも活きています。大手SIerだと堅苦しいシステムになりがちだったり、デザインオフィスだと要件が分かっていなかったりがありますが、うちは公共サービスを理解しつつ“そうそう、これが欲しかったんだよね”というユーザーニーズをきっちり掴んだ開発ができる。この絶妙なバランス感覚が他社との圧倒的な差別化になっています」(品川氏)。
クラウド開発部で部長を務める近藤大機氏は、魅力の一つとして“エンジニアの居心地の良さ”を挙げる。
「とにかくできることの幅が広い。顧客と直接話をしながら企画・設計の上流から携わり、実際に手を動かして開発を行い、テストを経てリリースして、保守運用までできる。一人のエンジニアが一つの案件を丸ごと担当するスタイルです。そのため日々の研究や調査結果、アイデアを反映できる余地が多い。会社はいまだ成長過程で、自分自身の成長も共に実感できる環境です。派手さはないものの、じっくり腰を据えて開発に取り組みたいエンジニアにとっては最高の環境です。居心地が良くて離職率が少ないんですよ」
大手にありがちな、年数を経たら上流に行ってプログラムは書かないという風潮に対し、近藤氏は異論を唱える。
「当社には上流から下流まで全部できる面白さがあり、”IT職人“としてのスキルを伸ばせます。また直接契約が主体で、悪い評価も含めて率直な顧客の声が聴ける。発注者が別の顧客を紹介してくれることがあり、それは満足の証だと受けとめています。エンジニアとして嬉しさを感じるところですね」
地図情報を活用したシステム開発を行っているが、地図に関する知識は一切不要だという。
「当社は、様々な業界を経験したエンジニアが自由に発言し、活躍できる環境です。あなたの経験や考えを是非サービスづくりに活かしてください。また“世の中を変えるサービスを開発したい”という高い志を持った方も歓迎です。是非我々と一緒に成長しましょう」とは近藤氏からのメッセージだ。
同社だからこそ可能なモノづくりがある。魅力を感じたならば、是非コンタクトをとってほしい。
募集している求人
アシスタント・事務職・オフィスワークの求人(2件)
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)
営業職の求人(1件)
PR
すべて見る社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
会社名
株式会社ドーン
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場、自社サービス製品あり、シェアトップクラス資本金
3億6395万円
売上(3年分)
2025年 5月 1646百万円
2024年 5月 1500百万円
2023年 5月 1368百万円
設立年月
1991年06月
代表者氏名
代表取締役 宮崎 正伸
事業内容
・「安心・安全」をテーマにした各種クラウドサービス(SaaS)の開発・提供
・地理情報システム又は地理情報に関連づけたシステム(アプリケーションソフトウェア)の開発・保守
・地理情報システム構築用ソフトウェアのライセンス販売
株式公開(証券取引所)
東証スタンダード
主要取引先
警察庁 海上保安庁 東京都 警視庁 東京消防庁 兵庫県警察本部 埼玉県警察本部 栃木県警察本部 長野県警察本部 愛知県警察本部 岡山県警察本部 広島県警察本部 大分県警察本部 宮崎県警察本部 長野県 茨城県 兵庫県 高知県 神戸市 京都市 大阪市 西宮市 川口市 柏市 宇都宮市 富士通(株) 日本電気(株) 沖電気工業(株) (株)日立製作所 (株)STNet その他民間企業
従業員数
63人
平均年齢
38.6歳
本社住所
兵庫県神戸市中央区磯上通 2-2-21 三宮グランドビル5F
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社ドーンに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社ドーンの中途採用/求人/転職情報