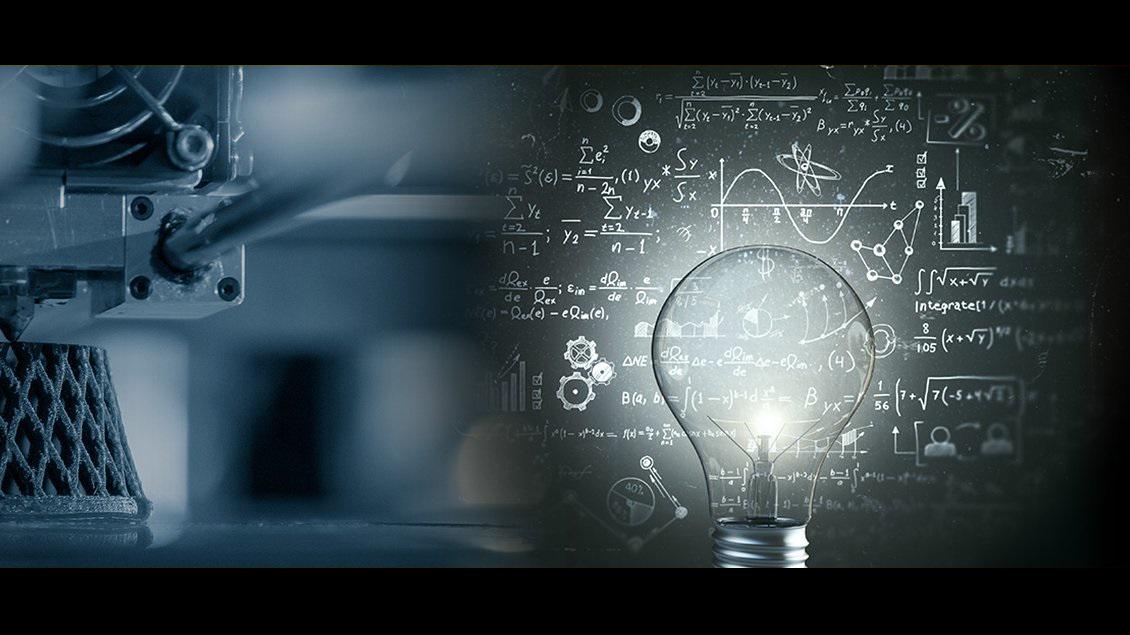株式会社ストラテジット
- IT/Web・通信・インターネット系
【ストラテジット】「全てのDataと企業をJointする存在に」SaaSの導入と連携開発の専門企業
上場を目指す
自社サービス製品あり
グローバルに活動
カジュアル面談歓迎
企業について
【全てのDataと企業をJointする存在に】
「StrategIT」という社名は、お客様のStrategy=戦略をITで解決することに由来します。
クラウド化が進み、SaaSを活用した経営効率向上や業務のDX化が課題になっている時代、多くのソリューションが提供されても、活用についてはまだまだ改善の余地があります。
当社ではSaaSのソリューションを導入している企業に対し、BtoBとBtoBtoBの両面から、より連携しやすい環境づくりを提案しています。企業単位にこだわらず、分野や業務の範囲ごとに最大限の活用ができるソリューション提供がミッションです。
2023年にリリースした「JOINT」は、SaaSを企画・構築・運用するためのプラットフォームです。国内外50以上のSaaSとの連携を実装実績のあるストラテジットだからこそ提供できる機能を備えています。
SaaS市場が拡大しているいま、世の中には素晴らしいソリューションが多くあります。私たちは、この「JOINT」を通してSaaS間のデータ連携をシームレスにすることで、日本のSaaS利用をサポートします。そうすることで、まだまだ無駄の多い日本企業の作業効率を上げて国全体の生産性を向上させ、世界と戦える国にしたいと思っています。
クラウド化が進み、SaaSを活用した経営効率向上や業務のDX化が課題になっている時代、多くのソリューションが提供されても、活用についてはまだまだ改善の余地があります。
当社ではSaaSのソリューションを導入している企業に対し、BtoBとBtoBtoBの両面から、より連携しやすい環境づくりを提案しています。企業単位にこだわらず、分野や業務の範囲ごとに最大限の活用ができるソリューション提供がミッションです。
2023年にリリースした「JOINT」は、SaaSを企画・構築・運用するためのプラットフォームです。国内外50以上のSaaSとの連携を実装実績のあるストラテジットだからこそ提供できる機能を備えています。
SaaS市場が拡大しているいま、世の中には素晴らしいソリューションが多くあります。私たちは、この「JOINT」を通してSaaS間のデータ連携をシームレスにすることで、日本のSaaS利用をサポートします。そうすることで、まだまだ無駄の多い日本企業の作業効率を上げて国全体の生産性を向上させ、世界と戦える国にしたいと思っています。
自身の裁量を活かせる環境で、共に成長を
ストラテジットでは営業一人で仕事を完結することなく、提案段階からクロージングまで、エンジニアをはじめ経験豊かなメンバーがフォローしながら仕事を進めます。私自身、営業職としての3年間に、会社としての価値をチームで提供できる体制を活用してきました。現在社員の平均年齢は30代後半ですが、20代前半の若手から経験豊かな50代のベテランまで多士済々、カフェ店員から独学でITの勉強をして入社された方や、ITとはまるで違う業界から来て活躍している営業職の方もいます。今後は経験者だけでなくポテンシャル採用として会社と一緒に成長できるメンバーも積極的に加える方針です。
勤務形態についてはフルフレックス・フルリモートを導入し、プロ意識の高いメンバーたちがしっかり結果に結びつけています。お子さんがいるスタッフは送り迎えや授業参観などの学校行事に合わせて昼間の数時間を抜け、夜間に埋め合わせをするなど、お客様への対応を前提に、個人の裁量で仕事を進めています。
フルリモートも完全に定着し、北は北海道から南は沖縄まで社員が分散しています。会社でも全国規模のワーキングスペースと契約し、自宅作業が難しいときや出張先でのデスクワーク、地方在住社員によるミーティングなどに活用してもらうフォロー体制をとっています。私自身は神奈川県在住で週に2〜3回は東神田本社に出勤していますが、リモート中心のIT業界の特性を活かし、プロジェクトもERPも全てリモートで行っています。
その上で社員間のコミュニケーションも推奨しており、IT業界は女性の比率が低いので月に一度のランチミーティングを行ったり、地方在住メンバーのランチミーティングに補助を出したりもしています。1年に1回は全社員が顔をあわせる場を設け、昨年は東京本社でマグロの解体ショーを行い盛り上がりました。今後は1年に2回くらいに増やしたいですね。
3年目のベンチャー企業だけに、安定していない部分もあります。しかしSaaSのベンダーさんをはじめ上場企業のARI上位企業などお客様に恵まれ、自分の裁量で働ける大手企業にはないやりがいがきっと見つかるはずです。会社と一緒に楽しく成長したいと思う方に来ていただきたいと思います。
勤務形態についてはフルフレックス・フルリモートを導入し、プロ意識の高いメンバーたちがしっかり結果に結びつけています。お子さんがいるスタッフは送り迎えや授業参観などの学校行事に合わせて昼間の数時間を抜け、夜間に埋め合わせをするなど、お客様への対応を前提に、個人の裁量で仕事を進めています。
フルリモートも完全に定着し、北は北海道から南は沖縄まで社員が分散しています。会社でも全国規模のワーキングスペースと契約し、自宅作業が難しいときや出張先でのデスクワーク、地方在住社員によるミーティングなどに活用してもらうフォロー体制をとっています。私自身は神奈川県在住で週に2〜3回は東神田本社に出勤していますが、リモート中心のIT業界の特性を活かし、プロジェクトもERPも全てリモートで行っています。
その上で社員間のコミュニケーションも推奨しており、IT業界は女性の比率が低いので月に一度のランチミーティングを行ったり、地方在住メンバーのランチミーティングに補助を出したりもしています。1年に1回は全社員が顔をあわせる場を設け、昨年は東京本社でマグロの解体ショーを行い盛り上がりました。今後は1年に2回くらいに増やしたいですね。
3年目のベンチャー企業だけに、安定していない部分もあります。しかしSaaSのベンダーさんをはじめ上場企業のARI上位企業などお客様に恵まれ、自分の裁量で働ける大手企業にはないやりがいがきっと見つかるはずです。会社と一緒に楽しく成長したいと思う方に来ていただきたいと思います。
募集している求人
営業職の求人(3件)
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)
PR
すべて見る社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
会社名
株式会社ストラテジット
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場を目指す、自社サービス製品あり、グローバルに活動資本金
4,521万円
売上(3年分)
2022年 6月 3.9億円
2021年 6月 1.8億円
2020年 6月 0.5億円
設立年月
2019年07月
代表者氏名
加藤 史恵
事業内容
■SaaS事業者向けシステムの連携(iPaaS)開発
■SaaS連携アプリストアの開発・運営
■SaaS導入コンサルティング、ERP導入の支援
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
HEROZ株式会社 (TYO:4382)
主要取引先
freee株式会社 マネーフォワードグループ スターティアラボ株式会社 株式会社ヌーラボ 株式会社コラボスタイル ウイングアーク1st株式会社 他(順不同)
従業員数
34人
平均年齢
35.5歳
本社住所
東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社ストラテジットに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社ストラテジットの中途採用/求人/転職情報