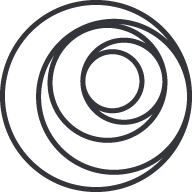
パレットクラウド株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
SaaS『パレット管理』の大手企業導入実績と生成AI新規事業拡大中の企業
自社サービス製品あり
残業少なめ
カジュアル面談歓迎
企業について
不動産賃貸物件約300万戸に導入される住生活支援サービスで急成長を果たす
アパート・マンションなどの不動産賃貸物件の管理会社と、その物件の入居者をつなぐシステムを開発・運営するパレットクラウド株式会社。
当社は、「住まいに不安のない国へ。」という理念を掲げ、不動産関連事業者の業務を支援するサービス、そして入居者の快適な生活を実現するサービスという2つの要素をもっています。
管理会社向け入居者管理システム『パレット管理』は、業界トップシェアの企業をはじめとした多くの企業にご契約いただき、日本全国に約900万戸と言われている賃貸物件の中、300万戸を超える規模で導入されています。
『パレット管理』は、管理会社と入居者がコミュニケーションを取る上で必要な機能を、自由に組み合わせて利用できる点に大きな特徴があります。
たとえば、新規入居者向けのマニュアルを失くしたり汚したりしないようアプリで閲覧できる機能、お問い合わせ対応のためのオンライン窓口、契約更新や解約手続きをオンラインで完結する機能など、管理会社ごとに必要とする機能は異なります。
利用機能を組み合わせられるという利便性と、ブランドロゴの表示など個社特性が出せる点などを高く評価をいただき、多くの賃貸管理業界の企業やハウスメーカーの賃貸部門で導入いただいています。
本来、紙のやり取りを対面や郵送で行ったり、なにか確認や問い合わせをする際は電話が必要だったりと、管理会社も入居者もコストが掛かるような手続きが多くありましたが、そういった点をシンプルにDX推進できる、それがこのサービスの成長要因となっています。
当社は、「住まいに不安のない国へ。」という理念を掲げ、不動産関連事業者の業務を支援するサービス、そして入居者の快適な生活を実現するサービスという2つの要素をもっています。
管理会社向け入居者管理システム『パレット管理』は、業界トップシェアの企業をはじめとした多くの企業にご契約いただき、日本全国に約900万戸と言われている賃貸物件の中、300万戸を超える規模で導入されています。
『パレット管理』は、管理会社と入居者がコミュニケーションを取る上で必要な機能を、自由に組み合わせて利用できる点に大きな特徴があります。
たとえば、新規入居者向けのマニュアルを失くしたり汚したりしないようアプリで閲覧できる機能、お問い合わせ対応のためのオンライン窓口、契約更新や解約手続きをオンラインで完結する機能など、管理会社ごとに必要とする機能は異なります。
利用機能を組み合わせられるという利便性と、ブランドロゴの表示など個社特性が出せる点などを高く評価をいただき、多くの賃貸管理業界の企業やハウスメーカーの賃貸部門で導入いただいています。
本来、紙のやり取りを対面や郵送で行ったり、なにか確認や問い合わせをする際は電話が必要だったりと、管理会社も入居者もコストが掛かるような手続きが多くありましたが、そういった点をシンプルにDX推進できる、それがこのサービスの成長要因となっています。
生成AIを活用したサービスを展開
お問い合わせに対しマニュアルなど個社保有のドキュメントや生成AIモデルから最適な回答を提示する機能をはじめとし、『パレット管理』だけでなく新規事業においても、人間が本当に注力するべき業務に集中できるようテクノロジーの力でサポートし続けます。
職種の垣根のないチームワークでチャレンジを応援
開発サイドもビジネスに関わり、ビジネスサイドも開発に関わることでよりスピーディーな成長を実現しています。
専門分野を突き詰めたり、興味やキャリアプランに応じて別領域、別職種を兼務するなど個々のチャレンジを応援する環境です。
専門領域に特化してスペシャリストを目指すことはもちろん、自身の市場価値や業務の効率化を図るためにフロントエンドの担当者がバックエンドにチャレンジしたり、カスタマーサポートと企画領域を兼務するなど、それぞれの興味やキャリアプランに合わせたチャレンジをしています。
専門分野を突き詰めたり、興味やキャリアプランに応じて別領域、別職種を兼務するなど個々のチャレンジを応援する環境です。
専門領域に特化してスペシャリストを目指すことはもちろん、自身の市場価値や業務の効率化を図るためにフロントエンドの担当者がバックエンドにチャレンジしたり、カスタマーサポートと企画領域を兼務するなど、それぞれの興味やキャリアプランに合わせたチャレンジをしています。
PR
すべて見る企業情報
会社名
パレットクラウド株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、自社サービス製品あり、残業少なめ資本金
1億円
設立年月
2010年11月
代表者氏名
代表取締役CEO 城野 公臣
事業内容
・不動産管理会社の管理業務DX支援(toB)
・不動産管理会社と入居者様を繋ぐDX支援(toBtoC)
・パレット電気・パレットガス等の取次サービス
・生成AI活用のソリューション事業
株式公開(証券取引所)
従業員数
45人
本社住所
東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9階
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- パレットクラウド株式会社の中途採用/求人/転職情報


















