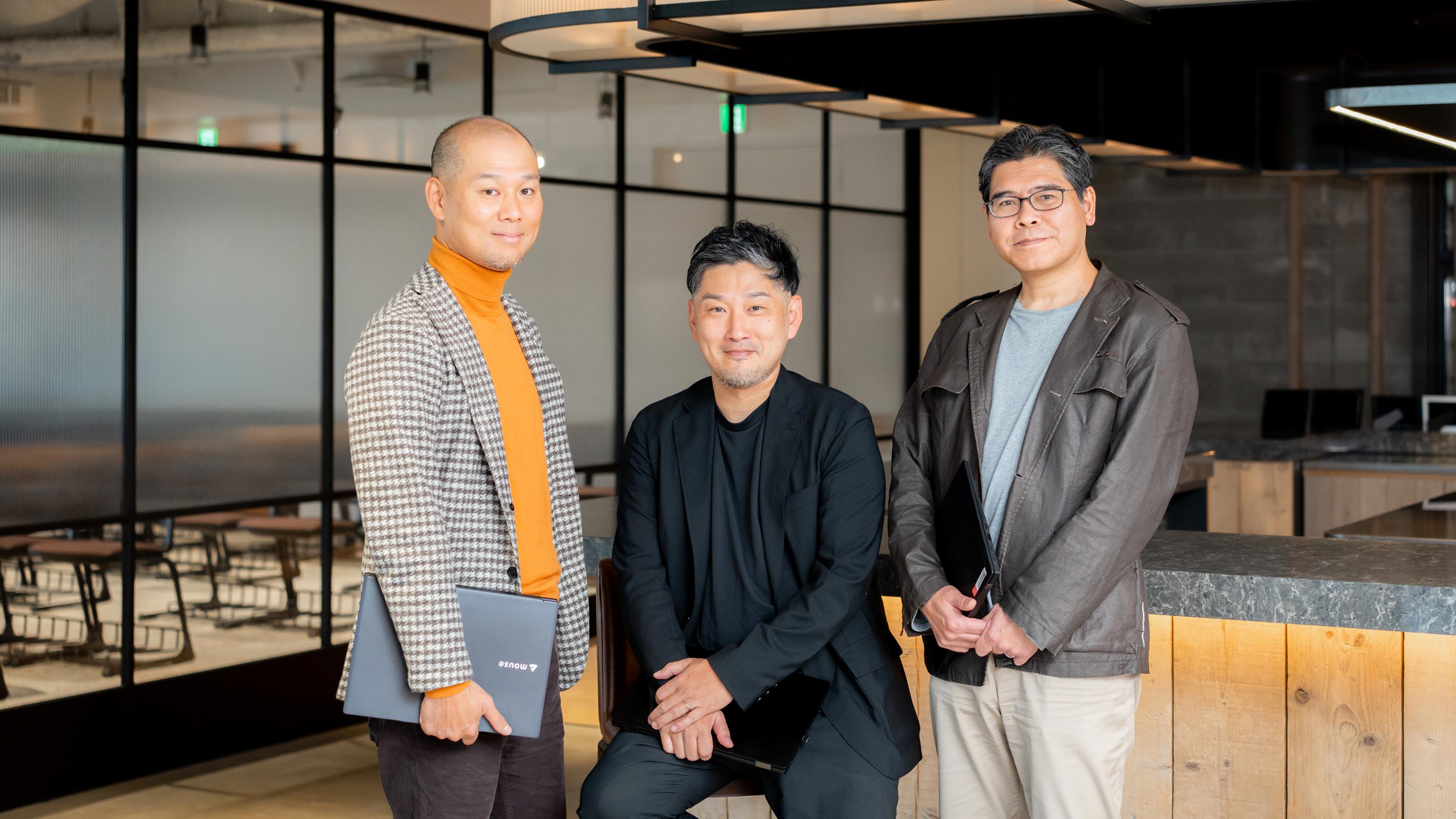BEMAC株式会社
- 製造・メーカー系
- IT/Web・通信・インターネット系
造船は世界の物流を支える重要産業。そのIT部分を担う国内トップメーカー
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
グローバルに活動
企業について
大型船舶の電気機器のトップメーカー。IT化による需要増大で業績拡大中
BEMAC株式会社は、大型船舶の配電システムや制御システム等の製造、船内電気工事、アフターメンテナンスをワンストップで手掛けている会社だ。船舶の総合電機メーカーとして設計から工事まで一括して担える会社は、国内では同社のみ。他社との大きな差別化ポイントであり、船舶の配電、制御システムの国内シェアは56%を超えるトップメーカーだ。具体的には船舶の配線工事と、これらに電気を送る配電システム、各種機器を監視・制御する監視制御システムの製品を製造。大型船舶は量産するものではないため、これらの製品を個々の船に最適化した形で設計・製造・導入し、導入後の保守や改善までを手掛ける。近年は、これらの技術を生かして、ビルやプラントの電気機器、電動三輪車両(アジア諸国の乗り合いタクシー等に使われている車両)の開発にも事業を広げている。
同社は、戦後すぐに創業。船舶用の蓄電池からスタートし、船の進化と足並みを合わせて、同社の取り扱う領域も高度化。主力製品の配電盤、監視盤は、かつては船の中で、さらにいえば「箱」の中で完結していたが、今では情報化・ネットワーク化し、陸上とも繋がる「システム」に進化している。
「自動車をイメージすると分かりやすいと思います」と話すのは製造本部 MP設計部 MP計装課 課長 工藤 秀紀氏だ。自動車がスマート化し、「機械」から「コンピューターの塊」になり、技術的には自動運転も可能になったように、「船も、究極的には自動運転を目指していくでしょう」と工藤氏は言う。今は、その過程にあり、造船会社とタッグを組んでシステムを急速に進化させているところだ。
船の自動化とは、例えば航路だ。「港から港への通り方次第で、燃料の消費量が違います。船は莫大な燃料を消費するので、この違いが大きなコストの差になります。気象や船の状態、燃料の値段等を考慮し、もっとも燃費のいい航路を選びます。昔は船長が判断しましたが、今は排ガス規制等もできてさらに複雑化し、判断するのは、コンピューターの役目になりました」(工藤氏)。
かつては船員のマンパワーに頼っていた給油や荷役といった作業も、自動化が進んでいる。完全な無人化には議論が必要だが、安心、安全、効率化等の観点で自動化し、いずれ無人化へという流れは必然だ。このような状況下、建造量自体が増えているわけではないものの、船舶関連のIT需要の増大により、BEMACの技術が求められる場面は増え、業務量、売上は拡大を続けているところだ。
同社は、戦後すぐに創業。船舶用の蓄電池からスタートし、船の進化と足並みを合わせて、同社の取り扱う領域も高度化。主力製品の配電盤、監視盤は、かつては船の中で、さらにいえば「箱」の中で完結していたが、今では情報化・ネットワーク化し、陸上とも繋がる「システム」に進化している。
「自動車をイメージすると分かりやすいと思います」と話すのは製造本部 MP設計部 MP計装課 課長 工藤 秀紀氏だ。自動車がスマート化し、「機械」から「コンピューターの塊」になり、技術的には自動運転も可能になったように、「船も、究極的には自動運転を目指していくでしょう」と工藤氏は言う。今は、その過程にあり、造船会社とタッグを組んでシステムを急速に進化させているところだ。
船の自動化とは、例えば航路だ。「港から港への通り方次第で、燃料の消費量が違います。船は莫大な燃料を消費するので、この違いが大きなコストの差になります。気象や船の状態、燃料の値段等を考慮し、もっとも燃費のいい航路を選びます。昔は船長が判断しましたが、今は排ガス規制等もできてさらに複雑化し、判断するのは、コンピューターの役目になりました」(工藤氏)。
かつては船員のマンパワーに頼っていた給油や荷役といった作業も、自動化が進んでいる。完全な無人化には議論が必要だが、安心、安全、効率化等の観点で自動化し、いずれ無人化へという流れは必然だ。このような状況下、建造量自体が増えているわけではないものの、船舶関連のIT需要の増大により、BEMACの技術が求められる場面は増え、業務量、売上は拡大を続けているところだ。
世界の物流インフラに欠かせない造船業。世界で勝つためにIT化が急務
2020年春、新型コロナウイルスが世界で猛威を振るうなか、飲食や観光のように大きな打撃を受けた業界と、重要性や強さを再確認された業界がある。造船は後者だ。というのも、コロナ禍で社会インフラとしての物流の重要性が再確認され、さらに世界の輸送量の99%を担っているのが船だからだ。
その船を動かしているのが海運会社で、船を造っているのが造船会社。BEMACの主要取引先は、日本一の造船会社で、世界でもトップクラスにある。その造船会社は、日本国内では一人勝ちの状態にある。また、今治には数々の中小の造船会社があり、それらの電気系統もほぼBEMACが担う。造船は、今治が世界に誇る地場産業で、それを電気機器、システムの面で支えているのがBEMACだ。
造船はグローバルな業界で、世界中の造船会社が競合となる。受注を目指して、世界中の造船会社が鎬を削るなかで、今治の造船会社が勝つには付加価値が必要だ。その有力な付加価値がIT化だ。世界の物流の大動脈として、世界中の海を商船が行き交っているが、昨今、船員の不足・高齢化は世界共通の課題となっている。慢性的な人手不足により、労働力が豊富な国から人を集めて来ざるを得ない状況だ。そのため、技術の伝達やコミュニケーションに困難が生じ、コンピューターによる複雑な業務の自動化、あるいは業務支援機能が必要となる。人力に頼らない、安心安全な運行を可能にできれば、船の大きな付加価値になるのだ。
「造船業界は常に世界と戦っています。日本の造船業界は、付加価値を出さなければ、例えば、中国のような国を挙げて造船業に力を入ている国に、価格競争で負けてしまいます」と工藤氏。そのような状況下で、造船会社からBEMACに対して「こんな付加価値をつけたい」、「こんなことはできないだろうか?」といった相談、要望が多く寄せられる。引き合いもどんどん増えるなか、これまで培ったノウハウに新しい知識や人材をプラスして、その期待に応えたい考えだ。そして数々の要望を実現し、その先には、「船のIT企業」として、地位を不動のものすることを狙う。
その船を動かしているのが海運会社で、船を造っているのが造船会社。BEMACの主要取引先は、日本一の造船会社で、世界でもトップクラスにある。その造船会社は、日本国内では一人勝ちの状態にある。また、今治には数々の中小の造船会社があり、それらの電気系統もほぼBEMACが担う。造船は、今治が世界に誇る地場産業で、それを電気機器、システムの面で支えているのがBEMACだ。
造船はグローバルな業界で、世界中の造船会社が競合となる。受注を目指して、世界中の造船会社が鎬を削るなかで、今治の造船会社が勝つには付加価値が必要だ。その有力な付加価値がIT化だ。世界の物流の大動脈として、世界中の海を商船が行き交っているが、昨今、船員の不足・高齢化は世界共通の課題となっている。慢性的な人手不足により、労働力が豊富な国から人を集めて来ざるを得ない状況だ。そのため、技術の伝達やコミュニケーションに困難が生じ、コンピューターによる複雑な業務の自動化、あるいは業務支援機能が必要となる。人力に頼らない、安心安全な運行を可能にできれば、船の大きな付加価値になるのだ。
「造船業界は常に世界と戦っています。日本の造船業界は、付加価値を出さなければ、例えば、中国のような国を挙げて造船業に力を入ている国に、価格競争で負けてしまいます」と工藤氏。そのような状況下で、造船会社からBEMACに対して「こんな付加価値をつけたい」、「こんなことはできないだろうか?」といった相談、要望が多く寄せられる。引き合いもどんどん増えるなか、これまで培ったノウハウに新しい知識や人材をプラスして、その期待に応えたい考えだ。そして数々の要望を実現し、その先には、「船のIT企業」として、地位を不動のものすることを狙う。
他業界の技術の横展開で画期的なことができる可能性も!やりがいは大きい
需要の拡大に伴い、現在、BEMACは積極的に中途採用を進めている。一昨年来、約60人の仲間が加わった。大半が業界未経験者だ。皆、他業界の知見、経験を活かして活躍中だ。未経験者も大歓迎であり、新しい風を吹かせてくれることに、大いに期待している。
工藤氏は言う。「船のIT化は、これから大きく進んでいくステージにあります。というのも道路や信号、細かな交通ルールや規制がある自動車は、その枠組みに沿って、業界が一丸となって技術開発を進めてきたのに対し、船はそこまでの枠組みはなく、また建造に何年もかかることあり、柔軟に新しい技術を取り入れることが難しかったのです。でも、それも一気に変わろうとしています」。変革期にある今、他業界で使っていた技術が、船の世界で新しい価値を生み出す場合もある。自分の技術を船に展開することで、画期的なことができるかもしれない。そのような楽しさがあると思います」(工藤氏)。
造船は、非常にグローバルでダイナミックに変革している産業ながら、BEMACは、製造や工事を担うメンバーも含めて社員数1,000人余りの規模。十分に大きな会社ではあるが、世界に何万人と社員がいるメーカー等と比べると少数精鋭であり、一人ひとりの裁量も大きい。実際、幅広い業務を担い、しかも挑戦的な開発ができる環境に惹かれて、異業種の大手メーカーから転職してくるメンバーもいる。技術的な手応え、物流の本流を担う社会的意義を感じながら、やりがいを持って仕事に臨んでいるという。
今治市にある本社社屋は、みらいの船をイメージしたユニークな目を引く外観を持つ。社屋内は落ち着いた内装が施され、オープンで快適な働きやすいオフィス環境となっている。地場産業である造船業を支え、地元に根差して発展してきた会社らしく、社内の雰囲気は家族的。社員旅行、運動会といった古き良き社内行事も健在だ。サークル活動等、社員の活動も盛んで、コミュニケーションは極めて良好だ。
世界中の海には、BEMACの配電システム、監視システムを積んだ船が走っている。船の自動運転という大きな構想も、夢に終わらせず、自らの手で実現させることになるだろう。BEMACはそんな、とてつもないやりがいに満ちた会社だ。ロマンや社会的意義、あるいは挑戦する楽しさを感じたら、一度、訪ねてみるといいだろう。
工藤氏は言う。「船のIT化は、これから大きく進んでいくステージにあります。というのも道路や信号、細かな交通ルールや規制がある自動車は、その枠組みに沿って、業界が一丸となって技術開発を進めてきたのに対し、船はそこまでの枠組みはなく、また建造に何年もかかることあり、柔軟に新しい技術を取り入れることが難しかったのです。でも、それも一気に変わろうとしています」。変革期にある今、他業界で使っていた技術が、船の世界で新しい価値を生み出す場合もある。自分の技術を船に展開することで、画期的なことができるかもしれない。そのような楽しさがあると思います」(工藤氏)。
造船は、非常にグローバルでダイナミックに変革している産業ながら、BEMACは、製造や工事を担うメンバーも含めて社員数1,000人余りの規模。十分に大きな会社ではあるが、世界に何万人と社員がいるメーカー等と比べると少数精鋭であり、一人ひとりの裁量も大きい。実際、幅広い業務を担い、しかも挑戦的な開発ができる環境に惹かれて、異業種の大手メーカーから転職してくるメンバーもいる。技術的な手応え、物流の本流を担う社会的意義を感じながら、やりがいを持って仕事に臨んでいるという。
今治市にある本社社屋は、みらいの船をイメージしたユニークな目を引く外観を持つ。社屋内は落ち着いた内装が施され、オープンで快適な働きやすいオフィス環境となっている。地場産業である造船業を支え、地元に根差して発展してきた会社らしく、社内の雰囲気は家族的。社員旅行、運動会といった古き良き社内行事も健在だ。サークル活動等、社員の活動も盛んで、コミュニケーションは極めて良好だ。
世界中の海には、BEMACの配電システム、監視システムを積んだ船が走っている。船の自動運転という大きな構想も、夢に終わらせず、自らの手で実現させることになるだろう。BEMACはそんな、とてつもないやりがいに満ちた会社だ。ロマンや社会的意義、あるいは挑戦する楽しさを感じたら、一度、訪ねてみるといいだろう。
企業情報
会社名
BEMAC株式会社
業界
製造・メーカー系 > 電気・電子・機械・半導体
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
製造・メーカー系 > その他メーカー系
企業の特徴
自社サービス製品あり、シェアトップクラス、グローバルに活動資本金
9000万円
売上(3年分)
2016年 3月 280億
2017年 3月 330億
2018年 3月 380億
設立年月
1956年07月
代表者氏名
代表取締役社長 小田 雅人
事業内容
船は世界の物流の99%を担っており、造船は社会インフラを支える重要産業です。
BEMACは、大型船舶の配電システムや制御システム等、電気機器全般の設計、製造、工事、メンテナンスをワンストップで手掛けています。
国内シェア50%を超えるトップメーカーで、船の省人化、自動化といったデジタルシフトを手掛け、「船のIT企業」を目指し、進化を続けます。
株式公開(証券取引所)
非上場
従業員数
945人
平均年齢
34歳
本社住所
愛媛県今治市野間甲 105 番地
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- 製造・メーカー系
- 電気・電子・機械・半導体
- BEMAC株式会社の中途採用/求人/転職情報