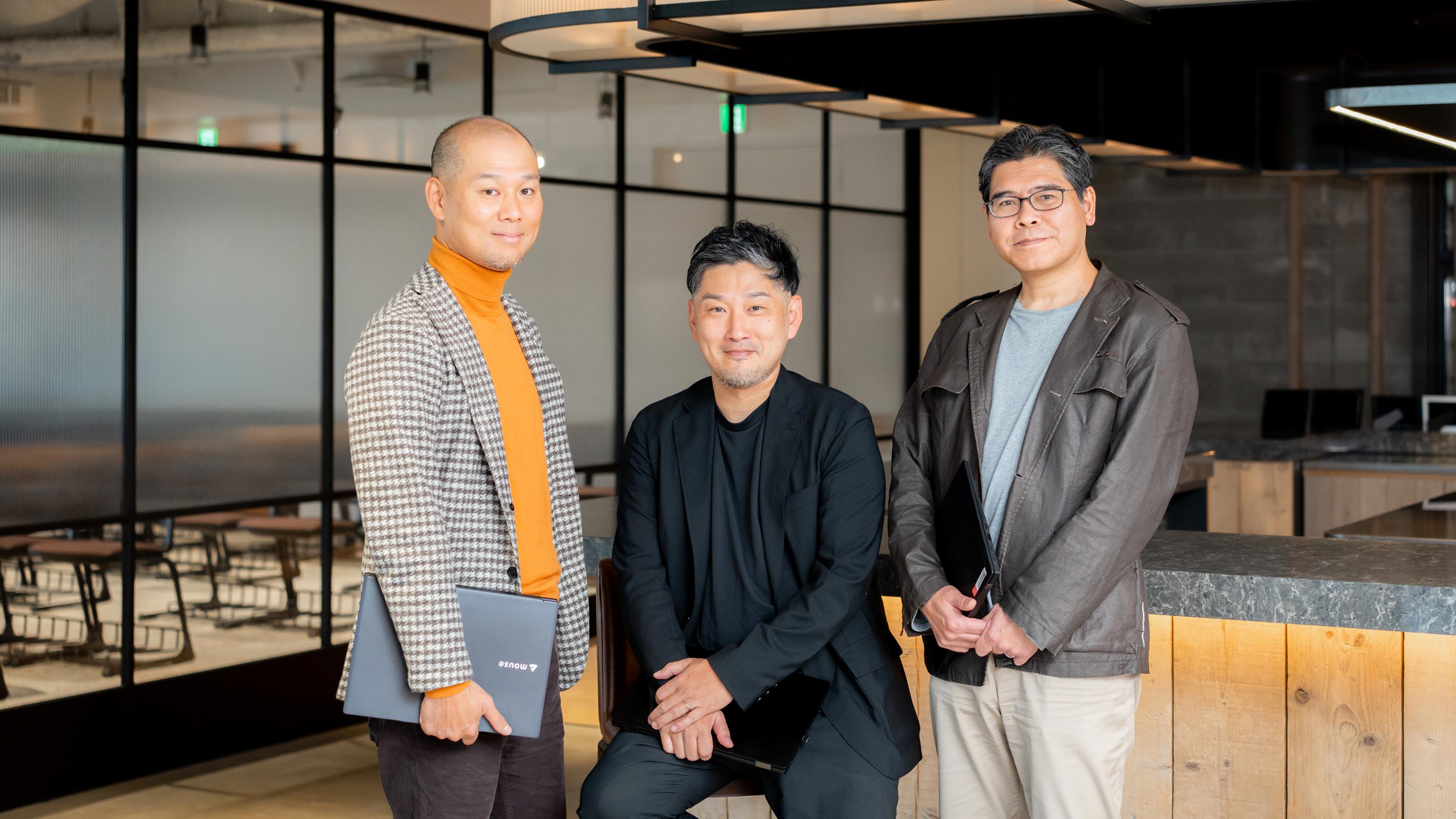新東電算株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
創業45年の堅実経営+AI製品にもチャレンジ! 技術力が身につき、離職率7%!
企業について
同社は、受託開発(持ち帰り/客先常駐)および自社製品の開発・販売を手がけている。
受託開発における主な領域としては、まずは医療機器。国内大手メーカーの血液検査装置(ロボット)のソフトウェア開発を独占的に受託している。また、放射線を測定し様々なデータとしてアウトプットできるIoT機器のほか、CTやMRI、PET、遠隔読影システムなど多彩な実績を持つ。同社が開発した「生活習慣病リスクシミュレーションシステム」は、テレビ番組で取り上げられるほど注目されている。
放送分野にも強い。NHKの全国36局にある「システム監視装置」「ラジオ監視装置」をNHKと共同開発し、4件の特許を取得。ソフトウェアだけでなく、ハードウェア開発能力もあるところは特長の1つだ。
これら以外では、物流会社の業務改善システムや受発注システムをほぼすべて、持ち帰りで開発。そのほか、多様な領域でのWeb系業務システムも数多く手がけている。
取引先としては、三菱電機、NEC、日本放送協会(NHK)、キヤノン、日立製作所、日本アイ・ビー・エム、凸版印刷、山崎製パンといった大手企業が顔を揃える。いずれも上流工程からの包括的な直取引だ。
自社開発においては、主に“簡単入力”をウリにした次のタッチ式オリジナル製品をリリースしている。
●行動予定表サイネージ「Touch DE Schedule」:従来型のホワイトボードの行動予定表をタッチパネル式のデジタルサイネージ化した製品。
●ペーパーレスサイネージ「Touch DE Paperless」:カタログやパンフレットの取り扱いが多いユーザーのペーパーレス化を実現する、タッチ式デジタルサイネージ。
●電子タイムレコーダー「Touch DE Record」:タイムカードレスで簡単に入退時刻を記録。
「いちいちPCを立ち上げてアクセスして入力しなくても、ワンタッチするだけで済む簡単便利なUI/UXが好評です」と取締役の牧野章子氏は言う。
そして目下、AIを活用した顔認証機能を物の認識に応用するパッケージを開発している。
「流通業などにおける棚卸しには膨大な手間暇がかかるもの。このシステムは、カメラを使って物体を識別することにより、当該作業を自動化するものです。圧倒的な業務効率化が図れると思います」(牧野氏)
「ミッションを果たすと保守ばかりとなり、もっと開発に関わりたいと会社を飛び出して当社を創業することにしました」と井手口氏は述懐する。
メインフレーム系ディーラーから取引先を紹介されるなどして案件を獲得し、スタート。経営方針として最重視したのは、“堅実経営”であった。
「前職の建設会社ではトップに近いポジションで仕事をしましたが、そのトップが堅実経営の見本のような存在でした」(井手口氏)
その後同社は、今日まで“無借金経営”を続けている。地下鉄千代田線「湯島」駅から徒歩1分という好アクセスの立地に、全額自己資金で自社ビルも建設した。会社設立5年以内に85%の企業が消えていく中、同社は45年間もの長きに渡って安定経営を続け、全国優良法人ランキングで常に上位に位置するとともに、新領域へのチャレンジも怠らずにきた。
そこには、最先端技術への先行投資や人材育成への投資に潤沢な資金を確保すべく、ムダなコストを削ぎ落し、間接費用をできるだけ減らすという経営方針が貫かれている。2019年8月現在115名の社員のうち、間接部門の社員比率はわずか3%。「社内には、声を大にして『資金はあるから、新しいサービスや領域へのチャレンジをどんどん提案しろ』と発破をかけている」と井手口氏は言う。
そして、財務内容もオープンにし、黒字が出れば決算賞与として営業利益の3分の1を全社員に分配している。社員の経営への参画意識を高めるための「若手経営ボード」も運営。
「当社には『会社は社員みんなのもの』という価値観が強くあります。社員を大切に思う気持ちはどこにも負けません。その結果、7%という非常に低い離職率に結び付いていると自負しています」と井手口氏は胸を張る。
「技術力を高めるために、新しい技術要素のある案件を積極的に確保するようにしています。それを社内に水平展開し、全体的な底上げを図っています」
それとともに、社員の技術や業務対応力のレベルを細かく把握し、ステップアップできるような業務をアサインする。こうして徐々に難易度の高い案件に取り組めるようにしている。
「その一方で、特定の分野に偏り過ぎないよう、いろいろな領域も経験できるようにし、フルスタック的な幅の広いエンジニアやプロジェクトマネージャーになれるよう育成しています。技術のことだけでなく、社会・経済情勢にも関心を持ち、広範な視点を持つバランスの取れた人材になることも重視しています。転職を奨励しているわけではありませんが、どこでも通用する人材であると自負しています」(牧野氏)
こうして、プロ意識の高い人材が育つ同社であるが、平均年齢34歳という社内のカルチャーはフラットで「大学の研究室やゼミのようなフランクな雰囲気」(牧野氏)だという。
働き方としては、フレックスタイム制度や産休・育休、時短制度を設け、取得しやすいようバックアップ体制も整えている。平均残業時間は月18時間(1日1時間未満)程度だ。ちなみに女性社員比率は22%で、20代に限れば43%と多い。
社員同士の親睦を深めるため、数年ごとに海外社員旅行も実施している。
極めて安定した経営基盤と、長年の信頼関係を構築した多数の取引先があるからこそ、新しいことにも思い切りチャレンジできる風土がある同社。経験が浅くても、マインドがあればいくらでも成長できる環境がある。ステップアップしたい求職者にとっては、見逃せない募集といえるだろう。
企業情報
新東電算株式会社
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > IoT・M2M・ロボット
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
4,000万円
2018年 7月 11億円
1974年10月
代表取締役 井手口 博登
放送・医療・通信・銀行・物流・保険・食品・ホテル等の幅広い業界で受託ソフトウェア開発しています。
ヘルスケア分野では、TV番組「おはよう日本」で当社が開発している
ソフトウェアが紹介されました。
●各種業務別ユーザーソフトウェア開発・保守管理業務
太陽光発電の分野では、ハードメーカーと協力し太陽光発電の監視や電力量の情報収集ができるシステムをすでに3カ所へ導入済み。今までのノウハウを活かして、新しい分野にも挑戦しています。
●各種ハードウェアの開発
ソフトウェア開発だけでなく、主に放送関係でハードウェアにも力を入れていて売上げの20%を占めるまでに成長しています。
●各種コンサルティングサービス
金融分野では、銀行へ信用リスク管理システムのコンサルティングで信頼を得ています。また、金融分野同様にミスの絶対許されない全国の空港管制システムも手がけています。
三菱電機(株)、三菱電機エンジニアリング(株)、三菱地所(株)、三菱電機グループ、日本アイ・ビー・エム(株)、日本電気(株)、日本放送協会(NHK)、(株)NHKアイテック、(株)NHKメディアテクノロジー、(株)日立製作所、富士フイルムソフトウエア(株)、日本メジフィジックス(株)、常陽銀行、北國銀行、筑波大学、東京家政大学、日本ユニシス(株)、エリクソン・ジャパン(株)、(株)NTTドコモ、ドコモ・システムズ(株)、凸版印刷(株)、(株)ヤマザキ物流、(株)パール物流、株式会社フィリップス・ジャパン、北海道大学、日本電気通信システム(株)、千葉銀行、(株)インテック、(株)竹中工務店、イオングループ、味の素(株)その他多数(順不同)
115人
35歳
〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-7 新東ビル
この企業と同じ業界の企業
ぜひ探してみてください🔍
ぜひ探してみてください🔍
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 新東電算株式会社の中途採用/求人/転職情報