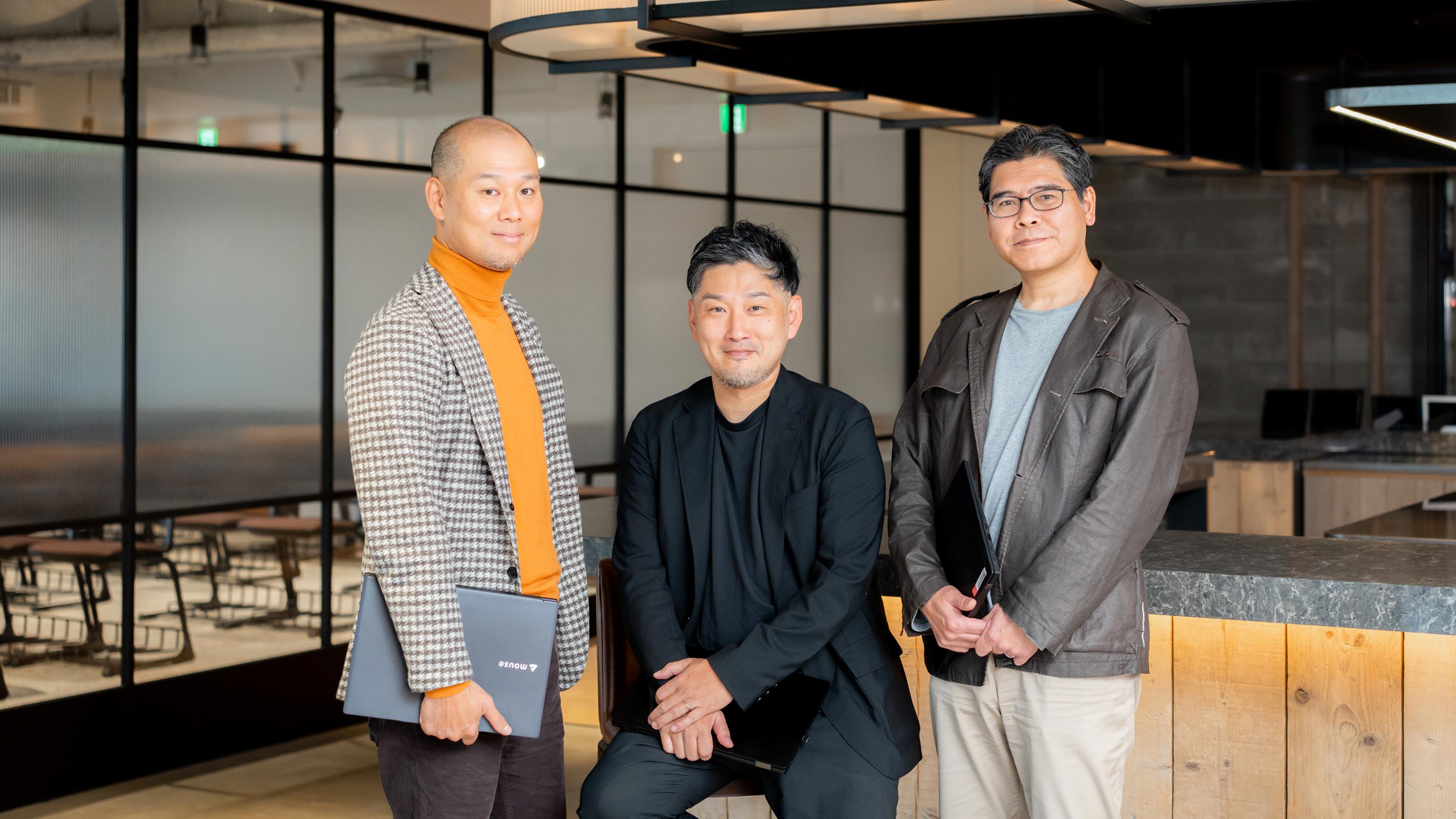株式会社リンネット
- IT/Web・通信・インターネット系
流通・小売業に特化したシステム開発で九州No.1を目指す。堅実性と創造性を兼ね備えたITソリューション企業
企業について
流通のトータルサポーター「ヤマエグループ」企業として安定成長
受発注システムや物流管理システムをはじめ、食品流通に関わる幅広いITソリューションを提供する株式会社リンネット。最大の強みは、メーカーから物流、小売に至る食品流通プロセス全体、つまりSCM(サプライチェーンマネジメント)における情報課題を知り尽くしていることだ。
生産管理システム、受発注EDI(データ交換)システム、商品規格管理システム、多店舗展開の小売向けシステム、ピッキングシステム、IDC(データセンター)サービスなど、柱となるソリューションを列挙するだけでも、同社が手がける領域の幅広さが見えてくる。取引先は、食品製造・加工会社からロジスティクスを担う物流・倉庫会社、GMS(総合スーパー)・ドラッグ・コンビニといった小売チェーンまで、食品流通に関わる企業を中心に1000社を超える。
同社の母体は、福岡に本社を置き、人々の生活に欠かせない「食」と「住」の中間流通業として、長きにわたり信頼と実績を積み重ねてきた『ヤマエグループホールディングス(株)』。1985年、食品流通プロセスの急速な情報化を背景に、グループのIT戦略を担う会社として設立された経緯がある。グループ会社であるヤマエ久野(株)は全国の卸売ランキング(食品部門)でも上位につける九州トップの卸売会社であり、その強力なバックボーンを生かし、浮き沈みの激しいIT業界にあって、30年以上にわたって安定成長を継続している同社。直近の10年間だけでも、税引き後利益を5倍以上も伸ばしている。代表取締役社長の石上武徳氏は語る。
「よく同業他社の経営者から“御社は顧客開拓に苦労しなくて済むから羨ましい”と言われます。もちろん新規開拓はそんなに甘くはありませんが、“ヤマエグループのリンネットです”と挨拶すれば、無理なく商談のテーブルにつけるのも確か。基幹システムや業務管理システムなど、流通の枠を超えてITソリューション全般を任される取引先も少なくありません」
一方、技術面のアドバンテージは、営業から開発・運用、メンテナンスまで一気通貫で手がける開発環境の厚みにある。
「当社の社員は現在、約60名。一般に数十名体制のIT企業は、受託開発に特化しているか、歴史の浅いベンチャーかのどちらかであるケースが多いと思いますが、当社では受託開発はもちろんゼロからの新規案件の開発・運用も行いますし、EDIクライアントパッケージや企業間電子データ交換のASPサービスといった自社製品の開発も手がけます。また将来を見据えた独自領域への挑戦も始まっています。新卒でも中途でも、エンジニアの採用面接で“この規模の会社で、これほどチャンスの多い会社はそう多くはないはずだ”という話をすると、大きくうなずきながら聞いてくれますよ」(石上氏)
生産管理システム、受発注EDI(データ交換)システム、商品規格管理システム、多店舗展開の小売向けシステム、ピッキングシステム、IDC(データセンター)サービスなど、柱となるソリューションを列挙するだけでも、同社が手がける領域の幅広さが見えてくる。取引先は、食品製造・加工会社からロジスティクスを担う物流・倉庫会社、GMS(総合スーパー)・ドラッグ・コンビニといった小売チェーンまで、食品流通に関わる企業を中心に1000社を超える。
同社の母体は、福岡に本社を置き、人々の生活に欠かせない「食」と「住」の中間流通業として、長きにわたり信頼と実績を積み重ねてきた『ヤマエグループホールディングス(株)』。1985年、食品流通プロセスの急速な情報化を背景に、グループのIT戦略を担う会社として設立された経緯がある。グループ会社であるヤマエ久野(株)は全国の卸売ランキング(食品部門)でも上位につける九州トップの卸売会社であり、その強力なバックボーンを生かし、浮き沈みの激しいIT業界にあって、30年以上にわたって安定成長を継続している同社。直近の10年間だけでも、税引き後利益を5倍以上も伸ばしている。代表取締役社長の石上武徳氏は語る。
「よく同業他社の経営者から“御社は顧客開拓に苦労しなくて済むから羨ましい”と言われます。もちろん新規開拓はそんなに甘くはありませんが、“ヤマエグループのリンネットです”と挨拶すれば、無理なく商談のテーブルにつけるのも確か。基幹システムや業務管理システムなど、流通の枠を超えてITソリューション全般を任される取引先も少なくありません」
一方、技術面のアドバンテージは、営業から開発・運用、メンテナンスまで一気通貫で手がける開発環境の厚みにある。
「当社の社員は現在、約60名。一般に数十名体制のIT企業は、受託開発に特化しているか、歴史の浅いベンチャーかのどちらかであるケースが多いと思いますが、当社では受託開発はもちろんゼロからの新規案件の開発・運用も行いますし、EDIクライアントパッケージや企業間電子データ交換のASPサービスといった自社製品の開発も手がけます。また将来を見据えた独自領域への挑戦も始まっています。新卒でも中途でも、エンジニアの採用面接で“この規模の会社で、これほどチャンスの多い会社はそう多くはないはずだ”という話をすると、大きくうなずきながら聞いてくれますよ」(石上氏)
自社パッケージ、AIやRPA… 開発力強化を見据えた新たなチャレンジ
安定した経営基盤と自由度の高い開発環境の両方を兼ね備えていること。かつては石上氏自身も、そうしたリンネットらしさに魅せられたエンジニアの1人だった。
「私は今から25年前、30歳を過ぎた頃に当社に中途入社しました。前職は大手SIerのSE。納入したシステムの運用スタッフとして当社と出会い、今に至っています。当時のリンネットは、グループの中核企業であるヤマエ久野関連のシステム開発で経営基盤を固め、グループ外への新たな展開を模索する過渡期にありました。ここなら経営面の心配もなく、エンジニアとして自由に発想を伸ばせそうだと考えたのです」(石上氏)
石上氏は以後、物流企業や小売チェーン向けシステム開発、IDCサービスなど、現在に至る業容拡大を最前線のエンジニアの1人として担い、5年前に社長に就任。近年では、エンジニア出身の経営トップらしく、開発力強化に向けた多彩なチャレンジをスタートさせている。大手CVSチェーン関連のパッケージ開発もその一例だ。
「九州から北海道まで、ここ数年でコンビニに弁当や総菜を納入する食品工場との取引が大きく広がっています。こうした取引先に対し、生産管理システムや賞味期限システムなど、従来から手がけてきたソリューションではカバーしきれない部分、たとえば受注予測から食材の仕入れまで一括して管理できる原材料管理システム、新しい弁当商材のレシピから価格・ラベルイメージの自動出力までカバーする新商品規格書システムといった自社開発のパッケージシステムを提案して喜ばれています」(石上氏)
また将来を見据えて、AIの活用や、業務プロセスの自動化を図るRPAの研究にも着手。2019年4月には、こうした新規の研究開発に特化した専任部署も立ち上げる。新部門のスターティングメンバーは全員、自ら手を挙げた社員。開発テーマはもちろん、部署名も自分たちで決める自律運営のスタイルを徹底している。すでに各種セミナーでの登壇、メディアへの掲載、九州各県から社内見学を受け入れるなど、業界内外の注目を集めている。
「リンネット=RINNETのRは“流通”のR、INは“Information”、そして”Network”の頭文字を取ったもの。個別企業へのソリューション提案にとどまらず、食品流通全体を見据え、ITでSCMの最適化を実現することが当社の使命です」(石上氏)
同社では今後、これまでに蓄積した知見とスキルを集約しながら、物流向け、小売り向けなど、あらゆる領域で自社パッケージ開発を加速させていく方針だ。設立40年にして、意欲あるエンジニアの活躍舞台がかつてないスケールで広がっているといえるだろう。
「私は今から25年前、30歳を過ぎた頃に当社に中途入社しました。前職は大手SIerのSE。納入したシステムの運用スタッフとして当社と出会い、今に至っています。当時のリンネットは、グループの中核企業であるヤマエ久野関連のシステム開発で経営基盤を固め、グループ外への新たな展開を模索する過渡期にありました。ここなら経営面の心配もなく、エンジニアとして自由に発想を伸ばせそうだと考えたのです」(石上氏)
石上氏は以後、物流企業や小売チェーン向けシステム開発、IDCサービスなど、現在に至る業容拡大を最前線のエンジニアの1人として担い、5年前に社長に就任。近年では、エンジニア出身の経営トップらしく、開発力強化に向けた多彩なチャレンジをスタートさせている。大手CVSチェーン関連のパッケージ開発もその一例だ。
「九州から北海道まで、ここ数年でコンビニに弁当や総菜を納入する食品工場との取引が大きく広がっています。こうした取引先に対し、生産管理システムや賞味期限システムなど、従来から手がけてきたソリューションではカバーしきれない部分、たとえば受注予測から食材の仕入れまで一括して管理できる原材料管理システム、新しい弁当商材のレシピから価格・ラベルイメージの自動出力までカバーする新商品規格書システムといった自社開発のパッケージシステムを提案して喜ばれています」(石上氏)
また将来を見据えて、AIの活用や、業務プロセスの自動化を図るRPAの研究にも着手。2019年4月には、こうした新規の研究開発に特化した専任部署も立ち上げる。新部門のスターティングメンバーは全員、自ら手を挙げた社員。開発テーマはもちろん、部署名も自分たちで決める自律運営のスタイルを徹底している。すでに各種セミナーでの登壇、メディアへの掲載、九州各県から社内見学を受け入れるなど、業界内外の注目を集めている。
「リンネット=RINNETのRは“流通”のR、INは“Information”、そして”Network”の頭文字を取ったもの。個別企業へのソリューション提案にとどまらず、食品流通全体を見据え、ITでSCMの最適化を実現することが当社の使命です」(石上氏)
同社では今後、これまでに蓄積した知見とスキルを集約しながら、物流向け、小売り向けなど、あらゆる領域で自社パッケージ開発を加速させていく方針だ。設立40年にして、意欲あるエンジニアの活躍舞台がかつてないスケールで広がっているといえるだろう。
よく学び、よく休み、よく伸びる。絶妙のワークライフバランス
同社のエンジニアは30代をコアに、20代から40代まで、バランスの取れた世代構成となっている。現在の開発環境はWindows/Oracle/SQL server系が主体だが、Ruby on Rails、Python、PostgreSQLといったオープンソース中心の環境へのシフトを進めていて、開発現場は新たな刺激に大いに活気づいている。GeneXusなど第4世代言語の導入も検討中だ。
「現場は風通しがよすぎるくらい、自由な空気に満ちています。若手エンジニアが私に直接、“ちょっといいですか“”こんなことがやりたい”と、相談を持ちかけてくることも多いですよ」(石上氏)
こうしたエンジニア個々の意欲を確かな成長につなげるために策定されたのが、同社独自の人事評価システム「G-UP2」だ。年1回、社長がエンジニア全員と個別面談。中長期的な目標や身に付けたい技術・スキルなど、個々の意向を踏まえたうえで、各自の具体的な成長目標を設定し、目標に沿って必要な勉強会や外部研修への参加をセッティングしていく。もちろん、研修はすべて業務扱いだ。
ワークライフバランスも良好だ。休日は土日連休の完全週休2日制。取引先が流通業界主体とあって、週末に運用やメンテナンスの緊急対応を求められるケースもゼロではないが、あっても年間に数度のレベルだ。また業務を進める上で、開発のチームメンバーはもちろん、営業など他職種、グループ会社などと連携する場面も多く、チームワークは欠かせないが、社内コミュニケーションを深める機会も少なくない。
福岡に拠点を置く企業だけに、東京や関西からUターン入社するなど、九州ゆかりの社員が目立つが、住まいのサポートも手厚く、月額2万円の住宅補助が支給される。本社はJR博多駅から徒歩10分弱のオフィス街にあるが、歩いて通える範囲に手ごろな物件も多く、実際、徒歩通勤の社員が少なくないそうだ。「住みやすい街調査」の類でしばしば上位にランクされる福岡ならではのメリットといえる。
堅実性と創造性を兼ね備え、暮らしやすさも享受できる職場。自由度の高い開発をしたいエンジニアにとっては、間違いなく魅力的な環境だろう。
「現場は風通しがよすぎるくらい、自由な空気に満ちています。若手エンジニアが私に直接、“ちょっといいですか“”こんなことがやりたい”と、相談を持ちかけてくることも多いですよ」(石上氏)
こうしたエンジニア個々の意欲を確かな成長につなげるために策定されたのが、同社独自の人事評価システム「G-UP2」だ。年1回、社長がエンジニア全員と個別面談。中長期的な目標や身に付けたい技術・スキルなど、個々の意向を踏まえたうえで、各自の具体的な成長目標を設定し、目標に沿って必要な勉強会や外部研修への参加をセッティングしていく。もちろん、研修はすべて業務扱いだ。
ワークライフバランスも良好だ。休日は土日連休の完全週休2日制。取引先が流通業界主体とあって、週末に運用やメンテナンスの緊急対応を求められるケースもゼロではないが、あっても年間に数度のレベルだ。また業務を進める上で、開発のチームメンバーはもちろん、営業など他職種、グループ会社などと連携する場面も多く、チームワークは欠かせないが、社内コミュニケーションを深める機会も少なくない。
福岡に拠点を置く企業だけに、東京や関西からUターン入社するなど、九州ゆかりの社員が目立つが、住まいのサポートも手厚く、月額2万円の住宅補助が支給される。本社はJR博多駅から徒歩10分弱のオフィス街にあるが、歩いて通える範囲に手ごろな物件も多く、実際、徒歩通勤の社員が少なくないそうだ。「住みやすい街調査」の類でしばしば上位にランクされる福岡ならではのメリットといえる。
堅実性と創造性を兼ね備え、暮らしやすさも享受できる職場。自由度の高い開発をしたいエンジニアにとっては、間違いなく魅力的な環境だろう。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)
営業職の求人(1件)
企業情報
会社名
株式会社リンネット
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
資本金
5,000万円
売上(3年分)
2024年 3月 1,463百万
2023年 3月 1,126百万
2022年 3月 1,195百万
設立年月
1985年04月
代表者氏名
石上 武徳
事業内容
受発注システムや物流管理システムをはじめ、食品流通に関わる幅広いITソリューションを提供しています。
取引先は、食品製造・加工会社から物流・倉庫会社、総合スーパー・ドラッグ・コンビニといった小売チェーンまで、食品流通に関わる企業を中心に1000社を超える。
また、近年では自社パッケージ開発やAI事業、RPA事業など、開発力強化をにらんだ新たなチャレンジにも力を入れています。
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
ヤマエグループホールディングス(株)
主要取引先
ヤマエグループホールディングス(株) ヤマエ久野(株)
従業員数
53人
平均年齢
38.3歳
本社住所
福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル4階
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社リンネットに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社リンネットの中途採用/求人/転職情報