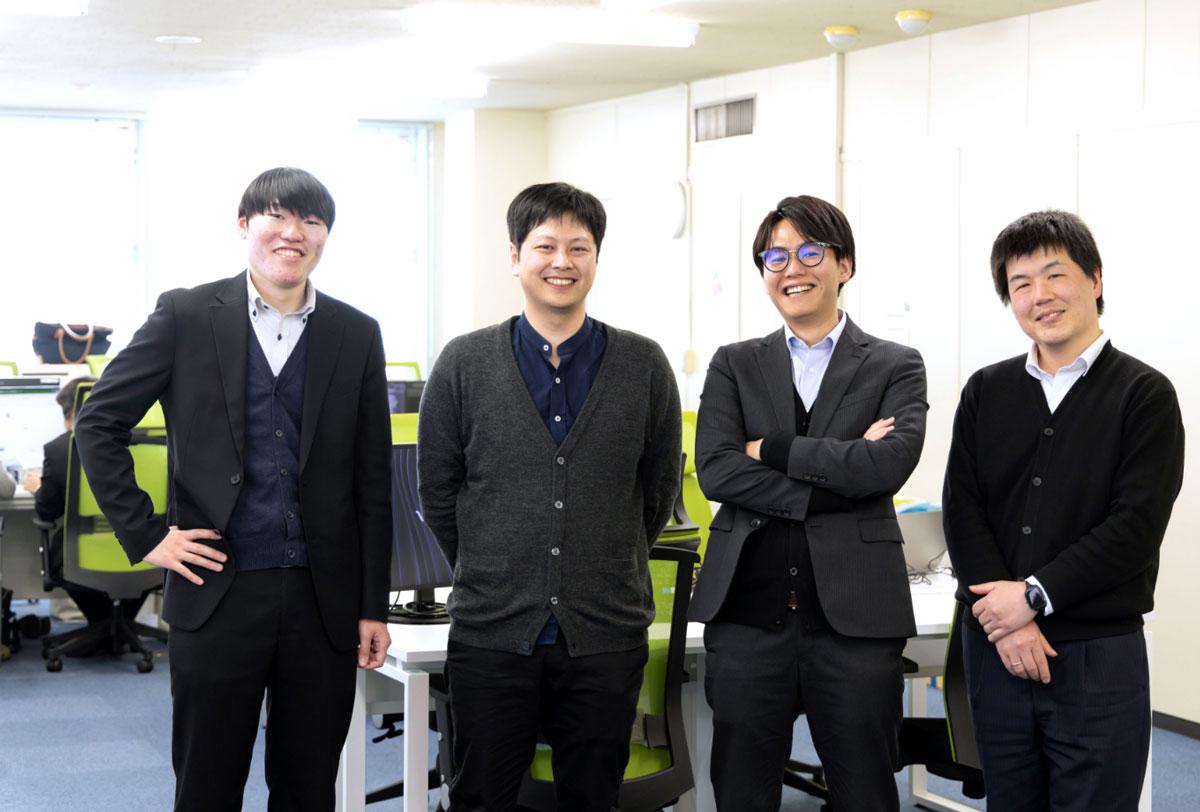HiCustomer株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
“カスタマーサクセス”のデファクトスタンダードを目指す!
企業について
“カスタマーサクセス”とは、「顧客が自社の課題を解決し、成功することを導く」サービスを指す。“カスタマーサポート”がエンドユーザーからの問い合わせに受動的に対応するサービスであるのに対し、“カスタマーサクセス”はエンドユーザーのサービス利用状況に応じて能動的にアプローチする姿勢を指している。
同社が対象としているのは、SaaS型のB to Bプロダクトをサブスクリプション型で提供している事業者。こうした事業者においては、マーケティング活動を行ってユーザーを獲得し契約すればそれで終わり、ではない。プロダクトを使い続け、毎月使用料を支払い続けてもらう必要がある。一般的に新規ユーザー獲得コストは高くつくので、できるだけ長く使い続けてもらう“LTV”(Life Time Value)をいかに高めるかが最重要の施策となる。
ところが、プロダクトを十分に使いこなせなかったり、サービスに不満を感じるといった理由で解約するユーザーが出現する。苦労して獲得した労力やコストが水泡に帰す瞬間だ。
こうした事態を避けるために、定期的な連絡や、CRMやSFAなどのツールを工夫して施策を講じる事業者もある。しかし、それではエンドユーザーの利用状況を正確に把握し適切な対応を講じることは難しく、各事業者共通の悩みとなっていた。
「HiCustomer」は、プロダクトに接続することで、個別のエンドユーザーの利用状況を把握。エンドユーザーの“健康状態”を表すヘルススコアを「GOOD」「NORMAL」「BAD」の3段階で算出、プロダクト運営者への“見える化”を行う。その健康状態の基準は自由に定義・設定できる。これによって、「BAD」のエンドユーザーに個別にコンタクトして解約を防いだり、「GOOD」のエンドユーザーに対して割引サービスやアップセル・クロスセルの案内をするといった“カスタマーサクセス”施策を講じることが可能となる。そういった対象者を検知する独自アラートの作成機能もあり、運営担当者の「todo」を通知して着実な打ち手を支援する。
同様のプロダクトはほかになく、2018年12月に正式リリース後、1カ月で数十社が導入するという好調なスタートを切った。リリース前から対象事業者の悩みを共有するコミュニティをつくり、「HiCustomer」の認知度の向上に努めてきた成果も奏功している形だ。
「近年、あらゆるモノが“所有から使用へ”“モノからコトへ”とサービス化する“サブスクリプション経済”が進展しています。SaaS型のB to Bプロダクトはまさにその典型で、このモデルを採用する事業者が急増しています。ところが、せっかくいいプロダクトをつくっても、使い続けてもらう努力をしなければ使われなくなるケースが多いことを肌で感じていました。そこにビジネスチャンスを見出したのです」と鈴木氏は同社創業の契機を説明する。
仲間に声を掛けるなどしてチームを立ち上げ、「HiCustomer」開発に着手。1年で正式リリースに漕ぎつけた。
同社が「HiCustomer」を通じて実現したいと考える世界観は、大きく2つあるという。SaaS型B to Bプロダクトのユーザーと、提供する側のそれぞれがよりハッピーとなることだ。
「『HiCustomer』のユーザーが増えれば増えるほど、ユーザー志向の事業者が増え、世の中に一層便利なサービスが増えることに繋がります。また、サービスを提供する事業者側としては、『HiCustomer』によって自らのサービスがユーザーに使われ、喜ばれている状況がより明確にわかるようになります。その結果、大きなモチベーションをもたらすことに繋がると思います」(鈴木氏)
当面の目標としては、2018年末までに100社のユーザーを獲得し、カスタマーサクセス管理プラットフォームとしてのデファクトスタンダードとなること。その先には、“カスタマーサクセス・オーケストレーション”の実現がある。鈴木氏は次のように説明する。
「カスタマーサクセスに隣接する領域に、マーケティング・オートメーションやCRMなどがあります。カスタマーサクセスには、エンドユーザーの利用状況というコアとなるデータが蓄積されます。そこで、カスタマーサクセスから隣接領域にバリューチェーンを伸ばすことで、LTVベースでマーケティング施策の評価を行うといった、より緻密で有効なマーケティング戦略が実現できるようになります。この、いわば“カスタマーサクセス・オーケストレーション”を、当社がコアとなって推進していきたいと考えています」
「以前、システムの営業を手がけている時、営業と開発のコミュニケーションの在り方に問題を感じていました。クライアントに接する営業は、納品したシステムが評価される声も聞くのですが、それを開発に伝えることはなく、もっぱらクライアントが不満に感じて改善を求められた要件ばかりを伝えるのです。開発にしてみれば、楽しいことではありません。そのうち、営業が近づくと開発はガードを上げるといったスタンスになってしまうわけです。それでいいサービスが提供できるとは思えません。そうではなく、営業と開発がタッグを組んでクライアントの課題に取り組み、どう貢献できているのか、何が足りないのかを共有し改善に繋げなければなりません。ですから当社では、お客様の評価が透明性をもって全員に伝わる環境づくりにこだわっています」
その点、同社は顧客との距離感が近い。プライベートセミナーにユーザーを招いて講演してもらうといった機会を多く設けている。
「お客様に近い環境で仕事がしたいという人にはフィットしていると思います」(鈴木氏)
全員がプロダクトオーナーとなり、主体性をもって課題を把握し、追加機能や改善点の企画・開発・実装に取り組む。そんなカルチャーが形成されているという。
したがって、開発においてはスクラムの手法を導入し、2週間に1回機能をリリースすると定めてどんな機能をどんな優先順位で開発するかを全員で議論して決めている。これにより、短サイクルで多くの機能を実装している。
ビジネスサイドにおいては、100%インバウンドへの対応で商談を進めている。「LTVを高めるプロダクトだけに、きちんとした価値評価の上で導入してもらう丁寧なアプローチを心がけている」と鈴木氏。自社も「HiCustomer」を使ってユーザーの活用度合を把握し、きめ細かいフォローアップを行っているという。
経営状況の共有などは、毎月末に1時間程度のミーティングの場で行い、その後は軽食やアルコールも入れてカジュアルにコミュニケーションする時間をつくっている。
働き方などの制度はこれからつくるフェーズにあるが、「成果を上げやすくすることを第一に考え、時間や場所などは柔軟に決めてられるようにする」と鈴木氏は言う。
同社が迎えたい人材は、人の悪口を言ったり裏切ったりは決してしない“いい人”であり、スタートアップとして経営環境が変化する中、意欲的に学び続けられる人だ。
新しい概念の“カスタマーサクセス”のデファクトスタンダードを目指す同社。その中核メンバーとなれるチャンスが、ここにある。
企業情報
HiCustomer株式会社
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
1.5億円
2017年12月
鈴木 大貴
HiCustomerは、SaaSプロダクトを使うユーザーが、その価値を最大限に引き出すことができるようにするためのSaaS事業者による取り組み (=カスタマーサクセス活動) を支援するサービスを提供しています。
【私たちが目指していること】
突然ですが、「2025年の崖」という言葉をご存知でしょうか?
2018年に経済産業省が発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」(*)で喚起されている、企業のITシステム老朽化やデジタル化の遅れにより、2025年以降、毎年12兆円の経済損失が発生するとされる問題です。
この問題は、生活者である私達にとって、本来インターネット経由で出来てほしいことが対面や紙で強いられるという不便に接続しています。
HiCustomerが提供する「ノーコードで作成できる顧客と共有できるワークスペース Arch(アーチ)」は、IT製品の売り手が、買い手から製品を正しく評価してもらうことを助け、買い手が製品をスピーディに活用できる状態を作るプロダクトです。
私たちは、Archを広めることで以下のような世界を作りたいと考えています。
・IT製品が世に浸透するスピードを早め、一人ひとりの生活をより便利に
・成熟し硬直しがちな社会が改善する速度を早め、誰もが幸せに生きていける環境へ
このような世界を一緒に目指してくれる仲間を探しています!
非上場
Coral Capital, BEENETX, アーキタイプベンチャーズ
11人
31歳
東京都品川区西五反田2-29-9 五反田アルファビル401
この企業と同じ業界の企業
ぜひ探してみてください🔍
ぜひ探してみてください🔍
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- HiCustomer株式会社の中途採用/求人/転職情報