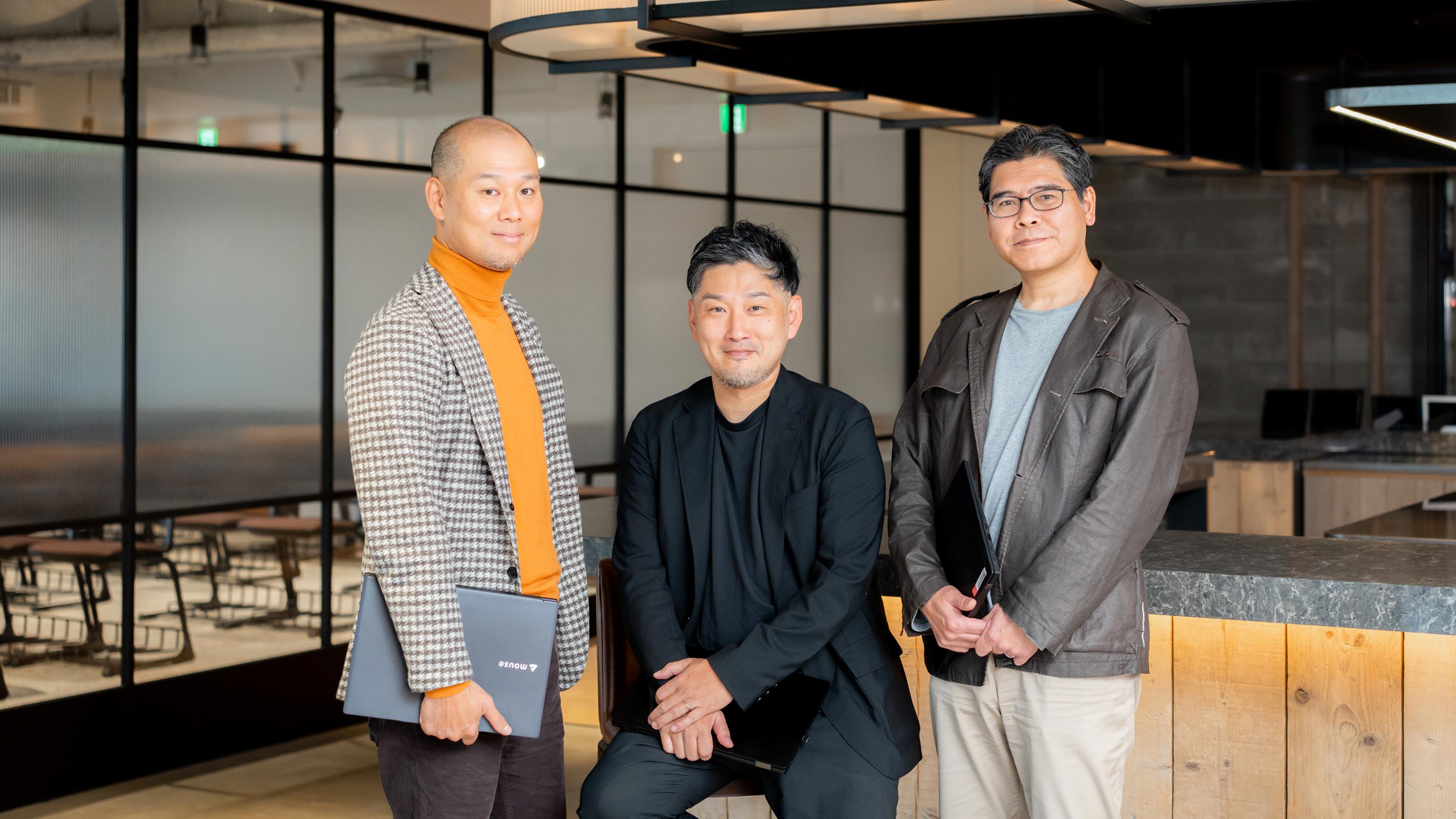株式会社ウイズ
- IT/Web・通信・インターネット系
開発実績400社以上。自社クラウドサービス「haruka」もローンチするなど、バリエーションが豊かな進化系Sier企業
企業について
基幹システムからレゲエフェスのオリジナルアプリ開発まで。イノベーティブなマインドでIT領域に挑戦!
株式会社ウイズは大阪と東京に事業拠点を置き、着実に成長を続ける設立23年目のSIerである。際立った特長は、あらゆる業種のオファーに対応できるシステム構築力と、斬新な技術提案でクライアントの業績向上をサポートするイノベーティブな開発マインドを兼ね備えている点だ。
社内は主として業務系ソリューションを手がけるシステム事業部と、さまざまな付加価値提案を担うビジネスソリューション事業部に分かれ、多種多様なニーズに対応している。
400社を超えるクライアントは、公共、電力、金融、教育、各種製造業まで、あらゆる業種をカバー。手がける領域も、基幹システムから販売管理、生産管理、ナレッジ管理、学習支援、ECサイト、スマートフォンアプリ、ブランディング戦略などと幅広い。
システム事業部長の魚住圭一氏は「開発だけでなく、企画段階のコンサルティングから関わり、運用保守までサポートする総合力が強み。クライアントの評価も高く、ほとんどの案件がリピートしています。おかげさまで、新規の案件がなかなか受けられない状況です」と胸を張る。
一方ビジネスソリューション事業部では、システム事業部で培った豊富な技術蓄積をベースに、リッチコンテンツ構築を軸に高付加価値の技術提案でクライアントの事業戦略を支え、WEBを中心とするクロスメディア戦略を広げている。ASPを利用したオンラインショップのカスタマイズ、ARを用いたパブリシティ、CMSとASP ECサービスを連携させた通販サイトなど、提案事例は枚挙に暇がないほどだ。
「両事業部とも、クライアントのオファーに対応するだけでなく、先方の業務内容と経営課題を的確に把握したうえで、課題解決や需要創出につながる施策を当社から提案する攻めの営業スタイルで実績を広げています。たとえば関西最大のレゲエフェスのオリジナルアプリは、レコード会社とつながりのある営業担当と組んでゼロから提案し、実現した事例です。フェスのパンフレットにアプリを入れたスマホをかさずとレコードが回り出して曲が流れるなど、遊び心満載。いい意味の遊び心を取り入れる傾向は、ビジネスソリューション事業部の方がより強いかもしれませんね。エンジニア目線で言えば、どちらの事業部でも常に新しいこと挑戦できるので、開発現場は常に刺激に満ちています」と語るのは、システム事業部でキャリアを築き、現在はビジネスソリューション事業部で開発・運用サポート課長を務める河嶋健太氏だ。河嶋氏の言葉は、両事業部の開発現場を知り尽くしたエンジニアならではの説得力に満ちている。
社内は主として業務系ソリューションを手がけるシステム事業部と、さまざまな付加価値提案を担うビジネスソリューション事業部に分かれ、多種多様なニーズに対応している。
400社を超えるクライアントは、公共、電力、金融、教育、各種製造業まで、あらゆる業種をカバー。手がける領域も、基幹システムから販売管理、生産管理、ナレッジ管理、学習支援、ECサイト、スマートフォンアプリ、ブランディング戦略などと幅広い。
システム事業部長の魚住圭一氏は「開発だけでなく、企画段階のコンサルティングから関わり、運用保守までサポートする総合力が強み。クライアントの評価も高く、ほとんどの案件がリピートしています。おかげさまで、新規の案件がなかなか受けられない状況です」と胸を張る。
一方ビジネスソリューション事業部では、システム事業部で培った豊富な技術蓄積をベースに、リッチコンテンツ構築を軸に高付加価値の技術提案でクライアントの事業戦略を支え、WEBを中心とするクロスメディア戦略を広げている。ASPを利用したオンラインショップのカスタマイズ、ARを用いたパブリシティ、CMSとASP ECサービスを連携させた通販サイトなど、提案事例は枚挙に暇がないほどだ。
「両事業部とも、クライアントのオファーに対応するだけでなく、先方の業務内容と経営課題を的確に把握したうえで、課題解決や需要創出につながる施策を当社から提案する攻めの営業スタイルで実績を広げています。たとえば関西最大のレゲエフェスのオリジナルアプリは、レコード会社とつながりのある営業担当と組んでゼロから提案し、実現した事例です。フェスのパンフレットにアプリを入れたスマホをかさずとレコードが回り出して曲が流れるなど、遊び心満載。いい意味の遊び心を取り入れる傾向は、ビジネスソリューション事業部の方がより強いかもしれませんね。エンジニア目線で言えば、どちらの事業部でも常に新しいこと挑戦できるので、開発現場は常に刺激に満ちています」と語るのは、システム事業部でキャリアを築き、現在はビジネスソリューション事業部で開発・運用サポート課長を務める河嶋健太氏だ。河嶋氏の言葉は、両事業部の開発現場を知り尽くしたエンジニアならではの説得力に満ちている。
自社クラウドサービス「haruka」を2016年にローンチ!自社製品にも力を入れる。
近年では、多年にわたる開発実績を活用した自社製品のリリースも目立つ。2016年4月にローンチした原価管理を軸とするパッケージ「haruka」は、業務系システムを通じたシステム事業部の分厚いノウハウを生かしたクラウドサービスだ。
ビジネスソリューション事業部発のパッケージでは、「CARM」と「FIL」が二枚看板。どちらもARコンテンツの戦略的な活用を促す販促ツールで、導入後の拡張性の高さとあいまって幅広い業種で支持を広げている。
自社開発を含めた重厚な開発体制の背景には、言うまでもなく、卓越した技術力がある。2016年には、有志による研究開発チーム「LABO」が発足し、開発重視の姿勢がより鮮明になっている。
「当社の開発現場はもともと自由闊達で、やりたいこと、試したいことに自由に挑戦できる空気があります。ただ、私もそうですがエンジニアなら誰しも、業務の枠にとらわれず、より貪欲に新しいことに挑戦したいという気持ちを持っています。ある日、そうしたモチベーションが一番目立つ若手をつかまえて、“予算も権限もすべて渡すから、好きにやってみろ”と背中を押したことが、LABO発足につながりました」。(魚住氏)
「LABOはバーチャルな研究開発チーム。メンバーは各自の担当業務の合間に、Slackやチャットツールなどを駆使して連絡を取りながら、SPAやドッカー、IoT、VRやMRなど、旬のテーマを選んで自由に研究を進めています。研究成果を社内で共有しているので、営業担当を通じてクライアントの開発案件に組み込み、新たな提案につなげるケースも増えています」。(河嶋氏)
生協やメーカー向けに提案したSPAを用いたアプリもその一例。配送担当者のタブレットにアプリを組み込むことで、開発コストを抑えつつ業務効率化を実現し、クライアントに大いに喜ばれた。アルバム制作会社に提案した編集・制作用サイトでも、SPAのライブラリーを生かして操作性を飛躍させている。
植物を育てる「植育」サイトには、植木鉢の湿度の推移を把握し水やりのタイミングを知らせるなど、研究が佳境に入ったIoTの知見をふんだんに盛り込んでいる。同サイトは現在プロトタイプの開発中。ガーデニング関連業界などでのブレークを狙っている。
「ショールーム向けにARコンテンツを提案した原材料メーカーでは、“社会見学に訪れた小学生が大喜び”と反響を呼び、ニュースや新聞にも取り上げられました」と川嶋氏は満面の笑みで語る。
ちなみに、ショールーム向けの提案では工務店やインテリアデザイナー、音楽フェス向け提案ではイベント運営会社とコラボするなど、ITソリューションにとどまらない総合提案を心掛けているのも同社らしさの発露。あくまでクライアント目線に立ち、より広い視野で付加価値提案を行う姿勢が、圧倒的なリピート率につながっている。
ビジネスソリューション事業部発のパッケージでは、「CARM」と「FIL」が二枚看板。どちらもARコンテンツの戦略的な活用を促す販促ツールで、導入後の拡張性の高さとあいまって幅広い業種で支持を広げている。
自社開発を含めた重厚な開発体制の背景には、言うまでもなく、卓越した技術力がある。2016年には、有志による研究開発チーム「LABO」が発足し、開発重視の姿勢がより鮮明になっている。
「当社の開発現場はもともと自由闊達で、やりたいこと、試したいことに自由に挑戦できる空気があります。ただ、私もそうですがエンジニアなら誰しも、業務の枠にとらわれず、より貪欲に新しいことに挑戦したいという気持ちを持っています。ある日、そうしたモチベーションが一番目立つ若手をつかまえて、“予算も権限もすべて渡すから、好きにやってみろ”と背中を押したことが、LABO発足につながりました」。(魚住氏)
「LABOはバーチャルな研究開発チーム。メンバーは各自の担当業務の合間に、Slackやチャットツールなどを駆使して連絡を取りながら、SPAやドッカー、IoT、VRやMRなど、旬のテーマを選んで自由に研究を進めています。研究成果を社内で共有しているので、営業担当を通じてクライアントの開発案件に組み込み、新たな提案につなげるケースも増えています」。(河嶋氏)
生協やメーカー向けに提案したSPAを用いたアプリもその一例。配送担当者のタブレットにアプリを組み込むことで、開発コストを抑えつつ業務効率化を実現し、クライアントに大いに喜ばれた。アルバム制作会社に提案した編集・制作用サイトでも、SPAのライブラリーを生かして操作性を飛躍させている。
植物を育てる「植育」サイトには、植木鉢の湿度の推移を把握し水やりのタイミングを知らせるなど、研究が佳境に入ったIoTの知見をふんだんに盛り込んでいる。同サイトは現在プロトタイプの開発中。ガーデニング関連業界などでのブレークを狙っている。
「ショールーム向けにARコンテンツを提案した原材料メーカーでは、“社会見学に訪れた小学生が大喜び”と反響を呼び、ニュースや新聞にも取り上げられました」と川嶋氏は満面の笑みで語る。
ちなみに、ショールーム向けの提案では工務店やインテリアデザイナー、音楽フェス向け提案ではイベント運営会社とコラボするなど、ITソリューションにとどまらない総合提案を心掛けているのも同社らしさの発露。あくまでクライアント目線に立ち、より広い視野で付加価値提案を行う姿勢が、圧倒的なリピート率につながっている。
常駐型・受託型・研究型など、様々なスタイルが許容されるからこそエンジニアが育つ環境がある。
受託案件で技術を磨き、提案案件で発想を広げて、よりレベルアップした技術力で大規模開発のプロジェクトを率いる。そんな重層的なキャリアメイキングも、同社ならではのステップアップルートと言えるだろう。その生きた事例が、河嶋氏だ。
「シールドマシンのメーカーやロボットメーカー、カード会社やアミューズメント企業など、さまざまな業種で常駐経験を積みました。個人的には、常駐の面白さは技術営業的な事業開拓にあると思いますね。開発実績に比例して業務知識が蓄積されるので、クライアントの課題が手に取るようにわかる。そこに提案をぶつけ、受託領域を広げるうちにメンバーも増える。この充実感はクセになりますよ。一方、提案案件の醍醐味は、やはりエンジニアとしての達成感。常に“こうすればもっと面白くなる”という発想で開発に臨んでいます」。と河嶋氏は実感を込めて語る。
毎月実施される全体会議には、客先に常駐するエンジニアも含めて全メンバーが参加。事例発表会や技術レビュー、バーベキューなど、硬軟取り混ぜたプログラムでモチベーション強化につなげている。最近ではチームビルディングを意図した「マシュマロチャレンジ」というゲームに全員で取り組み、楽しみながらチームワークを深めたこともあったという。
「客先常駐型、持ち帰りの受託開発型、研究ベースの技術提案型と、業務スタイルはさまざまですが、エンジニアの一体感は強いですよ」と魚住氏は強調する。
大人数で取り組む大規模な業務系システムもあれば、ゼロからニーズを創造する提案案件も。服装の縛りはないが、客先に失礼にならない範囲という注釈がつく。固すぎず緩すぎず、安心感と挑戦マインドが無理なく同居する同社の開発環境が、エンジニアにとってあらゆる意味でバランスの取れた居心地良さを生んでいる。
同社には同規模の他社同様に充実した資格取得奨励制度があるが、簿記検定の受験者が目立つあたりにも、同社のエンジニアが自然と身に付けている絶妙のバランス感覚がうかがえる。
中長期的には、スマートフォンアプリの開発体制を強化しながら全体の底上げを図り、総合力の強化を目指す同社。当面はスマートフォンアプリエンジニアや、サーバーサイドとフロントエンドの両面を担うWEBアプリケーションエンジニアの拡充が急務だが、同社の多彩な開発現場には、ITの世界で培ったあらゆるスキルを存分に活かす場がきっとある。前向きな成長意欲を自覚しつつ、長い目でキャリア形成を図りたいエンジニアには、ありそうでいて実際にはなかなかない、確かなチャンスと言えるだろう。
「シールドマシンのメーカーやロボットメーカー、カード会社やアミューズメント企業など、さまざまな業種で常駐経験を積みました。個人的には、常駐の面白さは技術営業的な事業開拓にあると思いますね。開発実績に比例して業務知識が蓄積されるので、クライアントの課題が手に取るようにわかる。そこに提案をぶつけ、受託領域を広げるうちにメンバーも増える。この充実感はクセになりますよ。一方、提案案件の醍醐味は、やはりエンジニアとしての達成感。常に“こうすればもっと面白くなる”という発想で開発に臨んでいます」。と河嶋氏は実感を込めて語る。
毎月実施される全体会議には、客先に常駐するエンジニアも含めて全メンバーが参加。事例発表会や技術レビュー、バーベキューなど、硬軟取り混ぜたプログラムでモチベーション強化につなげている。最近ではチームビルディングを意図した「マシュマロチャレンジ」というゲームに全員で取り組み、楽しみながらチームワークを深めたこともあったという。
「客先常駐型、持ち帰りの受託開発型、研究ベースの技術提案型と、業務スタイルはさまざまですが、エンジニアの一体感は強いですよ」と魚住氏は強調する。
大人数で取り組む大規模な業務系システムもあれば、ゼロからニーズを創造する提案案件も。服装の縛りはないが、客先に失礼にならない範囲という注釈がつく。固すぎず緩すぎず、安心感と挑戦マインドが無理なく同居する同社の開発環境が、エンジニアにとってあらゆる意味でバランスの取れた居心地良さを生んでいる。
同社には同規模の他社同様に充実した資格取得奨励制度があるが、簿記検定の受験者が目立つあたりにも、同社のエンジニアが自然と身に付けている絶妙のバランス感覚がうかがえる。
中長期的には、スマートフォンアプリの開発体制を強化しながら全体の底上げを図り、総合力の強化を目指す同社。当面はスマートフォンアプリエンジニアや、サーバーサイドとフロントエンドの両面を担うWEBアプリケーションエンジニアの拡充が急務だが、同社の多彩な開発現場には、ITの世界で培ったあらゆるスキルを存分に活かす場がきっとある。前向きな成長意欲を自覚しつつ、長い目でキャリア形成を図りたいエンジニアには、ありそうでいて実際にはなかなかない、確かなチャンスと言えるだろう。
企業情報
会社名
株式会社ウイズ
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
資本金
5000万円
設立年月
1996年01月
代表者氏名
代表取締役 澤田 稔
事業内容
■企業ブランディングに関するコンサルティング業務
■商品、サービスの販売促進に関するコンサルティング業務
■広告代理店業務
■デジタルマーケティング業務
■コンピュータシステムに関するコンサルティング業務
■コンピュータシステムのインテグレーション業務
■コンピュータシステムの開発業務
■OA関連システムの開発、販売、運用及び保守業務
■開発支援システムの開発、販売、運用及び保守業務
■ネットワークシステム(LAN,WAN)の開発、販売、運用及び保守業務
■コンピュータハードウェア/ソフトウェアの仕入販売及び設置導入業務
■労働者派遣事業
株式公開(証券取引所)
従業員数
106人
本社住所
大阪府大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル6階
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社ウイズの中途採用/求人/転職情報