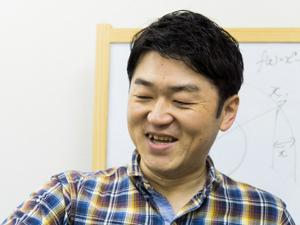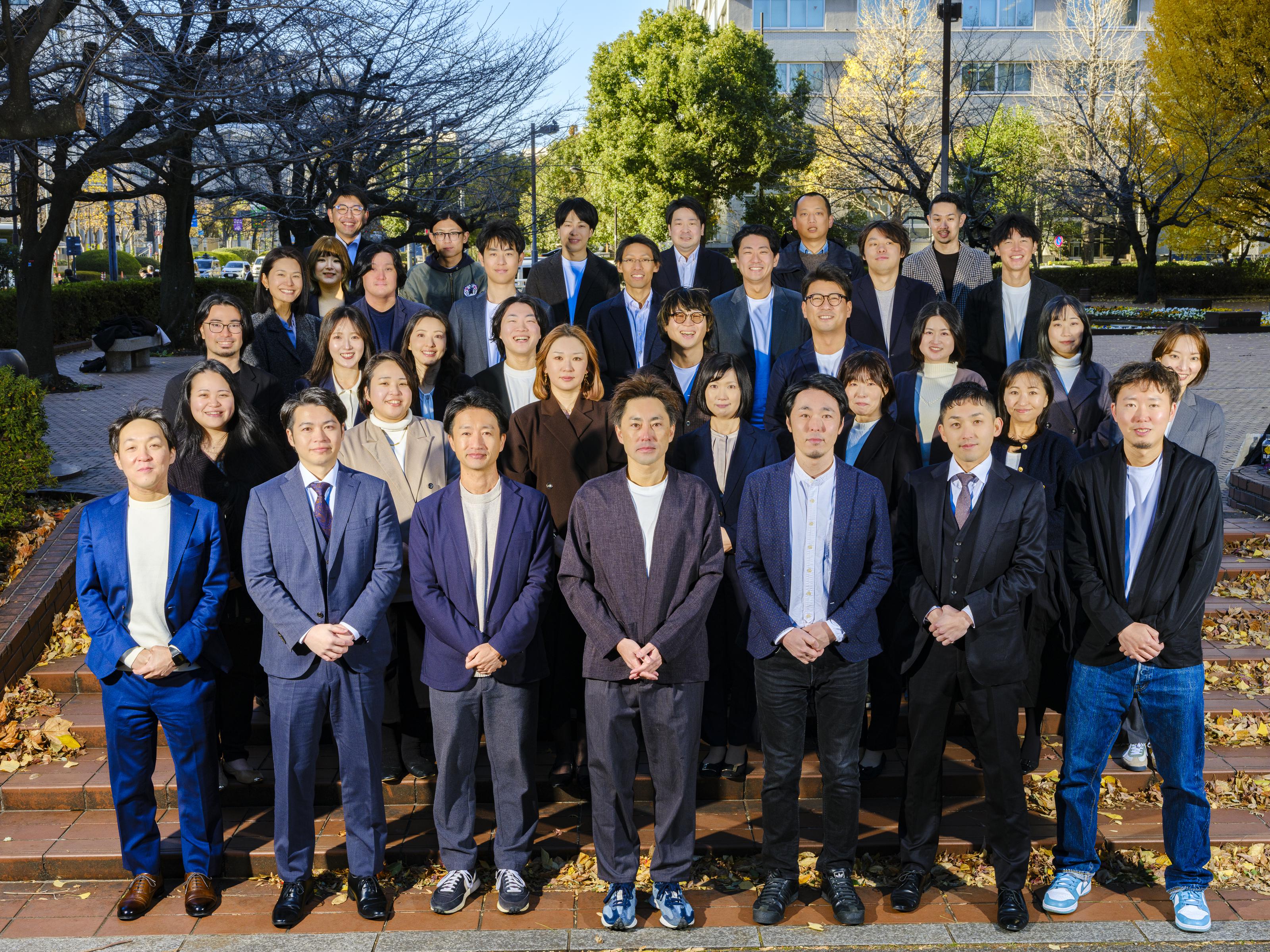クーガー株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
LUDENSによる「あらゆる人に寄り添い、支援する人型AI」を、全世界へ展開します。
自社サービス製品あり
残業少なめ
カジュアル面談歓迎
企業について
ファミリーマートに人型AI「レイチェル」を提供:2023年度末までに5,000店舗に導入
伊藤忠商事との資本業務提携により進めてきた人型AI「レイチェル」はファミリーマート国内全店の半数近くにあたる約7,000店に導入されております。人型AIプラットフォーム「LUDENS」を構成する画像認識は視覚、音声認識は聴覚となり、ゲームAIは人間のような性格や個性となります。我々は「あらゆる人に寄り添い、支援する人型A」を全世界に展開することを目指しています。
機械学習、脳科学、ゲームAIで世界トップクラスのエンジニアや研究者が集まっています
・IEEEやFacebook主催の画像認識コンペティションで世界トップ3に入るAIリサーチャー
・京都大学院卒業後、クーガーに入社。現在は東京大学博士課程に在籍しつつ自然言語処理プロダクトを開発するエンジニア
・楽天やメルカリで大規模検索エンジンの開発に携わってきた検索・自然言語処理エンジニア
・Final Fantasyシリーズの開発メンバー
・PlayStation Networkのシステム設計・研究に関わったエンジニア
・イーサリアム財団認定のオープンソースソフトウェアを開発しているブロックチェーンエンジニア
・京都大学院卒業後、クーガーに入社。現在は東京大学博士課程に在籍しつつ自然言語処理プロダクトを開発するエンジニア
・楽天やメルカリで大規模検索エンジンの開発に携わってきた検索・自然言語処理エンジニア
・Final Fantasyシリーズの開発メンバー
・PlayStation Networkのシステム設計・研究に関わったエンジニア
・イーサリアム財団認定のオープンソースソフトウェアを開発しているブロックチェーンエンジニア
自律的で大胆なチャレンジを支援し、個性を生かした技術と創造性を追求
理想のプロダクトを実現するため、各担当者の得意分野や個性、思考を最大限に生かして業務を進めています。
チームは高いスキルや実績を持つ一方、皆穏やかで親切。仕事に対しては妥協を許さず真剣に取り組む職人気質なチームです。また、外国人や育児真っ最中のパパやママ、博士課程の大学院生など様々な環境のメンバーがおり、個々の事情を考慮した柔軟な働き方が認められています。
ぜひ、私たちと一緒に挑戦しましょう。ご応募、心よりお待ちしています。
チームは高いスキルや実績を持つ一方、皆穏やかで親切。仕事に対しては妥協を許さず真剣に取り組む職人気質なチームです。また、外国人や育児真っ最中のパパやママ、博士課程の大学院生など様々な環境のメンバーがおり、個々の事情を考慮した柔軟な働き方が認められています。
ぜひ、私たちと一緒に挑戦しましょう。ご応募、心よりお待ちしています。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(8件)
すべて見る
PR
すべて見るインタビュー

── まず、略歴についてお教えください。
学生時代は機械工学専攻で、自動車エンジンの設計などを行いました。卒業後は発電所の制御システム用ソフトウェアを手がける会社に就職し、発電所全体を制御するシステムの最適化や設計などを行なっていました。発電機を回転させるボイラーの蒸気温度などを秒単位で制御するわけですが、基準温度に収まらないと爆発などの大事故にもつながる仕事です。つまり、大変重要な仕事ですが、ほとんど新たなチャレンジができないという特性がありました。そこで、日本アイ・ビー・エムの藤沢事業所に転職しました。製品開発やプロバイダーを行うグループ会社でエンジニアを務め、ITの世界に入っていきました。... 続きを読む
企業情報
会社名
クーガー株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、自社サービス製品あり、残業少なめ設立年月
2006年12月
代表者氏名
代表取締役 CEO 石井 敦
事業内容
伊藤忠商事との資本業務提携により進めてきた人型AIアシスタント「レイチェル」を提供。ファミリーマート国内全店の半数近くにあたる約7,000店に導入されており、店長さんをサポートしています。
人型AIプラットフォーム「LUDENS」を構成する画像認識は視覚、音声認識は聴覚となり、ゲームAIは人間のような性格や個性となります。我々は「人間に寄り添う人型AI」を全世界に展開していくことを目指しています。
株式公開(証券取引所)
従業員数
48人
本社住所
東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル201
この企業と同じ業界の企業
クーガー株式会社
採用担当 辰巳
プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャーを積極採用中です。カジュアル面談もお気軽にご連絡ください。
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- クーガー株式会社の中途採用/求人/転職情報