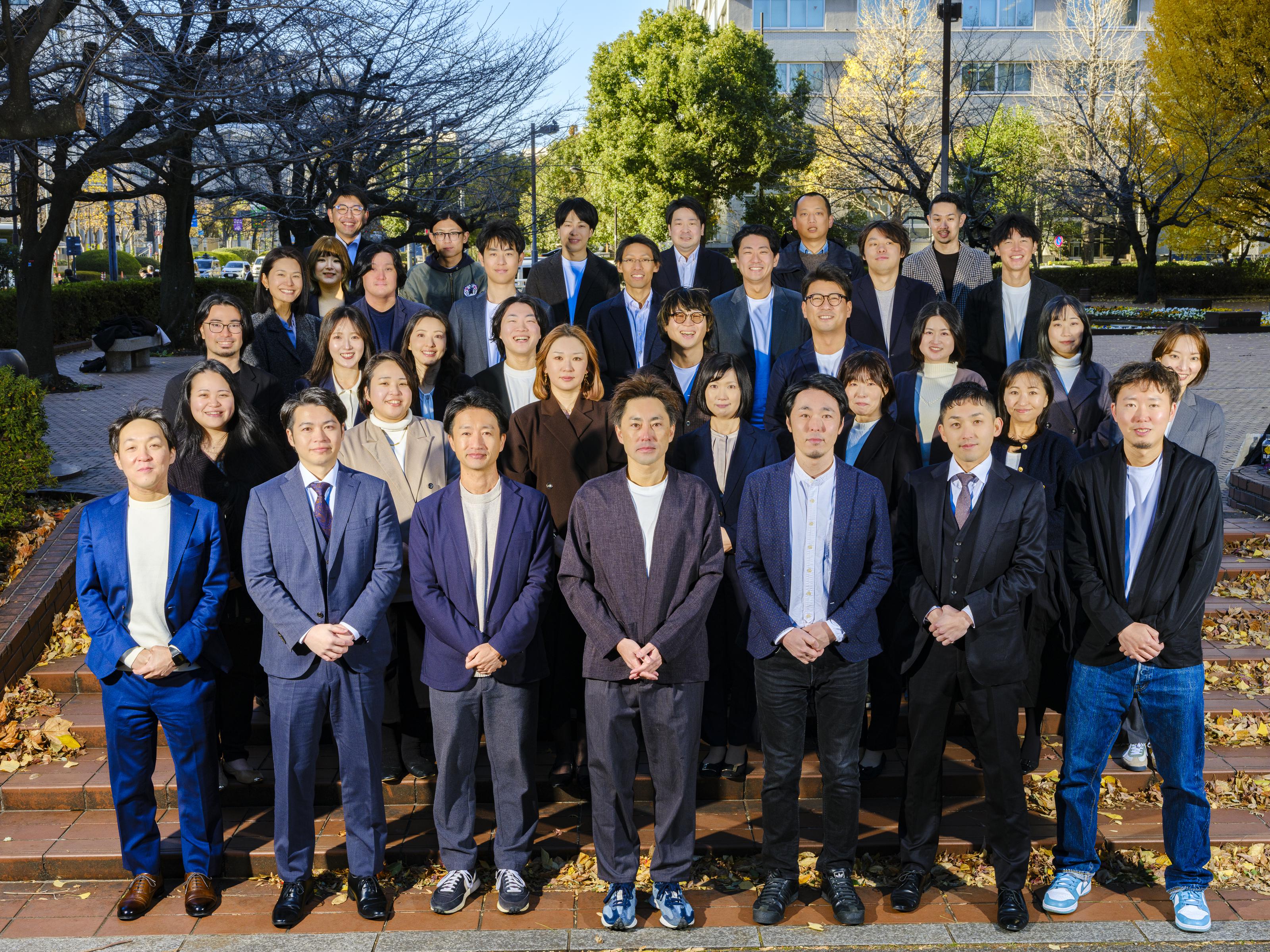株式会社フォトラクション
- IT/Web・通信・インターネット系
まちづくりを支える新たなデジタル産業を拓く
上場を目指す
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
残業少なめ
カジュアル面談歓迎
企業について
400,000を超える建設プロジェクトで使用されている国内最大級のソフトウェア
「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービスPhotoructionの開発を行なっています。
建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。
Photoructionはゼネコンの工事現場をはじめ、専門工事会社、設計事務所など、 400,000件以上の工事現場で利用されている国内最大規模の建設業向けサービスへと進化してきました。
今後も更なる発展を目指して、組織の拡大を実施していきたく様々なポジションで積極的に採用活動を行っております。
建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。
Photoructionはゼネコンの工事現場をはじめ、専門工事会社、設計事務所など、 400,000件以上の工事現場で利用されている国内最大規模の建設業向けサービスへと進化してきました。
今後も更なる発展を目指して、組織の拡大を実施していきたく様々なポジションで積極的に採用活動を行っております。
組織の成長を支えるMission・Vision・Values
わたしたちがフォトラクションで働くにあたり、最も重要視している要素がMission・Vision・Valuesです。
刻々と変化する状況の中でも、本来の目的や「なぜ働くのか」という原点に立ち返ることが、組織の持続的な成長を支える礎となります。
Mission:
建設の世界を限りなくスマートにする
Vision:
まちづくりを支える新たなデジタル産業を拓く
Values:
職務洗練 - Result & Growth
何かを成し遂げるため、あらゆる面で最高のクオリティを保つ努力をします。私たちは現状に決して満足することなく、結果と成長に対する拘りを常に持ち続けます。
最速挙動 - Iteration
より良い結果に辿り着くために、まずは行動してみることが重要です。私たちは1秒でも早く手と足と頭を動かし経験を積み重ね、次なる最善の一手を生み出します。
創始壮快 - Enjoy a Challenge
出来ていないコト、経験したことがないコト、難易度が高いコトへ真摯に向き合います。私たちは挑戦を楽しみ、組織や事業に新たな付加価値を創出していきます。
敬意尊尚 - D&I
私たちは関わる全ての人達に敬意を持って接します。相手の立場に立ち耳を傾け、ステークホルダーにとって、最良の結論を導き出す努力を決して怠りません。
共創共栄 - Collaboration
私たちはプロとしての自覚を持ち、知を結集させます。自分たちの思考や創ったモノやコトを恥じることなく積極的にチームで共有し、共に助け合い成長していきます。
目的逆算 - Efficiency
私たちは目的の解像度を高め自分たちの存在を明確にし、そこから逆算して行動することで壮大なミッションへ効率良く向かっていけるように努めます。
刻々と変化する状況の中でも、本来の目的や「なぜ働くのか」という原点に立ち返ることが、組織の持続的な成長を支える礎となります。
Mission:
建設の世界を限りなくスマートにする
Vision:
まちづくりを支える新たなデジタル産業を拓く
Values:
職務洗練 - Result & Growth
何かを成し遂げるため、あらゆる面で最高のクオリティを保つ努力をします。私たちは現状に決して満足することなく、結果と成長に対する拘りを常に持ち続けます。
最速挙動 - Iteration
より良い結果に辿り着くために、まずは行動してみることが重要です。私たちは1秒でも早く手と足と頭を動かし経験を積み重ね、次なる最善の一手を生み出します。
創始壮快 - Enjoy a Challenge
出来ていないコト、経験したことがないコト、難易度が高いコトへ真摯に向き合います。私たちは挑戦を楽しみ、組織や事業に新たな付加価値を創出していきます。
敬意尊尚 - D&I
私たちは関わる全ての人達に敬意を持って接します。相手の立場に立ち耳を傾け、ステークホルダーにとって、最良の結論を導き出す努力を決して怠りません。
共創共栄 - Collaboration
私たちはプロとしての自覚を持ち、知を結集させます。自分たちの思考や創ったモノやコトを恥じることなく積極的にチームで共有し、共に助け合い成長していきます。
目的逆算 - Efficiency
私たちは目的の解像度を高め自分たちの存在を明確にし、そこから逆算して行動することで壮大なミッションへ効率良く向かっていけるように努めます。
デジタルゼネコンという挑戦 -建設BPaaSとプラットフォームの拡大-
私たちは便利なソフトウェアを提供するだけではなく、建設産業にとって必要不可欠な存在になることを目指しています。
この実現に向けて、AIを活用したBPOサービスをクラウド経由で提供する「BPaaS(Business Process as a Service)」という新しい事業モデルに挑戦しています。
また、昨年だけでも以下のような多くの取り組みを行ってきました:
aoz cloud:
建設業特化のAIソリューション
ARCHITREND ONE:
上場企業である福井コンピュータグループ様との共同事業
スタートアップエコシステムへの貢献:
2024年11月より沖縄県那覇市に新たな開発拠点を設立
デジタル技術を武器に建設業と共に建物を建てていく存在を「デジタルゼネコン」と位置づけ、この大きなビジョンの実現に向けて共に挑戦してくれる仲間を募集しています。
この実現に向けて、AIを活用したBPOサービスをクラウド経由で提供する「BPaaS(Business Process as a Service)」という新しい事業モデルに挑戦しています。
また、昨年だけでも以下のような多くの取り組みを行ってきました:
aoz cloud:
建設業特化のAIソリューション
ARCHITREND ONE:
上場企業である福井コンピュータグループ様との共同事業
スタートアップエコシステムへの貢献:
2024年11月より沖縄県那覇市に新たな開発拠点を設立
デジタル技術を武器に建設業と共に建物を建てていく存在を「デジタルゼネコン」と位置づけ、この大きなビジョンの実現に向けて共に挑戦してくれる仲間を募集しています。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(7件)
営業職の求人(3件)
社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
会社名
株式会社フォトラクション
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場を目指す、自社サービス製品あり、シェアトップクラス、残業少なめ資本金
2,482百万円
設立年月
2016年03月
代表者氏名
中島 貴春
事業内容
「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービスPhotoructionの開発を行なっています。建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。
株式公開(証券取引所)
非上場
従業員数
85人
本社住所
〒141-0031東京都品川区西五反田7-9-5 SGテラス4階 ■アクセス 五反田駅 徒歩6分 大崎広小路駅 徒歩3分
この企業と同じ業界の企業
株式会社フォトラクション
採用担当 藤田
当社は「応募者も会社もハッピーになれる採用」を目指しています。まずはお気軽にお話しください!挑戦と成長を一緒に楽しみましょう。
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社フォトラクションの中途採用/求人/転職情報