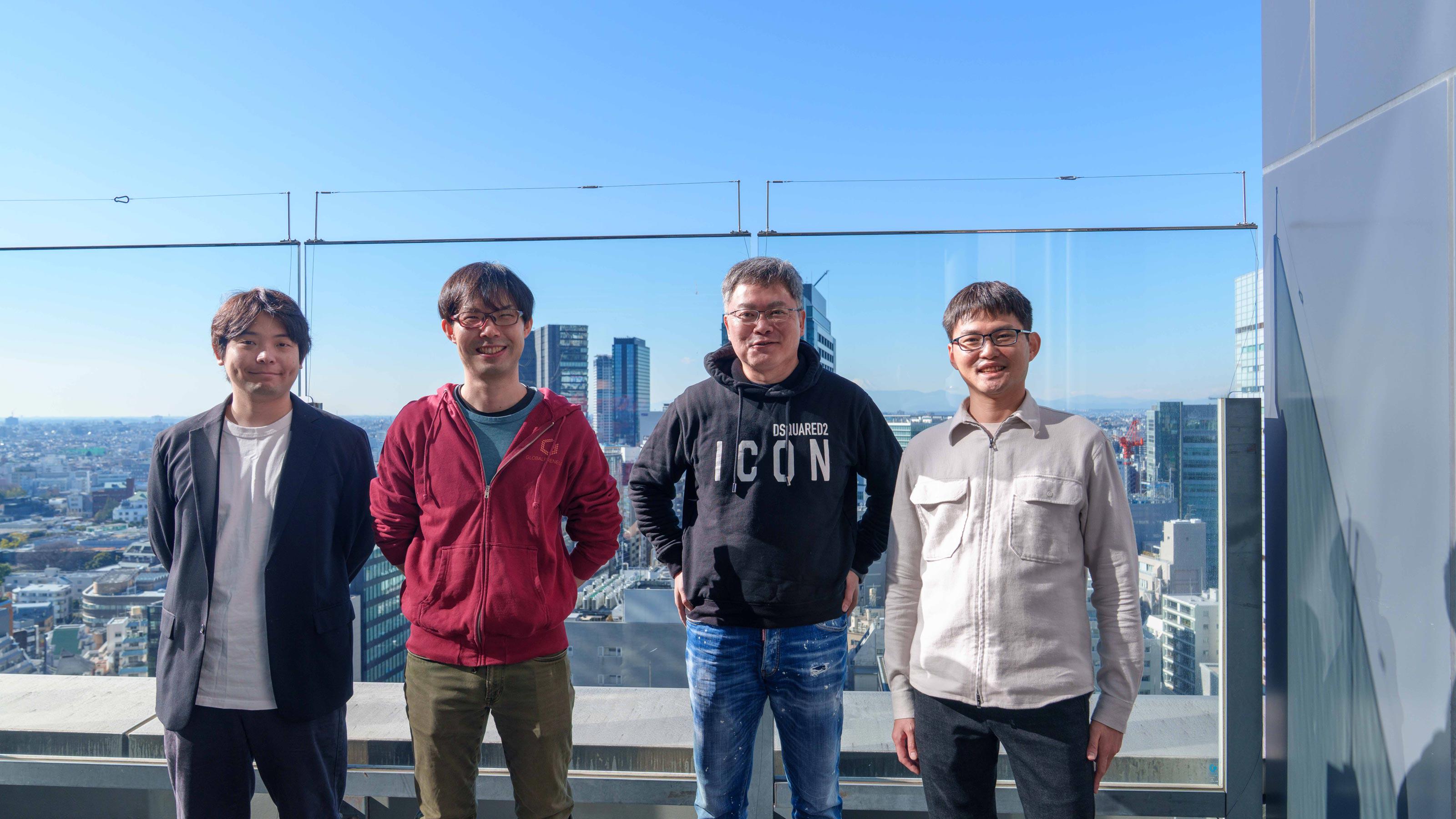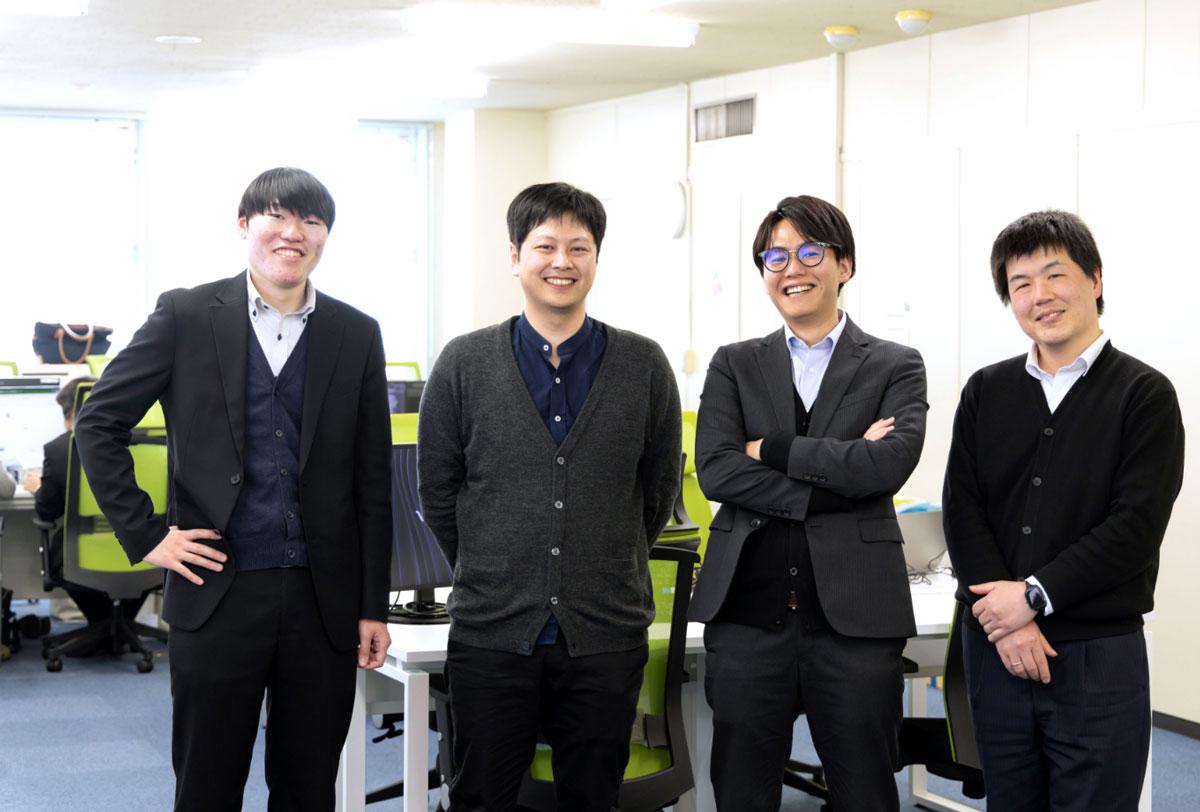株式会社社会情報サービス
- サービス系
- IT/Web・通信・インターネット系
医薬の明日への貢献を目指す医療マーケティングリサーチのパイオニア
自社サービス製品あり
企業について
医療マーケティングリサーチ業界を牽引するリーディングカンパニー
1982年、市場調査事業、コンピュータソフトウェアの開発を主業務として、社会情報サービスは発足した。設立から5年ほど経った1988年、医療分野に特化した調査へとその業務内容を移行していく。
当時、日本には、医療におけるマーケティングリサーチのという市場はほとんど存在しなかった。海外ではすでにスタートしていたこの市場において、日本が後発となった要因は、医療・医薬業界にマーケティングという概念がまだ育っていなかったからだった。しかし、同社はそこに早くから注力し、努力の末、当時困難であった医師や医療の現場への調査に取り組んでいったのだ。こうして、医療分野における調査会社のパイオニアとなり、市場拡大とともに、業績を伸ばしていくこととなる。
医療分野におけるマーケティングリサーチでは、新薬の開発から発売に至るまでの課題が、顧客である製薬会社から提起されることが多い。(多くの場合、顧客は製薬会社製薬会社であり、調査対象は医師である。)
リサーチャーは、医師へのインタビューやアンケート等から情報を集積し、そこに潜むメディカルニーズ等をキャッチする。そして、顧客に調査結果やインサイトを提供する。それらは、新薬開発の方向性やコンセプト、発売におけるキーメッセージを決定するために使用されるのだ。
同社の強みは、あらゆる調査手法を使い分けること。アンケート・インタビュー・インタネットなど、課題に最適な手法を企画し、情報収集することができるのだ。さらに、社員の提案力も重視する。同社には、与えられた課題のみをこなすのではなく、集積したデータを分析し、別の視点から新たな課題を提起することができる人材が育っているのだ。
医療調査には、二つの種類がある。顧客に与えられた課題に沿って、最適な手法を選定し、調査を実施するアドホックリサーチと、自ら収集した情報を基に、潜在的なメディカルニーズを探っていくシンジケートと呼ばれるリサーチだ。同社は、この両方を巧みに使いこなし、医療分野に有益な情報を発信しつづけている。
当時、日本には、医療におけるマーケティングリサーチのという市場はほとんど存在しなかった。海外ではすでにスタートしていたこの市場において、日本が後発となった要因は、医療・医薬業界にマーケティングという概念がまだ育っていなかったからだった。しかし、同社はそこに早くから注力し、努力の末、当時困難であった医師や医療の現場への調査に取り組んでいったのだ。こうして、医療分野における調査会社のパイオニアとなり、市場拡大とともに、業績を伸ばしていくこととなる。
医療分野におけるマーケティングリサーチでは、新薬の開発から発売に至るまでの課題が、顧客である製薬会社から提起されることが多い。(多くの場合、顧客は製薬会社製薬会社であり、調査対象は医師である。)
リサーチャーは、医師へのインタビューやアンケート等から情報を集積し、そこに潜むメディカルニーズ等をキャッチする。そして、顧客に調査結果やインサイトを提供する。それらは、新薬開発の方向性やコンセプト、発売におけるキーメッセージを決定するために使用されるのだ。
同社の強みは、あらゆる調査手法を使い分けること。アンケート・インタビュー・インタネットなど、課題に最適な手法を企画し、情報収集することができるのだ。さらに、社員の提案力も重視する。同社には、与えられた課題のみをこなすのではなく、集積したデータを分析し、別の視点から新たな課題を提起することができる人材が育っているのだ。
医療調査には、二つの種類がある。顧客に与えられた課題に沿って、最適な手法を選定し、調査を実施するアドホックリサーチと、自ら収集した情報を基に、潜在的なメディカルニーズを探っていくシンジケートと呼ばれるリサーチだ。同社は、この両方を巧みに使いこなし、医療分野に有益な情報を発信しつづけている。
事業の鍵を握る「リサーチャー」と「事業推進スタッフ」。
同社には約20名のリサーチャーが在籍している。男女の割合はほぼ同数。20代から50代まで、年齢層も様々だ。
リサーチャーの業務範囲は実に広い。顧客からあがってきた課題に対して、まずは調査内容や調査方法を企画、調査票を作成し、社内の調査専門部署に調査を依頼、時には自分で医師へのインタビューを実施しつつ、情報を収集する。そして、その調査の結果を分析し、企画書を書き、顧客へプレゼンテーションを行う。リサーチャーが担当するのは、アドホック型の調査であることが多いという。
顧客は製薬企業が主であるが、新薬の広告を担う広告代理店とのやりとりを行なうこともある。発売後は、その浸透具合をリサーチし、さらなる浸透に貢献していく。
幅広い業務を行なうリサーチャーに求められる資質とは、こつこつときめ細やかな仕事ができること、人とコミュニケーションをとり相手の考えを引き出す能力、そして、受動的ではなく、能動的に、自ら提言をできることだという。
一方、顧客へのアプローチという面で活躍しているのが、事業推進グループのスタッフである。こちらは、いわゆるシンジケート型の企画を行なっており、まず医療マーケティングに必要となるデータ製品を発案し製品化を主導する。そして、潜在ニーズを抽出し、顧客に提案、アプローチをしていく。
一般企業における営業の役割を担うことになるので、コミュニケーション能力に長けた人が活躍できる職種なのだという。
現在、年間2名から3名ずつ中途社員の採用を行っている同社だが、意外にも、入社する社員の前職は、決して医療関連のみではない。
医療関連企業従事経験よりも、むしろ、「医療に興味があること」「医療の発展に貢献できることに喜びを感じること」の方が素養としては、重要なのだという。
社員が、時間や課題の複雑さからくるプレッシャーに打ち勝つことができるのは、この「医療への思い」を持っているからなのだ。
リサーチャーの業務範囲は実に広い。顧客からあがってきた課題に対して、まずは調査内容や調査方法を企画、調査票を作成し、社内の調査専門部署に調査を依頼、時には自分で医師へのインタビューを実施しつつ、情報を収集する。そして、その調査の結果を分析し、企画書を書き、顧客へプレゼンテーションを行う。リサーチャーが担当するのは、アドホック型の調査であることが多いという。
顧客は製薬企業が主であるが、新薬の広告を担う広告代理店とのやりとりを行なうこともある。発売後は、その浸透具合をリサーチし、さらなる浸透に貢献していく。
幅広い業務を行なうリサーチャーに求められる資質とは、こつこつときめ細やかな仕事ができること、人とコミュニケーションをとり相手の考えを引き出す能力、そして、受動的ではなく、能動的に、自ら提言をできることだという。
一方、顧客へのアプローチという面で活躍しているのが、事業推進グループのスタッフである。こちらは、いわゆるシンジケート型の企画を行なっており、まず医療マーケティングに必要となるデータ製品を発案し製品化を主導する。そして、潜在ニーズを抽出し、顧客に提案、アプローチをしていく。
一般企業における営業の役割を担うことになるので、コミュニケーション能力に長けた人が活躍できる職種なのだという。
現在、年間2名から3名ずつ中途社員の採用を行っている同社だが、意外にも、入社する社員の前職は、決して医療関連のみではない。
医療関連企業従事経験よりも、むしろ、「医療に興味があること」「医療の発展に貢献できることに喜びを感じること」の方が素養としては、重要なのだという。
社員が、時間や課題の複雑さからくるプレッシャーに打ち勝つことができるのは、この「医療への思い」を持っているからなのだ。
成果や成長が適性に評価される評価制度など、独自のスタイルを持つ。
同社は、社員を大切にする会社である。自分で勤務時間をコントロールできるフレックス制を採用し、休日等もしっかりとれる制度を作っていることも、その一つの表れだ。
評価制度においては、自らが立てた目標への達成率はもちろん、実績、職務態度などが考慮される。評価は年2回実施されるが、ここで面白いのが、同社の「参考人制度」だ。
これは、上司以外の、もう一人の評価者を、評価される本人が選択できる、という制度である。
例えば、ある案件を、直属の上司を離れて他部署のメンバーと協力して進めていたとする。そういった場合、直属の上司では見えにくい成果や成長を、他部署の上司が分かっていることがある。そこで、評価される本人が、より自分の成果を見ていてくれた他部署の上司を参考人として指名し、直属の上司と共に自分の評価を行なうように進言できるのだ。
社員に納得感のある、フェアな評価をしようという企業姿勢がこの制度に表れている。
賞与の制度もユニークである。通常年2回の賞与とは別に、会社の業績、部門、そして個人の成績やがんばりを大きく反映させた「期末賞与」が存在する。一人ひとりの成果・成長をしっかり評価してもらえる、ありがたい制度だ。
評価制度においては、自らが立てた目標への達成率はもちろん、実績、職務態度などが考慮される。評価は年2回実施されるが、ここで面白いのが、同社の「参考人制度」だ。
これは、上司以外の、もう一人の評価者を、評価される本人が選択できる、という制度である。
例えば、ある案件を、直属の上司を離れて他部署のメンバーと協力して進めていたとする。そういった場合、直属の上司では見えにくい成果や成長を、他部署の上司が分かっていることがある。そこで、評価される本人が、より自分の成果を見ていてくれた他部署の上司を参考人として指名し、直属の上司と共に自分の評価を行なうように進言できるのだ。
社員に納得感のある、フェアな評価をしようという企業姿勢がこの制度に表れている。
賞与の制度もユニークである。通常年2回の賞与とは別に、会社の業績、部門、そして個人の成績やがんばりを大きく反映させた「期末賞与」が存在する。一人ひとりの成果・成長をしっかり評価してもらえる、ありがたい制度だ。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(1件)
PR
すべて見るインタビュー

── ご自身もリサーチャーとして長く活躍されてきた経験をお持ちですが、リサーチャーの仕事の醍醐味を教えてください。
医療の分野に関らず、マーケットリサーチャーの仕事は、顧客企業を動かす大きな力を持っています。企画内容が、顧客企業のコアな部分、方針等を左右する内容を含んでいますし、情報に基づいた信頼に値するものだからです。プレゼンテーションに、重役が出席することも珍しくありません。
だからこそ、やりがいはありますし、20代から精神的にも鍛えられる仕事だと思いますよ。
また、調査により、新製品における大切なメッセージだと認められた場合などには、開発に影響を与えたり、広告に使用されたり、学会で使用されたりします。そういったシーンに出会うと、やはり感動しますね。
大企業が、若... 続きを読む
企業情報
会社名
株式会社社会情報サービス
業界
サービス系 > その他サービス系
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
企業の特徴
自社サービス製品あり資本金
2700万
設立年月
1982年04月
代表者氏名
代表取締役社長 牧田 孝
事業内容
市場調査・世論調査の企画・実施・分析
市場調査・世論調査データの販売
コンピュータソフトウェアの企画・開発・販売
アンケート・統計データなど各種のコンピュータ入力・集計(データ処理)
インターネットサーバーのホスティング、ホームページの企画・製作・運営
データベースの作成・販売
マーケティング・コンサルティング
株式公開(証券取引所)
従業員数
137人
平均年齢
38歳
本社住所
東京都 新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社社会情報サービスに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- サービス系
- その他サービス系
- 株式会社社会情報サービスの中途採用/求人/転職情報