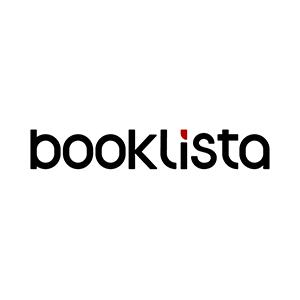
株式会社ブックリスタ
- IT/Web・通信・インターネット系
- マスコミ・エンターテイメント・メディア系
電子書籍/WEBTOON/新規事業|アジャイル開発で世の中に「感動」を創出する「エンタメ×テック(知的好奇心×感動体験)」カンパニー
企業について
【電子書籍ストア】
当社では、「auブックパス」「Reader Store」「コミックROLLY」など、電子書籍ストアと包括的なパートナーシップを結んでいます。ストアシステムや配信プラットフォームの提供はもとより、ストア内における企画の立案・実施、作品の特長に応じたストア編成などを行っています。ユーザー特性の分析では、カスタマーサポートから得る「ユーザーの声」を活かして読書傾向などを分析し、戦略的なアプローチでストアをバックアップ。ユーザー応募型のリアルイベントを開催するなど、多角的なプロモーションを行っています。
【コンテンツ制作スタジオ「booklistaSTUDIO」】
「booklistaSTUDIO」は、通称webtoonともいわれる「タテ読みコミック」などのオリジナルコンテンツを制作・プロデュースするコンテンツ制作スタジオです。webtoon編集部としては国内初となるwebマンガ誌「booklistaSTUDIOweb」の運営、マンガ賞の開催など、さまざまな取り組みをおこなっています
【新規事業】
「エンタメ×テック(知的好奇心×感動体験)」のビジョンのもと、電子書籍事業の枠にとらわれない新規事業の創造に取り組んでいます。ユーザー目線を意識した新しい価値を探し、ワクワクする新しい体験をエンジニアリングで実現し、未来の企業成長に繋げていきます。
全ビジネスファンクションの強化を行う中、日々刻々と変化する市場にアジャイル・スクラムといったスタイルで対応し、各メンバーがプロ意識を持って取り組んでいます。
本で培ってきたさまざまな知見を活かし、あらゆるエンタテインメントに対象を広げ、デジタルテクノロジーを駆使しながら、新しい価値の創出を実現していきます。
【行動指針】
『自由を楽しもう』
自分たちのちからを十分に発揮するために自由であろう。
固定概念にとらわれることなく、ゼロベースで考え、行動しよう。
そして、互いに自由であることを尊重しよう。
『挑戦を楽しもう』
挑戦することは、常に私たちをワクワクさせてくれる。
自らを乗り越え、暗闇の荒野に進むべき道を切り拓こう。
これまで取り組んでいないこと、困難に思える壁にも、臆さず大胆に挑戦しよう。
失敗しても学び、次の一歩をより確かなものとしていこう。
『違うことを楽しもう』
一人ひとりの価値観、考え方、能力を互いに認めあい、尊重しよう。
同調ではなく、協調によって高めあうことで、大きな力を発揮していこう。
『責任を楽しもう』
責任を持ってやり抜くことで、仕事での満足感や達成感を得ることができる。
一人のプロフェッショナルとして、自分の役割を理解し、目に見える形になるまで力を尽くそう。
『お客さまと楽しもう』
本に綴じられた様々な物語や知見、感動をお客さまに届け、喜んでもらえることを常に意識しよう。お客さまの信頼に応え、共に楽しもう。
ブックリスタでは、カルチャーマッチをとても大切にしています。面接だけではどうしても分からない社風を、可能な限りお伝えします。結果として、入社半年以内のアンケートで、入社後のギャップがあったという回答は、5%未満になっています。
研修や資格補助などを通して、メンバー一人ひとりのスキルアップや成長を積極的にバックアップしています。また、エンジニアは独自の評価制度もありますので、上司と一緒に目指すキャリアパスを実現していただくことができます。入社後のミスマッチが少なく、メンバーが働きやすい環境づくりを目指して、更なる制度や環境の充実をはかっていきたいと考えていますので、ぜひご応募お待ちしています。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(3件)
PR
すべて見るインタビュー
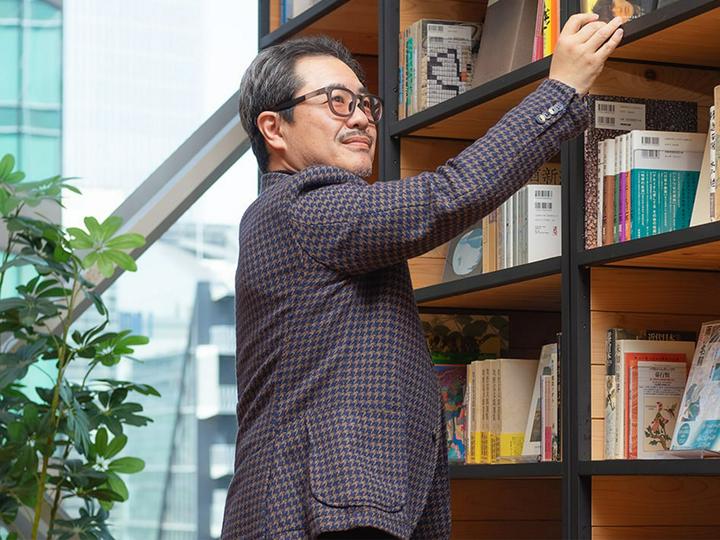
── ──これまでの社長のキャリアを教えてください。
私のキャリアは出版社(CBS・ソニー出版社:現ソニー・ミュージックエンタテインメント社のグループ会社)からスタートして、新卒で入社し、長く編集者をしていました。書籍やコミックをたくさん作って来ましたが、特に雑誌の編集歴が長いですね。雑誌というメディアは、0から1の構築ではなく「1を大きくすること」で、世の中の役に立つ新しい形での情報提供、トレンドに対して独自の意見を出していく展開、言い換えるなら情報提供者と社会を繋ぐことを行なってきました。他にも、”ソニープラザ”や”ヴァージン・メガストアーズ”などのフリーペーパー(店頭雑誌)を制作していました。業界のビ... 続きを読む
社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
株式会社ブックリスタ
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
マスコミ・エンターテイメント・メディア系 > 出版・新聞・雑誌
8億9000万円(資本準備金含む)
2010年07月
村田茂
当社は、電子書籍に関する各種事業を展開し、電子書籍ストアの総合的な運営のサポートをしています。同時に「エンタメ×テック(知的好奇心×感動体験)」のビジョンのもと、既存事業の枠にとらわれない新規事業の創造に取り組んでいます。
【電子書籍ストア】
当社では、「auブックパス」「Reader Store」「コミックROLLY」など、電子書籍ストアと包括的なパートナーシップを結んでいます。ストアシステムや配信プラットフォームの提供はもとより、ストア内における企画の立案・実施、作品の特長に応じたストア編成などを行っています。ユーザー特性の分析では、カスタマーサポートから得る「ユーザーの声」を活かして読書傾向などを分析し、戦略的なアプローチでストアをバックアップ。ユーザー応募型のリアルイベントを開催するなど、多角的なプロモーションを行っています。
【コンテンツ制作スタジオ「booklistaSTUDIO」】
「booklistaSTUDIO」は、通称webtoonともいわれる「タテ読みコミック」などのオリジナルコンテンツを制作・プロデュースするコンテンツ制作スタジオです。webtoon編集部としては国内初となるwebマンガ誌「booklistaSTUDIOweb」の運営、マンガ賞の開催など、さまざまな取り組みをおこなっています
【新規事業】
「エンタメ×テック(知的好奇心×感動体験)」のビジョンのもと、電子書籍事業の枠にとらわれない新規事業の創造に取り組んでいます。ユーザー目線を意識した新しい価値を探し、ワクワクする新しい体験をエンジニアリングで実現し、未来の企業成長に繋げていきます。
非上場
130人
〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-27 SKIビル4F
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社ブックリスタの中途採用/求人/転職情報



























