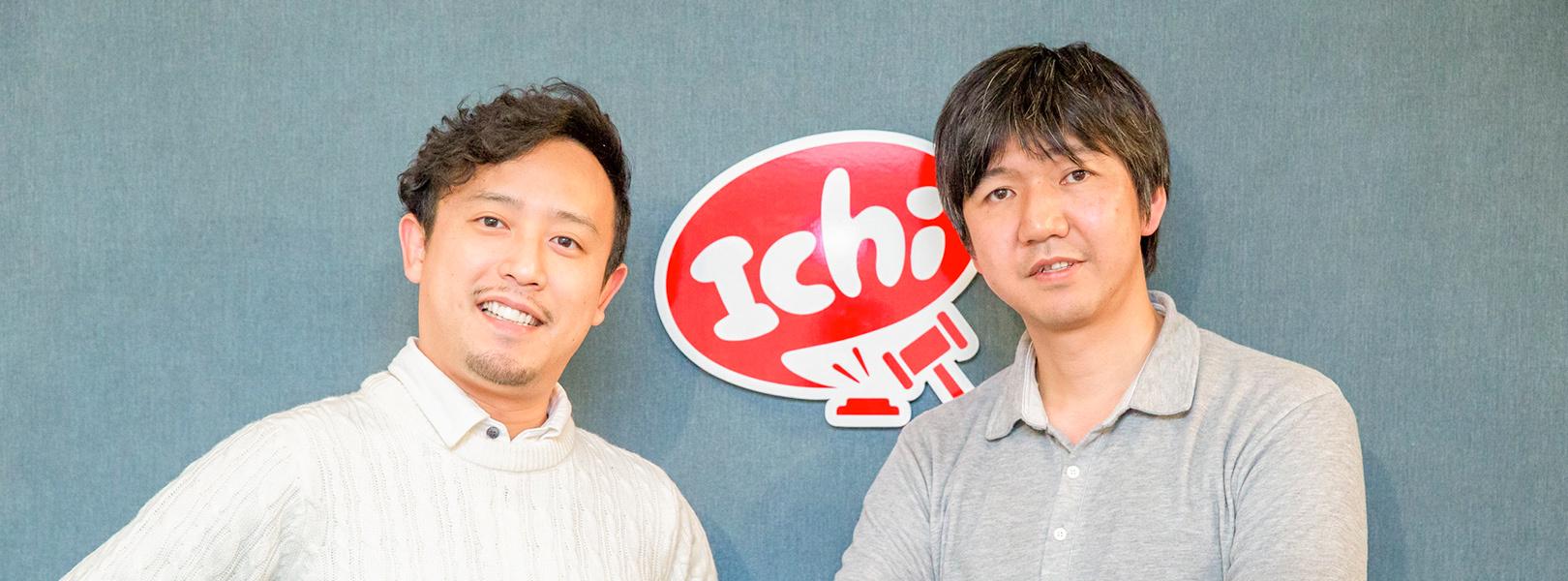Ichi株式会社
- IT/Web・通信・インターネット系
Webシステム開発を通して、ミャンマー人の生活を、便利で豊かなものにする。
上場を目指す
自社サービス製品あり
グローバルに活動
残業少なめ
企業について
ITでモノやサービスをシームレスに繋ぎ、ミャンマーの不便を解消したい
ミャンマー向けにWebシステム開発を行うベンチャー企業、Ichi(イチ)株式会社。同社は2019年に、配送会社比較サイト『PoPoPoh』(ポーポーポー)をリリース。ミャンマー国内のエンドユーザー(法人・個人)が荷物を送る時に、集荷地と配達地をプルダウンで選ぶと、配送会社各社の料金一覧が表示される。エンドユーザーは、最もリーズナブルな料金を提示している配送会社に荷物を依頼する。その一連のプロセスをサポートするサイトだ。“Po”はミャンマーの言葉で“送る”という意味。一緒に働くミャンマー人のエンジニア達が、意味と響きの面白さから命名したそうだ。さらに同社は現在、同じくミャンマー向けにCtoCオークションサイト『Ichi』の開発を進めている。こちらは2020年初頭リリース予定だ。
代表取締役の市村幸士氏は、2007年、長野県上田市で会社を立ち上げる。廃車を仕入れて解体し、部品をリサイクル販売する会社だ。2016年、市村氏は販売先を海外に広げるために、様々な国を回っていた。その一環でミャンマーを訪れた時、現地のアナログな販売方法に驚かされたと語る。
「一言で言えば“露天商”です。部品毎に店があり、その店が集まり、車のリサイクル部品だけで一つの市場を形成しているのです。どの店で何が売っているか、その店はどこに行けば見つかるか、といった情報は全部口コミ。車の部品に限らず、商品をサイトに載せる・探す・売買できるというプラットフォームがあれば、この国の人達の暮らしもビジネスも、もっと便利になるのに…と感じました」(市村氏)。
一方、スマートフォンの普及率はほぼ100%で、この数字は日本よりも高い。実は市村氏がミャンマーを訪れる前、同国に対するアメリカの経済制裁が解除されていた。ビジネスチャンスと捉えた中国をはじめとする各国外資系企業が一気に参入。あっという間にスマートフォンが普及したことが、上記の数字の背景にある。
日頃スマートフォンを使う生活を送っているのであれば、ネットへの抵抗感はないはず。この素地を活かして、ネット上で商品を売り買いできる新しいプラットフォームを作ったら面白いのではないか。市村氏はそう考えた。同時に、現在同社が掲げる“IT, leading Myanmar into the future”(ITでモノやサービスをシームレスにつなぎ、ミャンマーの不便を解消したい)というビジョンも浮かび上がってきたという。
しかし冒頭で触れたように、先行リリースしたのは配送会社比較サイト『PoPoPoh』の方である。これは何故だろうか。
代表取締役の市村幸士氏は、2007年、長野県上田市で会社を立ち上げる。廃車を仕入れて解体し、部品をリサイクル販売する会社だ。2016年、市村氏は販売先を海外に広げるために、様々な国を回っていた。その一環でミャンマーを訪れた時、現地のアナログな販売方法に驚かされたと語る。
「一言で言えば“露天商”です。部品毎に店があり、その店が集まり、車のリサイクル部品だけで一つの市場を形成しているのです。どの店で何が売っているか、その店はどこに行けば見つかるか、といった情報は全部口コミ。車の部品に限らず、商品をサイトに載せる・探す・売買できるというプラットフォームがあれば、この国の人達の暮らしもビジネスも、もっと便利になるのに…と感じました」(市村氏)。
一方、スマートフォンの普及率はほぼ100%で、この数字は日本よりも高い。実は市村氏がミャンマーを訪れる前、同国に対するアメリカの経済制裁が解除されていた。ビジネスチャンスと捉えた中国をはじめとする各国外資系企業が一気に参入。あっという間にスマートフォンが普及したことが、上記の数字の背景にある。
日頃スマートフォンを使う生活を送っているのであれば、ネットへの抵抗感はないはず。この素地を活かして、ネット上で商品を売り買いできる新しいプラットフォームを作ったら面白いのではないか。市村氏はそう考えた。同時に、現在同社が掲げる“IT, leading Myanmar into the future”(ITでモノやサービスをシームレスにつなぎ、ミャンマーの不便を解消したい)というビジョンも浮かび上がってきたという。
しかし冒頭で触れたように、先行リリースしたのは配送会社比較サイト『PoPoPoh』の方である。これは何故だろうか。
GO言語、VUEベースのSPA/PWAでの開発を選択した理由
売買ができる決済プラットフォームは、単体で存在しても魅力的なサービスとは言えない。配送プラットフォームとの連携を果たして初めて、エンドユーザーを惹きつける存在となるのだ。また、配送が未整備のまま決済だけを可能にしてしまうと、個人間の売買リテラシーが確立されていないミャンマーでは、「送らない」「届かない」「受け取らない」「払わない」等のトラブルが発生しかねないという。それではプラットフォームの利用そのものを妨げかねない。そこで市村氏は配送環境にテコ入れするため、まず配送会社比較サイト『PoPoPoh』を先行リリースしたのだ。
ミャンマーには中小20社の配送会社が乱立。エンドユーザーは「料金はいくらかかるか」「どこに頼めばお得か」が掴みにくい状況だった。そこで、各社で提示している料金表を取りまとめ、『PoPoPoh』ですぐに把握できるようにした。ただ、比較サイトという概念がすぐには理解できない、そもそもHPすら持っていない、という会社も多い。そこで、現地スタッフがねばり強く交渉を重ね、徐々に提携先を開拓。『PoPoPoh』を見たエンドユーザーが、サイトから直接各社に依頼できる環境を整備している真っ最中だという。
その進捗を見据えつつ、1年以上前から急ピッチで開発を進めているのが、CtoCオークションサイト『Ichi』である。GO言語、VUEベースのSPA/PWAでの開発を選択した理由について、市村氏はこう語る。
「ミャンマー人は、ネットに対する抵抗感はありません。が、スマートフォンのリテラシーは決して高くないのです。アプリの入れ方が分からないため、ショップに行ってダウンロードを依頼するような状況ですから。中には“アプリは最初から全てスマートフォンに入っているもの”と思い込んでいる人もいます。ならばネイティブアプリではなく、ワンクリックで操作できるWebアプリで行こう、と。そこでPWAでの開発を選択したのです」(市村氏)。
様々な場面で“リテラシーの低さ”と向き合わざるを得ない状況だ。しかし、毎年7%の経済成長率を誇るミャンマーというマーケットの伸びシロを考えれば、市村氏にとって大した問題ではないようだ。
「2030年には、ミャンマー全域に電気等の生活インフラが整備される予定です。同じタイミングで、中国のインド洋方面における一帯一路政策が完成する、と言われています。中国〜ベトナム〜タイ〜ミャンマー〜インドのルートが繋がるまで、あと10年しかありません。できれば5年以内に、マーケットで『Ichi』と『PoPoPoh』のポジションを確立しなければと考えています。立ち止まって悩んでいるヒマは、ないのです」(市村氏)。
ミャンマーには中小20社の配送会社が乱立。エンドユーザーは「料金はいくらかかるか」「どこに頼めばお得か」が掴みにくい状況だった。そこで、各社で提示している料金表を取りまとめ、『PoPoPoh』ですぐに把握できるようにした。ただ、比較サイトという概念がすぐには理解できない、そもそもHPすら持っていない、という会社も多い。そこで、現地スタッフがねばり強く交渉を重ね、徐々に提携先を開拓。『PoPoPoh』を見たエンドユーザーが、サイトから直接各社に依頼できる環境を整備している真っ最中だという。
その進捗を見据えつつ、1年以上前から急ピッチで開発を進めているのが、CtoCオークションサイト『Ichi』である。GO言語、VUEベースのSPA/PWAでの開発を選択した理由について、市村氏はこう語る。
「ミャンマー人は、ネットに対する抵抗感はありません。が、スマートフォンのリテラシーは決して高くないのです。アプリの入れ方が分からないため、ショップに行ってダウンロードを依頼するような状況ですから。中には“アプリは最初から全てスマートフォンに入っているもの”と思い込んでいる人もいます。ならばネイティブアプリではなく、ワンクリックで操作できるWebアプリで行こう、と。そこでPWAでの開発を選択したのです」(市村氏)。
様々な場面で“リテラシーの低さ”と向き合わざるを得ない状況だ。しかし、毎年7%の経済成長率を誇るミャンマーというマーケットの伸びシロを考えれば、市村氏にとって大した問題ではないようだ。
「2030年には、ミャンマー全域に電気等の生活インフラが整備される予定です。同じタイミングで、中国のインド洋方面における一帯一路政策が完成する、と言われています。中国〜ベトナム〜タイ〜ミャンマー〜インドのルートが繋がるまで、あと10年しかありません。できれば5年以内に、マーケットで『Ichi』と『PoPoPoh』のポジションを確立しなければと考えています。立ち止まって悩んでいるヒマは、ないのです」(市村氏)。
ミャンマー人エンジニアの育成経験は、エンジニアとしての市場価値向上に繋がる
現在、東京本社は6人で運営している。代表取締役の市村氏、CTOの加藤明生氏、日本人エンジニア1名、ミャンマー人エンジニア3名で開発を行っている。ミャンマーのサポートセンターには4名で日本人支店長を中心としたマーケティング活動を行っている。
CTOの加藤明生氏は、小学1年の時に、円周率を1,000桁まで計算するような“こだわり”の強いエンジニアだ。2008年には、経済産業省がIPA(独立行政法人情報処理推進機構)を通じて行う未踏事業(未踏IT人材発掘・育成事業)に応募。Xorgのネットワーク機能とJavaScript、HTML5を活用することでWebブラウザ上にウィンドウマネージャを構築し、デスクトップのネイティブアプリを稼働させることを目指す“Web接続型ウィンドウマネージャの開発”が採択された。
そんな加藤氏は、さらに面白いシーズ(種)を探しつつ、自分の知見を後輩エンジニアに伝える機会もほしいと考えるようになっていた。そこに『Ichi』の話を持ってきたのが市村氏である。加藤氏はじっくり話を聞いた上で、参加を決意した。
スーパーエンジニアとも言える加藤氏にとって、新たな課題はミャンマー人エンジニアの育成である。
「ミャンマー人は勤勉で記憶力が良いので、学んだことはしっかり覚える。目上の人からの指示は確実に遂行してくれます。その特性は是非とも活かしてほしいです。一方で当社は、ミャンマー人向けのプラットフォームを開発していますから、ミャンマー人ならではの視点が欠かせません。“もっとこうしてみよう”“ミャンマー人にはこうした方が受けますよ”等、応用を利かせた意見がほしい場面もたくさんあります。そんな応用力、発信力を磨いてあげるために、教える側の私達も成長していかなければなりません」(加藤氏)。
加藤氏が語る“教える側の成長”は、エンジニアにとって、開発経験とは異なった特殊なスキルを実装するチャンスではないだろうか。日本国内では少子高齢化・人口減少が進む現在、外国籍のエンジニアを育成するスキルは今後、多方面で求められるはず。加藤氏ほどのエンジニアが苦心しているのだから、決して簡単なことではないが、コーチングスキルが実装されれば、エンジニアとしての市場価値は高い。
現在、2人のミャンマー人エンジニアは現地の日本語学校で6ヶ月かけて日本語を学んでいる。そして2020年2月に来日し、日本のオフィスで本格的な開発実務に携わりながら、さらにスキルを習得していく予定だ。2人をしっかり育て、ミャンマーの人達の役に立つプラットフォームをリリースすることが、同社の当面の目標である。
「そのプラットフォームを浸透させて、ミャンマーのITインフラに貢献したいですね。そしてミャンマーの人達の生活を、より便利に、より豊かなものにしたいと考えています。それが当社のビジョンですから」(市村氏)。
CTOの加藤明生氏は、小学1年の時に、円周率を1,000桁まで計算するような“こだわり”の強いエンジニアだ。2008年には、経済産業省がIPA(独立行政法人情報処理推進機構)を通じて行う未踏事業(未踏IT人材発掘・育成事業)に応募。Xorgのネットワーク機能とJavaScript、HTML5を活用することでWebブラウザ上にウィンドウマネージャを構築し、デスクトップのネイティブアプリを稼働させることを目指す“Web接続型ウィンドウマネージャの開発”が採択された。
そんな加藤氏は、さらに面白いシーズ(種)を探しつつ、自分の知見を後輩エンジニアに伝える機会もほしいと考えるようになっていた。そこに『Ichi』の話を持ってきたのが市村氏である。加藤氏はじっくり話を聞いた上で、参加を決意した。
スーパーエンジニアとも言える加藤氏にとって、新たな課題はミャンマー人エンジニアの育成である。
「ミャンマー人は勤勉で記憶力が良いので、学んだことはしっかり覚える。目上の人からの指示は確実に遂行してくれます。その特性は是非とも活かしてほしいです。一方で当社は、ミャンマー人向けのプラットフォームを開発していますから、ミャンマー人ならではの視点が欠かせません。“もっとこうしてみよう”“ミャンマー人にはこうした方が受けますよ”等、応用を利かせた意見がほしい場面もたくさんあります。そんな応用力、発信力を磨いてあげるために、教える側の私達も成長していかなければなりません」(加藤氏)。
加藤氏が語る“教える側の成長”は、エンジニアにとって、開発経験とは異なった特殊なスキルを実装するチャンスではないだろうか。日本国内では少子高齢化・人口減少が進む現在、外国籍のエンジニアを育成するスキルは今後、多方面で求められるはず。加藤氏ほどのエンジニアが苦心しているのだから、決して簡単なことではないが、コーチングスキルが実装されれば、エンジニアとしての市場価値は高い。
現在、2人のミャンマー人エンジニアは現地の日本語学校で6ヶ月かけて日本語を学んでいる。そして2020年2月に来日し、日本のオフィスで本格的な開発実務に携わりながら、さらにスキルを習得していく予定だ。2人をしっかり育て、ミャンマーの人達の役に立つプラットフォームをリリースすることが、同社の当面の目標である。
「そのプラットフォームを浸透させて、ミャンマーのITインフラに貢献したいですね。そしてミャンマーの人達の生活を、より便利に、より豊かなものにしたいと考えています。それが当社のビジョンですから」(市村氏)。
インタビュー

── 市村様は、ご自身の将来についてどのようにお考えでしょうか。
まず、私という人間は、社会をより良くするために頑張る“貢献型”ではないと自己分析しています。むしろ、“こうじゃないかな?”という仮説を、実際のマーケットにぶつける“検証型”です。検証が済み、納得がいけば、次の検証に向かう、というようなタイプですね。
最初に立ち上げた会社は、“こうすれば業界を変えられるのでは?”という仮説を検証する場でした。おかげさまで軌道に乗ったので、後任を立てようと考えられる段階に来ています。Ichi株式会社も、ある意味検証の場ですね。日本に定着したCtoCプラットフォームを、ミャンマーに導入すれば革新的なものになるのではないか... 続きを読む
企業情報
会社名
Ichi株式会社
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
企業の特徴
上場を目指す、自社サービス製品あり、グローバルに活動、残業少なめ資本金
300
設立年月
2019年07月
代表者氏名
代表取締役 市村 幸士
事業内容
■ミッション:
CtoCのプラットフォーマーとしてミャンマーNo1になる。オークションサイト「Ichi」の開発運営。
ベンチャーとしてSPA/PWAの新しい技術に挑戦しております。
一人ひとりがスキルを発揮でき成長できるのがベンチャーのいい所だと思います。
道なき道を進むベンチャーのつらさもありますが、そこにはワクワクする楽しさがあります。
株式公開(証券取引所)
従業員数
4人
本社住所
東京都江戸川区平井3丁目16−22 R-rooms4F
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- Ichi株式会社の中途採用/求人/転職情報