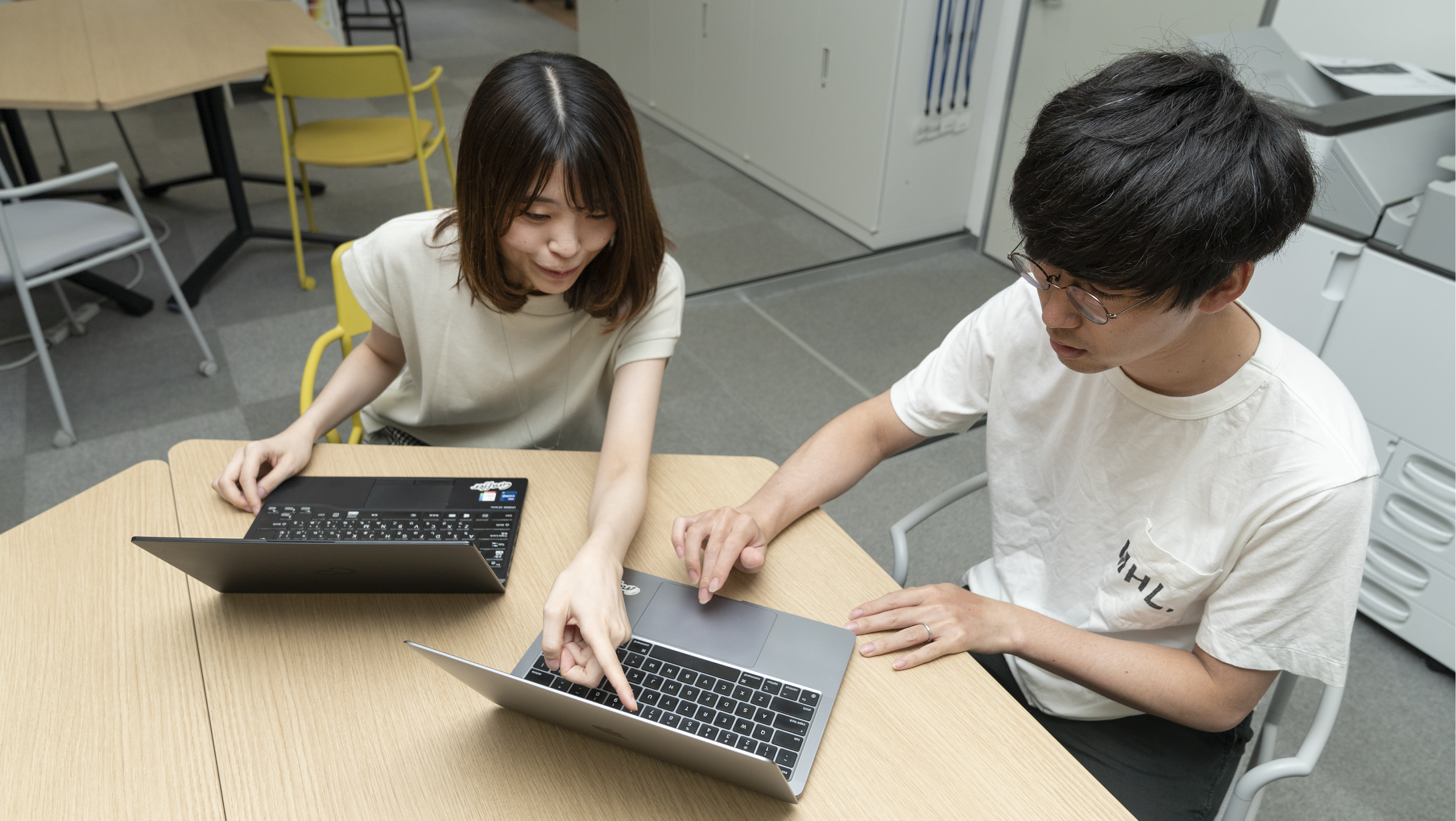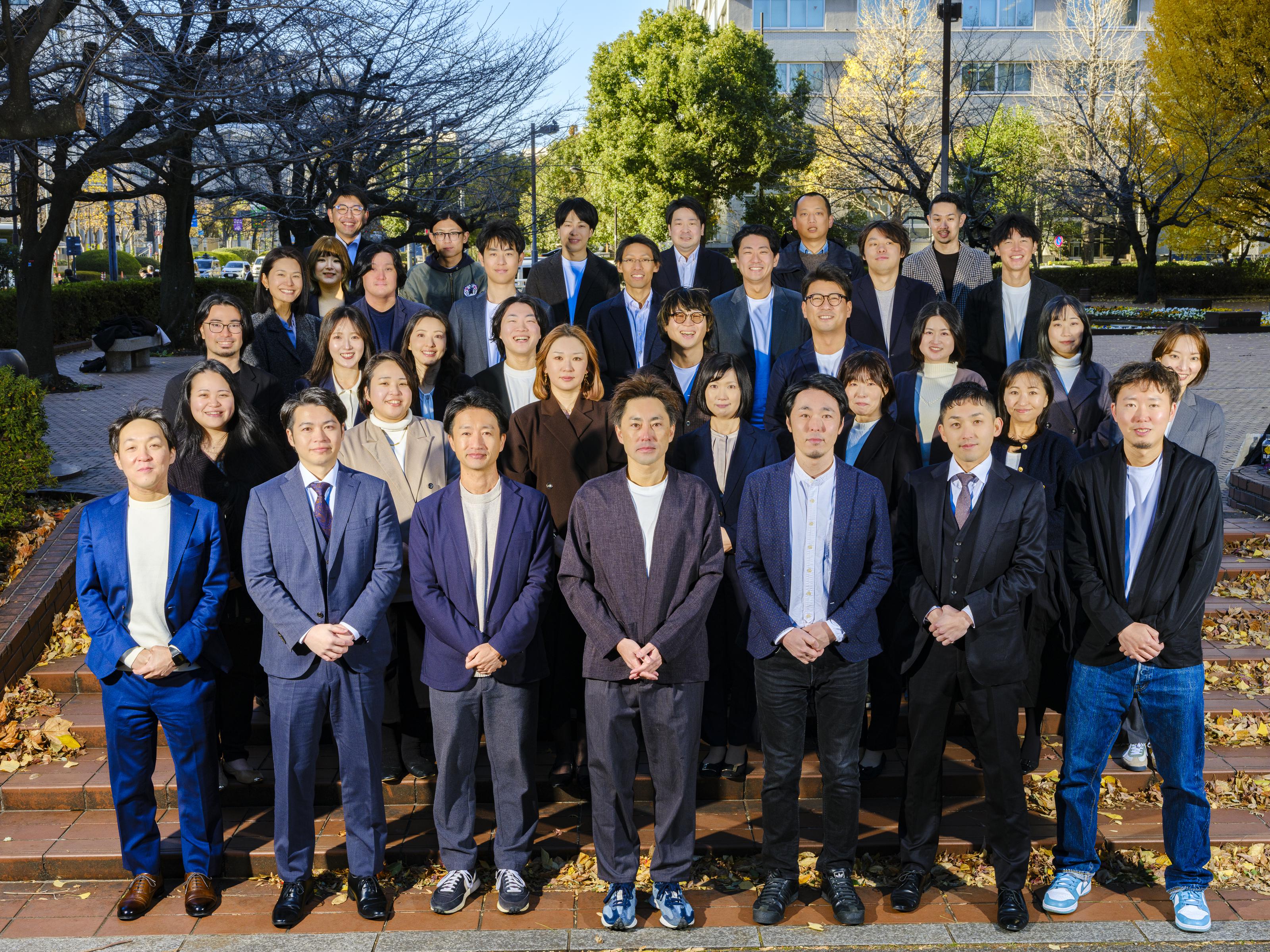株式会社グラファー
- IT/Web・通信・インターネット系
一億二千万人のくらしと仕事を変革する
上場を目指す
自社サービス製品あり
シェアトップクラス
カジュアル面談歓迎
企業について
誰もが避けては通れない、“隠れた巨大市場” にアプローチ
株式会社グラファー(Graffer, Inc.)は、テクノロジーが世界を変えるその最前線に立ち、誰もが等しくテクノロジーの恩恵を受け、自由を享受することができる社会の実現に向け、行政サービスのデジタル化、生成AIの安全な業務利活用促進といった、様々なプロダクトを開発・提供しているスタートアップ企業だ。
代表取締役を務める石井大地氏は、東京大学医学部に進学後、同大学文学部に転部。その後、大学院在学中の2011年に第48回文藝賞(河出書房新社主催)を受賞し、小説家としてプロデビューした人物だ。その後、複数社の起業や経営を経て、株式会社リクルートホールディングスに参画。事業戦略の策定や国内外テクノロジー企業への事業開発投資を手掛けたのち、2017年7月にグラファーを創業した。石井氏やインキュベイトファンドの代表パートナーを務める投資家・村田祐介氏など創業経営陣は、政治や行政などの関係セクターへの豊富な人的コネクションを誇る。
設立の端緒は、起業の題材を探していた石井氏と村田氏の出会いから始まる。「ニッチではなくマスなビジネス」、「広く社会全体に貢献できる題材」を求めていた石井氏と、そのような領域で起業する人材を探していた村田氏が、さまざまな議論やブレーンストーミングを繰り返し、たどり着いたテーマが「行政手続き」だった。言うまでもなく行政手続きは、法律に定められているため誰もが避けることのできない、とてつもなく「マス」なテーマ。その後、起業に向けての調査や聞き込み、自身の実体験などから見てきた問題点を洗い出していくと、そこには意外に大きな「市場」があることがわかり、起業に踏み切った。
代表取締役を務める石井大地氏は、東京大学医学部に進学後、同大学文学部に転部。その後、大学院在学中の2011年に第48回文藝賞(河出書房新社主催)を受賞し、小説家としてプロデビューした人物だ。その後、複数社の起業や経営を経て、株式会社リクルートホールディングスに参画。事業戦略の策定や国内外テクノロジー企業への事業開発投資を手掛けたのち、2017年7月にグラファーを創業した。石井氏やインキュベイトファンドの代表パートナーを務める投資家・村田祐介氏など創業経営陣は、政治や行政などの関係セクターへの豊富な人的コネクションを誇る。
設立の端緒は、起業の題材を探していた石井氏と村田氏の出会いから始まる。「ニッチではなくマスなビジネス」、「広く社会全体に貢献できる題材」を求めていた石井氏と、そのような領域で起業する人材を探していた村田氏が、さまざまな議論やブレーンストーミングを繰り返し、たどり着いたテーマが「行政手続き」だった。言うまでもなく行政手続きは、法律に定められているため誰もが避けることのできない、とてつもなく「マス」なテーマ。その後、起業に向けての調査や聞き込み、自身の実体験などから見てきた問題点を洗い出していくと、そこには意外に大きな「市場」があることがわかり、起業に踏み切った。
巨大な市場で、人々の主体性と創造性を引き出す新しい社会インフラを構築
日本国内では、行政手続きに消費者や事業者がどのくらいのコストを投下しているか、試算や統計が十分に整備されていないのが実情だ。グラファーによる調査によると、欧州諸国では2000年代に“Standard Cost Model”などの手法に基づく事業者の行政手続きコストが試算されている。たとえば、英国では年間GDPの1%ほどの金額を、「行政手続きに費やす人件費」として事業者が負担していることがわかった。こうした試算に基づき、各国で行政手続き簡素化などの負担軽減目標が掲げられ、政策課題となっていった。これらのことからすると、日本においても年間数兆円規模のコストが行政手続きに費やされているであろうと推定される。
グラファーでは現在、住民向けおよび事業者向けに行政手続きを便利に行えるクラウドサービスを提供し、導入自治体からの利用料を中心に収益化を図っている。行政手続きのデジタル化は現在の政権において最優先課題に位置付けられており、マイナンバーカードの活用も大きく進んでいる。今後も民間企業による行政関連ソリューションは拡大していくとグラファーは見ており、こうした潮流に合わせながら、行政手続きを効率化するクラウドサービスの開発・提供を進めている。
また、2023年4月より生成AIを業務で安全に利活用するためのツールキットである「Graffer AI Solution」の提供を開始。今後も引続き「業務のデジタル変革 × 大きな社会課題 × プロダクトを主軸とした価値提供」の3軸が重なる領域において、人々の手に自由な時間を取り戻し、社会を変えていくためのソリューションを提供し続けていく。
グラファーでは現在、住民向けおよび事業者向けに行政手続きを便利に行えるクラウドサービスを提供し、導入自治体からの利用料を中心に収益化を図っている。行政手続きのデジタル化は現在の政権において最優先課題に位置付けられており、マイナンバーカードの活用も大きく進んでいる。今後も民間企業による行政関連ソリューションは拡大していくとグラファーは見ており、こうした潮流に合わせながら、行政手続きを効率化するクラウドサービスの開発・提供を進めている。
また、2023年4月より生成AIを業務で安全に利活用するためのツールキットである「Graffer AI Solution」の提供を開始。今後も引続き「業務のデジタル変革 × 大きな社会課題 × プロダクトを主軸とした価値提供」の3軸が重なる領域において、人々の手に自由な時間を取り戻し、社会を変えていくためのソリューションを提供し続けていく。
We Remove Steps.
【Mission】
We Remove Steps.
【Values】
行動者であれ
個人の尊重
未来から逆算
資産と仕組みの最大化
相互信頼を積み上げる
かざりけなく正直に
制度や法律に基づいて行われる活動を起点とした社会課題を解決するうえで、行政を避けて通ることはできない。
その行政を含む、個人、事業者という全ての経済主体と接点を持ちながら社会課題を解決してきたのがグラファーであり、この三者全てに働きかけることができる企業は、それほど多くはない。
また、全ての経済主体と接点を持つビジネスモデルだからこそ、あっちを立てればこっちが立たないといったトレードオフの関係に陥りやすいのも事実だ。
だからこそ、グラファーのプロダクト導入を通じ、ビフォー・アフターで価値の総量を最大化する方法を考え続け、実行していく。その実行を通じて、人々に自由と選択肢を提供し、人々の行動を変えることで社会課題を解決していくことが、グラファーの責務である。
We Remove Steps.
【Values】
行動者であれ
個人の尊重
未来から逆算
資産と仕組みの最大化
相互信頼を積み上げる
かざりけなく正直に
制度や法律に基づいて行われる活動を起点とした社会課題を解決するうえで、行政を避けて通ることはできない。
その行政を含む、個人、事業者という全ての経済主体と接点を持ちながら社会課題を解決してきたのがグラファーであり、この三者全てに働きかけることができる企業は、それほど多くはない。
また、全ての経済主体と接点を持つビジネスモデルだからこそ、あっちを立てればこっちが立たないといったトレードオフの関係に陥りやすいのも事実だ。
だからこそ、グラファーのプロダクト導入を通じ、ビフォー・アフターで価値の総量を最大化する方法を考え続け、実行していく。その実行を通じて、人々に自由と選択肢を提供し、人々の行動を変えることで社会課題を解決していくことが、グラファーの責務である。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(2件)
求職者の声
企業情報
会社名
株式会社グラファー
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
企業の特徴
カジュアル面談歓迎、上場を目指す、自社サービス製品あり、シェアトップクラス資本金
15億4497万7927円
設立年月
2017年07月
代表者氏名
代表取締役 石井 大地
事業内容
行政インターフェース事業
行政ソリューション事業
データプラットフォーム事業
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
経営陣及び従業員 Incubate Fund Coral Capital (旧500 Startups Japan) 凸版印刷株式会社 個人投資家
従業員数
61人
平均年齢
32.7歳
本社住所
千駄ヶ谷本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷1-5−8 神戸オフィス 〒650-0021 神戸市中央区三宮町1-1-1 新神戸ビル5F
この企業と同じ業界の企業
株式会社グラファー
HR 畑中五月
今すぐの転職をお考えじゃなくても大丈夫です。ぜひ気軽にご連絡ください!
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社グラファーの中途採用/求人/転職情報