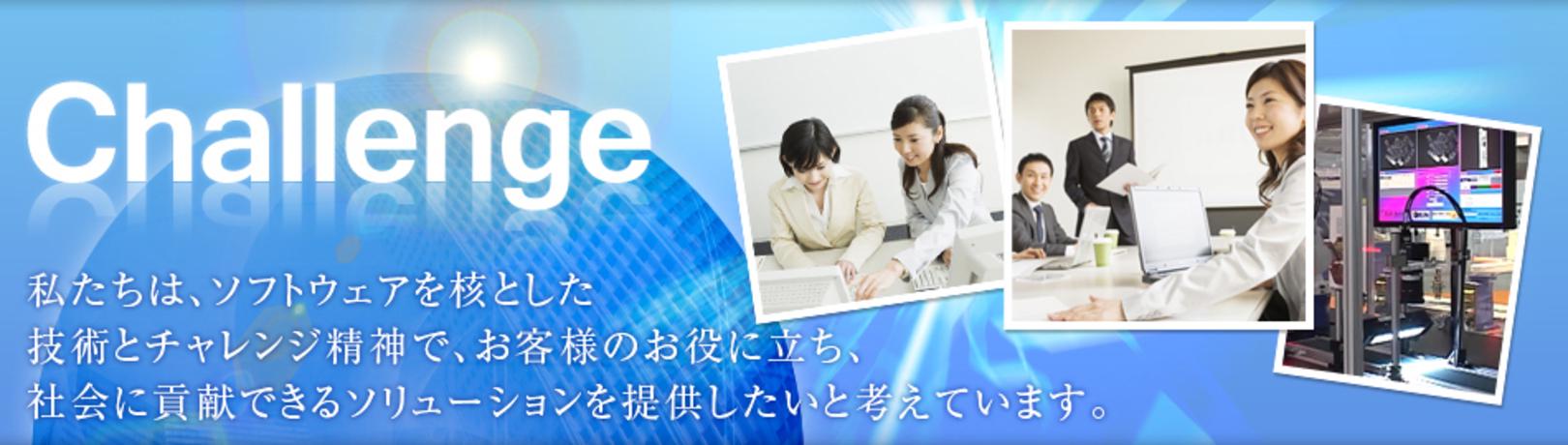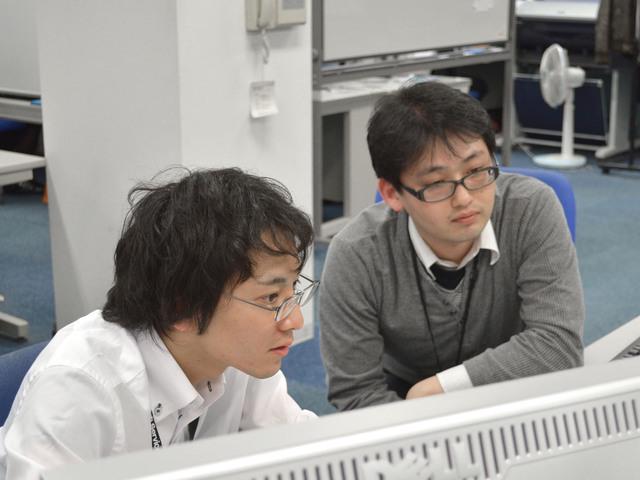株式会社ソフトサービス
- IT/Web・通信・インターネット系
福岡から全国へ、制御システムの強みを背景に自社サービスの展開を加速する!
上場を目指す
自社サービス製品あり
残業少なめ
企業について
制御系や業務系、医療介護系ソフトウェア開発を軸に、自社商品の開発にも力を入れる
株式会社ソフトサービスの創業は1986年。元々、大学で科学技術の研究をしていた代表取締役の野見山章氏が、メーカーでマイコン開発に携わった後に独立し創業。本社のある福岡県福岡市から始まり、現在は東京、大阪、熊本、甲府に事業所を持つ。創業当初から新卒採用に力をいれ、未経験者を中心にした採用を行ってきた。
同社の事業は、ソフトウェアの開発が中心となっている。創業当初から力を入れているのが、制御・組み込み系のソフトウェア開発だ。さらに、業務の効率化・簡素化、業務プロセスの改善などのソリューション提案をともなうビジネスソリューション事業、医療・介護系サービスに特化したパッケージソフトの開発事業、装置・組み込みシステム開発技術をベースにしたFAソリューション事業、ネットワークインフラの構築・技術支援事業を展開している。
「現在、制御系、業務系、医療・介護の3つで、当社の事業の8割を占めています。その中で、医療・介護の分野については、他の事業と違ってサービスを主体としています。当社は創業以来、技術力には強い自負を持っていますが、今後はさらに、医療や介護におけるパッケージソフトやFA機器の開発など、自社商品の開発の部分にも力を入れていきたいと考えています」と野見山氏は話す。
主要な取引先として大手企業や公官庁の名前が並んでいることからも、その技術力が高く評価されてきたことがわかるだろう。それを支えているのが、現在160名を数える社員たちだ。平均年齢は31歳と若く、20代後半でマネジメントを任されるようなケースも多いという。
社員たちのやりがいについて、同社最年少執行役員で事業部長の大寶竜一氏は以下のように語る。「上流の提案・設計から開発、運用・サポートまでを一貫して関われることは、技術者にとって大きなやりがいです。当社は、エンドユーザーと直接取引を行うため、若いうちからクライアントとの交渉や導入後のブラッシュアップなどの部分も担当してもらいます。作って終わりではありません。いろいろな人との関係性を通じて、開発に関われることが、やりがいでもあり、モチベーションにもなっているようです」
自社開発商品については、たとえばリハビリステーション支援システム「RehaSta(リハスタ)」は既に導入実績が140社を超えており、今後も展開が期待される。こうした商品はクライアントありきの開発ではないため、マーケットに向けてどういう商品を提供していくかを提案していくところから関われることになる。こうしたチャレンジングな仕事に関われることも、大きなやりがいとなるはずだ。
同社の事業は、ソフトウェアの開発が中心となっている。創業当初から力を入れているのが、制御・組み込み系のソフトウェア開発だ。さらに、業務の効率化・簡素化、業務プロセスの改善などのソリューション提案をともなうビジネスソリューション事業、医療・介護系サービスに特化したパッケージソフトの開発事業、装置・組み込みシステム開発技術をベースにしたFAソリューション事業、ネットワークインフラの構築・技術支援事業を展開している。
「現在、制御系、業務系、医療・介護の3つで、当社の事業の8割を占めています。その中で、医療・介護の分野については、他の事業と違ってサービスを主体としています。当社は創業以来、技術力には強い自負を持っていますが、今後はさらに、医療や介護におけるパッケージソフトやFA機器の開発など、自社商品の開発の部分にも力を入れていきたいと考えています」と野見山氏は話す。
主要な取引先として大手企業や公官庁の名前が並んでいることからも、その技術力が高く評価されてきたことがわかるだろう。それを支えているのが、現在160名を数える社員たちだ。平均年齢は31歳と若く、20代後半でマネジメントを任されるようなケースも多いという。
社員たちのやりがいについて、同社最年少執行役員で事業部長の大寶竜一氏は以下のように語る。「上流の提案・設計から開発、運用・サポートまでを一貫して関われることは、技術者にとって大きなやりがいです。当社は、エンドユーザーと直接取引を行うため、若いうちからクライアントとの交渉や導入後のブラッシュアップなどの部分も担当してもらいます。作って終わりではありません。いろいろな人との関係性を通じて、開発に関われることが、やりがいでもあり、モチベーションにもなっているようです」
自社開発商品については、たとえばリハビリステーション支援システム「RehaSta(リハスタ)」は既に導入実績が140社を超えており、今後も展開が期待される。こうした商品はクライアントありきの開発ではないため、マーケットに向けてどういう商品を提供していくかを提案していくところから関われることになる。こうしたチャレンジングな仕事に関われることも、大きなやりがいとなるはずだ。
読書を通じた人間育成を重視し、社長自ら読書会を実施
同社の強みについて、野見山氏に伺った。「制御系の技術に強いところですね。特に制御系で使われるOSやミドルウェアに非常に精通している点でしょうか。多くのソフトハウスがありますが、うちのように制御系の高い技術を持ち、ソフト開発に発揮できるところは多くはないと思います」
業務用などのロボット製作に欠かせない画像処理技術の高さも、業界では一目置かれている。こうした強みを生かし、ハードやメカの設計にも力を入れて行く予定だという。
「コンピューターの有効活用については早くから力を入れています。例えばシステムの運用テストの自動化です。業務が終わった夜の時間を使って自動テストをかけることで、業務の軽減はもちろん、トラブルやミスを減らすことができています」(野見山氏)
人の手できちんとしないといけない仕事は、マネジメントによってきちんと行える環境をつくる。一方でコンピューターにもできる仕事は自動化する。そのための設備投資にはきちんとお金をかける。こうした哲学が、多くの企業に支持されるものづくり環境を支えているのだ。
また、各事業所に営業職を多く配置している点も、特徴といえるだろう。技術営業ではなく、技術に精通する営業職がいる開発会社は意外と珍しい。そして、この点が、今後の事業拡大のうえで大きな強みとなるはずだ。
ソフトサービスらしさを語るうえで忘れてはいけないのが、読書への取り組みだ。同社は、経営方針の中に「本をよく読み、よく観察し、人の話をよく聴き、よく考え、実践することで「創造力・決断力・行動力」を培い、グローバル社会に通用する人材を育成する」と明記している。「私は社員の人生を見ているからこそ、彼らがいい人生を送れるようにしたい。人生とは『考え方×情熱×能力』であり、考え方を養うためにも、読書が必要だと考えているのです」(野見山氏)
現在は「木鶏会」という読書会を毎月開催。会社が残業手当を払って社員に参加を促している。本の感想文を発表し合い、それに対して意見し合う交流の場だ。「読書は疑似体験です。人のいい経験を読むことで、あたかも自分自身の体験であるかのように脳に錯覚を起こさせることができます。読書を通じて、人生を豊かにしてほしいと思っているのです」(野見山氏)
業務用などのロボット製作に欠かせない画像処理技術の高さも、業界では一目置かれている。こうした強みを生かし、ハードやメカの設計にも力を入れて行く予定だという。
「コンピューターの有効活用については早くから力を入れています。例えばシステムの運用テストの自動化です。業務が終わった夜の時間を使って自動テストをかけることで、業務の軽減はもちろん、トラブルやミスを減らすことができています」(野見山氏)
人の手できちんとしないといけない仕事は、マネジメントによってきちんと行える環境をつくる。一方でコンピューターにもできる仕事は自動化する。そのための設備投資にはきちんとお金をかける。こうした哲学が、多くの企業に支持されるものづくり環境を支えているのだ。
また、各事業所に営業職を多く配置している点も、特徴といえるだろう。技術営業ではなく、技術に精通する営業職がいる開発会社は意外と珍しい。そして、この点が、今後の事業拡大のうえで大きな強みとなるはずだ。
ソフトサービスらしさを語るうえで忘れてはいけないのが、読書への取り組みだ。同社は、経営方針の中に「本をよく読み、よく観察し、人の話をよく聴き、よく考え、実践することで「創造力・決断力・行動力」を培い、グローバル社会に通用する人材を育成する」と明記している。「私は社員の人生を見ているからこそ、彼らがいい人生を送れるようにしたい。人生とは『考え方×情熱×能力』であり、考え方を養うためにも、読書が必要だと考えているのです」(野見山氏)
現在は「木鶏会」という読書会を毎月開催。会社が残業手当を払って社員に参加を促している。本の感想文を発表し合い、それに対して意見し合う交流の場だ。「読書は疑似体験です。人のいい経験を読むことで、あたかも自分自身の体験であるかのように脳に錯覚を起こさせることができます。読書を通じて、人生を豊かにしてほしいと思っているのです」(野見山氏)
レクリエーションも充実。家族も含めたコミュニケーションを重視する
同社はこれまで新卒採用を中心に展開し、未経験者を多く採用してきた。そのため、教育面では力を入れている。基本的にはOJTが中心となるが、外部協力機関を利用する場合も。経験者、未経験者問わず、各々のレベルに合った育成方法をとっている。
「メンバーたちには、日頃から”ワンランク上のポジションの目線”を持って働こうという話をしています。リーダーでなくても、リーダーがどのような意識で仕事をしているのかを考えて働くことで、仕事の成果は大きく変わります」(大寶氏)
福利厚生の面では、社員寮の存在が大きい。社が借り上げたセキュリティ面でも安全なマンションには寮母もおり、食事や安全の面で社員をサポートしている。また、育児休暇や産前産後休暇は多くの社員が取得。さらに、職場復帰後も子育てに無理のない範囲で働けるように配慮している。
レクリエーションも盛んだ。拠点ごとに企画されるものの中には、家族も含めたコミュニケーションを重視するものも多い。マラソン大会に参加したり、フットサルやゴルフ、テニス、スキーといったスポーツに取り組むなど、社員やその家族の交流を大切にしている。
ちなみに、こうした事業所間の連携については、2週間に一度行われる定例ミーティングで、密な情報交換が行われている。客先常駐の社員も含めて、全社員の連携はさまざまな方法でとられているのだ。
また、前述したように、コンピューターによる自動化のおかげで社員の業務負担が軽減され、残業も少なくなっている。現場のマネジメントがうまく回っていることの証ともいえるだろう。
最後に、求める人物像について野見山氏に聞いた。
「チャレンジする人。さらに、自分から提案し実行できる、素早い動きがとれる人です。面接では、これまでにどういうポジションで働いてきたのかを重視します。その上で技術のエキスパートか、マネジメント経験があるのかといったことを考慮していきます。協調性の有無や、人の気持ちがわかるといった人間性が重要になる部分だからこそ、『マネジメントのできる人』にぜひチャレンジしてもらいたいですね」
「メンバーたちには、日頃から”ワンランク上のポジションの目線”を持って働こうという話をしています。リーダーでなくても、リーダーがどのような意識で仕事をしているのかを考えて働くことで、仕事の成果は大きく変わります」(大寶氏)
福利厚生の面では、社員寮の存在が大きい。社が借り上げたセキュリティ面でも安全なマンションには寮母もおり、食事や安全の面で社員をサポートしている。また、育児休暇や産前産後休暇は多くの社員が取得。さらに、職場復帰後も子育てに無理のない範囲で働けるように配慮している。
レクリエーションも盛んだ。拠点ごとに企画されるものの中には、家族も含めたコミュニケーションを重視するものも多い。マラソン大会に参加したり、フットサルやゴルフ、テニス、スキーといったスポーツに取り組むなど、社員やその家族の交流を大切にしている。
ちなみに、こうした事業所間の連携については、2週間に一度行われる定例ミーティングで、密な情報交換が行われている。客先常駐の社員も含めて、全社員の連携はさまざまな方法でとられているのだ。
また、前述したように、コンピューターによる自動化のおかげで社員の業務負担が軽減され、残業も少なくなっている。現場のマネジメントがうまく回っていることの証ともいえるだろう。
最後に、求める人物像について野見山氏に聞いた。
「チャレンジする人。さらに、自分から提案し実行できる、素早い動きがとれる人です。面接では、これまでにどういうポジションで働いてきたのかを重視します。その上で技術のエキスパートか、マネジメント経験があるのかといったことを考慮していきます。協調性の有無や、人の気持ちがわかるといった人間性が重要になる部分だからこそ、『マネジメントのできる人』にぜひチャレンジしてもらいたいですね」
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(7件)
営業職の求人(1件)
企業情報
会社名
株式会社ソフトサービス
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
企業の特徴
上場を目指す、自社サービス製品あり、残業少なめ資本金
7,000万円
売上(3年分)
2015年 6月 1,728百万円
2014年 6月 1,651百万円
2013年 6月 1,518百万円
設立年月
1986年03月
代表者氏名
代表取締役 野見山 章
事業内容
制御システム開発(設計、製造)
組込み/リアルタイム製品販売/関連技術開発
画像処理システム構築
システムインテグレーション
コンサルティング(ERP,情報分析、スケジューラ、セキュリティ)
ビジネスソリューション(生産管理、販売管理、図面管理等)
医療・介護システム開発・販売
ネットワークシステム構築、保守サービス
株式公開(証券取引所)
従業員数
155人
平均年齢
34.1歳
本社住所
福岡市博多区博多駅東3-3-22
この企業と同じ業界の企業
👋
株式会社ソフトサービスに興味を持ったら、まずは一度気軽に話を聞いてみませんか?
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社ソフトサービスの中途採用/求人/転職情報