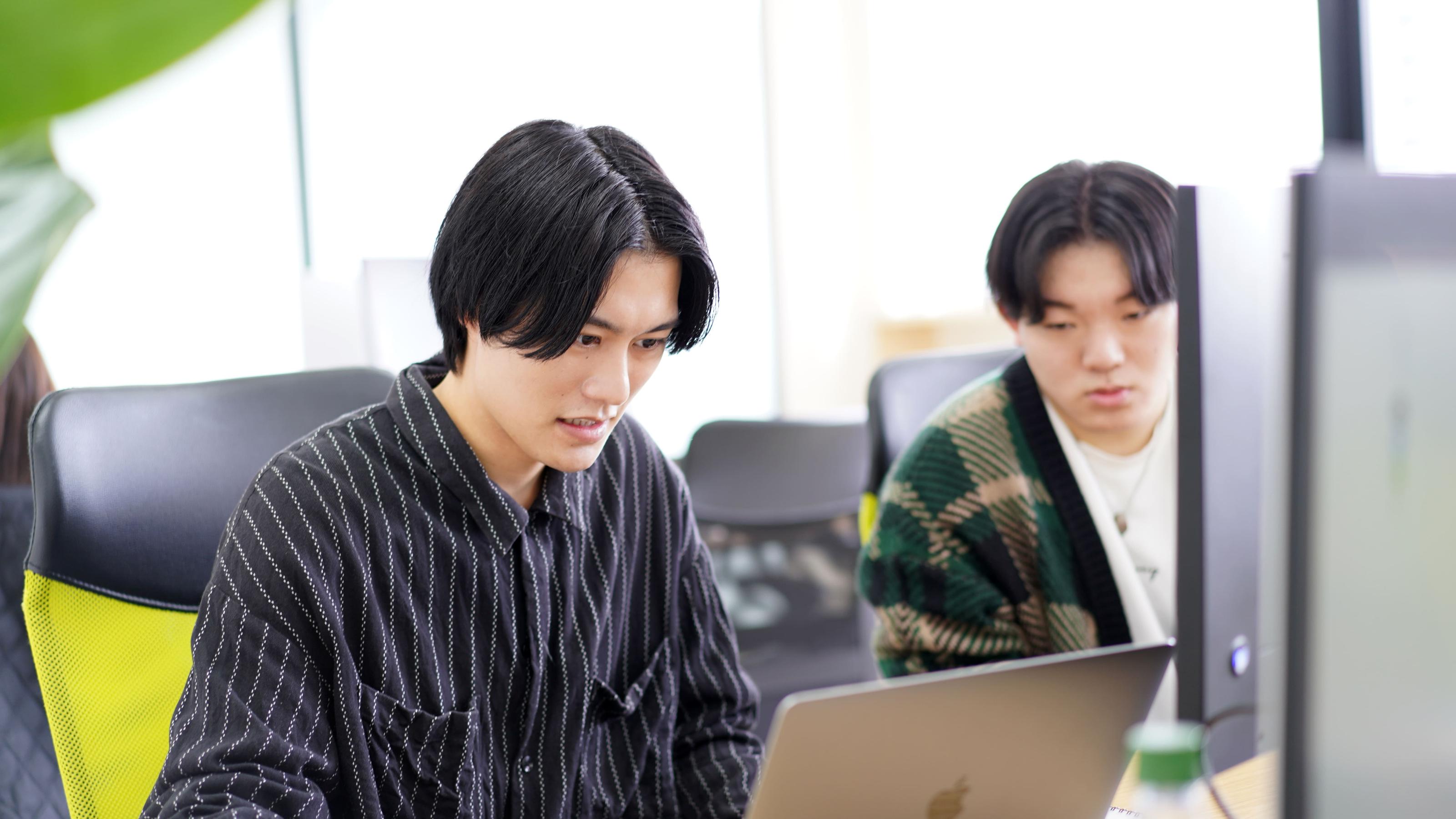株式会社NetValue
- IT/Web・通信・インターネット系
社会インフラ分野で幅広い実績と安定した経営基盤を築くシステム開発会社
企業について
同社が担う業務は、企業・自治体向けの各種業務アプリケーションから、通信制御系システム、さらにネットワークインフラの設計・開発または構築・運用保守までと幅広い。特に、電話・インターネットなどの通信設備や電力、ガスといった社会インフラ系の分野における実績が豊富だ。電話料金統合システムなど支払い系の業務に使われるビリングシステムやエネルギー事業者における設備管理システムなどの基幹業務システム、通信キャリア設備管理システム、通信網監視システムといった通信制御系システム、大規模から小規模サーバ、ネットワークなどに関連するプロジェクトに携わっている。また、いずれの領域においても、上流から下流までワンストップで受託出来る体制を整え、顧客のニーズやプロジェクトに合わせた技術サービスを提供することが可能だ。
同社は1990年1月に東京で設立された株式会社システムイオの関西事業部(1997年4月開設)を母体とする会社である。システムイオ社自体、国内大手ITベンダーを主要取引先として、業務系アプリケーションから制御系システム、ネットワークインフラと幅広い案件を請け負うシステム開発会社だ。その中で西日本全体を担当し、新しい技術にも対応しながら実績を重ね、2004年6月に株式会社NetValue IOとして分社している(2010年1月に現社名に変更)。以降、クライアントとの関係性を深めながら持続的な成長を遂げてきたのである。
代表取締役社長・中森将雄氏は、自社の技術について次のように語る。
「社会インフラの仕組みを作る上で大事なことは確実性です。技術者には機能するかどうかわからない最先端の技術ではなく、確実に動かせることが担保された技術と、その技術を使って確実に仕事が出来るという信頼性が求められます」(中森氏)
同社には営業専任の部隊はあるが、どちらかというと新規顧客や新規市場の獲得をミッションとする。既存顧客に対しては、開発現場に常駐している技術者が窓口とした現場営業を主体に取引を広げてきた。メインフレームの時代から蓄積してきた豊富な業務経験と知識、その知見を引き継ぐ技術者の技術力およびコミュニケーション力が同社の最大の武器だ。
リーマンショックの際は影響を受けたものの、2年で業績が回復させた。国内全体の景気が大きく後退する中、その影響を最小限に抑えて乗り切ることが出来たのは、ニーズがなくならない社会インフラ分野に軸足を置いたことが要因でもあった。2009年には、システムイオ社を母体として、持ち株会社の株式会社MITホールディングスが設立され、同社もその傘下に入った。それによりさらに事業に専念する環境が整備されている。
さらに変化が激しく、不安定さが増すこれからの時代も社会インフラは動き続ける。ただでさえシステムが古くなれば更新する必要がある。技術革新や社会の変化への対応も迫られる。近年では電力分野における発送電分離、モバイル通信分野における5Gのサービス稼働などが記憶に新しい。モバイル通信においてはすでに6Gの声も聞こえ始めている。今後も、同社を含むMITグループ全体に求められる役割は途絶えることはないだろう。
このような事業を展開しながら同社が目指すのは“社員が仕事を通じて幸せを掴める会社”だ。2004年の設立以降、取締役を務めていた中森氏が、ホールディングス制に移行した際に社長へと就任した頃から思い描き続けるビジョンだ。
「今後もインフラ系の分野を中心に仕事をしていくことに変わりはありません。日本の社会生活の一部を支え続けるというモチベーションを軸にしながらも、仕事をする意味や自分が一体何をしたいのかということを、社員一人ひとりが考えて実感出来る、そんな場にしていきたいと考えています」(中森氏)
それを実現するため、中森氏が言い続けていることは「意味のある仕事をしよう」ということと「その仕事を楽しもう」ということだ。
「その仕事に関わるメンバーの中に一人でも“この仕事をなんとしてでも成功させたい”、“この仕事は面白い”と熱を持って語れる人間がいれば良いのです。それがチーム全体に波及し、メンバー全員が意味のある仕事として動けるようになります。そのような日々を持つことが出来れば幸せになれるのではないかと考えています」(中森氏)
「この仕事が好きであることはもちろんのこと、他社で経験を積んで入社する方に期待したいことは、既存の社員に同調するのではなく、刺激を与えてくれることです。将来的にはリーダーとして若い技術者を束ねてくれるような資質を持った方も歓迎です」(中森氏)
中森氏曰く、新卒か中途かに関わらず、同社が求めているのは、仕事に魂を売ることが出来る人材である。“会社に”ではなく“仕事に”である。“社員が仕事を通じて幸せを掴める会社”を実現するために、それは重要な要素だ。もちろん、社員の資質のみに委ねるのではなく、社員一人ひとりが“仕事に魂を売る”ことが出来る環境作りも大事にしてきた。それが「意味のある仕事をしよう」「その仕事を楽しもう」と言い続けることにも繋がっている。
制度面の充実も図ってきた。性別に関わらず長く働けるよう産休育休制度なども早くから取り入れている。また、開発現場に常駐する社員同士の交流を活発化させるために、社内イベントへの参加を促進する制度も導入している。新聞でも取り上げられた『スタンプラリー制度』だ。会社が主催する飲み会などのイベントに出席するとポイントが付与され、1ポイント=1,000円が賞与に上乗せされるという制度だ。それによって参加への心理的ハードルが下がる。プロジェクト外の同僚とコミュニケーションを図ることで、普段はなかなか吐き出す機会がない悩みの解消や仕事へのヒントに繋がるという効果が得られている。さらに、技術研修や階層別研修などMITグループが用意したカリキュラムを必要に応じて受講出来るなど成長支援制度も充実している。
「社会インフラ分野が安定していることは確かです。ただシステム開発という仕事に関しては、どう変化していくのか予測不可能なところまで技術革新は進んでいます。最近はユニット化も進んでいますし、ひょっとしたら明日突然、開発する必要などなくなるかも知れない。どう変化するにしても、仕事に魂を売ることが出来る人なら対応することが出来ます。そういう会社を一緒にいる仲間と作って行きたいと考えています」(中森氏)
社会はますます混迷の度合いを深めており、出口のない息苦しさを感じる人も少なくはないだろう。そんな時、目の前に没頭出来る仕事があるだけで人は救われる。NetValue社への参画は、そのための足がかりの1つだ。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(6件)
PR
すべて見るインタビュー

── 「仕事に魂を売れる場所」にしたいという想いが生まれたきっかけをお話し下さい。
明確にこれがきっかけだと言える何かがあったわけではありませんが、会社を分社化したことが大きな要因でした。
もともと私自身、ステムエンジニアになった時は大志を抱いていたわけではありません。27歳の時にミュージシャンになる夢を諦めて、職業選択をしなければいけないと初めて思った時に、これからはITだと思いました。Windows95が出たばかりの頃でした。
それぐらいの気持ちでエンジニアになりましたが、分社化して会社を運営する側に立った時に、何を知っておくべきなのかが全くわかりませんでした。そこで色々と模索している中で考え方が変わっていきました。
... 続きを読む
企業情報
株式会社NetValue
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
IT/Web・通信・インターネット系 > ITコンサルティング
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
2500万円
2019年 11月 1,103百万
2018年 11月
2017年 11月
2004年06月
中森 将雄
株式会社NetValueは大阪に本社を置くシステム開発会社。大手ITベンダーとの直取引により、通信、電力、ガスなどの社会インフラ分野で、幅広い実績を築いている。2004年6月、東京のシステムイオ社の関西事業部から分社化して設立された会社で、設立時約30名から16年間で100名以上の規模へと成長している。メインフレーム時代から培ってきた業務知識を受け継ぎ、確実な仕事でクライアントからの信頼を得る技術者の存在が最大の武器だ。“社員が仕事を通じて幸せを掴める会社”を目指し、社内制度の充実にも力を注ぐ。
非上場
MITホールディングス株式会社
富士通株式会社 富士通関西中部ネットテック株式会社 株式会社富士通九州システムズ 株式会社日立社会情報サービス 株式会社日立インスファーマ アドソル日進株式会社 ジャパンシステム株式会社 株式会社ミライト情報システム 株式会社アスパーク
105人
33.5歳
〒540-6126 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー26F
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- システムインテグレータ・ソフトハウス
- 株式会社NetValueの中途採用/求人/転職情報