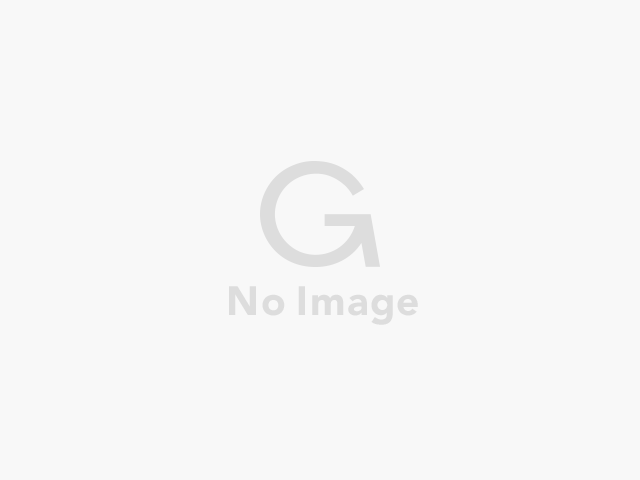株式会社FLINTERS
- IT/Web・通信・インターネット系
社会に役立つ事業を通じて未来につながる火を灯そう
企業について
デジタルマーケティング領域において、WEBアプリ開発、大規模データ基盤構築や、AI技術を用いたデータ活用など、様々なDX支援事業を展開しています。
グループに所属する安定した事業基盤を持ちつつも、スタートアップ特有のスピード感や大きな裁量を併せ持つ、ハイブリットな環境が特徴です。
また、グループ会社が運営する累計1700万DLを突破したオリジナルマンガアプリ「GANMA!(ガンマ)」などBtoCサービスの企画開発も担当しています。
私たちの経営方針として、社会に役立つ事業を通じて未来につながる火を灯し続けるため、ニューノーマルな時代の生活をよりデータドリブンでありながら、ユーザー体験として豊さを感じられる魅力的なものに変革させ、DXを流行り言葉で終わらせることなく社会を前に進めるチャレンジを続けます。
株式会社FLINTERSは2014年に設立し今年10周年を迎えました。設立当初から開発組織として評価制度や開発環境に力を入れています。
ハイスペックPC貸与、モダン技術の採用、開発有料ツールを会社契約でのアカウント発行などを実施しています。
◆圧倒的な開発体験◎エンジニアに裁量があり、なんでも挑戦できる環境
セプテーニグループで培ったデジタルマーケティング業界のDXツール開発ノウハウを活かし、様々な開発を行っています。
技術向上や多種多様な挑戦ができる環境があります。
◆働く環境が充実◎ワークライフバランスをとり高パフォーマンスを発揮
在宅勤務の推奨や残業月20時間以内、休暇の取りやすさを徹底しており、安心して働ける環境を整えています。
◆企業と共に成長していく◎大手とベンチャーのいいとこ取りで成長実感
大手グループに所属していることから安定した事業基盤がありつつも、個社としては100名程度の組織であるからこそのスピード感でまでまで成長企業です。
事業と共に成長できます。
●大丈夫、やってみよう。 全ては一人の熱量から始まる。
●異なる意見を歓迎し、 アイデアを発展させよう。
●なぜやるか? 目的意識を大切に。
●学びを結集し、 新たな付加価値を見つけよう。
●顧客を知り、 期待値を超えよう。
●批判より提案、 そして行動を。
●最終的に決めたことには、 惜しみない協力を。
これらに沿って半年に一度、全社総会内でMVPを選出し、プレートに名前を刻んで永く栄誉を表彰しています。
なお、行動規範は人事考課の項目ともなっており、同社ではメンバー同士が評価し合う「360度サーベイ」を取り入れてますので、公平・公正な人事考課となるよう仕組み化しています。
また「ユーザー価値の高いシステムを素早く提供し続けることで、今までにない未来を作り出す。」これの達成のために、下記のエンジニアリング指針を掲げて推進しています。
•ユーザー価値を確かめる
•変化に強い構造を作る
•適正な品質を目指す
•個人の強みを磨きチームで活かす
•新しいことに挑戦する知性と勇気を持つ
この技術指針は、常にアップデートして生きたものにし続けていて、2022年3月に更新されたものです。
技術向上への意識も高く、恒常的に勉強会が行われているほか、プロジェクト横断でコミュニケーションを深める機会も設けられています。
当社のエンジニアには、ギークもいれば、コミュニケーションにポジティブなタイプもいます。
共通しているのは、自分の強みを自覚し、積極的に伸ばそうとしているところ、また、チームで働くことにポジティブであることも共通しています。
募集している求人
エンジニア・技術職(システム/ネットワーク)の求人(11件)
クリエイティブ職(Web)の求人(2件)
PR
すべて見るインタビュー

── まずはご略歴からお教えください。
最終学歴は東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系で、当時は自然言語処理を研究していました。実は学生時代に、インターネットのあまりの面白さにヒートアップし、“ビットバレー”と呼ばれていた渋谷のITベンチャーに泊まり込んで熱中していたため、大学には2年ほど余計に在籍して卒業することになりました(笑)。
2005年に修了後、SIerに入社してメーカーのR&Dの支援業務を手がけた後、「セカイカメラ」というARアプリに出会い、「これは世界を変えるサービスだ!」と衝撃を受け、開発に関わらせてほしいと志望しその企業に入社しました。結果的にサービスを続けること... 続きを読む
社員の声
すべて見る求職者の声
企業情報
株式会社FLINTERS
IT/Web・通信・インターネット系 > インターネット/Webサービス・ASP
IT/Web・通信・インターネット系 > Webマーケティング・ネット広告
IT/Web・通信・インターネット系 > モバイル/アプリサービス
50,000,000円
2014年01月
武藤 政之
私たちFLINTERSは、SEPTENI(セプテーニ)グループに所属する現在約90名のエンジニアリング企業です。
セプテーニグループで長年培われたデジタルマーケティングやアドテクノロジーの知見を活かして、数千億レコードにもおよぶ大規模データ処理基盤の設計や開発、AI技術を用いたデータ活用、DX支援事業などBtoBサービスを展開しています。
また、グループ会社が運営する累計1700万DLを突破したオリジナルマンガアプリ「GANMA!(ガンマ)」などBtoCサービスの設計及び開発も担当しています。
株式会社セプテーニ・データ・ソリューションズ(100%)
90人
32歳
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-5-1 新宿セントランドビル8F
この企業と同じ業界の企業
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- インターネット/Webサービス・ASP
- 株式会社FLINTERSの中途採用/求人/転職情報