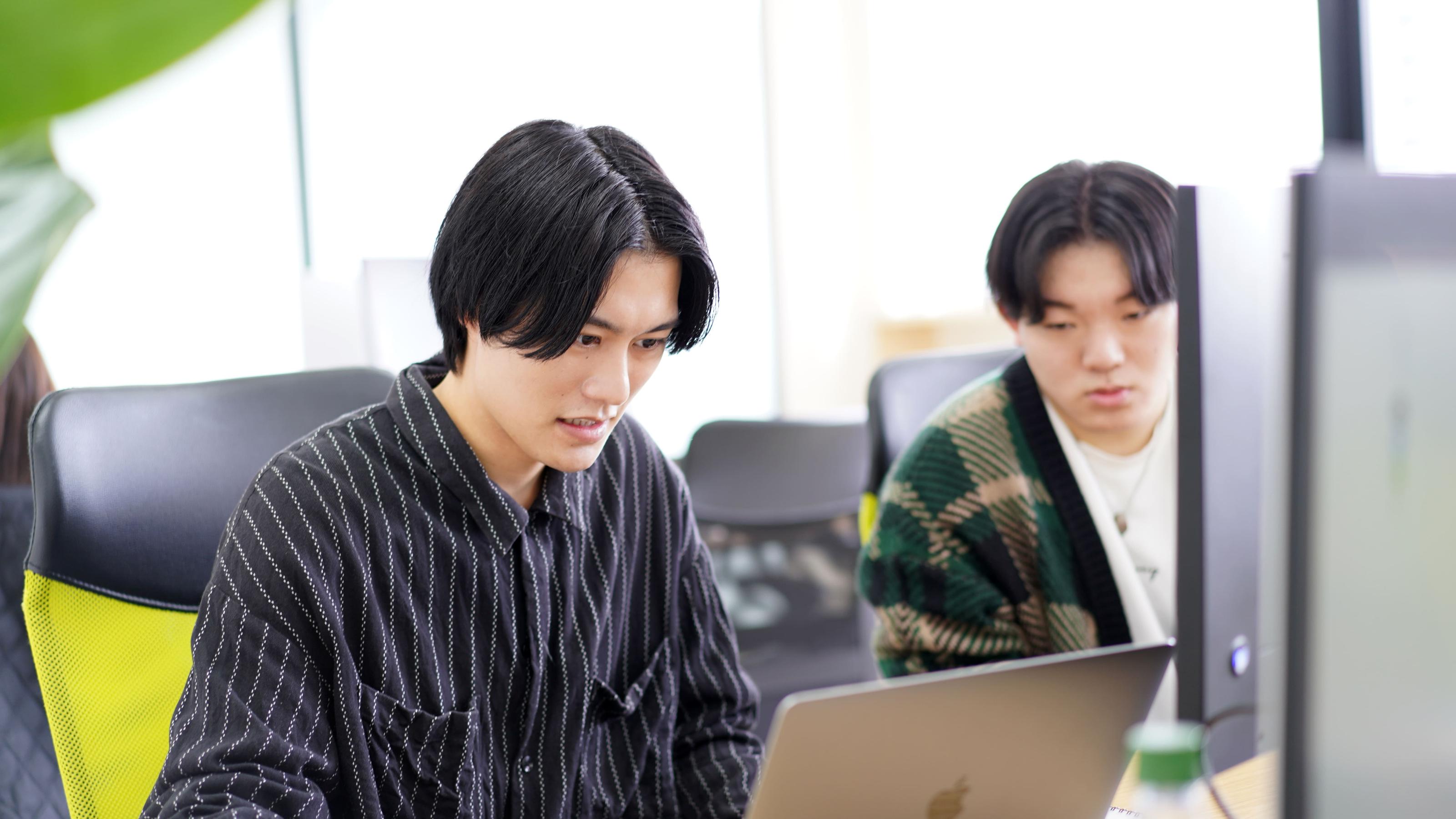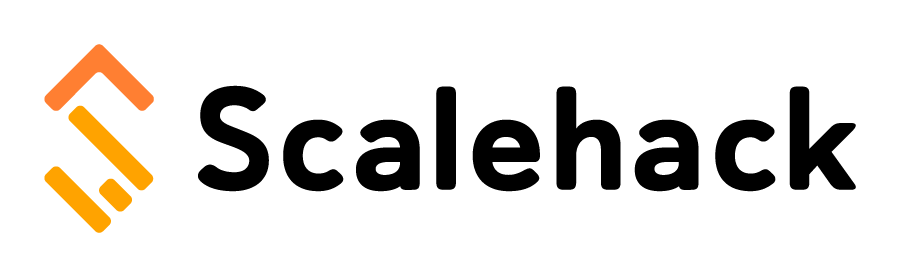株式会社グラッド・ソフトウェア(旧名:株式会社グローバル・アドバンテージ)
- IT/Web・通信・インターネット系
中国におけるオフショア開発に強み、SEとして飛躍できる会社
外資系
グローバルに活動
企業について
オフショア開発で成長
「中国」と「日本」の違いを知りつくし、中国オフショア開発で着実に成長している企業が、グラッド・ソフトウェアだ。
オフショア開発とは、SI企業などが、システム開発・運用管理などを海外の事業者や海外子会社に委託することである。グラッド・ソフトウェアは日本と中国に拠点を置き、日本企業のオフショア開発を受託している。
一般的に、オフショア開発で問題となりがちなのが、言葉や文化の違いである。同社は中国に開発拠点を置いているものの、日本語教育を徹底しており、言葉の壁を感じさせずにオフショア開発が出来ることや、日本と中国の開発における文化の違いを踏まえたうえでのプロジェクト管理能力を持ち、基本設計から詳細設計、製造、連結テストまでの開発を行うことにより、オフショア開発市場での実績を確実に出しているのが最大の特徴だ。
事業内容は金融、証券、通信、流通、ERP・SCM・CRMとOA系のソフトウェアの開発や、ネットワーク、通信・制御、製品組込、画像処理などのソフトウェア開発、またシステムのコンサルティング、構築、代理販売、技術サポートなど、非常に多岐に渡っている。
このように幅広い開発を手がけ、成長を続ける同社の売上高は年間15億円。リーマンショック後一時売上を下げたが、その後は順調に毎年増収増益の一途を辿っている。当社の日本法人、中国法人が協力して、最適な人材配置と、開発工程の分担を行い、またこうした努力の成果として、当社の開発動員力、開発品質、マネジメント力がお客様から高く評価され、発注量が年々増大していているためである。
日本のソフトウェア業界におけるオフショア開発は特殊な事ではなくなり、日本のソフトウェア開発現場では外国人と一緒に仕事をすることは日常となっている。昨今では日中関係の悪化もあり、ベトナム、フィリピン、インドなど東南アジア諸国にオフショア開発先を求める動きもあるが、それでも中国オフショア開発の20年に渡る実績が生み出す信頼性と人材の厚みはそう易々と超えられるものではなく、また日本語に対する親和性やソフトウェア専門人材の育成力や人数も他の東南アジア諸国の比ではなく、中国が今後も日本の最大のオフショア先であることは変わらないものと予測される。
またユーザ企業自ら社内システムの開発、維持管理でオフショアを利用する動きも活発化してきており、グラッド・ソフトウェアはこうしたユーザ企業への対応も進めている。
今後もグラッド・ソフトウェアが活躍する場が広がることは間違いない。
オフショア開発とは、SI企業などが、システム開発・運用管理などを海外の事業者や海外子会社に委託することである。グラッド・ソフトウェアは日本と中国に拠点を置き、日本企業のオフショア開発を受託している。
一般的に、オフショア開発で問題となりがちなのが、言葉や文化の違いである。同社は中国に開発拠点を置いているものの、日本語教育を徹底しており、言葉の壁を感じさせずにオフショア開発が出来ることや、日本と中国の開発における文化の違いを踏まえたうえでのプロジェクト管理能力を持ち、基本設計から詳細設計、製造、連結テストまでの開発を行うことにより、オフショア開発市場での実績を確実に出しているのが最大の特徴だ。
事業内容は金融、証券、通信、流通、ERP・SCM・CRMとOA系のソフトウェアの開発や、ネットワーク、通信・制御、製品組込、画像処理などのソフトウェア開発、またシステムのコンサルティング、構築、代理販売、技術サポートなど、非常に多岐に渡っている。
このように幅広い開発を手がけ、成長を続ける同社の売上高は年間15億円。リーマンショック後一時売上を下げたが、その後は順調に毎年増収増益の一途を辿っている。当社の日本法人、中国法人が協力して、最適な人材配置と、開発工程の分担を行い、またこうした努力の成果として、当社の開発動員力、開発品質、マネジメント力がお客様から高く評価され、発注量が年々増大していているためである。
日本のソフトウェア業界におけるオフショア開発は特殊な事ではなくなり、日本のソフトウェア開発現場では外国人と一緒に仕事をすることは日常となっている。昨今では日中関係の悪化もあり、ベトナム、フィリピン、インドなど東南アジア諸国にオフショア開発先を求める動きもあるが、それでも中国オフショア開発の20年に渡る実績が生み出す信頼性と人材の厚みはそう易々と超えられるものではなく、また日本語に対する親和性やソフトウェア専門人材の育成力や人数も他の東南アジア諸国の比ではなく、中国が今後も日本の最大のオフショア先であることは変わらないものと予測される。
またユーザ企業自ら社内システムの開発、維持管理でオフショアを利用する動きも活発化してきており、グラッド・ソフトウェアはこうしたユーザ企業への対応も進めている。
今後もグラッド・ソフトウェアが活躍する場が広がることは間違いない。
日本と中国の違いを熟知
ではなぜグラッド・ソフトウェアは日中双方の文化の違いを超えて成長しているのか。一つの要因は、社長である陳旋氏の経歴に由来する。
陳氏は1983年に中国・南京大学で理学学士号を取得後、翌年に国費交換留学生として来日。工学博士号を取得してからも、日本の大手企業で研究開発や、中堅企業での技術開発、営業、マネジメントを勤め上げてきた。
2001年10月、「日本と中国の良いところ(=アドバンテージ)を持ったグローバルな企業にしたい」という思いから、グローバル・アドバンテージという社名で会社を設立、日中の架け橋になるべくオフショア開発に乗り出した。(その後グラッド・ソフトウェアに改名)
陳氏が日本企業で長く勤めていたため、同社は日本と中国で仕事のスタイルの違いがあることをよく理解している。
たとえば、日本人開発者は、指示が曖昧でもフレキシブルに対応できるが、慎重すぎるきらいもある。一方、中国では分業が徹底しており、一人一人に細かい指示を出さなければいけない。その代わり、指示が的確であれば仕事は非常に早いのだという。
こうした違いを踏まえ、双方の良さを引き出すことが、オフショア開発を成功させるために重要になってくるのであるわけだが、陳氏が積み上げたノウハウを社員が徹底することで、同社は成長し続けているというわけである。
そんなグローバルな雰囲気を持つ同社であるが、社内はどうか。
横浜にある本社は中国人が多い職場ではあるが、日本語教師を週三回招いて日本語の勉強会を社内で開いており、仕事中はずっと日本語が使えると考えておけばよい。「特に中国語ができる人を採っているわけではなく、どちらかといえばいろんな人とコミュニケーションが取れる人を求めています」と陳氏は言う。
SEは基本的に現場勤務となるが、中国拠点とのやり取りもすべて日本語でOKなので、言語の壁はないといえよう。日本で起業している会社であるため、いわゆる「外資系」とはイメージが全く違うのだ。
陳氏は1983年に中国・南京大学で理学学士号を取得後、翌年に国費交換留学生として来日。工学博士号を取得してからも、日本の大手企業で研究開発や、中堅企業での技術開発、営業、マネジメントを勤め上げてきた。
2001年10月、「日本と中国の良いところ(=アドバンテージ)を持ったグローバルな企業にしたい」という思いから、グローバル・アドバンテージという社名で会社を設立、日中の架け橋になるべくオフショア開発に乗り出した。(その後グラッド・ソフトウェアに改名)
陳氏が日本企業で長く勤めていたため、同社は日本と中国で仕事のスタイルの違いがあることをよく理解している。
たとえば、日本人開発者は、指示が曖昧でもフレキシブルに対応できるが、慎重すぎるきらいもある。一方、中国では分業が徹底しており、一人一人に細かい指示を出さなければいけない。その代わり、指示が的確であれば仕事は非常に早いのだという。
こうした違いを踏まえ、双方の良さを引き出すことが、オフショア開発を成功させるために重要になってくるのであるわけだが、陳氏が積み上げたノウハウを社員が徹底することで、同社は成長し続けているというわけである。
そんなグローバルな雰囲気を持つ同社であるが、社内はどうか。
横浜にある本社は中国人が多い職場ではあるが、日本語教師を週三回招いて日本語の勉強会を社内で開いており、仕事中はずっと日本語が使えると考えておけばよい。「特に中国語ができる人を採っているわけではなく、どちらかといえばいろんな人とコミュニケーションが取れる人を求めています」と陳氏は言う。
SEは基本的に現場勤務となるが、中国拠点とのやり取りもすべて日本語でOKなので、言語の壁はないといえよう。日本で起業している会社であるため、いわゆる「外資系」とはイメージが全く違うのだ。
SEとして成功するチャンスが転がっている会社
グラッド・ソフトウェアで働くことの面白さは、何といっても仕事に枠組みがないこと。
「日本の大企業でSEをやっていると、どうしてもある枠の中で仕事をしなければならなくなります。しかし、この会社では自分がやりたいと思えばどこまででも広げていけます」と取締役・システム開発事業部部長の佐藤理洋氏は話す。
佐藤氏は日本の中堅ソフトウェア開発会社から転職してきた経歴を持つが、同社に入社後は仕事の範囲が広がっていき、「前の会社にいたらここまで成長しなかったかもしれない」と話す。
どんどん挑戦し、失敗してもそれを糧に伸びていける人ならもってこいの会社だろう。
同社の平均年齢は32歳で、男女比は8:2程度。中途採用で入社する社員は経験者が大半で、中国人の割合が多いのは確かだ。
だが、現在同社では特に日本人SEを採用したいという機運が高まっている。
「プロジェクトマネジメントなど、プロジェクト全体をまとめたり、お客様との折衝を行ったりするような責任ある仕事を任せていきたい」と陳氏は期待を込める。中国人社員が多い分、かえって日本人社員が活躍できる場も多いというわけだ。
陳氏を含め、社内のフォローは万全であるため、SEとしての成長を図りたいと思う人なら、チャンスはいくらでも転がっているといえる。
「これから発展していく会社なので、自分も一緒に伸びていきたいという人にぜひ来てほしいと思っています」(佐藤氏)
文化の違いを超え、グローバルな仕事を求める人材なら、この会社に飛び込んでみる価値は十分にありそうだ。
「日本の大企業でSEをやっていると、どうしてもある枠の中で仕事をしなければならなくなります。しかし、この会社では自分がやりたいと思えばどこまででも広げていけます」と取締役・システム開発事業部部長の佐藤理洋氏は話す。
佐藤氏は日本の中堅ソフトウェア開発会社から転職してきた経歴を持つが、同社に入社後は仕事の範囲が広がっていき、「前の会社にいたらここまで成長しなかったかもしれない」と話す。
どんどん挑戦し、失敗してもそれを糧に伸びていける人ならもってこいの会社だろう。
同社の平均年齢は32歳で、男女比は8:2程度。中途採用で入社する社員は経験者が大半で、中国人の割合が多いのは確かだ。
だが、現在同社では特に日本人SEを採用したいという機運が高まっている。
「プロジェクトマネジメントなど、プロジェクト全体をまとめたり、お客様との折衝を行ったりするような責任ある仕事を任せていきたい」と陳氏は期待を込める。中国人社員が多い分、かえって日本人社員が活躍できる場も多いというわけだ。
陳氏を含め、社内のフォローは万全であるため、SEとしての成長を図りたいと思う人なら、チャンスはいくらでも転がっているといえる。
「これから発展していく会社なので、自分も一緒に伸びていきたいという人にぜひ来てほしいと思っています」(佐藤氏)
文化の違いを超え、グローバルな仕事を求める人材なら、この会社に飛び込んでみる価値は十分にありそうだ。
企業情報
会社名
株式会社グラッド・ソフトウェア(旧名:株式会社グローバル・アドバンテージ)
業界
IT/Web・通信・インターネット系 > ソフトウェア/パッケージベンダ
IT/Web・通信・インターネット系 > システムインテグレータ・ソフトハウス
企業の特徴
外資系、グローバルに活動資本金
5,000万円
売上(3年分)
2021年 12月 1,487百万円
2020年 12月 1,359百万円
2019年 12月 1,059万円
設立年月
2001年10月
代表者氏名
代表取締役社長 陳 旋
事業内容
◆金融、通信、流通、生産管理などの業務系ソフトウェアの開発。
◆システム開発のコンサルティング、構築、代理販売とその技術サポート。
◆システムの多言語化、現地化移植、その技術者の派遣と技術サポート。
株式公開(証券取引所)
非上場
主要株主
宏智科技(蘇州)股份有限公司(代表は当社社長の陳旋が兼務)
主要取引先
株式会社野村総合研究所 株式会社村田製作所 コベルコシステム株式会社
従業員数
52人
平均年齢
33.4歳
本社住所
神奈川県 横浜市西区北幸2丁目10番33号 マニュライフプレイス横浜5階
この企業と同じ業界の企業
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
この企業の募集は終了しました。他にも求人を募集している企業がたくさんあるので、
ぜひ探してみてください🔍
他の企業の求人を探すぜひ探してみてください🔍
Copyright© Atrae, Inc. All Right Reserved.
- 転職サイトGreen
- IT/Web・通信・インターネット系
- ソフトウェア/パッケージベンダ
- 株式会社グラッド・ソフトウェア(旧名:株式会社グローバル・アドバンテージ)の中途採用/求人/転職情報